前回みたように物価が景気の波にかかわらず動きにくくなっている。これは価格の粘着性(硬直性)が強まっていることを示唆している。
この粘着性は従来、総務省の消費者物価指数(CPI)を用いて測られてきたが、最近は、個別商品の価格改定の規則性を詳細に調べ、その集計から全体の物価変動をみる手法が注目されている。
この発想は一般的な物価統計の考え方とは対極にある。CPIは総務省の統計に含まれる600近い品目の価格の「平均」であり、その平均値の変化率をみる。つまり手順としては、個別商品の価格を平均したうえで平均値の動きを観察する。一方、最近の手法は逆に、まず個別商品の価格改定の頻度や幅などを調べたうえで、そうした価格変動の分布の全体像を把握することで物価に接近するのである。個々の商品価格の動きが同じであれば、先に平均をとるか後でとるかは大差ない。だが、本当にそうだろうか。
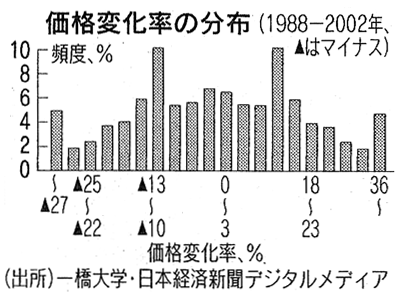
図にスーパーのPOS(販売時点情報管理)データから得た価格変動率の分布を示した(一橋大学物価研究センターと日本経済新聞デジタルメディアの共同研究に基づく。以下、本稿で用いるPOSデータも同じ)。ここでの商品はバーコード単位で区別され約20万種類ある。図では1988-2002年の期間について個別商品の価格改定ごとに、改定幅を横軸に、その頻度(全改定に占める割合)を縦軸に示した。
図からは、個別商品だと変化の程度が非常に大きいことが読み取れる。1回の改定で20%超値上がり・値下がりしたものも少なくない。同じ期間中にCPIの振幅が年率4-5%(最高で3-4%上昇、最低で約1%下落)にとどまったのとは対照的だ。これは個別商品の価格変化のうち経済全体に共通する要因に左右される部分より、最近の資源高に伴う生活関連品の値上がりなどのように、商品に固有の要因に影響される部分が大きいことを示している。
この結果は、平均値で物価を語ることの危うさと、個々の商品価格を基に物価全体の粘着性を測ることの有用性を示しているといえよう。
2007年8月3日 日本経済新聞「やさしい経済学―動かぬ物価の深層」に掲載

