昨年夏のサブプライム問題の深刻化から始まった米国の金融不安は、欧州諸国を巻き込んだ世界規模の金融危機に拡大した。特に9月15日のリーマン・ブラザーズの破綻以後、米国最大級の保険会社であるAIG(アメリカン・インターナショナル・グループ)の急速な経営悪化、一部MMF(マネー・マーケット・ファンド)の元本割れ、モルガン・スタンレーなどに対する預かり資産の大量引き出しなどが重なり、世界のドル短期金融市場は閉塞状態に陥っている。こうした危機は1929年の大恐慌以来のことといえよう。本稿では、当初は米国の住宅金融市場に限られていた金融不安が、世界的に拡大した背景を探った上で、日本の金融システムへの影響を分析する。
◆◆◆
第1に指摘すべきは、多くの欧州の金融機関が、米サブプライム問題の損失を相当程度負担していたことだ。スイス、英国、ドイツなどの金融機関は米市場でも積極的に資金運用を増やし、サブプライム関連商品を保有していた。問題の深刻化でこうした金融機関も損失を被り、急速に自己資本が消耗した。また、英国など欧州連合(EU)諸国の一部でも、不動産価格下落し、これも金融機関の経営に対する不安感を強めた。
第2に、多くの銀行や投資銀行は、信用デリバティブ(派生商品)取引を通して、相互に巨額の信用リスクの連鎖を保有していた。特にクレジット・デフォルト・スワップ(CDS)と呼ばれる信用デリバティブが重要である。
CDSは、信用保証に似た金融派生商品である。例えば、A社(例えばリーマン)発行の額面1億ドル満期5年の債券を保有していたB銀行がA社の万一の破綻に備える場合を考えてみよう。この場合、B銀行は、信用がおけるC保険会社からA社が破綻した場合に備える満期5年、想定元本1億ドルのCDSを購入、C保険に債務保証料として毎年元本の一定金額(例えば1%)を支払う。万一A社が倒産して社債の償還がされなくなった場合、C保険は社債の価値の減損分を保証金としてB銀行に支払う。
実際、リーマンの場合には減損分確定のため、リーマン債の公開入札が行われ、元本1ドルに対して91セントの保証金が支払われた(損失率は91%)。仮に先の例にあてはめれば、C保険がB銀行に9100万ドル支払うことになる。
CDSにはこうした債務保証としての機能がある一方、実際は純粋な投機として使われがちだ。例えばB銀行は、もともとA社債に投資していなくても、C保険からA社に関するCDSを購入できる。この場合、B銀行はA社破綻に賭ければ、C保険から巨額の利益を得ることになる。
CDS取引は急増し、想定元本は、今年6月末で54.6兆ドルとなった。この金額は、2007年の世界全体の国内総生産(GDP)に匹敵する。実際リーマン破綻では想定元本が約4000億ドルにのぼっていた。リーマンは破綻直前まで高い格付けを得ていたが、損失率が91%と非常に高率だったこともあり、CDS清算に際しリスクを引き受けていた金融機関が保証の履行を迫られ巨額の損失を被る可能性も指摘されていた。だが実際の損失額は60億-80億ドルにとどまったとみられ、幸い大きな連鎖破綻も報道されていない。
◆◆◆
CDS取引に伴う大きなリスクが顕在化したのが、AIGの突然の経営悪化である。AIGはその傘下に金融派生商品を扱うロンドン法人を抱えていた。米ニューヨーク・タイムズ紙によれば、CDSで巨額の保証を行って得た保証料を利益計上することで、05年にはAIG全体の利益の17.5%を稼ぎ出した。だがサブプライム関連の保証履行債務が急激に拡大して巨額損失の計上を迫られ、同社の格付けはダブルA格から大幅に引き下げられた。これにより、AIGにはCDSの信用保証先に巨額の担保を差し入れる義務が発生し、政府から2回にわたり12兆円を超える資金支援を受ける、実質破綻状態になった。
仮にAIGが政府から支援を得られなかった場合、同社からリーマンなど経営悪化企業の信用保証を買っていた大手投資銀行などが損失保証を喪失し、連鎖的な経営危機に陥る可能性もあった。
CDS取引による保証供与からの収入は、将来の保証債務の負担に見合っているはずで、大半を引き当て処理する必要がある。だがAIGは受け取った保証報酬の大半を利益計上していたとみられる。
CDS取引では、欧米の有力金融機関が軒並み上位に名を連ね、特に大手投資銀行はいわば胴元になっている。CDSは利益操作などに使いやすく、世界の金融市場にばらまかれた連鎖的に爆発しかねない「地雷」になっている。しかも情報開示が不足し、どこに埋まっているかわからない。これが世界的な金融市場閉塞の背景にある。
3カ月物のドルのロンドン銀行間取引金利(LIBOR)と米短期国債(TB)利回りの推移をみると、昨年夏から広がりはじめた金利差は、リーマン破綻後に一気に拡大。インターバンク市場はマヒ状態に陥っている。
10月3日の米金融安定化法の成立で、ようやく金融市場の安定化に向けた対策が具体的に動き出した。だが短期金融市場は、なお正常な状態から程遠い状況にある。これは、金融機関や企業が相互に取引相手の健全性に対し不信感を抱いているからである。
この正常化には、財務情報の徹底開示、特に不良債権の状況、CDS取引に伴うリスクや評価基準などの開示で不信感を徐々に低下させる必要がある。CDSには5年程度の長期契約が多く、その評価基準もあいまいである。
CDSや長期のデリバティブ商品に関するリスクの低減と会計の透明性を図るには、米連邦準備理事会(FRB)やバーゼルの金融安定化フォーラムなどが提唱しているCDSなどデリバティブの集中取引決済機関の設置が望ましい。中立的なデリバティブの値付け機関の設立で、取引の当事者間で同じ金額の「勝ち」と「負け」が計上されることが望ましい。また従来の相対取引が、取引所を相手方とする取引に移行されれば、取引相手が破綻して「勝ち」の回収が不可能になる事態を回避することが可能になる。
◆◆◆
こうした金融市場の混乱や株安の影響は国内金融機関にも顕著に表れている。全国銀行の業況を振り返ると、05年度まで緩やかな回復基調にあった粗利益は、06、07年度と二期連続で減益となった。これは、07年9月の金融商品取引法施行や世界的な株安で、保険や投資信託などの窓販が振るわず、それまで資金運用差益の減少を補っていた役務取引等差益が減少したことが影響している。
さらに、9月以降の株価下落で、銀行の自己資本比率はかなり低下している。全国銀行の実質自己資本比率の08年3月末までの実績値と、日経平均株価の水準ごとに想定される比率をみてみよう(図)。この実質自己資本比率は、日本経済研究センターが繰り延べ税金資産や不良債権の引当率を調整して、厳しめのコア自己資本を推定することで独自に試算したものだ。08年9月末の数値を用いたケース(A)でも、08年3月決算時点から比べ、すでに約0.3ポイント低下している。
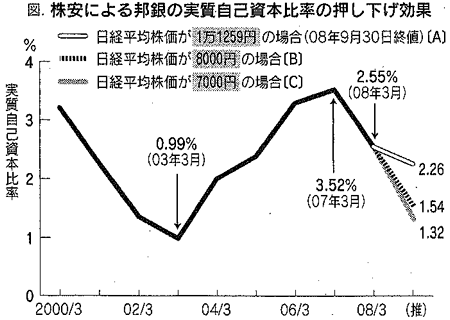
10月に入り株価は8000円を割り込んだが、日経平均8000円のケース(B)では、全国銀行ベースで実質自己資本比率が1.54%、同7000円のケース(C)では1.32%まで低下する。この数字は、銀行が不良債権処理と株安に苦しんでいた最悪期の03年3月末決算時を多少上回る程度のものである。
また、株価の想定水準別に個別行の実質自己資本比率を推計してみると、日経平均が7000円になると、全国銀行124行のうち、実質自己資本比率が0%を下回り実質的に債務超過となる銀行が20行近くにもなる。このように日本の銀行部門は、株価下落に対する耐久力はなお弱く、株価下落で、かなりの銀行の自己資本が脆弱になっている。こうした自己資本不足は、銀行の貸し出し態度悪化を通じ、日本の景気回復を遅らせる。わが国でも銀行の自己資本増強を援助・奨励する政策を早急に実施に移すべきだろう。
2008年10月29日 日本経済新聞「経済教室」に掲載


