日銀はデフレからの確実な脱却を優先すべきで、2月21日の利上げはデフレ再燃のリスクを伴うといわざるを得ない。国内総生産(GDP)ギャップなどから見ると、日本経済は現状ではデフレを払拭したといえないからだ。20年来の安値水準にある円相場も、日米金利差が縮小すればさらに円高に振れる可能性が強く、これもデフレ要因になる。
金融政策のかじ取りは、息の長い景気拡大を続ける日本経済を大きく左右する。デフレに逆戻りしたり、景気を下支えする円安基調が反転したりするリスクはないのか。今回の金融研究報告では、こうした観点から、GDPギャップや為替レートを計量的に分析して、リスクを検証した。
2月21日に再利上げに踏み切った日銀は「緩やかな景気拡大を続ける蓋然性が高いと判断した」と説明している。しかし、物価動向やGDPギャップの推計結果から判断すると、現状の日本経済はデフレから完全に脱却したかどうか微妙な水準であると言うべき状況だ。
GDPギャップ プラス幅小さく
GDPギャップは、マクロ経済の需給ギャップとも呼ばれ、経済の潜在的な実力を示す潜在GDPから計った実際のGDPの乖離の割合を示す。マクロ的に見た生産要素の稼働率ともいえる。これがプラスならば好況、マイナスであれば不況を意味する。しかし、潜在GDPやGDPギャップは直接観測できないため、計量分析による推計が必要となる。
まず最大生産可能GDP(資本と労働がフル稼働状態で達成できる生産水準)をマクロ生産関数から推計し、実際のGDPをこの推計値で割ることで「マクロ稼働率」を計算した。次に物価上昇率とマクロ稼働率の関係を表す物価関数を推計して、インフレ中立的なマクロ稼働率に対応するGDPの水準が潜在GDPである。最後に実際のGDPと潜在GDPの乖離幅としてGDPギャップを導出した。
物価関数の推計では、期待インフレ率を加味した場合と加味しない場合の2つに分けた。その結果推計されたGDPギャップを図1に示す。1990年代終盤からマイナス推移が続き、01年10-12月期を底として上昇トレンド(マイナス幅の縮小)に転じたが、06年は7-9月期までゼロ近傍で横ばいだった。06年10-12月期に前者で0.71%、後者で1.06%と両者ともようやくプラスになった。
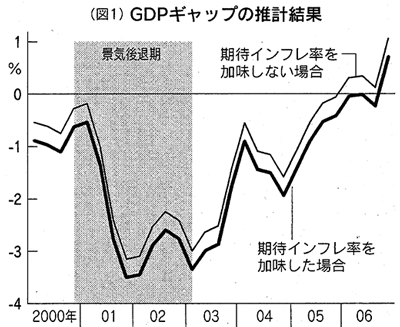
内閣府は先月、昨年10-12月期のギャップが約10年ぶりに需要超過に転じたと発表したが、もともと推計方法によって振れやすく、かなりの幅で考える必要がある。最近の動きからギャップが徐々にプラスに向かっていると見ることは可能だが、ゼロから大きく離れた値ではない。
物価動向を見ても、下落リスクはぬぐえない。すなわち、昨年12月の食料(酒類を除く)とエネルギーを除く消費者物価指数は前年同月比0.3%の下落となっている。原油価格が一段と下がれば、近い将来生鮮食品を除くコアの消費者物価上昇率は「水面下」にしずむ可能性が大きい。
したがって日本経済には、今後の海外経済や為替相場次第で、デフレが再燃するリスクがある。このように物価動向については、これから確実に上昇していくとは判断しにくい状況にある。
日米実質金利差 為替相場に影響
今後の景気悪化要因としては円高のリスクがある。実質金利差と国際収支(累積経常収支と累積直接投資収支の合計額の世界GDP比率)を変動要因として円の対ドル相場を推計したところ、日本の当局による為替市場介入を考慮したケースで、実績値を比較的よく追う結果が得られた(図2)。例えば03年度の理論値の大幅な下落は、日本政府による3300億ドルにも上る円売りドル買い介入が原因である。
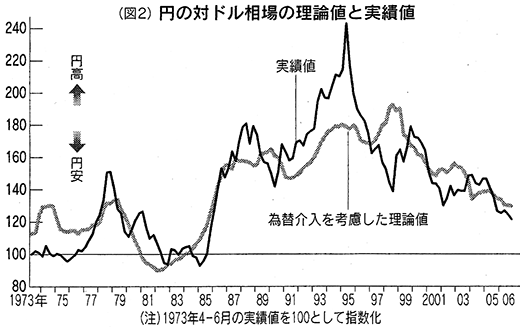
日本の対外大幅黒字が続いているにもかかわらず、このところ円安傾向になっている点も、この推計式で分析できる。下表を使い、直近で最も円高だった05年1-3月期から06年4-6月期までで見てみよう。この間の日本の黒字幅は1070億ドルで、これに伴い円相場は本来、5.5%(=0.51%×10.7)高くなってもおかしくない。ところが、米利上げなどで日米実質金利差(日本-米国)が1.69%からマイナス0.63%へと2.32ポイント縮小。4.0%(=2.32%×1.73%)の円安要因になった。その他の押し上げ要因もあって、実際に円安基調になった。
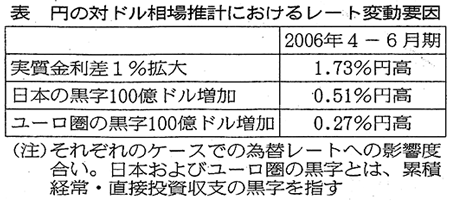
言い換えれば、今後日銀が利上げをすれば実質金利差のマイナス幅が縮小し、大幅黒字と相まって本格的な円高局面が到来する可能性もある。そうなれば、これまで円安の恩恵を受け過去最高を更新してきた企業収益に冷や水を浴びせる恐れが十分あろう。
また、円高のリスクは円金利の上昇だけで生じるわけではない。近年、国際収支不均衡が世界的に拡大しており、世界の経常赤字を米国が一手に引き受け、日本、中国、ロシア、中近東諸国の黒字がそれを補う構図になっている。これまで黒字国は、米ドル建ての外貨準備を蓄積し、米国の赤字をファイナンスしてきたが、徐々にドル安への警戒感を強めている。
米国は依然、世界一の経済大国で、高い成長力と堅調な景気に加え財政赤字も縮小傾向にある。しかし、米国が景気後退に見舞われてドル金利が低下したり、黒字国が運用先を他通貨にシフトしたりすれば、米国から資金が流出し、ドル安が進む恐れがある。実際、今週の世界同時株安を受けて、米国経済の先行き懸念から円が急伸する場面が見られた。
世界の外貨準備の通貨構成は、米ドルのウエートが低下する一方、ユーロ割合が直近では4分の1以上に上昇した。これが現在のユーロ高の背景にある。実際、ユーロ対ドル相場の推計でも、経常収支や直接投資収支に加え、各国外貨準備のドルからユーロへのシフトを考慮に入れた理論値は、実績値との当てはまりが非常に良かった。
一方、世界の外貨準備に占める円の比率は低下傾向にあり、06年9月では3%強と、英ポンドを下回った(図3)。これは量的緩和政策の下で金利が極めて低く円運用が不利だったこと、不良債権問題で日本の金融機関の信用力が低下していたこと、巨額の財政赤字で日本国政府に対する信用も低下していたこと、の3つが背景にある。
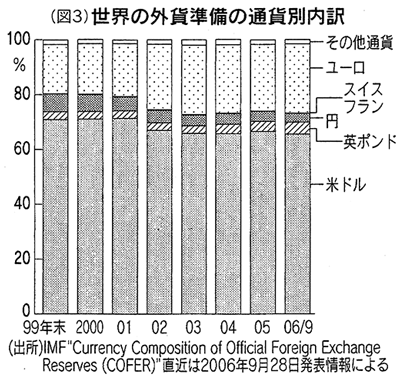
金融機関や政府が「失われた10年」で低下した信頼を取り戻せば、外貨準備でも円が運用通貨として見直され、ドル売り円買い圧力が高まる可能性は十分にある。
政策判断誤れば日銀の信認低下
実質金利差、国際収支不均衡、外貨準備の運用など、現在の円安基調は円高に転じるリスクをはらんでいる。デフレ脱却や金利正常化といった日本経済の立ち直りが円高を呼び、再び経済に大きなマイナス要因になりかねないという微妙な状況の中で景気拡大が維持されているのが、現在の日本の姿である。
消費者物価も、原油価格が大幅に上昇する中で実質ゼロインフレである。海外経済の失速や円高で景気が悪化した場合における金利引き下げ余地はごく限られている。
こうした中で物価上昇率の高まりに見合い、短期市場金利を引き上げていくのは当然である。しかしGDPギャップがゼロ近傍にあり、食品・エネルギーを除く消費者物価上昇率も小幅のマイナスという現状で、いわゆる「のりしろ」、すなわち引き下げの余地を作るための利上げであれば、それは主客転倒である。
「消費者物価指数の前年比上昇率が安定的に0%以上」という量的緩和政策解除の条件として掲げたことすらおぼつかない現状で再利上げに踏み切ったことは、日銀に説明責任、市場との対話、信頼性などが求められていることを考えれば、疑問が残る政策判断であった。それが結果的に誤っていれば、日銀の責任を問う声が高まるのは必定だ。日銀が信頼を失えば日銀法改正圧力などの政治介入を強めかねない。先の再利上げは、今後の経済動向によっては、日銀の信頼を傷付けかねない大きなリスクを伴う決定だったといえよう。
2007年3月1日 日本経済新聞「経済教室」に掲載


