日本経済のデフレ脱却が進めば、中長期的には金利がかなり上昇する可能性が高い。変動金利住宅ローンは、金利上昇が家計の返済負担を大幅に増加させるので、貸し手は十分な説明責任を果たす必要がある。消費者金融は、上限金利引き下げに加え今後市場金利が上昇していくと、市場が大幅に縮小する可能性がある。上限規制金利は、市場連動にすべきである。
日本経済は「いざなぎ超え」が確実視される息の長い景気拡大が続いており、ゼロ金利政策の解除で、今後の金利上昇の余地も生まれている。現時点で急上昇する可能性は低いが、中長期的には金利上昇のリスクを認識し直す必要がある。
05年度の銀行決算は純利益が過去最高となり邦銀の格付けも改善しつつある(図表1)。銀行経営は大幅に改善しているが、資金の運用と調達の利回り差である銀行の「利ざや」は縮小傾向にある。不良債権処理に伴う費用・損失の軽減による増益の余地は減っており、営業経費は増加に転じるなど、回復基調にあった銀行収益は、踊り場にさしかかっている。
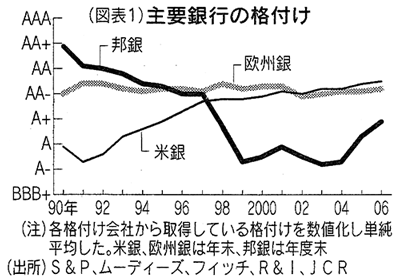
負担が重くなる変動金利ローン
こうした中で、邦銀にとって重要性を増しているのが個人向け貸出市場である。十分な利益を確保しにくい企業向け貸し出しの残高が減少するのを補う形で特に住宅ローン残高の伸びが目立つ(図表2)。独立行政法人移行を控えた住宅金融公庫による住宅ローン残高が減少傾向にあることも追い風になっている。
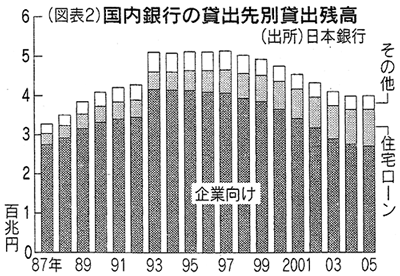
住宅ローンの中で、変動金利型ローンが多いことには注意すべきだ。住宅取得を最優先するあまり、借り手は当初の月次返済額が少なくてすむローンを組むことが多い。当初の一定期間は固定金利でその後は変動金利になる固定金利期間選択型の住宅ローンがその典型である。しかし、歴史的な超低金利時代は終わりを告げつつあり、今以上に金利が低下する余地は基本的に存在しない。
全期間固定金利型住宅ローン商品の代表である「フラット35」と当初固定型の変動金利型商品で、金利上昇の家計に与える影響を比較してみよう。フラット35は、ローン債権を銀行が住宅金融公庫に売却、証券化するタイプの商品である。
直近の平均融資利率3.096%のフラット35と、最初の5年間だけ固定金利が適用されその後変動金利になる商品(代表的な大手行の当初固定レートは1.85%)について、共に35年ローンで、5年後に1度だけ金利が上昇する場合で試算してみた。
その結果、最初の変動金利(ある大手行で2.375%)が3.7%以上になると、フラット35の方が総返済額が少なくなる。変動金利が低いまま推移すれば、結果的にフラット35の方が負担が重くなる可能性もあるが、市中の実勢金利からはそう推測できない。
将来の変動金利は、現在の市場金利から算出する将来の予想金利(インプライド・フォワード・レート=IFR)に住宅ローンの信用リスクプレミアムを足すことで推定できる。9年先の1年物のIFRは2.8-3.0%である。一方、現在の1年物金利は約0.6%であり、プレミアムは約1.8%(=2.375%-0.6%)である。したがって、変動金利期間である30年間の平均金利は少なくとも約4.6-4.8%と推定され、フラット35の3.096%より高くなることになる。
125%ルールで後年負担増す
変動金利の上昇は、家計に大きな負担増となる。全期間変動金利住宅ローンで借り入れ後間もなく金利が上昇した場合を試算したのが図表3である(金利は当初2%で1年後に1度だけ上昇、月次返済額見直しは5年ごとと仮定)。2年目以降の金利が3%、すなわち金利上昇幅が1%の場合は5年後からの月次返済額は約1.2倍に、上昇幅が3%になると5年後からの月次返済額は1.6倍に跳ね上がる。
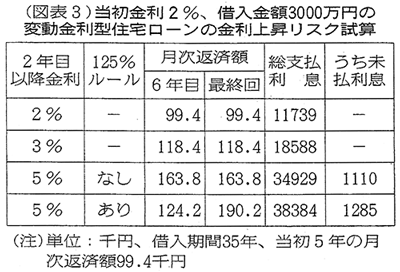
また、金利上昇幅が大きいと月次の返済が利息額を下回り、未払い利息が発生する。変動金利ローンの場合、金利上昇に伴う月々の返済額を急に増やさないようにするため、5年ごとの見直しの際に月次返済額をそれまでの1.25倍以下にする「125%ルール」がしばしば適用される。このルールが適用されると未払い利息はさらに積み上がり、後年度の負担が非常に重くなる。
金利上昇局面では、景気拡大に伴う家計所得増の期待もあるが、楽観は禁物だ。ローン負担が借り入れ当初の予想を超え、返済困難に陥る家計が続出する恐れもある。
住宅金融公庫の調査では、変動型の金利ルールについて「全く知らない」「あまり知らない」と回答した利用者が合わせて4割近くにも達した。こうした借り手の認識の甘さは、貸し手の説明不足に起因する面もあろう。個人向け不良債権が多発しないよう、銀行は十分な説明責任を果たしつつリスク管理の観点からも節度ある貸し出し行動をとるべきである。
消費者金融業 利ざや縮小へ
借りた資金を返済するのは借り手の当然の義務だが、貸し手のあり方が問われているのが消費者金融業界である。現行の上限金利は、利息制限法で法的に取り立てができる上限を20%と定められている一方、刑事罰を伴う出資法では上限が29.2%となっている。消費者金融業者は、利息制限法の上限は超えるが出資法の上限は超えない、いわゆるグレーゾーン金利で貸し付け、高い利回りを享受してきた。しかし、過剰貸し付け、多重債務、過酷な取り立てなどへの社会的批判が高まり、出資法の上限金利を利息制限法に合わせた20%に下げることなどがほぼ決まっている。
貸出残高急拡大で消費者金融業者が高水準の利益を上げる一方、銀行の消費財・サービス購入資金の個人向け貸し出しは減少傾向にある。利回りが高い消費者金融は大手行も強い関心を抱き、三井住友銀行とプロミス、三菱UFJグループとアコムなど、専業との資本・業務提携などでも銀行も個人向け貸し出し強化を進めてきたが、これにも強い逆風が吹いている。
企業と異なり、通常、消費者は借り入れた資金を元手に収益を生み出すわけではない。まして、30%近い高金利の金融債務を個人が年収の半分以上も負担すれば、ごく短期間のつなぎ資金とするなどの場合以外は、利息が積み上がり返済能力を超える可能性が高い。自己の返済能力を見極めないまま多額の借り入れを繰り返す借り手にも責任はあるが、それを知りながら高金利での過剰な貸し付けや過酷な取り立てを行う金融業者が批判されるのも当然である。
上限金利引き下げなどで消費者金融業者は大きな影響を受ける。貸し出し利回りが低下し、業者の貸し付け余力も縮小。利ざや縮小で、高リスクの顧客への貸し付けを抑制せざるを得なくなり、利用者の年収の3分の1を超える貸し付けも原則として禁止される。
そこで、現状23%強の平均貸付金利は18%に低下、借入残高は貸付残高連動で減少などいくつか前提を置き、調達金利上昇と貸出残高減少の影響を試算してみた(図表4)。残高が10%減る場合、調達金利が変わらなくても営業利益は半分以下になる。調達金利が5%上昇すれば営業赤字に転落する結果になった。
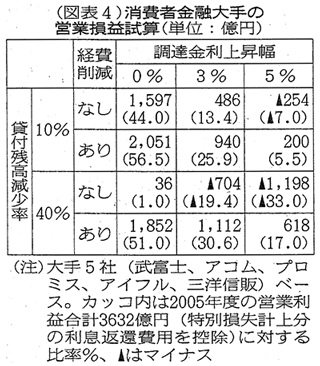
貸付残高が40%減少すると、3%の調達金利上昇でも営業赤字になる。貸し付けが減った分、比例して営業経費も減るという経費削減ケースでも、調達金利が5%上がると赤字回避がやっとという状態になる。
上限金利規制 独仏を参考に
上限金利規制の強化は、社会的な問題の解決を図るものとしては評価できるが、経済合理性の視点が不十分である。
懸念されるのは、今回の上限金利規制強化の議論が超低金利下でなされ、一定の名目金利による上限設定だということだ。日本の長期的な金利動向からすると、ゼロ金利は極めて特殊な状況である。今後日本経済が正常化するにつれて、金利が数%上昇することは決して不自然ではない。
上限金利が一定の名目金利として法律で定められていると、貸し手は適正な利ざやを確保することすらできない事態も起こる。貸付残高に対する貸倒費用の比率は、大手5社ベースで2000年度まで4%程度だったが、05年度で7%を超える。コスト削減努力にもかかわらず利益が確保できなければ、消費者金融は業種として成立しなくなる。金利が正常化したら産業としての消費者金融業が成り立たなくなるのは望ましくない。
上限金利の設定は、例えば「国債利回り+固定幅の利ざや」といった形にすべきだ。ドイツやフランスでは実際にそうした規定がおかれている。社会的見地からみて債務者保護という一定の歯止めは必要だが、市場連動型にすれば、経済合理性との両立は可能である。
2006年10月24日 日本経済新聞「経済教室」に掲載


