郵政民営化法は14日にも成立する。しかし株式会社化は民営化の第一歩にすぎない。郵貯、簡保の民営化が市場の活性化につながるか、ガリバー型寡占になるかは法律の運用次第である。株式完全売却までの期間を3年程度に短縮するとともに、その間の新規事業を限定するなど、民間との競争条件の均一化に細心の注意を払うべきである。
全国に展開されている2万5000近い郵便局ネットワークの大部分は、郵便事業ではなく、郵貯・簡保という金融事業からの収益で維持されている。そして郵貯・簡保の収益は、国からの年間約1兆円近い補助金で補てんされている。時に「郵政事業には一銭も税金を投入していない」と論じられることがあるが、これは事実に反する。以下では、まず郵政事業の収益構造を分析してみよう。
利益移転で黒字を確保
郵便は万国郵便条約により、全国で一定水準のサービスが受けられるように義務づけられている。料金は郵便事業全体で収支が合うように全国一律で決めているが、郵便の一通当たりコストは、利用者が集中する大都市圏で低く、顧客が少ない地方では高くなる。
この結果、大都市圏は黒字、地方は赤字になる。実際に2003年度決算では34道県が赤字で、黒字は13都府県にすぎない。このうち、東京都と周辺3県だけで利益の大半を稼ぎ出している。大都市から地方へ利益が移転されていることになる。
普通郵便と特定郵便局の間にも、似た構造がある。郵政公社は郵便局を「普通局」、郵便の集配をする「集配特定局」、集配をしない「無集配特定局」に分けて、三事業別損益を公表している(図)。なお、簡易局は管轄の普通局、特定局に含まれる。
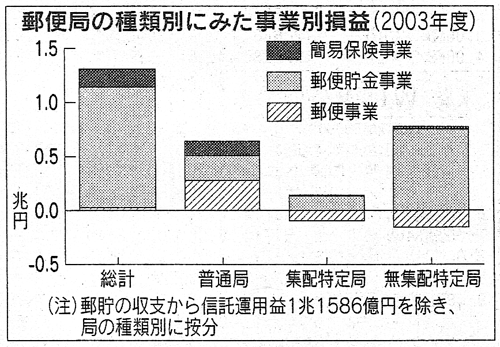
2005年3月末で1万5458ある無集配特定局では、郵便事業は切手の販売と小包の受け付け程度であり、郵便物の集配は普通郵便局に主に依存している(表1)。郵便事業の収支は、無集配、集配特定局とも赤字で、これを普通局の利益で埋め、全体でかろうじて黒字を保っている。
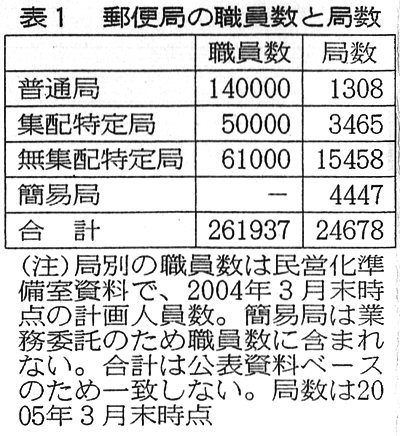
2003年度に大幅な黒字になった郵便貯金事業の収支をみると、がらりと変わる。3種類の郵便局とも黒字だが、その7割弱は無集配特定局が稼いだ利益である。簡保の収支は、全体は小幅な黒字だが、郵便局の種類別でほとんど差がない。このように特定局は実質的に郵貯、簡保に特化した拠点とみることができる。
郵貯事業は公社全体の利益をけん引している。2000年度までの3年間は大幅赤字に陥ったが、バブル崩壊後の高金利時に預けられた定額貯金が満期を迎えるにつれ、資金コスト負担が軽くなった。2001年度以降は黒字が定着している。
郵貯は2001年の財政投融資改革までは全額を資金運用部に7年満期の預託をしていた。民間金融機関であれば、貸し倒れリスクのない運用をする場合は7年物国債の市場利回りが上限になる。しかし郵貯の場合は、10年物国債利回りに0.2%程度上乗せした金利が適用されていた。残高に優遇金利分の約0.6%を掛けた金額が補助金となる。
公社の利益構造 国の補助に依存
2004年度にこの補助金がどのくらいあったかを推計したところ、5855億円となった。2001年度以降は預託が出来なくなったため、預託の満期が到来するにつれ、この補助金は減少していき、2007年度末までに消滅する。郵貯事業は2004年度の利益1兆2095億円の約半分に当たる補助金を失う計算になる。
表2にあるように、これ以外にも郵政公社は政府から様々な恩典を受けている。法人税や印紙税の免除、預金保険料の免除、生命保険契約者保護機構への負担金免除など合計9430億円にのぼるが、優遇金利の補助金は飛び抜けている。

郵政公社は2006年度までの中期計画で、郵貯事業で3兆9000億円の利益を目標にしている。年平均では9750億円になる。これを前提に、郵政民営化で政府からの恩典がなくなった場合、郵貯残高はどのくらい必要か。(1)何の対策もとらない(2)手数料収入を増やす(3)リスク資産を増やす(4)同時に(2)と(3)に取り込む――に分けて、シミュレーションした(表3)。
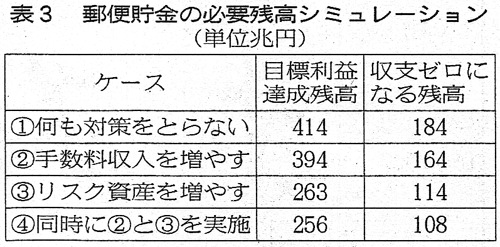
何も対策をとらない場合、目標利益の達成には、郵貯残高は414兆円と、現在(214兆円)の2倍弱の規模が必要になる。収支ゼロになる残高は184兆円。低金利の長期化で郵貯残高が過去5年、年10兆円近いペースで減っていることを考えると、赤字転落も現実味を帯びてくる。
(2)は振込手数料の大幅引き上げなどにより決済業務収入を2倍、金融商品の窓販手数料収入を3倍に想定、(3)は10年物国債利回りを0.2%程度上回る社債など長期固定利付き商品での運用比率を現状の2倍の20%、短期国債を2.8%上回る収益率の株式比率を2倍弱の5%に上げることを前提とした。手数料を伸ばすだけでは不十分だが、同時にリスク資産も増やす(4)の場合なら、目標利益達成の残高に実現性がある。収支がゼロに陥る郵貯残高も、現在の半分まで下がる。
赤字転落を回避するには、主力の定額貯金をやめて、定期貯金と通常貯金を主力商品にする選択肢もありうる。定額貯金は10年満期の固定金利貯金だが、半年経てばいつでも解約できる。金利リスクの管理が難しく、2000年度までのように逆ざやに陥る恐れがある。政府からの補助金がなくなれば、継続は困難になろう。
郵政民営化準備室は、郵貯事業は2016年度に総資産153兆円、税引き前利益2471億円になると試算している。郵貯残高の大幅な減少を見込みながら、これだけの利益を計画するのは、手数料拡大などの戦略や新規事業への進出を想定している証ともいえる。
郵政公社は日本郵政公社法で業務範囲が制限されている。銀行法上の主な業務で、公社が民間銀行と同様にできるのは、為替取引や国債の販売など一部にとどまる。貯金には1000万円の預金限度額がある。事実上、貸出業務などへ進出することもできない。
しかし、2007年10月に国有の株式会社になると、郵貯銀行は銀行法上の免許を受けたとみなされ、これまでやれなかった業務に参入できることになる。進出可能な業務は、株式会社化時点と2017年までの移行期間とで分けられる。
国有株式会社化直後は、有価証券売買や銀行代理店などが可能となる。移行期間中も1000万円の預入限度額は原則として残る。その一方で認可を受けさえすれば、住宅ローン、一般事業向け融資などの貸出業務や、店頭デリバティブ取引、証券仲介業などの証券業務も行うことが可能になる。
銀行業界からみれば、4大メガバンクの預金合計を上回る規模の巨大な国有銀行が出現し、預金だけでなく、貸し出しや窓販手数料などでも競合することになる。民主党は、これを「官業の焼け太り」と批判している。政府が直接間接に保有する株式がすべて売却され、完全民営化が行われた後の郵貯銀行は、民間銀行と何ら変わらない。
民主党の対案 無理が目立つ
その民主党は今国会で、郵政民営化法案の対案を提出した。郵便事業と業務を縮小した郵貯事業を、それぞれ公社、国有の銀行として維持することを柱としている。
この案には不備が目立つ。預入限度額の引き下げで郵貯残高を大幅に減らすとするが、郵政公社の収益を支えているのは郵貯である。郵貯に依存している地方特定局の人員や拠点の維持は国からの補助金なしでは困難になるだろう。
民主党は政府案との違いを出そうとして、無理な提案をしているように見える。むしろ民主党は小泉首相が当初に主張した郵便、郵貯、簡保の完全分離の早期実現という大方針からの後退を非難すべきではないか。
政府の民営化の進め方には問題がある。第1に、移行期間が10年間と長過ぎる。民間との競争条件の調整が困難となるからである。移行期間は3年程度に短縮すべきである。
第2に、制度上は政府保証がなくなっても国が大株主でいる間は、預金や保険契約は全額保護されていると国民が受け止める可能性が高い。政府は郵貯・簡保の株式を早急にすべて売り出し、民間に移す必要がある。持ち株会社などによる買い戻しも認めるべきでない。
第3に、既存契約は管理機構が保有し、新契約の勘定から形式的に分離される。しかし、管理機構は既契約の管理・運用を郵貯銀行、郵便保険会社に委託し、損益も郵貯銀行、郵便保険会社に帰属する。会計基準上、管理機構は新会社に連結すべきものであり、これは実質的な分離とは言えない。既契約は預金保険料や契約者保護機構への拠出金が軽減されているので、実質的な補助金を享受し続けるといえる。
第4に、郵貯、簡保の規模が民間金融機関に比較して大きすぎることに問題がある。郵貯銀行の支店網、口座数を考えれば、ネット通販の決済など小口決済業務を実質的に独占できる実力がある。4大生保合計に匹敵する資産を持つ簡保についても、顧客ベースは強大で、民間生保の強敵になろう。金融市場の競争条件を考えると、郵貯・簡保は民間の最大手以下の規模に分割した上で民営化するべきである。
政府保有株式をすべて民間に売却することで真の民営化を実現してこそ、初めて競争条件を同一化できるのである。
2005年10月14日 日本経済新聞「経済教室」に掲載


