2012年2月に、国務院は、戸籍取得の条件緩和を実施する都市を、従来の小都市から中都市にまで拡大する方針を発表した。戸籍制度改革の進展は、農民の社会的地位の向上につながるだけでなく、都市化の加速に拍車をかけることを通じて経済成長に寄与するだろう。
求められる戸籍制度改革
中国では1949年の共産党政権樹立以降、農村から都市への移動を厳しく制限する戸籍制度の下で、都市対農村という厳格な二元構造が作り上げられ、今日になっても農民の社会における地位は低い。中国の憲法では、公民は、高齢、病気あるいは労働能力喪失といった状況下で、国と社会から援助を受ける権利があり、国は公民がこのような権利を享受できるように、社会保障、社会救済および医療・衛生事業を整備しなければならないと規定されている。しかし実際には、農民は未だに国が提供する基本的な公共サービスを十分に享受できていない。
現在の戸籍制度では、農民は居住の自由が制限され、都市で就職先を見つけても、国内版ビザとも言うべき「暫住」の資格しか得られない。出稼ぎ農民(農民工)は、都市の戸籍を持っていないゆえに、雇用の機会が厳しく制限され、低賃金と長時間勤務といった劣悪な労働条件を強いられている。また、多くの名目で、税金や費用が徴収されるにもかかわらず、「暫住」の身分では医療や子供の義務教育をはじめとする都市住民が享受している公共サービスを受けることができず、失業しても失業保障の対象にはならない。さらに、都市部で生まれた自分の子供も農業戸籍のままになっており、都市戸籍(非農業戸籍)が与えられていない。
新たに発表された「分類の明確な戸籍移転政策」
農民と農民工の権利意識が高まる中で、戸籍制度改革を求める声が高まっている。しかしその一方で、戸籍制度改革により更なる人口の集中圧力にさらされ、また財政負担の増加が予想される一部の大都市は、強く抵抗している。双方の意見を考慮し、中国政府は一部の小都市を対象に、1997年から戸籍制度改革の実験を始め、2001年から全面的に展開した。そして、これまでの経験を踏まえて、国務院は、2012年2月23日に戸籍制度改革の対象を中都市に拡大する方針を盛り込んだ「積極的かつ着実に戸籍管理制度改革を推進することに関する国務院弁公庁の通知」(国弁発[2011]9号、以降「通知」)を発表した。
「通知」では、対象となる都市を大、中、小の三つに分類した上、その規模に比例して戸籍の申請基準が厳しくなるという「分類の明確な戸籍移転政策」が提示されている(注)。
まず、小都市の場合、合法的で安定した職業と住所(賃貸も含む)を有する人であれば、共に居住している配偶者、未婚子女、父母についても現地で「常住戸籍」を申請することができる。各都市は受容能力に合わせて、合法的で安定した職業の範囲、居住期間、合法的で安定した住所(賃貸も含む)の範囲といった具体的な条件を決めることができる。
次に、中都市の場合、3年以上安定した職業に就き、社会保障制度への参加が一定年限に達するという条件が追加される。
最後に、大都市の場合、人口規模を合理的範囲内にコントロールし、現行都市戸籍政策の実施と更なる整備を推進することが決められているが、明確な戸籍の申請基準は示されていない。
このように、「通知」は、小都市と大都市については従来の方針を確認するとともに、中都市の戸籍制度改革を加速させる方針を新たに加えたのである。
その上、「通知」には、「法に基づく農民の土地に関する権利・利益の保障」、「農民工の実際の問題の解決への注力」という方針も盛り込まれている。
前者に関しては、「農民の住宅建設用地の使用権と土地請負経営権は法律によって保護されている。現段階で、農民工の都市への定住は、住宅用地と請け負っている耕地・林・草地を放棄するか否かについて、必ず農民本人の意思を完全に尊重しなければならず、回収の強制も、形を変えた回収の強制もしてはならない。」と決められている。
後者に関しては、「すでに都市戸籍に転入した人々に対し、現地都市部住民と同等の権益の享受を保障しなければならない」上、「社会主義新農村の建設の加速、農村住民の生産と生活条件の改善、都市と農村における公共資源の均衡配置を通じて、次第に都市と農村の基本的公共サービスの均一化を実現させ、都市化と新農村建設の相互促進と調和の取れた発展を促す。都市と農村のどちらに居住するかという農民の選択権を尊重する。」と明記されている。
戸籍制度改革で促される都市化
戸籍をはじめとする人口の移動を妨げる要因が徐々に取り除かれていることを背景に、大規模な労働力の移動はすでに起きている。「中華人民共和国2011年国民経済と社会発展統計公報」(中国国家統計局、2012年2月22日)によると、2011年末には、居住地と戸籍登録地が乖離する「流動人口」は2.30億人に達しており、そのうち、農民工は1.59億人に上る。主に労働力の農村から都市への移動を反映して、1978年から2011年にかけて、都市人口は1.72億人から6.91億人に増えている一方で、農村人口は7.90億人から6.57億人に減っている。その結果、都市化率(都市人口/総人口)は17.9%から51.3%に上昇している(図1)。
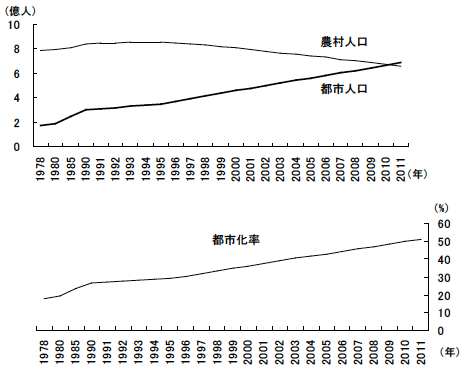
それでも、中国の都市化率は、先進国をはじめとする諸外国と比べて依然として低い(図2)。今後、さらなる戸籍制度改革の進展により、都市化と経済発展との好循環が定着していくことが期待される(BOX)。
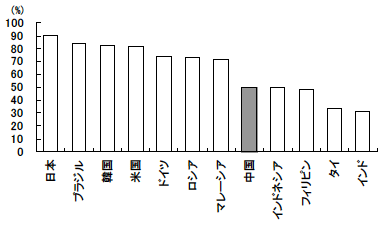
BOX:経済成長を牽引するエンジンとなる都市化
都市化は、供給と需要の両面から、中国経済の高成長を牽引している。
まず、供給の面では、都市化は第二次産業と第三次産業の発展を通じて、多くの雇用機会を創出し、農村の余剰労働力を吸収している。また、生産性の低い第一次産業から生産性の高い第二次と第三次産業へ労働力が移転することは、経済全体の生産性を押し上げる。さらに、経済活動の地域的な集中から発生する集積効果も生産性を高めている。都市化に伴う生産性の上昇は、経済成長、ひいては所得の上昇に大きく寄与している。
一方、需要の面では、戸籍制度改革を経て、出稼ぎ労働者が、家族と共に都市部に定住できるようになれば、住宅への需要は拡大するだろう。人口の流入に合わせて、受け入れ側も交通、電気、水道といったインフラ分野への投資を増やしながら、教育、医療などの公共サービスも充実させていかなければならない。このように、都市化は、内需拡大の有効な手段でもある。
これらを反映して、中国では、都市化が進んでいる地域ほど、一人当たりGDPが高いという傾向が顕著である(図)。
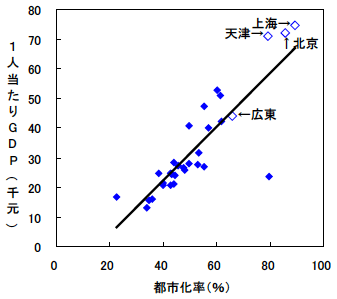
2012年5月28日掲載


