インフレも食料価格の上昇も景気次第
中国では、消費者物価指数(CPI)で見たインフレ率が、2008年9月のリーマンショック以来の高水準に達している。これは主にCPI指数の約3分の1のウェイトを占める食料価格の上昇を反映したものである(図1)。2011年1月の食料価格上昇率は10.3%と、インフレ率の4.9%を大きく上回っている。今後のインフレの行方を占う際、食料価格の動きはその鍵になると言える。
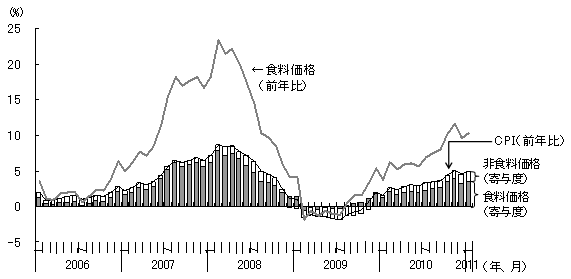
中国では、食料価格は、天候や海外市場の動向などに大きく左右され、国内の景気動向とほとんど関係がないとされているが、このような認識は必ずしも正しくない。実際、実質GDPで見た経済成長率、賃金、食料価格(いずれも前年比)の間では、一定の連動性が見られ、変数間のタイムラグを考慮すると、相関関係がいっそう高くなる(図2)。
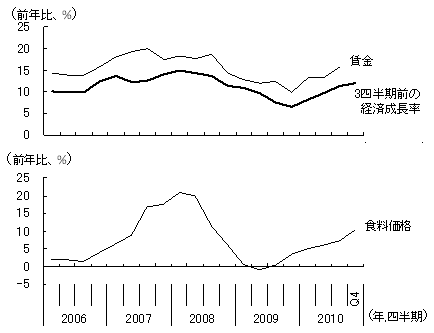
景気変動は、賃金変動を通じて、食料価格(ひいてはCPI)の変動をもたらしていると見られる。この仮説を検証するために、①経済成長率と賃金上昇率の関係、②賃金上昇率と食料価格上昇率の関係、そして③経済成長率と食料価格上昇率の関係を、変数間のタイムラグを考慮した上、2006年第1四半期以降の四半期データを使って回帰分析で確認した。その結果は次のようにまとめられる(表1)。
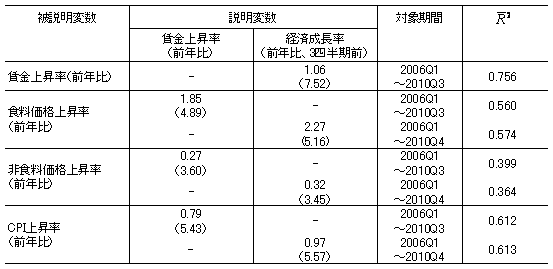
まず、賃金上昇率(前年比)は、3四半期前の経済成長率と緊密に連動している。3四半期前の経済成長率が1%上昇すれば、今期の賃金上昇率は1.06%上がるという後者の前者に対する弾力性が得られ、賃金は景気の変動に対して敏感に反応することが確認できた。
また、賃金の上昇は、食料価格を押し上げるが、両者の間にタイムラグは見られない。食料価格の賃金変動に対する弾力性は、1.85%と推計される(図3)。これは、CPI、または非食料価格の賃金上昇に対する弾力性(それぞれ0.79%と0.27%)より高くなっている。
(2006年Q1~2010年Q3)
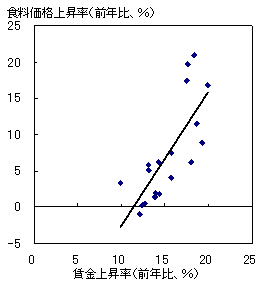
最後に、食料価格上昇率(前年比)は、賃金上昇率と同様に、3四半期前の経済成長率と緊密に連動している。3四半期前の成長率が1%上昇すれば、今期の食料価格上昇率は2.27%上昇するという結果が得られた。これは、CPIと非食料価格(いずれも上昇率)の経済成長率に対する弾力性(それぞれ、0.97%と0.32%)より高くなっている(注1)。
バラッサ=サミュエルソンの仮説による説明
経済成長率、賃金、食料価格(ひいてはCPI)のこのような関係は、国際経済学の教科書にも登場するバラッサ=サミュエルソンの仮説に沿って説明することができる(注2)。
すなわち、(国際市場で取引され、生産性の伸びが高い)貿易財と(国際市場から遮断され、生産性の伸びが鈍い)非貿易財という二つの部門からなる経済では、経済成長が加速すると、労働に対する需要が増え、賃金上昇、ひいてはインフレ圧力が高まる。貿易財部門においては、賃金が上昇しても、価格上昇圧力が比較的高い生産性の上昇によって吸収される上、その産出が国際市場での競争にさらされるため、コストの上昇は価格に転嫁されにくい。これに対して、労働力の部門間の移動が自由であれば、非貿易財部門では、生産性の上昇が低くても、賃金が貿易財部門並に上昇し、その産出が国際競争にさらされないため、コストの上昇は価格に転嫁されやすい。その結果、主に非貿易財価格の上昇という形でインフレが加速するのである。
一般的に、製造業部門や食料を生産する農業部門は貿易財部門に、サービス部門は非貿易財部門にそれぞれ分類される。しかし、中国の場合、食料は、自給率が95%を超える高い水準にあり、海外の市況の影響をそれほど受けていないことを考えれば、貿易財よりも、非貿易財としてとらえるべきであろう(注3)。その場合、先述の実証分析の結果が示しているように、経済成長の加速に伴う賃金上昇は、主に食料価格の上昇を通じて、物価を押し上げるのである(注4)。
転換点を迎えようとするインフレ率
中国では、リーマンショック以降に実施された4兆元に上る内需拡大策の効果が薄れてきたことに加え、インフレを抑えるために、金融政策のスタンスも緩和から引き締めに転じたことを受けて、経済成長率は2010年第1四半期の11.9%をピークに緩やかに低下してきている。賃金と食料価格、ひいてはCPIの上昇率が経済成長率より3四半期遅行することを合わせて考えれば、これまで上昇してきたインフレ率は、そろそろ転換点を迎えると思われる。
2011年2月25日掲載


