最優先課題となったインフレの沈静化
中国経済は緩やかに減速しながらも、比較的高い成長率を維持している。その一方で、インフレが加速しており、物価の安定が成長の維持に取って代わって政策の最優先課題となった。
リーマン・ショックを受けて、中国は、一時、輸出が大幅に落ち込み、景気後退を余儀なくされた。これに対して、政府は4兆元に上る景気対策をはじめとする、拡張的財政・金融政策を実施し、これらが功を奏する形で、先進国に先駆けて回復してきた。2009年第1四半期に6.5%に落ち込んだ経済成長率(実質、前年比、以下同じ)は、2010年上半期に11.1%と再び二桁台に乗った(そのうち、第1四半期は11.9%、第2四半期は10.3%)。これを背景に、インフレ率(前年比、以下同じ)が2010年第4四半期に4.7%まで上昇し、当局は金融政策のスタンスを次第に緩和から引き締めに転換させた。それまでの景気対策の効果が薄れたことも加わり、成長率は2010年下半期に9.7%に低下した(そのうち、第3四半期は9.6%、第4四半期は9.8%)。それでも、2010年年間の成長率は、2009年の9.2%を上回る10.3%に達している。需要項目別では、消費と投資といった内需が減速しているが、世界経済が回復する中で、外需が持ち直していることは、成長率を押し上げた(図1)。
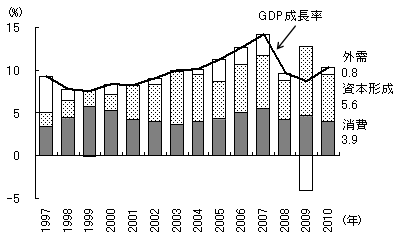
成長率とインフレ率の動きを中心に、リーマン・ショック以降の景気動向を追ってみると、中国経済は、低成長・高インフレというスタグフレーション期(2008年後半)、低成長・低インフレという後退期(2009年前半)、高成長・低インフレという回復期(2009年後半)を経て、2010年には、高成長・高インフレという過熱期に入っている(図2)。これまで、中国では、インフレ率は成長率より3四半期遅れて連動するという傾向が見られた。これをベースに推測すると、成長率が2010年第1四半期にピークを打ってから減速していることに対応して、インフレ率は同第4四半期をピークに、今後は低下傾向に転じるだろう(図3)。
― GDP成長率とインフレ率の推移 ―
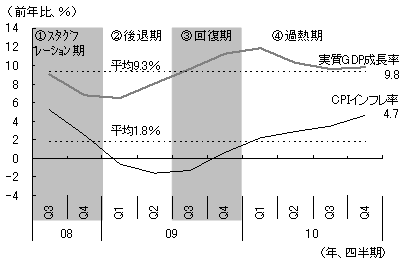
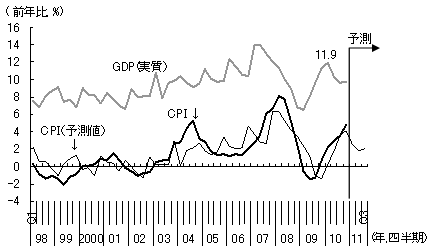
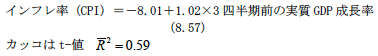 推計期間 1998年第1四半期(Q1)~2010年第4四半期(Q4)
推計期間 1998年第1四半期(Q1)~2010年第4四半期(Q4)景気の減速に加え、これまで当局が採ってきた金融引き締め策も、インフレに歯止めをかけている。まず、2010年以降、預金準備率が7回にわたって引き上げられ、現在19.0%という史上最高の水準にある。また、銀行の預金・貸出基準金利も2010年10月と12月の2回にわたって計0.5%切り上げられた。さらに、世界的金融危機によって一時中断された人民元の切り上げも、2010年6月に再開され、それ以来、人民元は年率6%程度でドルに対して上昇している。これを受けて、ピーク時(2009年11月)に29.7%に達したマネーサプライ(M2)の伸び(前年比)が、2010年6月以降は20%以内に収まっており、インフレ率も、2008年7月以来の高水準となった11月の5.1%から、12月には4.6%に低下している。
これから、中国経済は、減速が続く一方で、インフレがピークアウトしながらも比較的高い水準で推移し、高成長・高インフレという過熱期から、低成長・高インフレというスタグフレーション期に移る可能性が高い(図4)。2011年の後半には、インフレが沈静化に向かい、低成長・低インフレという後退期に入ると予想される。その段階になると、金融緩和の余地が生じてくるだろう。
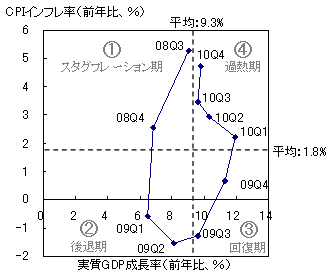
政治的景気循環に注目
インフレ動向に加え、今後の政治の日程も景気を左右する重要なファクターとなる。
中国における景気変動は、中国共産党全国代表大会(党大会)を中心に、「政治的景気循環」ともいうべき5年サイクルが見られる。経済成長率が党大会の前年にボトムを打ち、党大会の年にピークを迎えるというパターンが定着しており、近年になってこの傾向はさらに強くなっている。1981年から2010年までの中国の平均GDP成長率は10.1%だが、党大会が開催される年の平均は11.3%とこれを上回っており、前回の2007年に至っては14.2%に達した(図5)。
― GDP成長率の推移 ―
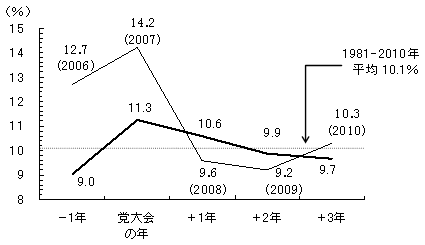
中国における景気変動が一種の政治的景気循環の体をなし、さらにそれが強まってきた理由として政治体制の変化が挙げられる。すなわち、毛沢東や鄧小平に代表される革命世代が政治の表舞台から去った後、共産党は、統治の正当性を、指導者のカリスマよりも、経済成長を通じて国民の所得を向上させることに求めざるを得なくなった。それ故に、重要な人事を決める一大政治イベントである党大会の開催に合わせて、拡張的なマクロ経済政策が採られがちである。また、中央のみならず、地方のレベルにおいても、幹部の評価と選抜の指標として所管地域の経済成長率が重要視されていることも、このような傾向に拍車をかけている。
2010年10月に行われた中国共産党第17期中央委員会第5回全体会議(五中全会)において、習近平国家副主席が中央軍事委員会副主席に選任され、胡錦濤党総書記・国家主席・中央軍事委員会主席の後継者としての地位を固めた。2012年秋に開催される第18回党大会において、胡錦濤氏の党総書記としての2期計10年の任期が満了し、党の指導部が刷新され、2013年3月の全国人民代表大会において国家主席や、総理など、政府のトップも交代される予定である。このような政治の日程に合わせて、金融緩和とともに、拡張的財政政策も実施されると予想され、これを受けて、2012年に景気は本格的回復に向かうだろう。
2011年1月31日掲載


