日本経済は、1990年のバブルの崩壊以降、長期低迷に陥っており、いまだその後遺症から完全には回復していない。バブルの発端は1985年9月のプラザ合意に遡る。プラザ合意を受けて円高が急速に進む中で、競争力の落ちた輸出産業を助け、また内需を拡大させるために、日銀が1986年1月から1987年2月までに5回にわたって公定歩合を5.0%から2.5%に引き下げ、過去最低となった金利水準は1989年5月まで続けられた。これにより、カネ余り現象が起こり、資金が株式市場や不動産市場へと向かった。その結果、バブル経済が形成され、バブルの崩壊とともに日本経済は「失われた20年」に突入したのである。
中国においても、金融緩和を背景に、不動産などの資産価格が急上昇しており、バブルの様相を呈している。中国は、日本の轍を踏まないために、その経験から何を学ぶべきだろうか。
資産価格も金融政策の重要な変数の1つ
まず、中央銀行の目標は、通貨価値(物価)の安定と金融システムの安定(信用秩序の維持)にあるが、資産価格の変動は、銀行の不良債権の拡大などを通じて、金融システムの不安定要因になることに鑑みれば、金融政策を策定する際、CPI(消費者物価指数)で見た物価だけでなく、株式や不動産価格の動向にも目を配るべきである。
この点を巡って、「行き過ぎた資産価格の上昇に伴う金融システムの不安定化を回避するため、仮に物価が安定していても、金融引き締めを行うべきだ」というBISの主張と、「金融政策の運営に当たり、あくまでも物価の安定に重点を置く」というFRBの主張が対立している。バーナンキFRB議長は、後者を代表する論者として知られているが、今回の金融危機を経て、スタンスをやや軟化させている。
日本では、1980年代後半の金融緩和を受けて、資産価格が大幅に上昇したが、景気の過熱や物価の上昇が顕著ではなかったため、当局には引き締め政策を急がなければならないという意識がほとんどなかった。インフレ圧力が高まったことを受けて、1989年に日本銀行は金融引き締めに転じたが、経済のバブル化はすでに進行していた。このように資産価格と物価の変動の間にかなりタイムラグがあることを考えれば、当面の物価動向にだけ注目して金融政策を運営すると、バブル防止には手遅れになる可能性がある。
中国はリーマン・ショック以降、思い切った金融緩和策を採ってきた。これを受けて、不動産価格の上昇のペースが加速している。70大中都市住宅販売価格は2月には前年比10.7%に達しており、警戒すべき水域に入りつつある。中国では、今回のように、金融緩和期において、株価や不動産価格など、資産価格が物価より先行して上昇する傾向が観測されている(図1)。したがって、資産価格を金融政策のターゲット変数に加えることは、バブルを防ぐためだけでなく、物価の安定にも役立つ。
-リーマン・ショック以降の状況-
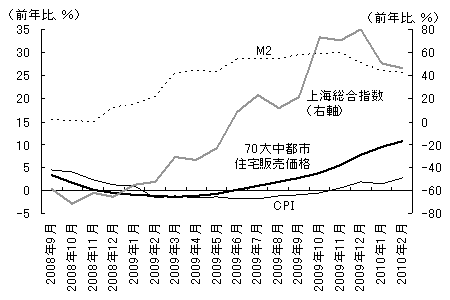
注目すべき不動産関連融資の動向
次に、バブルの拡大は信用の膨張を伴うが、中央銀行はその量的伸び率だけでなく、不動産関係を中心に融資の構成の変化についても注意を払う必要がある。
バブル期の日本においては、ノンバンク、不動産、建設の3業種の合計で銀行融資全体の25%に達していた。特に多くの不動産関連融資が、当局の監督が届かない「住専」といったノンバンクを経由したことは、不動産バブルの膨張に拍車をかけた一方で、バブル崩壊後の不良債権問題を深刻化させた。
中国における不動産関連の融資は住宅ローンを含んでも、銀行融資全体の20%程度にとどまっており、バブルの時代の日本と比べれば、まだ低い。しかし、2009年の新規住宅ローンの規模は一気に2008年の5倍になった(中国人民銀行、『中国貨幣政策執行報告、2009年第4四半期』、2010年2月11日)。このことは、警戒すべき現象である。また、銀行融資の内どの程度が、地方政府が設立した投資会社を経由して不動産市場に流れているかについても、厳しくモニターすべきである。
先行きを展望した金融政策の重要性
さらに、バブルが発生してから時間が経てば経つほど、それが崩壊した時の被害は大きくなり、政策対応もより困難になるため、当局は、経済が抱えるリスクを極力、潜在的段階で把握し、先行きを展望した(forward-looking)金融政策を実施すべきである。この点について、後に日本銀行が「中央銀行にとって(1980年代後半の)バブルの経験から得られる最大の教訓」だと「反省」している(翁邦雄・白川方明・白塚重典、「資産価格バブルと金融政策:1980年代後半の日本の経験とその教訓」、IMES Discussion Paper Series No. 2000-J-11,日本銀行金融研究所、2000年)。
当時の日本において、国内からは円高への懸念、米国からは経常黒字縮小と内需拡大の要請があった。また、インフレは落ち着いていたため、金融引き締めに対する世論の反対が根強く、資産バブルへの対応が遅れてしまった。金融引き締めがスタートしたのは資産価格の急激な上昇が始まってから3年以上経った89年5月であった。日経平均はプラザ合意の85年9月末から89年4月末の間に約2.7倍に、東京圏商業地地価も85年から88年の間に約2.5倍になった。引き締めがスタートしてからも、株価は半年以上、地価は2年以上さらに上昇を続けた。
中国では、不動産価格が急騰している上、CPIで見たインフレ率も去年の-0.7%から今年2月には2.7%(前年比)に加速している。中国ではインフレ率がGDP成長率に3四半期ほど遅行するという傾向が観測されている。景気の急回復(昨年第4四半期GDP成長率は10.7%)を受けて、インフレ圧力は今後さらに高まると予想される。バブルの膨張とインフレの高騰を防ぐために、利上げを含む金融政策の「出口戦略」が適時に実施されることが求められている(BOX)。
流動性膨張の原因となる為替介入
最後に、中央銀行の政策の重点を為替レートの安定に置こうとすると、為替市場への介入が必要となり、これにより金融政策の独立性が大幅に制約されることになる。
日本では、プラザ合意を受けて円高が進行した。1987年2月にドル高是正という目標が達成されたという認識の下で、G7参加国間でドルの安定を目指す「ルーブル合意」が交わされたことをきっかけに、日銀は積極的にドル買い介入を行うようになった。これは、金融緩和とともに、流動性、ひいては資産バブルの膨張に拍車をかけた。このように、バブル経済が発生した原因は、円高そのものではなく、円高を阻止するための為替介入と、円高に伴うデフレ圧力を和らげるための金融緩和にあると理解すべきである。
中国においても「元高」を抑えるための為替介入が流動性膨張の一因となっている。経済を安定化させるために、為替レートに柔軟性をもたせることを通じて、金融政策の独立性を高めていかなければならない。人民元の対ドルレートは2008年7月以降、危機対応の一環として、ほぼ固定されてきたが、危機が収まった今、金融政策と同様に、為替政策についても出口戦略を用意しておく必要がある。言うまでもないことだが、これは米国から圧力があったからではなく、中国自身のために行うべきことである。
BOX 本格化する中国における金融政策の出口戦略
安定成長を持続させるために、中国当局はこれまで採ってきた拡張的金融政策の出口戦略を実施し始めている(中国人民銀行、『中国貨幣政策執行報告、2009年第4四半期』、2010年2月11日)。
まず、中国人民銀行は昨年4月と5月に、商業銀行に対して融資急拡大に伴う信用リスクの上昇に注意するように呼びかけ、年央以降さらに窓口指導を強化した。続いて7月には1年物の中銀手形の発行を7ヵ月ぶりに再開し、融資の伸びが行き過ぎたと判断される一部の銀行を対象に、(市場金利を下回る利回りで)中銀手形の購入を義務付けるようになった。
これを受け、貸し出しの伸び(前年比)は昨年6月のピーク時の34.4%から、今年2月には27.2%まで低下しており、マネーサプライ(M2)の伸びも、昨年11月の29.7%をピークに今年2月に25.5%に鈍化している。さらなる金融引き締めに向けて、今年の3月に開催された全国人民代表大会の「政府活動報告」において、M2の伸びを17%に抑えることが年度の目標として定められている。
金融引き締めの一環として、中国人民銀行は、年明け後、大手銀行に適用される法定預金準備率を2回にわたって計1.0%ポイント引き上げた。金融機関が法定準備率に対応する分しか準備金を持っていなければ、これにより6000億元(60兆元に上る預金の1%)の資金が凍結されることになる。しかし、2009年末現在、金融機関の超過準備率(保有する準備金のうち、法定準備を上回る部分の預金残高に対する比率)が3.13%に達しており、対象となる銀行が直ちに貸し出しを回収し、準備金に当てなければならない状況には至っていないため、現段階では、預金準備率の引き上げによる引き締め効果は限定的である。
今後、インフレ率がいっそう高まるにつれて、利上げを含むさらなる引き締め策が採られるであろう。これまでの経験から判断して、消費者物価指数でみたインフレ率が4%を超えることは、利上げが実施される目安となる。その時期は今年年央になるだろう。
2010年4月12日掲載


