中国は、1978年にほぼ鎖国の状態から改革開放路線に転換した。それ以来、貿易の自由化と直接投資の受け入れを通じて世界経済との一体化が進んでおり、2001年の世界貿易機関(WTO)加盟を経て、そのペースは一段と加速している。中国は貿易大国にとどまらずに、貿易強国に向けて邁進している。高成長を背景とするGDP規模の拡大も加わり、中国は、「世界の工場」としてだけでなく、「世界の市場」としての存在感も増している。
貿易大国から貿易強国へ
中国の輸出入は、1978年には計206億ドルと世界第29位であり、2001年でもまだ世界第6位だった。だが2012年になると、輸出は2.05兆ドル、輸入は1.82兆ドルに達し、輸出入合計では3.87兆ドルと、米国(輸出は1.55兆ドル、輸入は2.28兆ドル、輸出入計では3.82兆ドル)を抜いて世界1位となっている。
貿易規模の急拡大により、世界貿易に占める中国のシェアは高まっている。2000年から2012年にかけて、輸出は、3.9%から11.2%へ、また、輸入は3.4%から9.8%に上昇している(図1)。これに対して、米国と日本のシェアは輸出においても、輸入においても、大幅に低下してきている。
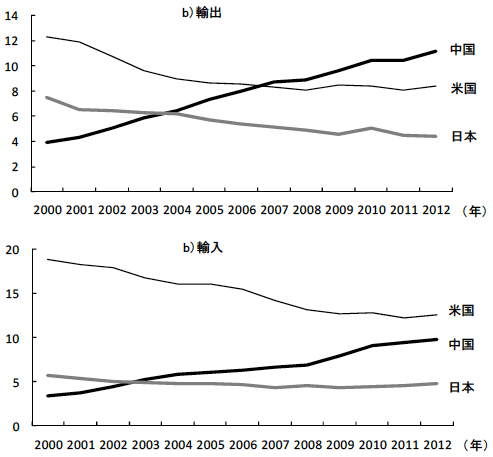
近年、中国では貿易額が拡大しているだけでなく、その構造の高度化も進んでいる。
まず、輸入においても、輸出においても、加工貿易のシェアが低下している。その代わりに、より付加価値の高い一般貿易のシェアが上昇している。特に、輸出よりも輸入における加工貿易のシェアの低下が目立っており、これを反映して、加工貿易の付加価値比率が高まってきている。
また、輸出入の品目別構成の変化も貿易構造の高度化を示している。
日本をはじめ多くの国では、経済発展とともに輸出の中心が一次産業から工業製品へ、工業製品の中では労働集約型製品から資本・技術集約型製品へと移っていくというパターンが見られる。これは主要品目の特化係数(輸出と輸入の差を輸出と輸入の和で割ったもの、その値が大きいほど国際競争力が強いことを示す)の推移を追うことで確認できる(図2)。具体的に、一次産品(SITC0―4部)、一般製品(同5、6、8、9部、機械類を除く製品)、機械類(同7部)のそれぞれの特化係数の相対的大きさによって、一国の貿易構造は、発展途上国型、未成熟NIEs型、成熟NIEs型、そして先進工業国型という4つの段階に分類することができる。
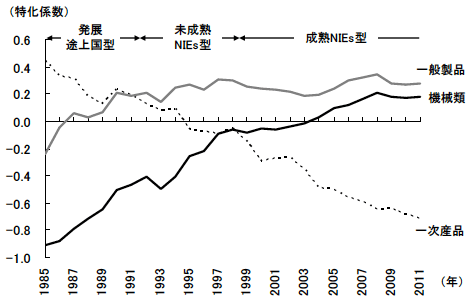
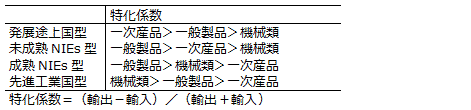
この枠組みに沿っていえば、1980年代の初め、改革開放政策に転じた当初、中国は一次産品を輸出し、機械類を輸入する典型的な発展途上国型の貿易構造を持っていた。香港と台湾から労働集約型産業の移転が進むにつれて、衣料品を中心に中国の一般製品の競争力が急速に伸び、特化係数で見て1992年には一次産品を上回るようになった。これをもって、中国の貿易構造は発展途上国型から未成熟NIEs型に移行した。
これよりやや遅れて機械産業の特化係数も徐々に上昇し、1999年には一次産品のそれを抜き、中国は成熟NIEs型の段階に入った。2001年のWTOへの加盟をきっかけに、中国は貿易構造の高度化が一層進み、先進工業国型に近づいている。このように、中国は貿易大国にとどまらずに、貿易強国に向けて邁進している。
軽工業から重工業へ
中国では、貿易構造だけでなく、工業部門全体の構造も高度化が進んでいる。1949年以降の工業発展は、計画経済時代の重工業化、改革開放初期の脱重工業化を経て、1990年代末から再重工業化の段階に入っている。
1950年代にはまだ農業国であった中国は、短期間に先進工業国に追いつくために重工業優先の発展戦略をとっていた(林毅夫、蔡昉、李周、1994)。発展段階が低く、資本と貯蓄が乏しいという厳しい状況からスタートしたために、比較劣位にあった資本集約型の重工業の育成には、政府の強い介入のもとで資源をできるだけ低価格で重工業部門に集中せざるを得なかったのである。具体的には金利、賃金、エネルギー・原材料・消費財の価格を人為的に低く抑え、市場に代わって政府が計画に基づいて資源を配分する一方で、国有企業(当時は「国営企業」と呼ばれていた)が生産の担い手となった。
しかし、こうした計画経済においては企業経営の自主性が認められず、利潤獲得のインセンティブと労働者の勤労意欲が失われた。また、軽工業やサービス業が犠牲となり、歪んだ産業構造のもとで、産業全体の生産性が低下した。その結果、中国は先進国に追いつくという目標を達成するどころか、低成長と国民の生活水準の低迷を長引かせることとなり、1970年代後半にはついに新しい発展戦略への転換を迫られるようになった。
計画経済の失敗という教訓を踏まえて、1978年以降の経済改革において、政府は企業にインセンティブを与えるようなミクロ面の改革から着手した。国有企業では、自主経営権が拡大され利益の内部留保が認められるようになり、その枠も段階的に拡大してきた。一方、農業部門においても人民公社が解体に向かった。
これにより、経営者や労働者、農民の生産意欲が高まり、生産性が急上昇した。計画分を超えた投入(原材料、労働力、資金)の調達や産出の販売経路を価格メカニズムの働く市場に求めざるをえなくなり、企業自主権の拡大は必然的に市場経済の発展につながった。一方、外資企業や郷鎮企業など非国有企業も奨励され、市場経済の担い手として登場してきた。市場経済の拡大と深化により、重工業に偏った産業構造が是正され、比較優位に沿った形で、軽工業が産業発展と輸出を牽引する担い手として力を発揮するようになった。
1990年代末になると、重工業が急速に成長し、再び経済成長のエンジンになってきた。重工業の工業生産に占めるシェア(一定規模以上の企業)は、1998年の57.1%から2011年には71.8%に上昇している(図3)。すでに工業化を遂げた欧米や日本などの先進国が経験してきたように、重工業化は、所得の上昇に伴う消費構造の高度化や、都市化とインフラ投資の拡大、世界の工場化に伴う機械と設備への需要拡大による必然的結果である。経済発展を目指す中国にとっても、重工業化は避けて通れない道であり、この段階はすでに到来している。
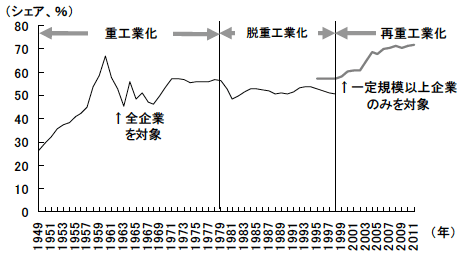
政府による計画と国有企業の主導で進められていたかつての重工業化とは対照的に、今回は市場メカニズムと民営企業や外資企業といった非国有企業が大きな役割を果たしている。このように、30年余りにわたった高成長を経て、中国にとって重工業は比較劣位産業から比較優位産業に変わったのである。
現在、中国における重工業の発展を牽引しているのは鉄鋼と自動車である。
1978年に中国の粗鋼生産量はわずか3,178万トンだったものが、1993年には8,956万トンとなり、中国は米国を抜いて世界第2位の粗鋼生産国となった。さらに、わずか3年後の1996年になると、中国の粗鋼生産量は1億トンの大台を突破し、それまで1位だった日本を抜いて世界最大の規模となった。2001年のWTO加盟を経て、中国の鉄鋼業の発展はさらに加速し、2012年の粗鋼生産量は7.2億トンに達し、世界全体の半分近くを占めるようになった。
鉄鋼産業に加え、所得の上昇に伴う需要の拡大と海外メーカーの進出を背景に、中国の自動車産業も爆発的発展を遂げてきた。改革開放に転換する前の1978年には、中国における自動車生産台数はわずか15万台しかなかったが、その後、経済の高成長とともに自動車産業も急速に発展してきた。特に、WTO加盟を経て、中国の自動車産業は黄金期を迎えた。中国の自動車生産台数は、2001年の233万台から、2012年には1,927万台に増えており、世界一の規模となっている(注1)。
このように中国における産業の中心は軽工業から重工業に移っているが、その過程において、一部の産業では生産と雇用の縮小が避けられない。現に2008年以降、「人民元高」や世界的金融危機などの影響を受けて、労働集約型産業は深刻な不況に陥っており、産業空洞化を懸念する声が内外から上がっている。しかし、鉄鋼と自動車をはじめとする重工業の急成長を合わせて考えれば、これは「産業の空洞化」ではなく、「産業の高度化」に伴う陣痛としてとらえるべきである(図4)。
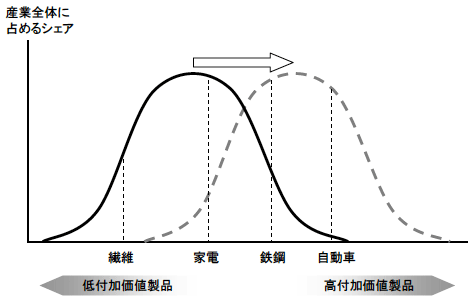
チャイナ・アズ・ナンバーワンへの道
中国の貿易や個別産業の規模が巨大化しているだけでなく、GDP規模はすでに2010年に日本を上回るようになり、米国を抜いて世界一になる日も近づいている。
改革開放当初の1980年の中国のGDP規模は、3034億ドルと、米国の10.9%しかなかったが、2012年には52.5%まで上昇しており、米中GDP格差は大幅に縮小してきている(図5)。しかし、そのスピードは時期によって大きく異なる。実際、中国のGDP(ドル換算)の対米国比(米中GDP比)は、1980年から1986年にかけて低下し、その後上昇傾向に転じたが、1996年になってようやく1980年の水準に回復した。米中GDP比の上昇ペースは、21世紀に入ってから、中でも2005年に中国が「管理変動相場制」に移ってから速まってきた。これは、主に中国における次の構造変化を受けて、(内外価格差を考慮した)人民元の実質対ドルレートが長期の下落傾向から上昇傾向に転じたことを反映している。
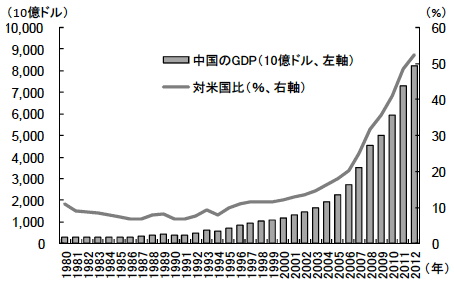
まず、労働力は過剰から不足へと急速に変わっている。一般的に、高成長している国では、貿易財部門(工業)における生産性の上昇は、貿易財部門だけでなく、生産性の上昇があまり見られない非貿易財部門(サービス業)の賃金水準も押し上げる。貿易財部門においては生産性の上昇に見合って賃金が上昇しても工業製品の価格が上昇しないが、非貿易財部門においては生産性の上昇を上回る賃金の上昇はサービス価格の上昇、ひいては一般物価と実質為替レートの上昇をもたらす(「バラッサとサミュエルソンの仮説」)。中国においては、長い間、農村部が余剰労働力を抱えていたために、貿易財部門における生産性が上昇しても、賃金がそれほど上昇しなかったが、近年、農村における余剰労働力が解消されるにつれて、高成長はようやく賃金上昇を通じて人民元の実質対ドルレートを押し上げるようになった。
また、中国では、長期にわたって、国際競争力の欠如を反映して、輸出(供給)拡大は輸出価格の低下と交易条件の悪化を招き、それを通じて、人民元の実質対ドルレートを押し下げていた。しかし、近年、中国の輸出競争力の向上とともに、中国製品に対する需要の増大は輸出価格の上昇と交易条件の改善を通じて、人民元の実質対ドルレートを押し上げるようになった。
中国のGDP規模がいつ米国を抜くかは、両国の実質GDP成長率と、人民元の実質対ドルレートの今後の動向に依存する(注2)。ここでは、「楽観シナリオ」、「標準シナリオ」、そして「悲観シナリオ」に分けて推計してみよう。
まず、経済成長率について、生産年齢人口の減少や、農村部における余剰労働力の解消を背景に、中国は1970年代末に改革開放に転換してから続いてきた10%前後の高成長が維持できなくなる。しかし、平均寿命や、乳児死亡率、第一次産業の対GDP比、エンゲル係数、1人当たり電力消費量などの経済指標から判断して、中国は発展段階において依然として先進国より40年ほど遅れている。このため、海外からの技術導入が容易であることや、産業の高度化を通じて生産性を高めていく余地が十分残っているという後発の優位性を発揮できれば、米国より高い経済成長率が当面維持できるはずである。ただし、中国の発展段階が先進国に近づくにつれて、後発の優位性が薄れ、成長率も低下するだろう。
これを踏まえて、中国の2020年までの成長率は、「楽観シナリオ」においては年率8%、2021年から2030年までは同6%、2031年以降は同5%、「標準シナリオ」においては、それぞれ同7%、5%、4%、「悲観シナリオ」においては、それぞれ同6%、4%、3%とする。また、比較の対象となる米国の成長率は今後年率2.5%とする。
一方、為替レートについては、人民元は実質ベースの年率で、楽観シナリオにおいては年率3%、標準シナリオでは同2%、悲観シナリオでは同0%とする。これらの前提の下で試算すると、中国のGDP規模が米国を抜く時期は、楽観シナリオでは2020年、標準シナリオでは2024年、悲観シナリオでは2078年となる(図6)。それを待たずに、2001年以降、中国の世界経済成長率への寄与度はすでに米国を上回っている(図7)。
-米国GDPに対する中国GDPの比率(試算)-
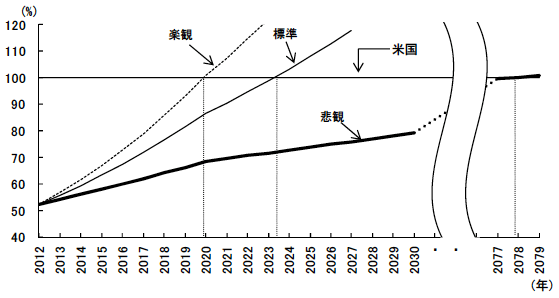
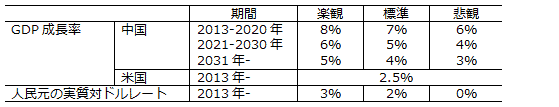
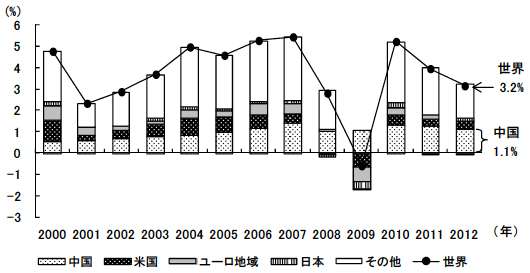
2012年中国の寄与度(1.1%) = (7.8%) × (14.3%)
2012年米国の寄与度(0.4%) = (2.2%) × (19.0%)
2013年5月8日掲載


