中国は、市場経済化の一環として金利の自由化を進めてきた(注1)。このプロセスは、今年の6月と7月には銀行を中心とする金融機関の貸出金利と預金金利の変動幅が拡大されることで、大きく前進している。
金利の自由化は、資金の利用効率の改善、資金の銀行部門への還流、銀行の商品・サービスの多様化、金融政策の有効性の向上につながるなど、メリットが多い一方で、銀行の収益の悪化、金利変動リスクと信用リスクの上昇、預金量の変動などを通じて、金融システム全体を不安定化させる恐れがある。金利の自由化に伴うリスクを抑えながら、そのメリットを最大限に活かすために、銀行のコーポレート・ガバナンスの強化と経営管理水準の向上や預金以外の資金調達方法の開発に加え、預金保険制度の整備や量的手段から金利誘導による金融調節への転換といった改革が求められる。
金利自由化の経緯
中国における金利の自由化は、「預金と貸出よりも、マネー・マーケットと債券市場の金利」、また、預金金利と貸出金利の自由化については、「人民元よりも外貨」、「預金金利よりも貸出金利」、「短期と小口よりも長期と大口」を先行させるという原則に沿って漸進的に進められてきた。
まず、マネー・マーケットと債券市場における金利の自由化は1990年代後半から始まり、すでにほぼ完了している(表1)。次に、外貨の貸出金利と預金金利の自由化も2000年代前半に大きく進展した(注2)。さらに、人民元貸出金利の上限の撤廃と人民元預金金利の下限の撤廃(いずれも2004年10月)が実施された。大口定期預金金利の自由化も進展が見られたが、金利自由化のプロセスはリーマン・ショック以降中断された。今年の6月に銀行を中心とする金融機関の預金金利と貸出金利の変動幅の拡大という形で再開された(表2)。
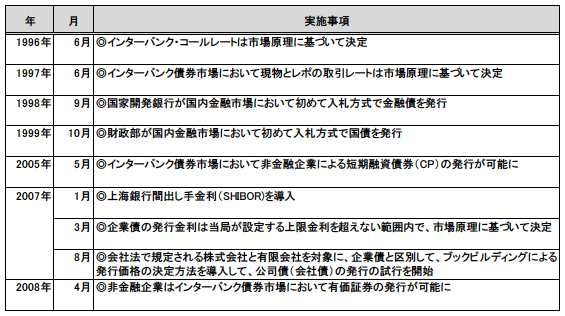
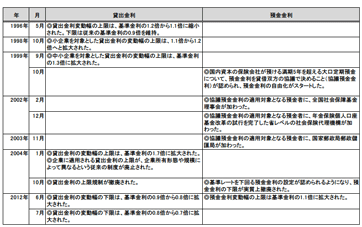
[ 図を拡大 ]
金利の自由化を巡る最近の動き
中国人民銀行(中央銀行)は、2012年6月8日と7月6日の二回にわたって、金融機関の人民元の預金と貸出の基準金利を引き下げると同時に、それぞれの変動幅の調整を実施した(図1)。具体的に、1年物貸出の基準金利は合わせて0.56%ポイント(一回目には6.56%から6.31%へ、二回目には6.00%へ)引き下げられ、その変動幅の下限は、一回目に基準金利の0.8倍、二回目には0.7倍に拡大された。一方、1年物預金の基準金利は合わせて0.5%ポイント(一回目には3.50%から3.25%へ、二回目には3.00%へ)引き下げられ、その変動幅の上限は基準金利の1.1倍に拡大された。こうした金利調整は、金融緩和の一環であると同時に、金利の自由化に向けた大きな一歩でもある。
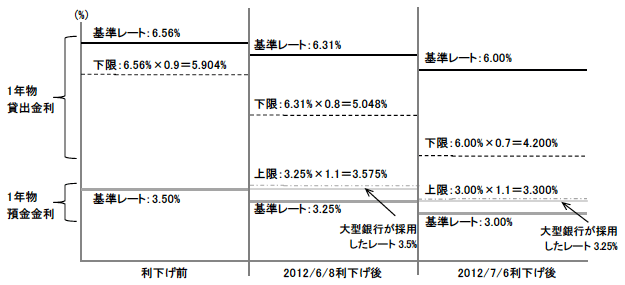
現在、商業銀行は、貸出金利について上限規制が存在しない上、基準金利の0.7倍という下限まで自由裁量の余地が与えられている。商業銀行は自身の経営コスト、リスク状況などに基づき、顧客と協議した上で個別に貸出金利を定めることができる。貸出金利の自由化が進んでいることを反映して、基準金利で行われた融資の割合は2012年6月現在、25.1%にとどまっている(図2)。
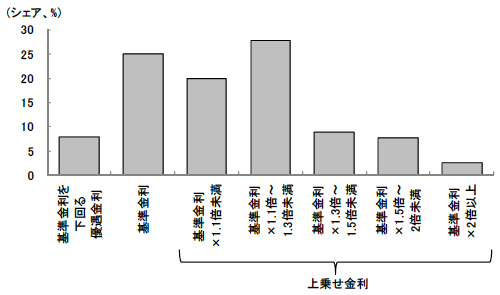
預金金利に関しても、各銀行は、新たに与えられた金利設定の裁量権を活かして、一部の預金を対象に当局が決めた基準金利を上回るレートを提示するようになった。その適用される範囲と金利水準は銀行の規模によって異なる。2012年7月6日以降、大型銀行は、3ヶ月から1年満期までの定期預金に限って、基準金利に0.25%ポイントのプレミアムを上乗せている。また、中型銀行は、普通預金と3ヶ月から1年満期までの定期預金を対象に、小型銀行の場合、普通預金とすべての定期預金を対象に、上限いっぱい(基準金利の1.1倍)の金利を提示している(表3)。
-大・中・小型銀行の比較(2012年7日6日現在)-
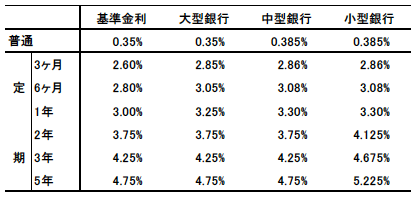
これまで、当局は、銀行間の預金争奪戦が激化し、銀行が直面するリスクを増大させかねないことを懸念し、預金金利の上限規制の緩和には慎重だっただけに、今回、預金金利の上限が初めて拡大され、また各銀行の預金金利の間に実際に差が生じるようになったことは、重要な意味を持つ。
このように、中国は、銀行金利の自由化の最終目標である貸出金利の下限と預金金利の上限の完全撤廃に向けて大きく前進している。
金利自由化の必要性
市場経済において、金利は資金という資源の配分を大きく左右する重要な「価格」である。次の理由から、金利の自由化は、市場経済を目指す中国にとって避けて通れないことである。
まず、金利の自由化により資金の利用効率が改善される。これまでのように金利が低水準に規制されている場合、資金に対する需要が供給を上回り、銀行は市場原理に拠らない方法で資金を割り当てなければならない。その結果、資金はリスクが低いが収益性も低いプロジェクトに集中しがちである。金利の自由化が進めば、借り手のリスクに見合った金利水準を決めることができるようになり、多くの民間企業も融資の対象となるだろう。
また、銀行の預金金利が規制によって低水準に抑えられているため、一部の資金が当局の監督が届かない非公式ルートに流れているが、金利の自由化により預金金利が上昇すれば、このような資金が銀行部門に還流するだろう。
さらに、これまで規制金利の下で、銀行は高い利ざや(貸出金利-預金金利)が保証され、新商品やサービスを開拓するインセンティブが働かなかった。しかし、金利の自由化が進めば、銀行間の競争が激しくなる。その結果、銀行が提供する金融商品やサービスが多様化し、質も向上する。
最後に、金利の自由化により金利が資金を誘導する機能が強化され、その結果、投資がより敏感に金利の変動に反応し、金融政策の有効性も高まるだろう。
金利自由化の影響
しかしその一方で、金利の自由化は、銀行の経営の悪化を通じて、金融不安をもたらしかねない。
まず、金利の自由化が進むと、銀行間の競争が預金金利を上げる一方で、貸出金利を下げるという形で展開される。その結果、利ざやの縮小、ひいては収益の減少は避けられない。
また、信用リスクが増大しかねない。金利の自由化により利ざやが縮小する中で、銀行は利益水準を維持するため、審査基準を緩和してでもリスクの高いプロジェクトへの貸出を増やすだろう。これらのプロジェクトは好景気やバブル膨張の間、収益を上げるが、一旦不況やバブル崩壊になると、赤字に転じ、債務の返済が滞ることなる。その結果、銀行が抱える不良債権も増えるだろう。
さらに、金利変動リスクが増大する。金利の自由化を受けて、金利変動が常態化し、変動幅も大きくなる恐れがある。銀行の資金調達(主に預金)と資金運用(主に貸出)の間では満期構造が異なることを反映して、金利変動によって収益が不安定になる。具体的に、運用は長期で固定金利の貸出が中心であるのに対して、調達は短期の預金が中心となるため、金利が上昇した場合には利ざや、ひいては収益は悪化してしまう。
最後に、資金は収益の高い方向に敏感に流れるため、金利の自由化により、金利が頻繁に変動するようになると、銀行にとって、最大の資金源である預金を安定的に確保することは難しくなる。
金利自由化の課題
このように、金利の自由化に伴うメリットは大きい一方で、リスクも高い。リスクを抑えながら、メリットを最大限に活かすために、次の対策を急がなければならない。
まず、銀行はコーポレート・ガバナンスの強化と経営管理水準の向上に努めなければならない。コーポレート・ガバナンスは銀行経営の基盤であるため、取締役会、監査役会、経営陣の役割分担と相互監督の機能を高める必要がある(注3)。また、中小銀行は経営基盤が比較的弱いため、金利の自由化が進む中、コスト管理、リスク管理、価格(金利)設定、資金収支管理などの能力を高め、流動性リスクと市場リスクに対応できる体力を育てなければならない。
また、銀行は預金以外の資金調達方法を開発しなければならない。預金という金融商品の差別化が難しく、価格競争が起こりやすいため、預金金利の自由化は通常、金利自由化の最終ステップに置かれている。多くの先進国では、譲渡性預金(CD)を導入することによって、預金に対する価格競争が回避されると同時に、普通預金と当座預金を区分することによって、銀行の資金調達コスト(預金の金利負担)が抑えられた。現在、中国では預金関連の金融商品の種類と価格設定メカニズムは同質化しており、加えて銀行は債券発行、資産証券化、譲渡性預金といった資金調達のチャンネルがまだ閉じられたままであるため、預金流出が発生すると、価格競争に頼るしかない。
さらに、預金保険制度を整備しなければならない。預金保険制度の設立により、預金者保護はこれまでの政府による暗黙的保証から法律で明文化されるものに変わる。このことは、銀行業の公平な競争市場の形成、中小銀行の直面する流動性リスクの軽減、銀行の破綻処理のルール化などを通じて、金融システムが不安定化するリスクを防止することに資する。2007年の全国金融工作会議において「預金保険条例」の制定に取り組むことが決定されたが、世界を巻き込んだ経済危機により、その進展が止まり、今年の1月に5年ぶりに開催された同会議においてようやく議論が再開された。
最後に、金利自由化の推進と債券市場の発展に伴い、政策金利と市場金利など各種の金利間の連動性がさらに高まるにつれて、金融政策の有効性を最大限に活かすために、これまで預金準備率の調整や貸出規模規制など量的手段に頼っていた金融調節は、金利誘導へと軸足を移す必要がある。そのために、金融市場基準金利システムの構築を強化しなければならない。それに向けて、2007年1月にSHIBOR(上海銀行間出し手金利、翌日、1週間、2週間、1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月、9ヶ月、1年の計8種類)が銀行間コール市場における基準金利として公表され始め、当局はそれを他の金融取引の基準金利としても定着させようとしている。また、「独立した金融政策、自由な資本移動、固定為替相場制という三つの政策目標は同時に達成できない」という「国際金融の三位一体説」が示唆しているように、中国において、資本の移動性が高まる中で、金融政策の独立性を維持するためには、人民元為替相場の完全変動制への移行を急がなければならない。
2012年9月6日掲載


