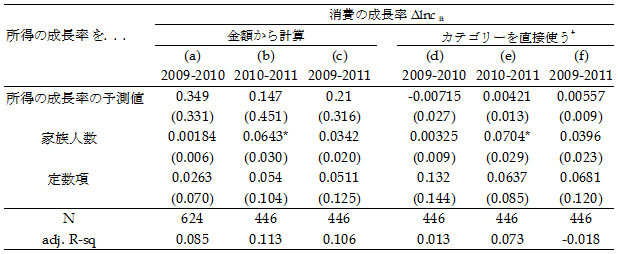| 執筆者 |
殷 婷 (研究員) 暮石 渉 (国立社会保障人口問題研究所) 若林 緑 (東北大学) |
|---|---|
| 研究プロジェクト | 少子高齢化における家庭および家庭を取り巻く社会に関する経済分析 |
| ダウンロード/関連リンク |
このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。
社会保障・税財政プログラム (第三期:2011~2015年度)
「少子高齢化における家庭および家庭を取り巻く社会に関する経済分析」プロジェクト
1. イントロダクション
標準的な消費理論である恒常所得仮説では、個人は異時点間の消費の期待限界効用を平準化し、貯蓄の積み増しや取り崩しを行うことで所得の変化に反応することができるという前提を置くことで、ある時点の個人の消費はその個人の生涯所得によって決定されるとする(Aguiar and Hurst (2007))。
恒常所得仮説が成り立っているのかどうかを明らかにすることは、消費者行動を理解し、家計の資源に影響をあたえる政策の効果を評価する点で重要である。特に、本研究で取り上げる中国については、家計の消費行動の分析は極めて重要である。中国は、2009年の住民消費支出が国内総生産に占める割合は約35% と、日本やアメリカと比較して低く、そのため、田中 (2006)がいうように、第10次5カ年計画(01~05年)において内需の拡大が経済発展の基本的立脚点、長期戦略方針とされており、第11次5カ年計画(06~10年)においても輸出・投資依存型の成長から、内需と外需、投資と消費のバランスのとれた成長への転換が目指されているからである。
2. 分析
本研究では、大阪大学の「くらしの好みと満足度についてのアンケート」の中国都市パネル調査における主観的な所得の予想に関する質問項目を利用し、消費が予期される所得の変化にどの程度反応するのかという過剰反応 (excess sensitivity) の検証を行う。つまり、恒常所得仮説からのインプリケーションである、今日の消費の変化が今日の所得の変化にどう反応するかは、所得の変化が予期されるか (expected)、それとも予期されないか (unexpected)によって異なるか否かを検証するということである。
本論文で用いるのは、大阪大学21世紀COE/グローバルCOEが実施している「くらしの好みと満足度についてのアンケート調査」における中国都市パネル調査からのデータである。この調査は、2009年から実施されており、主要6都市(北京、上海、広州、成都、武漢、瀋陽)に居住する満20~69歳の一般男女個人に対して、訪問面接調査法で実施されている。
本論文では、主に2010年から2012年の調査を用い、2009年の物価上昇率の予想にのみ2009年の調査を用いる。この調査では、各調査年の前年の世帯全体の支出額と総収入に関しての質問と今年の総収入の予測に関しての質問を毎年継続して含んでいることから過剰反応の検証に適している。
操作変数法を用い、実際の所得の成長率のうち実質所得の成長率から予測できる部分が消費の成長率にあたえる影響を推定した。表において、2009-2010年、2010-2011年、そして2009-2011年の消費の変化、また、所得の成長率を金額から計算するものの代わりに、何%~何%未満の増加(または減少)というようにカテゴリーで直接聞いたものに変えたどの推定においても、所得の成長率の予測 (Δ ln yit) の係数は有意ではなかった。つまり、実際の所得の変化率のうち予測された所得の成長率で説明できる部分は、消費の成長率に有意な影響を与えないということである。これは、予期される所得の成長は消費の成長に影響を与えないという恒常所得仮説における直交条件が成り立つということを支持するものである。
3. 政策インプリケーション
従来、恒常所得仮説は先進市場経済にのみあてはまると考えられ、名目GDPでは、日本の約2倍に近づきつつあるものの、1人当たり名目GDPでみると100位近辺に位置している中国の消費や貯蓄を分析するには、伝統的なケインズ型の消費理論(つまり、消費およびその残余としての貯蓄は現在の所得に依存して決定される)が重要な役割を果たすと考えられてきた。しかし、1978年からの改革開放による経済発展の過程で、中国は都市と農村、沿海部と内陸部、都市内部、そして農村内部において所得格差が拡大している。また、急速な市場経済化が進んでいる都市部において、所得や消費は大幅に増加し消費構造も変化している。
本研究の結果から、中国都市部において恒常所得仮説が成り立っていることが示されたが、これは、短期的な所得増加による消費拡大政策よりは長期的な所得増加による消費拡大策のほうが有効であることを示唆している。消費拡大を目指すため、2014年11月21日に人民銀行は金融機関の人民元預金基準金利を引き下げると発表したが、その効果は中国都市部において限定的なものになると思われる。
また、これまで先進国でしか成り立たないといわれてきた恒常所得仮説が中国都市部において成り立っていることが示されたわけだが、中国の農村部ではどうだろうか? 適用可能性について検証することも必要であろう。その際、主観的な所得の変化と客観的な所得の変化を把握する必要があるから、マイクロデータの整備が重要な課題となるであろう。