| 執筆者 | 小西 葉子 (上席研究員)/野村 浩二 (ファカルティフェロー) |
|---|---|
| 研究プロジェクト | 経済変動の需要要因と供給要因への分解:理論と実証分析 |
| ダウンロード/関連リンク |
このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。
産業・企業生産性向上プログラム (第三期:2011~2015年度)
「経済変動の需要要因と供給要因への分解:理論と実証分析」プロジェクト
2030年の電源構成の検討のため、経済産業省は長期需給見通し小委員会を設置し、本年1月末から議論が開始された。現在、福島原発の事故を受けてすべての原発が稼働を止めており、火力発電への依存度は、震災前(2010年度)の61.7%から13年度には88%に上昇し、14年までに電力価格は35%ほど上昇した。こうした状況下において、電力価格上昇を抑制しうるエネルギーミックスの姿が求められている。適切な電源構成を考える鍵の1つは、将来における省エネの実現可能性である。野村(2015)は、近年のエネルギー政策の検討において、将来における省エネの実現の程度が過大推計され、エネルギー需要予測を過小推計してきたことを指摘している。本稿では省エネの将来予測を考察するため、これまで半世紀にわたって日本産業における省エネがどのような要因によって実現されてきたのかを分析している。
エネルギー投入量を生産量で除した比によってエネルギー効率性を定義すれば、計量経済学的な測定によって、その変動要因を大きく「価格代替による効果」と「技術変化による効果」に分解することができる。前者は投入要素の相対価格の変化を反映して、エネルギーから資本や労働へと代替していくことで省エネを実現するものである。一般に省エネは、エネルギー価格が相対的に高くなる中で、省エネ投資(資本への代替)や課題を探し消費量をモニタリングするなどの人的努力(労働への代替)によって実現するだろう。こうしたものは前者に含まれる。後者は、ゼロないしほとんど費用負担なしに自律的に組み込まれる省エネである。いわゆる省エネ技術の採用は通常は前者に含まれるが、後者では生産拡張や更新投資によって意図せずとも組み込まれる省エネや、あるいは採用される技術変化(たとえば空気中における浮遊微小粒子を統御するクリーンルームが必要になり、そのために電力多消費的になる)などに依存している。
図1は1955-2012年を大きく3期間へと分け、産業別のエネルギー効率性の変化を観察したものである。その指標の減少(軸から左への変化)はエネルギー効率の改善であり、増加(右への変化)は効率の悪化である。高度成長期(左図)には、エネルギー価格は他の投入要素と比較して非常に安定的で、多くの産業でエネルギー使用的となり、結果的にエネルギー効率の悪化が観察される。73-91年(中央図)では、第一次石油ショックによる石油価格の高騰により省エネ技術の導入が進行し、35産業中33産業でエネルギー効率性の改善が実現した。この期間(とくに1970年代半ばから80年代半ばまで)を省エネの黄金期と呼んでおこう。91-2012年(右図)では、全般的にエネルギー効率性は改善しているものの、黄金期と比較してその程度は減速しており、一部の産業では悪化も見られている。
次に観察されるエネルギー効率の変化の要因を分解しよう。図2では紙・パルプ製造業と鉄鋼業の2つをピックアップしている。線グラフはエネルギー効率の推移を示している(マイナスは省エネの改善、プラスは悪化である)。両産業ともに75-85年のエネルギー効率の改善が最も大きく、近年になるほど改善度合いは小さい。棒グラフはエネルギー効率の変化を、価格変化効果による寄与度(白色:price change effect)と技術変化効果による寄与度(灰色:technical change effect)へと大きく分解したものである。技術変化効果が正値のときはエネルギー使用的(energy-using)な技術、負値の場合はエネルギー節約的(energy-saving)な技術が導入されていることを意味する。
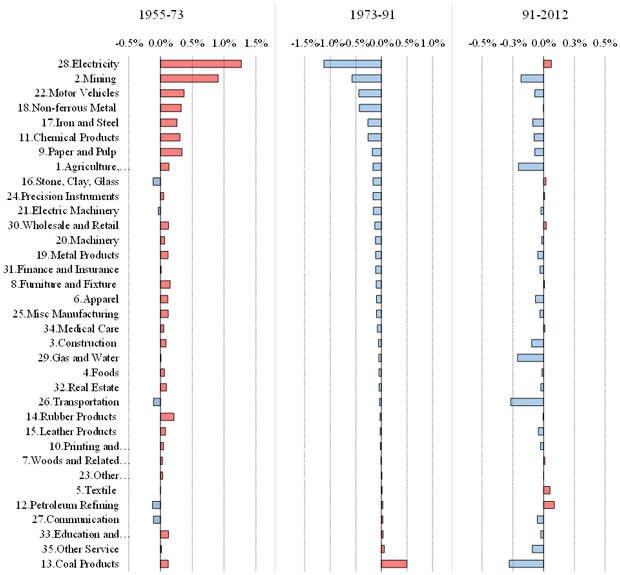
[ 図を拡大 ]
高度成長期には、エネルギー価格が相対的に安定しており、他の投入要素と比較してエネルギーの投入が増加した。しかし測定結果によれば、この期間においても(パルプ・紙製造業における1950年代後半や鉄鋼業における1955-65年など)、生産拡張投資などに伴ってエネルギー節約的な技術が自律的に組み込まれていたことが見出される。日本の高度成長期には、目的は生産拡張であっても、欧米から購入した資本財の導入により、同時に省エネ技術も組み込まれていったと捉えられる。こうした後発の利益は、1990年代以降における東欧諸国(ゆえにEU全体のエネルギー効率改善は高く、CO2削減量は多く見える)、あるいは成長著しいアジア経済において観察されている。日本経済においては、このようなエネルギー節約的な技術進歩は1970年代以降、急速に縮小している。
75-85年が省エネの黄金期であるが、その実現はもはや費用負担なしで使用可能な技術の利用ではなく、エネルギー価格高騰を反映した価格代替効果(白色のバー)が主である。そしてこの期間において新たに開発されたであろう省エネ技術は、当該産業内あるいは産業間の普及を通じて、80年代後半から90年代前半に今一度エネルギー節約的な技術変化として見出されている。
90年代は、経済停滞によって賃金や資本コストが低下し、それに伴うエネルギー価格の相対的な上昇が省エネの黄金期を超えるほどの水準であった。しかし黄金期を超える省エネを実現するには至っていない。第1の要因はエネルギー使用的へと転じた技術であり(黄金期では節約的)、第2は資本などへの価格代替がより困難(追加的なエネルギーの削減のためにより多くの省エネ投資が必要)になったことである。2030年までの予測では、ほとんどの産業でエネルギー使用的な技術変化が優勢と推計されている。現在、日本のエネルギー政策は、過去の黄金期のような省エネを再び実現しようと目標を定めている。しかし、黄金期のような省エネの実現には、電力価格が倍増以上となるような膨大な負担増や、エネルギー使用的な技術変化を相殺して余りある、高い水準の省エネ技術が開発されて自律的に組み込まれるようなことが必要である。しかしそれらはいずれもきわめて困難であると予測される。技術変化と価格変化の方向性と整合するものでなければ、今後の省エネ見通しは画餅に帰すだろう。
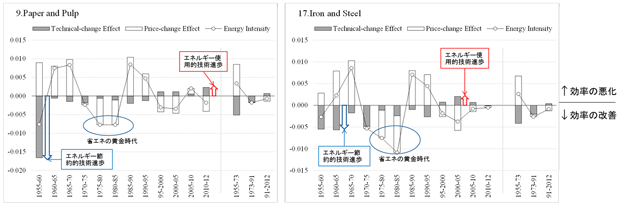
[ 図を拡大 ]
- 文献
-
- 野村浩二 (2015) 「経済教室:2030年の電源構成(下)」、2015年3月19日、日本経済新聞。(RIETIホームページに再掲: http://www.rieti.go.jp/p/papers/contribution/nomura/01.html )

