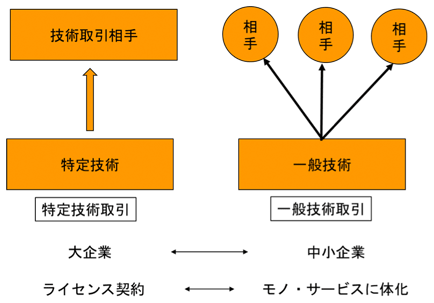| 執筆者 |
党 建偉 (東京大学) 元橋 一之 (ファカルティフェロー) |
|---|---|
| 研究プロジェクト | 日本型オープンイノベーションに関する実証研究 |
| ダウンロード/関連リンク |
このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。
技術とイノベーションプログラム (第三期:2011~2015年度)
「日本型オープンイノベーションに関する実証研究」プロジェクト
本論文は、RIETI新商品開発に関するアンケート調査のデータを用いて、オープンイノベーションの形態が、知的財産の有無や企業規模によってどのように異なるか分析を行ったものである。複数企業間で行われる技術取引は、特許やノウハウなどのライセンス契約によるものだけでなく、新しい部品や材料の提供や技術コンサルティングなどによって行われることがある。また、企業規模によって、技術取引におけるバーゲニング力や補完的資産(製造設備やマーケティング能力)が違うため、技術取引の形態が異なることが考えられる。ここでは、契約の相手先数(単独取引か複数取引か)に着目して、実証分析を行った。
分析結果としては、以下のとおりである(図参照)。
- 特許やノウハウなどのライセンス契約による技術取引において、より少数の相手先と取引を行うことが多い。その一方で、部品の供給や技術コンサルティングなどのモノ・サービスに体化された技術供与の場合は、多くの取引先を相手としている。
- 大企業と比べて中小企業は、より多くの取引先を相手としている。
- 一般的にライセンス収入と提供先数には正の相関関係が見られるが、大企業においては少数の取引先から多くの収入を上げている一方で、中小企業においてはなるべく多くの企業と取引をすることでライセンス収入を大きくする傾向が見られる。
これは、(1)中小企業は大企業と比較して技術取引における交渉力が弱いので、なるべく多くの提携先から収入を上げるようとするインセンティブが強くなること、および(2)中小企業においては技術を収益化する際の補完的な経営資源(生産設備、マーケティング能力など)が乏しく、より一般的なユーザーを意識した汎用技術を開発する誘因が強いこと、によるものと考えられる。また、中小企業においては、技術市場の不完全性の影響を強く受けていることから、製品・サービスの技術を体化させて、なるべく多くの収入を得ようとする動きをとっていると考えられる。
従って、大企業と比べて技術取引における交渉力が弱い中小企業が技術取引を行いやすい制度的な支援が必要である。また、中小企業においては、技術市場を通じて行われる技術ライセンスだけでなく、製品やサービスに体化された製品市場を通じた取引も重要であるため、中小企業が有する知的財産に関する技術流通事業に加えて、新製品や技術に関する販路開拓に関する資金面・情報面での中小企業支援策が重要である。