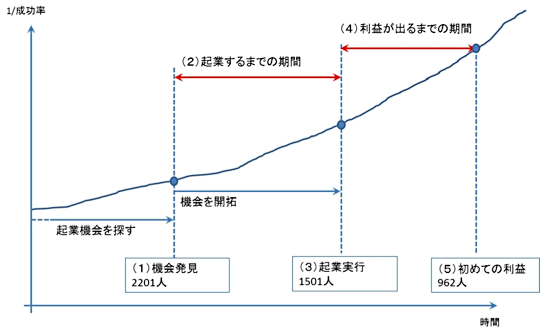| 執筆者 |
松田 尚子 (研究員) 松尾 豊 (東京大学) |
|---|---|
| 研究プロジェクト | SNSを用いたネットワークの経済分析 |
| ダウンロード/関連リンク |
このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。
特定研究 (第三期:2011~2015年度)
「SNSを用いたネットワークの経済分析」プロジェクト
論文の背景
本年6月14日、金融緩和、財政出動に次ぐアベノミクスの三本目の矢となる「骨太の方針」が閣議決定された。この中で新事業創出は大きな柱の1つであり、開業率10%台の実現が目標とされている。また、本年7月23日に発表された年次経済財政白書では、「企業家によるアニマルスピリットの発揮」が日本の経済成長の鍵であると指摘されている。
しかし日本の起業事情は、世界的に見て起業率が低水準であるだけでなく、IPO市場もGDPに比較して小さく、たとえ起業できたとしても大きく成長することが難しいという問題も抱えている。
このような状況の中、大きく成功する起業家を1人でも多く生み出すことは、単に個人の事業の成功という範囲を超えて、日本経済全体にとって重要な課題といえる。
分析結果の要約
本論では、昨年9月にRIETIで行われた「ベンチャーの起業意識に関するインターネット調査」を用い、図1のように起業活動を3つの段階と2つの期間に分類して、人的資本(注1)と社会関係資本(注2)の起業活動への影響を検証した。また起業家による相談相手や、相談相手に応じた相談内容の選択について、成功した起業家にみられる傾向について検証した。
その結果、人的資本については管理職経験の長さは、起業の3つの段階を越えるのに正の影響を与えるが、MBA資格やベンチャーキャピタルでの投資家経験は、起業前には正の影響を与えたが、起業後の利益には役立たなかった。また社会関係資本については、起業の実行に際しては起業家や経営者の家族がいることが正の影響を与えたが、起業後の利益については家族は関係が無く、むしろ起業家や経営者の友人がいることが正の影響を与えていた。つまり、起業前と起業後で起業家に求められる資質は異なっており、起業家や経営者の友人を作れば起業の成功率が上がる可能性があるといえる。
また起業後に利益を上げることのできた起業家は、そうでない起業家に比べて、経営相談をする相手の持つ人脈の広さを考慮し、起業経験者に「経営者としての心得」および「共同設立者、優秀な社員、取引先、顧問、サービス提供者探し」について特に相談するなど、相談相手に応じた相談内容を選択する傾向にあることも分かった。
政策的含意
起業家にとっての人的資本と社会関係資本の重要性は既に広く認識されており、民間のインキュベーション企業やベンチャーキャピタルでは、起業家育成プログラムの提供や起業関係者に出会いの場を提供する交流会や起業家に人材を紹介する事業が行われている。また中央・地方政府が、新事業創出のためそのような民間の取り組みを支援していることも多い。本研究の政策的含意として、このような取り組みを行う場合、支援対象となる起業家が起業プロセスのどの段階にあるかを考慮して、きめ細かく行われるべきであるということができる。