| 執筆者 |
徳井 丞次 (ファカルティフェロー) 牧野 達治 (一橋大学) 深尾 京司 (ファカルティフェロー) 宮川 努 (ファカルティフェロー) 荒井 信幸 (和歌山大学) 新井 園枝 (コンサルティングフェロー) 乾 友彦 (ファカルティフェロー) 川崎 一泰 (東洋大学) 児玉 直美 (コンサルティングフェロー) 野口 尚洋 (一橋大学) |
|---|---|
| 研究プロジェクト | 地域別生産データベースの構築と東日本大震災後の経済構造変化 |
| ダウンロード/関連リンク |
このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。
産業・企業生産性向上プログラム (第三期:2011~2015年度)
「地域別生産データベースの構築と東日本大震災後の経済構造変化」プロジェクト
戦後の高度成長期から1980年代にかけての時期にも、すでに地方のなかで地場産業の衰退や過疎地域の発生などが指摘されてはいたが、それでも都道府県単位でみれば、日本全国が共通に上り坂にあり、相対的に貧しい県もいつかはより豊かな都道府県に追いつけるものと期待されていたのではないだろうか。ところが、1990年代に入って日本が「失われた20年」と言われる停滞期に入ると、地域間の経済格差の拡大がより鮮烈に意識されるようになった。こうして地方経済衰退の原因とその活性化策を巡る議論が喧しくなったものの、残念ながらそれらの多くは幾つかの事例を取り上げた議論にとどまり、共通のデータによる分析に基づく議論は多くない。これは、我が国において、地域経済のデータ分析を行うために必要な精度の高い公開データの整備が遅れてきたことにもその一因があると言えよう。
この研究プロジェクトの参加者の多くは、日本産業別生産性(JIP)データベースの構築に加わっており、その経験を生かして、JIPデータベースの姉妹編ともいうべき都道府県別のデータベースを構築することになったのが今回のプロジェクトの柱である。JIPデータベースのデータは、都道府県別産業生産性(R-JIP)データベースの作成にあたっても、コントロールトータルとして活用されている。その一方で、R-JIPデータベースでは都道府県別情報が加わった一方で、産業部門数を23部門と少なくし、中間投入の情報はなく粗付加価値ベースの産出量を使っている点で姉妹編のJIPデータベースよりも簡略化がされている。それでも、23産業部門は、これまで分析に使われてきた地域別データベースに比べてより詳細に分類になっており、政府統計のデータの産業分割においても独自の工夫をこらしたものとなっている。それに加えて、本データベースでは労働投入と資本投入の地域別産業別属性の違いから生じる、「要素投入の質」の側面についてもできるだけ反映したものとなっている。これは、生産性計測においては要素投入の正確な計測が極めて重要という精神に基づくものである。
本ディスカッション・ペーパーでは、こうして作成した都道府県別産業生産性(R-JIP)データベースの作成方法をまとめるとともに、そのデータを使って地域間格差の分析を行っている。R-JIPデータベースが就業地ベースで整合的に構築されていることから、地域間格差の指標としては労働生産性を取り上げ、その地域間格差が1970年以降近年までにどのように変化してきたかを概観し、また変化の原因を資本装備率、労働投入の質、全要素生産性(TFP)に分解して分析した。さらに産業構造の違いの影響や、同一産業内での地域間労働生産性格差の原因についても分析している。
2008年について都道府県間のマクロ相対労働生産性の格差をサプライサイドの視点から要因分解した結果が、図1である。これによると、資本装備率、労働の質、TFP全ての要因が労働生産性の地域間格差に寄与していることが分かる。なお、1970年以降について時間を通じた変化を見ると、労働生産性の地域間格差が縮小した主因は、豊かな県ほど高かった資本装備率の地域間格差が縮小したことであるように思われる。一方TFPの地域間格差は減少せず、今日では労働生産性の地域間格差の主因となっているように思われる。
次に、地域間の労働生産性を縮小する上で各産業が果たした役割を見ると、不動産、運輸・通信など資本集約的な非製造業が労働生産性の高い県に集積し、サービス(民間・非営利)、運輸・通信などの産業が、資本装備率や人的資本を、東京をはじめとする労働生産性の高い県に集中させるなど、非製造業が格差を残存させる上で、重要な役割を果たしたことが分かった。また、建設、卸売・小売、サービス(民間、非営利)等が、労働生産性が高い県ほどTFPが高い傾向を維持する、主因ともなっていた。
一方製造業については、労働の質のシェア効果やTFPの産業内効果が著しく低下した。人的資本集約的な製造業の地方への集積、同一産業内でTFPが高い工場の地方への立地、といった過程を通じて、製造業では地域間の労働生産性格差を縮小するようなメカニズムが働いたことが分かる。
非製造業において地域間で大きなTFP格差が残存してきたことは、生産性の高い非製造業企業の地方進出や技術の地方への移転によって、日本全体のTFPやGDPを高めることができる可能性があることを意味している。また、仮に国土の均衡のとれた発展のためには労働生産性の地域間格差拡大を縮小することが望ましいのであれば、生産の海外移転と国内生産の縮小が急速に進みつつある製造業について、地方への新規立地や国内回帰を促す政策が有効であると思われる。
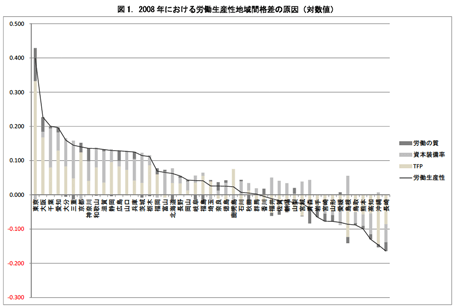
[ 図を拡大 ]

