このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。
人的資本プログラム (第三期:2011~2015年度)
「労働市場制度改革」プロジェクト
問題の背景
非正規雇用の雇用全体に占める割合が拡大傾向にある中で、正規雇用との処遇格差是正が重要な政策課題の1つとなっている。しかし、単純に正規雇用、非正規雇用の賃金格差を論じても意味がない。なぜなら、一般的に、正規雇用は雇用保障が厚いが、転勤や異動を伴う、非正規雇用は不安定雇用であるが、パート・アルバイトのように時間的な拘束が短い、といった労働条件や処遇の違いがあるからである。つまり、正規雇用と非正規雇用の処遇格差には、合理的に説明可能な部分として、企業の提示する労働条件とそれに対する労働者の嗜好の違いが反映されている可能性がある。
本研究では、2009年1月から6カ月毎に計5回にわたって(独)経済産業研究所が実施した『派遣労働者の生活と求職行動に関するアンケート調査』を用いて、非正規雇用における不安定雇用や転勤・異動に対する補償賃金に関する実証的な分析を行った。具体的には、非正規労働者に対して、雇用期間の短縮や転勤・異動を受け入れる場合に要求する賃金の上乗せ分を仮想的に質問して定量的に把握した。(注1)
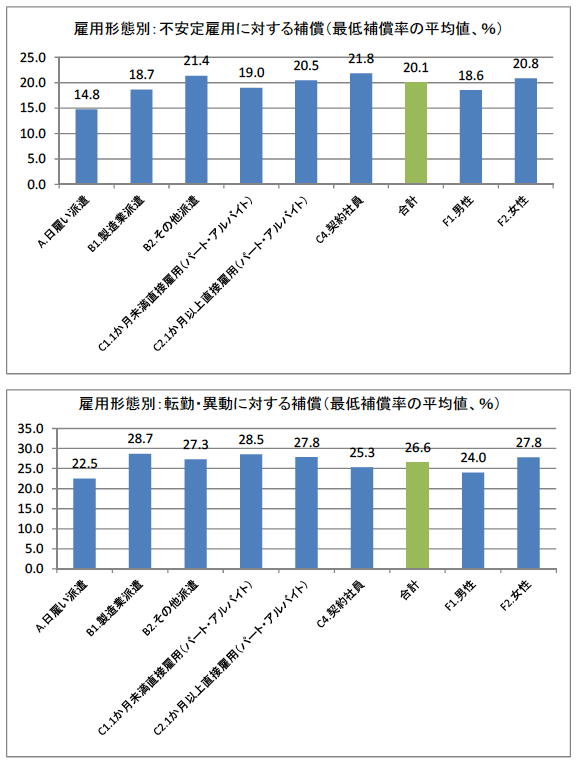
分析の結果
図1に、補償賃金率の水準を雇用形態別に示す。不安定雇用に対しては契約社員が、転勤・異動に対しては製造業派遣、パート・アルバイトが比較的高かった。さらに、補償賃金の決定要因を明らかにするべく、回帰分析を行ったところ、いずれのタイプにおいても、女性、年齢が高い(特に50歳以降)、危険回避的な人ほど、要求する補償率が高かった。一方、雇用形態に関わる要因では、正社員の経験がある人や正社員の職を希望する人の不安定雇用に対して求める補償は大きく、自発的にパートタイム労働に就いている人の転勤・異動に対して求める補償が大きかった。
さらには、賃金関数(時間当たり賃金と月収)を推計して、雇用形態や労働条件の違いが賃金水準に与える影響を分析して、補償賃金仮説の視点から解釈した。雇用形態別では、時間的な拘束の少ないパート・アルバイトが、また、労働者の属性別には、既婚女性や子どもの存在が賃金を有意に低くする要因となっており、労働者がワークライフバランスと引き換えにコストを負担している(相対的に低い賃金を受け取っている)可能性が示唆された。一方、雇用不安定の効果については、明確な結論は得られなかった。
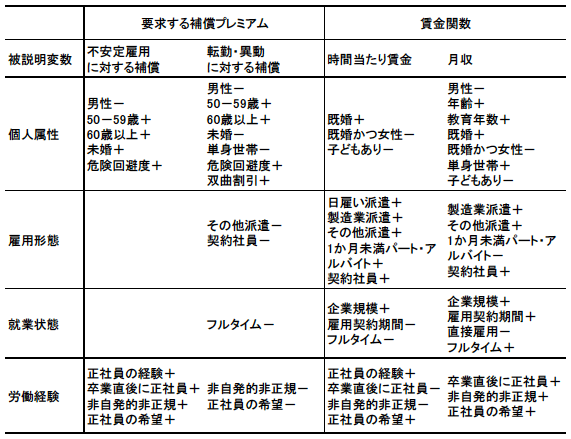
これらの結果は、労働者の効用を維持するためには、労働条件の不利益な変更が生じる場合にはそれを補償する手立てを用意することの重要性を示唆している。前述のように、正社員の経験がある人や正社員の職を希望する人の不安定雇用に対して求める補償は大きかったが、補償賃金仮説の立場からは、雇用の不安定に対する補償として、正社員への転換のみならず、たとえば、契約終了時にそれまでの賃金支払いの一定割合の金銭を支払う仕組みの導入を検討すべきであろう。
脚注
- ^ 具体的な質問形式については、RIETI派遣アンケート調査の報告書
http://www.rieti.go.jp/jp/projects/research_activity/temporary-worker/result_05-report.pdf
を参照されたい。

