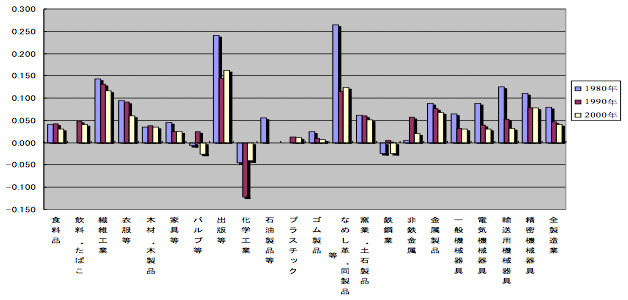| 執筆者 |
徳永 澄憲 (筑波大学) 影山 将洋 (常陽銀行) 阿久根 優子 (麗澤大学) 中村 良平 (ファカルティフェロー) |
|---|---|
| 研究プロジェクト | 持続可能な地域づくり:新たな産業集積と機能の分担 |
| ダウンロード/関連リンク |
このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。
地域経済プログラム (第三期:2011~2015年度)
「持続可能な地域づくり:新たな産業集積と機能の分担」プロジェクト
既存の集積の経済に関する研究では、集積の経済を「地域特化の経済」と「都市化の経済」の指標を用いて分析する論文は多いが、直接産業集積指数を用いて計測する論文は少ない。本稿では、地理的集中度と産業集中度を考慮したエリソン=グレイサーの雇用ベースの集積指数と異業種間の集積指数(共集積指数)を用いて、集積と共集積が生産に及ぼす正の外部経済を「集積の経済」とし、この集積の経済の外部効果を計測する。下図が示すように、経年的に低下傾向にあるが正の産業集積度を持つ産業は、一般機械、電気機械器具、輸送機械器具、精密機械器具の組み立て型産業である。そこで、組み立て型産業を対象として、1985年から2000年までの5年おきの生産のデータと集積・共集積指標を用いて、フレキシブルなトランスログ生産関数を推定し、その推定結果から、日本を代表する組み立て型産業では、同一地域に立地する当該業種の集積(γEG)と異業種との集積(共集積)がともに生産に対して正の外部経済を持つとともに、共集積の方が集積よりも生産に及ぼすインパクトが大きいことがわかった。
本研究の政策的含意としては以下が考えられる。本稿で明らかになった、生産に対して正の外部性を持つ集積の経済と規模の経済を促進するために、最終財の組み立て生産拠点が立地する域内に部品、特に基幹部品を集積させ、効率を向上させる生産ピラミッドの構築とその生産構造の継続的な維持が可能となるような地方政府の政策的サポートが今後とも必要である。