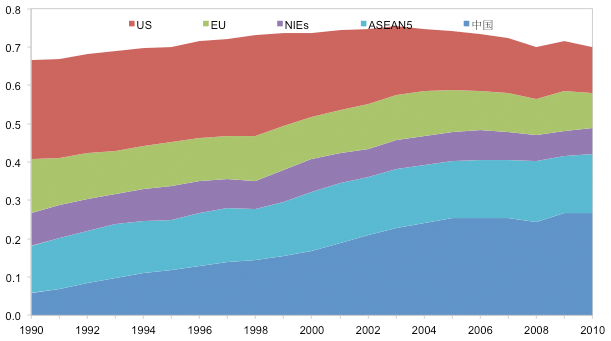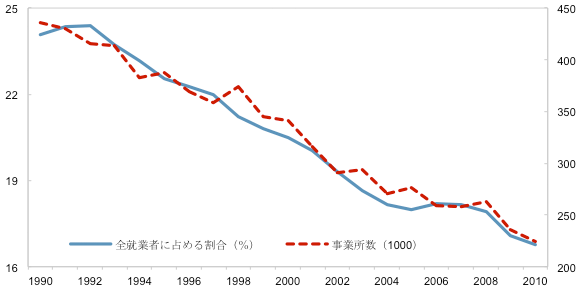| 執筆者 |
Anna Maria MAYDA (ジョージタウン大学) 中根 誠人 (コンサルティングフェロー) STEINBERG, Chad (コンサルティングフェロー) 山田 浩之 (大阪大学) |
|---|---|
| 研究プロジェクト | 産業・企業の生産性と日本の経済成長 |
| ダウンロード/関連リンク |
このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。
基盤政策研究領域II (第二期:2006~2010年度)
「産業・企業の生産性と日本の経済成長」プロジェクト
低賃金諸国、特に中国からの製造業品の輸入増加により、日本の貿易構造はこの20年間で大きく変化した(図1)。その一方で、同時期における我が国の製造業の変化をみると、就業者数の割合および事業所の数はともに減少の一途を辿ってきた(図2)。しかし、製造業がGDPに占める割合の変化を調べたところ、就業者数および事業所数に比べ、減少の速度が緩やかであった。
これらの点を踏まえ、我々は、1989年から2006年の間における、日本の製造業の構造変化において国際貿易が果たしてきた役割について分析を行った。とりわけ、低賃金諸国からの輸入品との競合にさらされることで、我が国の製造業の事業所の生存や雇用がどのような影響を受けたかについて考察を行った。分析の方法は、各産業ごとに低賃金諸国からの輸入浸透度(注1)を求め、それらが事業所の雇用者数の伸びおよび事業所の生存とどのような関係にあるのかを、回帰分析を用いて調べた。
分析の結果、事業所の生存確率や雇用の伸びは、低賃金諸国との競争が激しい産業ほど低い、という結論を得た。特に、労働集約的な産業など、我が国の比較優位のない分野において、低賃金諸国からの輸入が雇用および生存に与える影響は大きかった。同時に、標準的な国際貿易の理論と整合的な、労働集約的産業から我が国がより比較優位を持つ技術・資本集約的な産業への資源の再配分が推察された。
よって、我が国としては、国際貿易を推進することで、低賃金諸国に比較優位のある労働集約的な産業では輸入の割合を高め、国内の製造業に対しては、我が国に比較優位のある技術・資本集約的な産業へ資源をシフトしやすい枠組みを構築することが重要である。