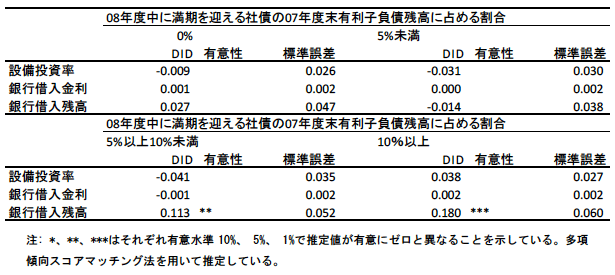| 執筆者 | 内野 泰助 (研究員) |
|---|---|
| 研究プロジェクト | 効率的な企業金融・企業間ネットワークのあり方を考える研究会 |
| ダウンロード/関連リンク |
このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。
特定研究 (第三期:2011~2015年度)
「効率的な企業金融・企業間ネットワークのあり方を考える研究会」プロジェクト
研究の目的
日本においては、メインバンク制に代表される緊密な銀行・企業間関係により情報の非対称性の問題が緩和されてきたと考えられている。しかし1980年代以降の社債市場の規制緩和に伴い社債による資金調達は増加し、上場企業においてメインバンクとの関係は希薄化していると指摘される(銀行依存度の低下)。企業にとってメインバンクとの緊密な関係を継続する利点の1つは、企業が不意の支出の必要性(流動性ショック)に直面した際に、銀行からの救済を受けられるということがある。企業が資金調達において銀行依存度を下げると、不意の支出の必要性が生じた時に銀行から十分な借入を受けられず資金難に陥るのであろうか。本稿は、2008年のリーマン・ショック時に日本の社債・CP市場が混乱した点に注目し、この点を実証的に解明することを目的としている。
分析方法
2008年のリーマン・ショック時には、日本の資本市場が大きく混乱した。日本銀行のレポートでは、日本の社債・CP市場が2008年度の後半に機能不全に陥ったことが報告されている。日本に限らず米国など諸外国も同様の資本市場の混乱に直面したが、日本では他国と異なり銀行部門の健全性は比較的維持されたと考えられている。従って、資金調達において社債依存度の高かった企業が同時期に資金調達面で最も強くショックを受けたことになる。
本稿では上場企業約2000社の財務データを用いて分析を行っている。企業が受けた流動性ショックの程度を識別するために、2007年度末段階で財務諸表に計上されていた「1年未満に満期を迎える社債」という項目に注目し、2008年度中に満期を迎える社債の2007年度末有利子負債に占める割合を情報として利用した。この割合が大きい企業ほど、社債発行による借り換えが困難となり、リーマン・ショック時に社債と代替的な資金調達、すなわち銀行借入の必要性に迫られていたと考えられるためである。
仮に社債満期を迎えた企業が十分な銀行借入を行うことができない場合、社債の返済原資を確保するために、企業は設備投資支出をはじめとする現金支出を大きく減らす可能性がある(資金制約)。更に、銀行から厳しい融資条件が課されることで銀行借入金利も上昇すると考えられる。逆に銀行が十分な貸し出しに応じる場合、社債の返済で失われたキャッシュ・フローを埋め合わせる様に銀行借入残高が増加し、設備投資支出は減少しないと考えられる。
分析結果:社債市場混乱時に代替的な役割を果たした銀行貸出
分析にあたっては、Difference-in-differences(DIDと略す)という推定方法を適用して、リーマン・ショック時に社債の満期を迎えた企業の設備投資支出や銀行借入条件が、社債を発行していなかったという仮想的な状況と比べてどの程度変化したのかを求める。具体的には、傾向スコアマッチング法を用いて「社債満期を迎えた企業」の2007年度から2008年度にかけての設備投資率、銀行借入残高、銀行借入金利の変化から、同様の企業属性を持つ「社債を発行していない企業」の変化をそれぞれ引くことで社債市場混乱の影響を識別している。
推定結果は表1の通りである。ここでは、満期を迎える社債の割合ごとにDIDの推定値が異なることを許容している。これをみると、社債満期の割合に関わらず、設備投資率の変化に社債を発行していなかった企業と有意な差がないことがわかる。同様に銀行借入金利の変化にも有意な差はみられない。しかし、銀行借入残高については、満期を迎える社債の割合が5-10%の企業において11.3%の増加が、同様に10%以上の企業においては18%の増加が、いずれも統計的に有意に確認できる。これはリーマン・ショック時に、銀行依存度の低い企業が資金制約に陥っていなかったことを示唆するものであり、社債市場の混乱時に銀行貸出が代替的な役割を果たしていたと結論づけられる。