景気の回復にもかかわらず価格が上がらないのは、他社に顧客を奪われるのを恐れるからだとの指摘が聞かれる。これをモデル化したのが、根岸隆東京大名誉教授らがかつて原型を示した「屈折需要曲線」とよばれるものである。
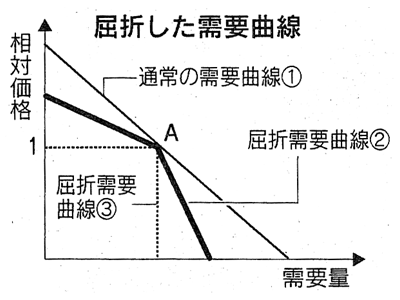
図はある企業についての需要曲線である。縦軸はその企業と同業他社の価格の比率(相対価格、1は他社の価格と同価格)を、横軸は相対価格に応じたその企業の商品への需要変化を示す。実線は通常の需要曲線((1)、価格弾力性は一定)である。
太線で示した屈折需要曲線(2)は通常の需要曲線と次の点で異なる。まずA点(同業他社と同価格の状況)から値上げすれば、他社に比べ高いのでより急激に客が減る。A点以上の価格で(2)が(1)の内側にあるのはこれを表す。
A点から値下げする場合はどうか。他社より安いので客は増える。しかし客が一気に他社から流れてくることはない。各社の値段に差がつき始めると、消費者はどの企業の商品がより安いか、またどこかがもっと下げないか時間をかけて探るからだ。A地点以下の価格で(2)が(1)の内側にあるのはこれを示している。
重要なのは、A地点から値上げした場合の効果と値下げした場合の効果が異なる(非対称な)ことである。この非対称性があるときは、企業にとっては価格を1から動かさないことが最適な選択となる。
たとえば、需要曲線が(3)のように極端に屈折した場合、少しでも値上げすればすべての客を失う一方、値下げしても顧客が反応しないため、企業はコストが変わっても価格をAに据え置く。これほどでなくても需要曲線が屈折していれば、価格は据え置かれやすくなる。これは多くの日本企業の現状に近い。この屈折が価格の粘着性(硬直性)を高めている可能性がある。
ただ、客が価格に敏感になるだけでは需要曲線は屈折しない。屈折が生じるのは、どの商品が安いかを消費者が知らず、それを調べる時間が長いときである。インターネットを利用し時間とコストをかけて価格を比較する消費者などが増えていることは、まさにこの状況を反映している。
2007年8月9日 日本経済新聞「やさしい経済学―動かぬ物価の深層」に掲載

