自然利子率は一定の仮定をおけば推計でき(図)、それは金融政策をめぐる論争を解くヒントにもなる。
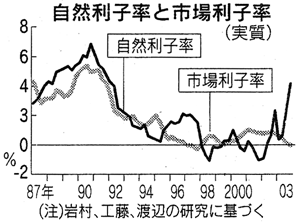
1980年代後半のバブル期には株や土地など資産価格が急騰した半面、一般の物価(消費税導入前)は落ち着き円高圧力も強かったことから、日本銀行は金融引き締めを急がなかった。当時も日銀の姿勢は問われ、論争は加速したが、自然利子率の観点からも、やはり早めの引き締めが適切であったことがわかる。図のように自然利子率を基準にすると、この時期(87年半ばから)の実質市場利子率は低すぎ、利上げのサインを発していたからだ。
一方、デフレが日本経済に押し寄せた98年には、その状況認識や克服策をめぐって百家争鳴の状態となった。P・クルーグマン氏らのインフレ政策論などが注目された時期だが、その年には自然利子率がゼロを下回っており、同氏らが指摘したように、名目利子率はマイナスにならないという制約が金融政策の足かせになっていたことが改めてうかがえる。
さらに注目したいのは、大論争が再び巻き起こるなかで前回ゼロ金利が解除された2000年8月の前後の時期である。自然利子率は2000年春にかけて1%程度に上昇したものの、経済環境の変化もあって同年後半には再び負に落ち込んでいたのだ。結果論だが、当時の解除尚早論に軍配が上がった形である。
では、今後の政策について自然利子率は何を示唆しているのだろうか。02年後半以降、それはかなり上昇し現時点でゼロを大きく上回っていると推察される。この面では、ゼロ金利解除の環境が整いつつあるといえる。その先の名目利子率は、自然利子率の上昇テンポなどで決まることになるが、それは(1)景気などの循環的要因(2)技術進歩などの趨勢的要因――に左右される。(1)は当面、自然利子率を上昇させる方向に作用しそうだが、(2)について楽観は禁物だ。クルーグマン氏は(2)の中で技術進歩と人口成長を重視するが、人口成長に関しては不安が増している。これは中長期的な自然利子率低下の要因となりうる。
2006年6月6日 日本経済新聞「やさしい経済学 ゼロ金利の解除」に掲載

