危うい農業ブーム
日本の農業を長年見てきた筆者にとって信じられないブームが起きている。最近の不況で農業が雇用の受け皿として注目を浴び始めているというのだ。その根拠は、農業は高齢化が進んで人手不足だというのだ。たしかに高齢化は進行している。年齢別農業就業人口の構成(2008年)をみると、39歳以下は8.5%に過ぎず、70歳以上46.8%となっており、日本農業の担い手の2人に1人は70歳以上ということだ。
しかし、高齢化が進んでいることは人手不足なのだろうか。農業が人手不足なら、これまでなぜ農業の後継者が出てこなかったのだろうか。農家の跡継ぎはなぜ農業をやろうとしないのだろうか。新規就農者もこの10年間7~8万人という微々たる数字である。2007年の新規就農者は、前年より9.3%減少し、7万3460人となっている。このうち、40歳未満は1万200人で14%に過ぎず、60歳以上が3万8800人と53%も占めている。新規就農者の半分以上は定年退職して実家に戻った人なのである。日本農業の実態は、80歳の人が引退して、60歳の人がその後継者となるというものだ。
2007年の農業の生産額は8兆2000億円であるが、これはパナソニック1社の売上9兆1000億円にも及ばない。そのパナソニックの従業員は30万人弱なのに、農業就業人口は252万人もいる。農業は、人手不足というよりむしろ過剰就労の状況なのである。過剰就労している人たちが高齢化しているのが実態である。高齢化は人手不足ではない。
生産額から肥料、農薬、機械などの投入材の額を引いた農業のGDPは4兆7000億円に過ぎない。これを農業就業人口で割れば、農業者1人あたりの平均所得は年間187万円、1カ月あたりでは15万5000円となる。最近、農業生産法人が人材を募集したところ、15万円の収入では家族3人食べていけないといって帰ってしまった人がいたという報道があったが、この15万円という収入は統計数値とほぼ一致している。
農業の収益が低いから、農家の跡継ぎも農業をやろうとはしないし、新規就農しようという人も出てこないのだ。高齢化はその結果である。農業の収益を上げることに成功できない現状では、農業での雇用創出は困難である。就農説明会にたくさんの人が集まっても、就農にはつながらない。
しかも、農業には技術がいる。天候、土壌などの地域によって異なる自然条件に見合った肥料・農薬や作物の選択など、多種多様な知識や技術が必要となるのだ。米、花、野菜、果樹それぞれ必要な技術は異なる。工場の流れ作業のなかで仕事をしていたから、あるいはマニュアルに沿ってハンバーガーを売っていたからといって、簡単に農業ができるわけがない。
就農した人達は、農業生産法人の従業員となったり、地域農業のリーダーである専業農家の指導を受けたりしながら、数年かけて農業技術を学んでいるのが実情だ。また、技術を磨いたからといって、地域の人と上手く交流できなければ、なかなかよそ者には農地を貸してくれない。農業はそんなに甘くない。
衰退してきた日本農業
米の778%という関税に代表される異常に高い関税で国内農産物市場を外国産農産物から守っているにもかかわらず、農業の衰退に歯止めがかからない。
明治初期の1875年から1960年まで実に85年間、農地面積600万ha、農業就業人口1400万人、農家戸数550万戸という3つの基本数字に大きな変化はなかった。皮肉にも農業基本法が作られた1961年以降、農業の衰退が始まった。
1960年から最近年までの約50年の推移を見ると、GDPに占める農業生産は9.0%から1.0%へ、農業就業人口は1196万人から252万人へ、総就業人口に占める農業就業人口の割合は26.6%から4%へ、農家戸数は606万戸から285万戸へ、食料自給率は79%から41%へ、いずれも減少した。農地面積は609万ha(1961年)から461万haへ減少した。農産物を販売している販売農家196万戸のうち、専業農家のシェアが34.3%から22.6%へ減少している一方で、農外所得(兼業所得)の比重の多い第2種兼業農家は32.1%から61.7%へと大きく増加している。専業農家といっても、65歳未満の男性のいる農家は全農家の9.5%に過ぎない。専業農家の多くは、第2種兼業農家が定年退職してサラリーマン収入がなくなったために、定義上専業農家となった高齢農家である。
2006年の農業生産額は8.5兆円、農業のGDP(国内総生産)はこれから農業中間投入額を差し引いた4.7兆円である。しかも、関税や価格支持等によって守られたところが大きく、これらの支持を示すOECDが計測した目本の農業保護額(PSE一生産者支持推定量)は4.5兆円で、農業のGDPとほぼ等しい。農業保護がなければ、農業のGDPはほとんどゼロ、ときによってはマイナスとなってしまうのだ。
食料安全保障の前提となるのは、農地資源の確保である。戦後、人口わずか7000万人で農地が500万ha以上あっても、飢餓が生じた。国民への食料の安定供給という目的のために、農業には手厚い保護が加えられてきたはずなのに、食料安全保障に不可欠な農地は転用、潰廃され続けた。
公共事業等により105万haの農地造成を行った傍らで、1961年に609万haあった農地の4割を超える250万haもの農地が、耕作放棄や宅地などへの転用によって消滅した。これは、北は北海道から南は沖縄に至る、現在の全ての水田面積250万ha(減反しているので、米を作っている面積は150ha)に等しい。
単純な算数だが、農地面積が一定で、農家戸数が減ると、1戸あたりの経営規模は拡大する。規模が拡大すると、コストは下がり、農業収益は増加する。しかし、我が国では、農地面積も大きく減少した。
高度成長期以後、農業の機械化が進んだ。機械(田植え機)により労働(手植え)を代替することができたので、1haあたりの労働時間が短縮した。労働時間が変わらなければ、より多くの面積を耕作できることになる。適切な政策が採られていれば、これを農業の規模拡大、体質強化につなげることもできたのだが、労働時問が余ったので、他産業への就業による兼業化が進み、零細な兼業農家が滞留してしまった。これは機械化の進展した米作において最も顕著だった。
フランスでは、農家戸数は大きく減少したものの、耕地面積の減少はわずかであったため、農家の経営規模は拡大した。 1980年から2006年にかけて、農家の経営規模は、フランスでは25.4haから52.3haへと拡大しているのに対し、日本では1.2haが1.8haになっただけである。
また、フランスでは、総投下労働時間のうち農業への投下労働時間が半分以上、所得のうち農業所得が半分以上を占めるという工業的農家に、農業政策の対象を限定した。パートタイム・ファーマーはフランス農政の対象ではない。農業を保護してもよいが、保護に値する農家は真剣に農業をやっている農家だというのだろう。我が国で増えている数字は、フランスではパートタイム・ファーマーといわれる兼業農家と高齢農家の比率だ。
農政の失敗
兼業農家が滞留して主業農家の規模拡大が進まなかった原因に、農政がある。所得は、価格に生産量を掛けた売上額からコストを引いたものである。我が国農政の特徴は、農家所得を向上させるために価格を引き上げたことである。その典型が米である。
「食糧管理法]は、当初は消費者保護を目的とした立法であり、国民の購買力が乏しい中で、米価は戦前の価格水準や当時の国際価格よりも低く設定された。1935年は国際価格の約半分の水準であり、国際価格よりも低い米価は1953年まで続いた。米も含め、輸入食料価格が国内価格よりも高かったため、1950年代前半まで政府は価格差補給金を支出して、輸入食料を安く国民に供給していた。
1961年の「農業基本法」が提唱した規模拡大を通じたコストダウンによって、農業だけて他産業並みの所得を得ることのできる「自立経営農家]を実現しようという考え方に対し組合員の圧倒的多数が米農家で、農家戸数を維持したい農協は、構造改革に反対した。米価を上げて、少数の主業農家ではなく多数の兼業農家を維持する方が、農協にとって政治力の維持や販売手数料収入の増加など、農協経営の安定につながるからである。食糧管理制度の時代、農協は米農家の所得向上のため、生産者米価引上げという一大政治運動を展開した。
選挙で戦後最大の圧力団体と言われた農協の支援を受けざるをえない自民党の圧力により、農業基本法の考え方とは逆に、実際の農政は、農家所得の向上のため米価を引き上げたのである。
農協の意図したとおり、コストの高い零細な兼業農家も高い米を買うよりも自ら米を作る方が得になり、農業を続けてしまった。零細な兼業農家が農地を手放さなかったため、農地は農業だけで生活していこうとする農家らしい主業農家に集積されず、規模拡大による米農業の構造改革は失敗した。農外所得を求めて離村した北海道では、残った農家の規模が順調に拡大したが、都府県ではほとんど農家経営規模は拡大しなかった。
高米価は、消費を減らす一方で生産を刺激し、米は過剰になった。このため、1970年以降実施しているのが「減反(生産調整)政策」である。1995年に食管制度が廃止されて、米の政府買入れが備蓄用に限定され、かつての生産者米価がなくなってからは、米価は減反によって維持されている。
減反は米価維持の「カルテル」である。およそカルテルというものは、カルテル参加者に高い価格を実現させておいて、その価格で制限なく生産するアウトサイダーの生産者が得をする。拘束力のあるカルテルが成立するためには、アウトサイダーが出ないよう、アメかムチが必要となる。現在、年問約2000億円、累計総額7兆円の補助金が、他産業なら独禁法違反となるカルテルに、農家を参加させるためのアメとして、税金から支払われてきた。
単収を向上させればコストが下がるが、総消費量が一定の下で単収が増えれば、米生産に必要な水田面積は縮小するので、減反面積をさらに拡大せざるを得なくなる。そうなると、政府は農家への減反補助金を増やさざるを得なくなる。このため、単収向上のための品種改良は、国や都道府県の試験場における農業技術者の間ではタブーとなってしまった。こうして、単収増加も阻害された。現在の米単収は、ヘリコプターで種まきしているカリフォルニアの粗放農業より3割も低い。終戦時で国際価格の半値、1953年まで国際価格より安かった米は、今では778%の関税で保護されている。
しかし、この減反政策はすでに限界に達している。農業の衰退を表すものとして、高齢化と並び、耕作放棄地が39万haにのぼり、東京都の面積の1.8倍、埼玉県の全面積に匹敵することが話題になっている。農林水産省の公式見解は、高齢化したから耕作放棄しているというものである。しかし、これは誤りである。
既に減反が水田面積の4割、100万haにも及び、限界に近いところにきているので、消費が減少しても、減反を十分には拡大できない。当然、米価は低下する。かつての食糧管理制度の下での高米価時代と異なり、1996年までは60kgあたり2万円以上していた米価が、1万5000円程度に低下した。米を作ると赤字になるので、コストの高い零細農家は農地を手放している。
しかし、受け手の主業農家も、米価の低下によって地代負担能力が低下しているため、農地を引き取れなくなっているのだ。両者の間に落ちた農地が耕作放棄地だ。
米価低落による農業収益の減少こそが、耕作放棄の本当の原因である。食糧管理制度の下での高米価時代には、耕作放棄は話題にも上らなかった。農林水産省が原因に挙げている高齢化も、耕作放棄と同様、農業収益低下の結果である。農業収益が高ければ、新規就農者や後継者が増えて、高齢化は起きない。高齢化と耕作放棄が同時に起こっているからといって、その間に因果関係はない。農林水産省が高齢化を原因に挙げるのは、農業収益の低下を認めたくないからだ。それは、農政の失敗を認めることと同じだからである。
少子高齢化・人口減少時代に生き残る道
米の1人当たりの年間消費量は過去40年間で118kgから60kgへ半減した。これまでは、総人口は増加したが、今後は高齢化し、1人あたり消費量がさらに減少するとともに、総人口も減少する。このため、米の総消費量は1人あたりの消費量減少と人口減少の二重の影響を受ける。これまでどおりの米価維持政策をとった結果、今後40年で1人あたりの消費量が現在の半分になれば、2050年頃には米の年間総消費量は今の850万トンから350万トンになる。減反は200万haに拡大し、米作は50万ha程度で済んでしまう。
これは米に限らない。高齢化が進むと、1人あたりの農産物消費量は減少する。それに人□減少が追い討ちをかけるのである。日本農業は大幅に縮小し、農地資源も大きく減少する。緊急時の消費を規定する国内の生産力が大幅に減少してしまうのである。
これまで政府による食料安全保障の主張は、高い関税を維持して農業の国内市場を守ろうとするものだった。しかし、少子高齢化、人口減少は国内市場を縮小させる。これは日本農業のさらなる衰退を招き、農地資源を減少させて食料安全保障を危うくさせる。農業の構造改革を推進し、日本の米などの農産物の価格競争力が高まれば、発展するアジア市場に輸出できるようになる。平時には米を輸出して、アメリカ等から小麦や牛肉を輸入する。食料危機が生じ、輸入が困難となった際には、輸出していた米を国内に向けて飢えを凌げばよい。こうすれば平時の自由貿易と危機時の食料安全保障は両立する。というよりも、人口減少により国内の食用の需要が減少する中で、平時において需要に合わせて生産を行いながら食料安全保障に不可欠な農地資源を維持しようとすると、自由貿易のもとで輸出を行わなければ食料安全保障は確保できないのである。これまで食料安全保障の主張は、国内農業保護、特に高い関税の維持、自由貿易反対のために利用されてきた。これからの人口減少時代には、自由貿易こそが食料安全保障の基礎になるのである。
実は、図が示す通り、国際価格の上昇によって、減反を廃止して米価を60kgあたり9500円程度に下げれば、輸出が可能な状況になっている、減反を段階的に廃止して米価を下げれば、コストの高い兼業農家は耕作を中止し農地をさらに貸し出すようになる。そこで、一定規模以上の主業農家に面積に応じた直接支払いを交付し、地代支払能力を補強すれば、農地は主業農家に集まり、規模は拡大し、コストは下がる。また、規模の大きい農家ほど肥料や農薬の投入量が少ないので、環境にやさしい農業を実現できる。
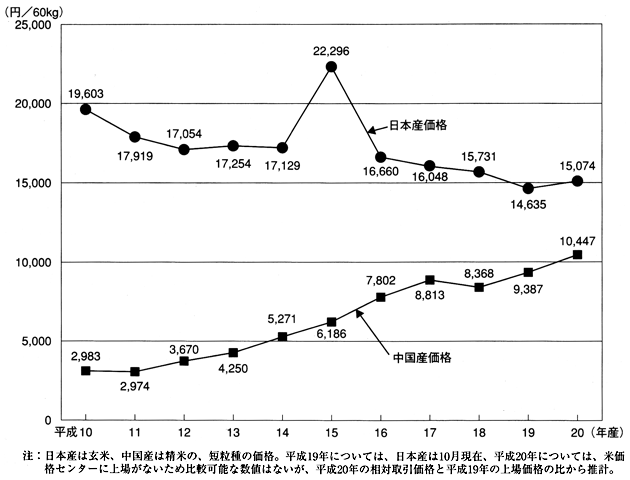
収益または所得は「価格×生産量-コスト」に他ならない。日本農業の収益を向上させ、食料安全保障に不可欠な農地を維持するためには、品質の良い高い価格の農産物を生産するか、生産を拡大し、生産量を増やすとともに、コストを下げるなどの方法を工夫していくしかない。その手段として、直接支払いとともに、金融に期待される役割が大きい。
農業発展に工夫の余地はある。(1)ゴボウが長くスーパーのレジ袋から飛び出るために売れないことに気づき、ゴボウを半分に切ってスーパーヘの売上を大きく伸ばした農家、(2)独特の技術を磨き野菜の苗作りに特化し、わずか数haの農地で数億円を稼ぐ農家、(3)農薬や化学肥料を使わない有機栽培、発芽玄米、冷めても硬くなりにくい低アミロース米、抗酸化作用のある色素を多く含む紫さつまいもなど付加価値の付いた農産物の栽培に取り組む農家、(4)加工・惣菜・外食・観光(グリーンツーリズム)という1次、2次、3次の合計6次産業化によって所得を伸ばしている農家等がある。
スーパーでは、規格外の曲がったキュウリも切ってしまえば普通のキュウリと同じく、外食用に活用できるのであり、外食だけをターゲットにする経営方法もある。南北半球の違いを利用して、ニュージーランドがキウイを供給できない季節に、ニュージーランド・ゼスプリ社と栽培契約を結び、同社が開発した黄色の果肉のゴールド・キウイを日本国内で生産・販売する方法もある。
グローバル化をうまく利用して成功した例として、(1)長いほど滋養強壮剤としてよいと考えられている台湾で、日本では長すぎて評価されない長いもが、高値で取引されている例、(2)日本では評価の高い大玉をイギリスに輸出しても評価されず、苦し紛れに日本では評価の低い小玉を送ったところ、「やればできるではないか」と言われたというあるリンゴ生産者の話、(3)多くの労働が必要な苗までは労賃の安い海外で生産し、それを輸入して日本で花まで仕上げるという経営方法で成功した農家がある。
条件が不利な中山間地域農業にも可能性がある。農業は、季節によって農作業の多いときと少ないとき(農繁期と農閑期)の差が大きいため、労働力の通年平準化が困難だという問題がある。米作でいえば、田植えと稲刈りの時期に労働は集中する。したがって、農繁期に合わせて雇用すれば、他の時期には労働力を遊ばせてしまい、大きなコスト負担が発生する。目本の稲作の平均的な規模は1ha程度である。平坦な北海道では農地の区画も大きく、大規模米作農業の展開が可能と考えられやすいが、田植えと稲刈りを短期間で終えなければならなくなることから、夫婦2人の家族農業で経営できる農地は10~20ha程度となってしまう。
これに対し、中山間地域では標高差等を利用すれば田植えと稲刈りにそれぞれ2~3カ月かけられる。これを活用して、中国地方や新潟県の典型的な中山間地域において、家族経営でも10~30haの耕作を実現している例がある。この米を冬場に餅などに加工したり、小売へのマーケティングを行ったりすれば、通年で労働を平準化できる。平らな北海道米作農業より、コスト面で有利になるのである。
つまり、中山間地域では、条件の不利性を逆手にとった対応が可能なのである。これをもっと大規模に展開できれば、人も雇えるようになる。ハンディキャップを持つとされる中山間地域農業にもこのような可能性がある。
特殊だった農業金融
従来、農業金融は、農協と日本政策金融公庫(旧農林漁業金融公庫)が独占してきた。農協は、施設や長期的な運転資金のための政府の利子補給による農業近代化資金や、農家の短期的な運転資金を中心に業務を行い、日本政策金融公庫は長期低利の設備資金を中心に業務を行うという仕分けがあった。しかし、公庫の支店店舗は限られているので、農協が公庫資金の窓口業務を行い、長期の資金需要には公庫資金の転貸と農業近代化資金、短期の資金需要には営農貸越といわれる農協の自己資金で対応してきた。つまり、農業金融は農協金融だった。
農協の金融業務は、農協職員が農家に生産技術や経営などの営農指導を行う一方、農家の肥料、農薬、農機具などの生産資材の購入代金と農産物の販売収入を、組合勘定と呼ばれる農協口座でまとめて管理することにより、農家の経営状況を常に把握したり、コントロールしたりすることによって可能となった。こうして情報の非対称性を解消するとともに、農地を担保に取った。しかし、これは農協による農家支配の手段ともなった。農協の組合勘定には、貸付限度額というものがあり、貸付がこれを超えると、農協は長期の資金に借り替えさせて、組合勘定の貸付残高をいったんゼロにする。こうして、また農家に肥料や農薬を買えるようにさせる。このため、借金が雪だるま式に膨れ上がる。ある農家は、これを水面下に潜りっぱなしで、浮上しない「原子力潜水艦」と呼んだ。いよいよ農家が返済できなくなると、農地を売却し離農させることによって借金を返済させるというやり方がとられた。
しかしこのような農協による独占的な金融業務は揺らいでいる。農家のなかで圧倒的に多いのは、米価政策によって温存された米の兼業農家である。農業から足抜きしようとしている兼業農家が多ければ、サラリーマン収入などの農外所得や農地の切り売りで得た転用売却利益を農協に預金してくれるので、農協は大きな運用益をあげることができる。また、農協の保険事業も少数の主業農家ではなく、多数の兼業農家相手に実施するほうが高い収益をあげることができる。こうして農協は「脱農化」によって莫大な利益を得た。
しかし、これは農業で生計を立てている主業農家を農協から離反させることとなった。主業農家が良い品質の農産物を農協を通じて販売しても、他の農家の生産物と一緒に販売されるので、単価は同じとなる。このため、量販店への直接販売など、農協を通さないで販売するようになった。また、肥料などの農業資材の購入についても、零細な農家への販売を主体とする農協はコスト高になるので、農業収益向上のため、大きなロットの資材をまとめて安く購入しようとする主業農家は、農協以外のルートで購入するようになった。減農薬、減肥料栽培を行う農家は、直接販売の比重が高いうえ、農協からの農薬などの資材の購入が少なくなる。いずれの場合でも、農協には手数料収入が落ちなくなるので、農協はこれらの農家に対して様々な圧力を加えてきた。地銀の預貸率8割に対して、農協は3割に過ぎず、しかも農協による融資のほとんどが住宅ローンやアパート経営資金などで、農業には農協融資のうち数%しか回っていないことは、農業が衰退し資金需要が減少するなかで、大きな資金を必要とする主業農家が農協から離反していることの証左でもある。農業金融全体は縮小しているが、1件あたりの貸出額は大口化している。これに農協は対応できなくなっている。
農協融資の農地担保主義も農業の発展に沿わなくなっている。現在、規模拡大している農家は、農地を売買によって取得しているのではなく、賃貸によって規模を大きくしている。たとえば、1haの所有地に29haの借地によって30haで営農している。このとき、農家の資金需要は30haに見合う規模の経営から生じるものである。これに対し、農地を担保にとって資金を貸せるのは1ha見合いの経営分に過ぎなくなる。さらに、農地の価格自体も低下し、担保価値が減少している。地銀などの民間金融機関がABL(動産・債権等担保融資)により経営全体を担保にとって融資を行えば、農協から離反している大規模な主業農家の資金ニーズを捉えることが可能となる。
農業金融のあり方
地銀に期待するところ大とはいえ、これまで農業関係の融資を行ってこなかったハンディキャップは存在する。農業と工業の大きな違いは、農業が自然を相手にすることだろう。天候不順によって収量は変化する。地域によっても自然条件は同一ではない。同じ県でも、ある地域は不作でも、別の地域は平年作という場合もある。農地の一筆ごとにも土壌、日照等の条件に変化がある。農家の農法によっても違いが出てくる。
加えて、経営の形態も、自然人、法人、集落営農など様々であるうえ、作る農産物も多様で技術面だけでなく、個々の生産物の需給などの経済状況も様々である。また、いくら大規模化か進行しているとはいえ、他の産業に比べると経営規模は零細で資金需要も小口である。
つまり、農家経営を営農指導や組合勘定から十分に把握できる農協と比べ、民間金融機関の場合、情報の非対称性が顕著となる結果、農業融資に関する情報生産にコストがかかってしまう。この1つの解決方法として、これまで長期の農業金融を行ってきた日本政策金融公庫と連携することが考えられる。農協金融と異なり、日本政策金融公庫には融資の窓口が少ない。地銀が窓口業務を担当する代わりに日本政策金融公庫から農業情報を人手し、公庫は長期の設備資金、地銀は運転資金を融資するという協調も考えられる。現に、公庫と地銀の連携は各地で進行しており、公庫は提携金融機関に有償でACRIS(農業信用リスク情報サービス)を提供するとともにプロパー資金に農業信用基金協会による債務保証が与えられない地銀に対してCDS(クレジット・デフォルト・スワップ)を行い、地銀の審査にかかる負担を軽減し、事実上の信用補完を提供している。政策的にも、このような流れを推進していくべきである。例えば、農業信用基金協会には、農家とともに農協も会員となれるが、一般の金融機関は会員とはなれない。信用保証の審査を受けようとしても、協会等の幹部が農林中金等農協関係者であれば、農協への情報流出を懸念してしまう。このような規制を徐々に緩和していくべきだろう。
農協金融は、昭和恐慌から農村を貧困から脱却させるために、有名な「経済更生運動」によって、産業組合のまだ設置されていない町村の解消を目指すとともに、全農家の加入、「信用・購買・販売・利用」の4種事業を兼営化する産業組合を推進したことに起源がある。これによって、商人系の金融機関は農村から駆逐され、農業・農村のすべてを事業とする世界に例を見ない総合農協ができあがった。民間金融機関の農業金融への参入は、農協による独占に風穴を開け、農業の構造改革を一層推進する可能性もある。
『地銀協月報』2010年4月号(全国地方銀行協会)に掲載


