食料危機
2008年、穀物などの農産物価格は、2000年に比べ大豆の価格は2.5倍、とうもろこしは3倍、小麦は5倍に高騰した。これは、人口・所得の増加による食用需要の増加やエタノール需要の増加等によるものである。世界人口は20世紀初めの16億人から2000年には61億人となり、2050年に92億人へ増加すると推測される。さらに、(畜産物1キログラムを作るのに、牛肉では11キログラム、豚肉では7キログラムのとうもろこしが必要なので)経済成長による畜産物消費の増加によって穀物需要は大幅に増加する。
世界のバイオ・エタノール生産は、2002年の3407キロリットルから2007年には6256キロリットルに約倍増した。このうち41.7%のシェアを持つアメリカは国内とうもろこし生産の3割を、32.3%のシェアを持つブラジルは国内サトウキビ生産の5割を使用している。穀物のエネルギー利用が進むことで、穀物価格と石油価格が連動するという新たな現象が起きている。
このような需要の増加に供給サイドが対応できなければ、国際価格はさらに上昇する。これまで世界の農業は、人口増加に単位耕地面積当たりの収量(単収)の増加で対応してきたが、単収の伸びは1960年代の3.0%から1970年代の2.0%、1980年以降の1.5%へと逓減傾向にある。
以前から、アメリカやオーストラリアなど世界の大規模畑作地域等において、土壌流出、地下水枯渇、塩害などによる生産の持続が懸念されている。土壌は風と雨によって浸食されるが、アメリカでは、大型機械の活用により表土が深く耕されるとともに、機械の専用機化により作物の単作化が進み、収穫後の農地が裸地として放置されるので、土壌浸食が進行する。かんがい等のための過剰な取水により、アメリカ大平原の地下水源であるオガララ帯水層の5分の1が消滅した。乾燥地で排水を十分しないままかんがいを行うと、地表から土の中に浸透する水と塩分を貯めた排水されない土の中の水が毛細管現象でつながってしまい、塩分が地表に持ち上げられ、表土に堆積する。これが塩害である。これで古くはメソポタミア文明が滅び、20世紀ではアラル海が死の海となった。さらに、地球温暖化が食料生産に与える影響がいまだ十分には解明されていないという問題がある。
農地確保こそ食料安全保障の基礎
我が国では「比較優位のない農産物を日本で生産するのは不合理だ。石油を輸入に頼っている日本では、食料安全保障だけ考えても幻想であり、自由貿易を守り、輸入供給ルートを確保することこそが重要だ」という議論がある。
農業の生産要素について、例えば除草剤や農業機械は労働で、化学肥料は堆肥でそれぞれ代替可能である。農業機械を動かすのに必要な石油の輸入ができなくなれば農業生産が行われなくなるという議論は、この生産要素間の代替性を考慮していない。農薬、化学肥料、農業機械がなくても戦前まで農業は営めたのである。
ウルグアイ・ラウンドで、1973年のアメリカの大豆禁輸のような輸出制限への規制を我が国は提案したが、インドの大使から不作の時に国内消費者への供給を優先するのは当然ではないかと反対された。また、輸出税は国際経済学では輸入関税と同様の効果を持つとされながら、GATT・WTOでは何ら規律もない。GATT・WTOは輸出国の論理で組み立てられている。輸出国にとって、他の国が輸出制限や輸出税を課せば、国際市場への供給が減少し価格が上昇するので、利益を受けるからである。現在、多数の国で輸出制限等が行われている。生命維持に不可欠な食料については、自国の国民も苦しいときにほかの国に食料を分けてくれるような国はない。自由貿易が食料安全保障を確保してくれるというのは国際食料市場の実情を理解しない議論である。
食料安全保障とは、国際的な食料・農産物価格が高騰したり、海外から食料が来なくなったときに、どれだけ自国の農業資源を活用して国民に必要な食料を供給できるかという主張である。このとき必要な農業資源が確保されていなければ飢餓が生じる。農業の生産要素の中でも水と土地は他の生産要素で代替できない。農地が減少していれば食料供給が脅かされるときに、必要な農地を確保できず農業生産を十分に拡大できなくなる。これが平時において農地資源を確保しなければならない国際経済学上の理由である。
このように食料安全保障の前提となるのは農地資源の確保である。戦後、人口わずか7000万人で農地が500万ヘクタール以上あっても飢餓が生じた。しかし、農地は1961年に609万ヘクタールに達したのち、公共事業等により110万ヘクタールの農地造成を行った傍らで、現在の水田面積を上回る260万ヘクタールもの農地が、耕作放棄や宅地などへの転用によって消滅した。小作人に転用させて莫大な利益を得させるためではなく、農地を農地として利用させるために農地改革は実施されたのに、小作人に開放した194万ヘクタールをはるかに上回る農地が潰されてしまった。現在では、イモだけ植えてやっと日本人が生命を維持できる463万ヘクタールの農地が残るのみである。
「自給率向上」議論の誤り
食料危機が唱えられる中で、60年の79%から40%にまで低下した食料自給率を向上させるべきだと主張されるようになった。食料自給率は国内の農業が国内消費だけではなく海外市場も含めどれだけの消費に対応しているのかという指標としては意味がある。しかし、食料安全保障とは、海外から食料を輸入できなくなったときにどれだけイモや米などカロリーを最大化できる農産物を生産して国民の生存を維持できるかという問題であり、飽食の限りを尽くしている現在の食生活を前提としたまま食料自給率を云々することは無意味である。畑に花を植えることは、食料自給率の向上には全く貢献しないが、農地資源を確保できるので食料安全保障に貢献する。目標とすべきは農地資源面積であって食料自給率ではない。
しかも農政は、食料自給率向上を唱えながら、実際には自給率が低下する政策を採り続けているという問題がある。自給率低下は食生活の洋風化のためであるというのが農林水産省の公式見解である。しかし、米の需要が減少し、麦(パン、スパゲッティ)の需要が増加することを見通していたのであれば、米価を下げて需要を拡大し、麦価を上げて生産を増加させるべきだった。米価を下げても農業の規模拡大等の構造改革を行い、コストを減少させれば、稲作所得は向上できるはずだった。
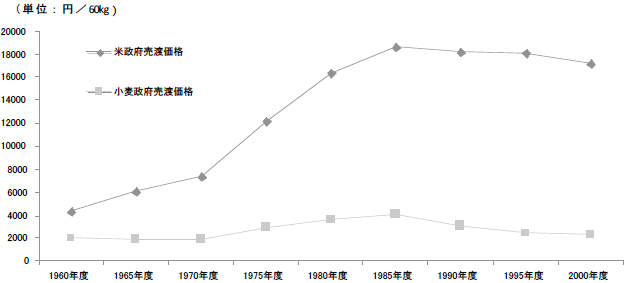
しかし、政治的な圧力に押された農政は、米価を大幅に引き上げて農家の所得を保障しようとした。高米価政策により消費は一層減少し、生産は刺激されたので米は過剰となり、70年から40年近くも減反(生産調整)を実施している。他方で、農業資源は収益の高い米から他の作物に向かわず、麦は安楽死した。減反は年々拡大し、現在では水田の4割に相当する110万ヘクタールに及んでいる。米については約1400万トンの潜在生産力がある中で約500万トン相当の生産調整を実施する一方、毎年約700万トン以上の麦を輸入している。図は米の価格が引き上げられる一方で、麦の価格はほとんど変化しなかったことを示している。米から麦へという洋風化の圧力があるにもかかわらず、自給できる米の価格を上げて輸入物の麦よりも米をいっそう不利にしてしまったのである。外国産優遇政策をとれば、自給率低下は当然ではないか。
EUも同じように高い農産物価格で農家を保護したが、日本が高価格で減少した国内需要量に生産をあわせて減反させたのに対し、EUは作りたいだけ作らせて過剰生産物に補助金をつけて国際市場に輸出した。域内の自給を超えて輸出するのだから、EUの食料自給率が100%以上となるのは当然である。これが、EUの自給率が向上し、日本では低下した大きな理由である。
減反を廃止して戦後農政を転換せよ
減反は米価維持のカルテルだ。消費者に高い価格を払わせ家計を圧迫しているうえ、現在約2000億円、累計総額7兆円の補助金が本来なら独禁法違反のカルテルに参加させるためのアメとして生産者に税金から支払われてきた。
高米価と減反政策は農業依存度の高い主業農家に悪い影響を与えた。低コスト生産のためには、高コストの零細兼業農家に減反面積を多く配分すべきなのに、転作する時間も技術もない兼業農家のために主業農家の負担を重くした。主業農家は、そもそも高米価政策で零細兼業農家が滞留したため農地を集積できないという不利益を受けたうえ過重な減反配分を強いられたことから、コストを十分低下できるまで米生産を拡大できず、所得を増加できないという不利益を受けた。高米価と減反という政策が健全な農家の育成・発展を阻み続けているのだ。主業農家の生産シェアは、野菜82%、牛乳95%に対し、米は38%にすぎない。米農家は戸数では全販売農家の6割も占めているが生産額では全農業の2割にすぎない。
農政の現場にも大きな負担がかかった。水田の4割にも及ぶ規模の減反面積の配分は困難な作業だった。米生産による収益の低い農家については、減反奨励金の水準は米と他作物の収益の均衡を図るという点では十分だが、秋田県大潟村のようなコストが低いところや新潟県のように米の値段が高いところでは、米生産収益が高くなり他作物からの収益と減反奨励金の合計を上回ることとなるため、米生産を行いたいという経済的に合理的な欲求を持つこととなる。このため、これらの地域では減反への協力はなかなか得られなかった。
これらの場合には減反奨励金を大きく設定すればよいのだが、財政的な理由から、減反奨励金は減額され続けた。このなかで減反面積を消化しようとすれば非経済的な手法に訴えざるを得なかった。このため、都道府県、市町村の減反担当者は農家の説得に多大な労力をかけてきた。兼業農家が多数なので日中に集会は開かれない。担当者は勤務時間外の夜の集会に出向いていったのだ。さらに、減反奨励金は転作による食料自給率向上が名目なので、転作作物を植えているかどうかという一筆毎の確認のために、市町村の減反担当者は現地確認を要求されるなど多大な労力を費やされた。本来ならば地域農政の先頭に立って農業の振興を図るべき優秀な人材が減反面積の消化という最も後ろ向きの行政に振り向けられたのである。
食料安全保障に必要な農地は足りないのに、減反で「農地も余っている」との認識が定着し、転用や耕作放棄が進んだ。戦後一貫して増加してきた水田面積は、生産調整を始めた1970年を境に減少に転じた。米価を今後も維持しようとすると国内の人口減少や高齢化による米消費量の減少にあわせて減反を拡大せざるをえない。これまでは総人口は増加したが、今後は高齢化しかつ減少する。これまでのように今後40年で1人当たりの消費量が現在の半分になれば、米総消費量は、1人当たりの消費量減少と人口減少の二重の影響を受け、現在の900万トンから350万トン程度まで減少する。減反は200万ヘクタールに拡大し、米作は50万ヘクタール程度ですんでしまう。
それだけではない。現在進行中のWTO交渉では、高い関税の品目には高い関税削減率を課すという方式が合意されている。高関税品目が多い日本は、できる限り多くの品目についてこの例外扱いを求めている。しかし、その代償として低税率の関税割当数量(ミニマムアクセス)の拡大が求められる。米のミニマムアクセスは消費量の13%、120万トンに増加し、減反のさらなる拡大、自給率の低下を招く。農地は一層減少し、日本の食料安全保障は危うくなる。
価格支持から直接支払いへ
アメリカやEUが財政による補助金で農家の所得を保証するという政策に転換しているのに、依然として日本では高い価格による消費者負担の割合が農業保護の9割を占めている。納税者負担による保護は累進的であるのに対し、これは貧しい人も負担するので逆進的である。国内の高い価格を維持しようとすれば、高い関税が必要になる。農業界がWTOやFTA交渉で関税引下げに強く抵抗するのはこのためである。
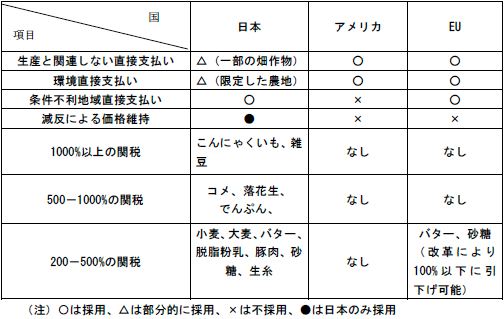
減反をやめれば米価は低下し、関税も要らなくなる。100万ヘクタールの減反面積を5年間かけて毎年20万ヘクタールずつ緩和していけば、米価は現在の60キログラムあたり1万4000円という価格から中国産米輸入価格約1万円を下回る9500円の水準にまで段階的に低下し、国内需要も拡大する。食管制度以来、米価を引下げようとすると、農協は農業依存度の高い主業農家が困ると反論してきた。そうであれば現在の米価低下分の8割程度を主業農家に財政で補てんすればよい。流通量650万トンのうち主業農家のシェアは4割なので、約1600億円で済む。これは、減反奨励金総額を下回る。
価格低下で高コストの零細兼業農家は農地を貸し出すようになる。EUが価格を引き下げて直接支払いという補助金を交付したように、減反奨励金を減反面積の縮小に合わせて削減する一方、段階的に拡大する価格低下分を主業農家に直接支払いしてその地代負担能力を高めてやれば、農地は主業農家に集積し、コストは低下する。主業農家の収益が向上すれば地主である零細な兼業農家の地代所得も増加する。だれに直接支払いを交付するかということと、誰にその利益が帰属するかということは別のものだ。
EUでは直接支払いのほとんどが出し手の地主に帰属した。農協が主張する零細農家切捨て論は誤りだ。また、兼業農家が退出したあとは主業農家が引き受けるので、食料供給にはなんら問題はない。さらに、週末片手間にしか農業を行えない兼業農家より、主業農家の方が肥料や農薬の投入量を減らすので環境に優しい農業が実現する。
減反奨励金総額が5年間で直接支払いに切り替わるということである。財政的な負担は変わらない上、価格低下で消費者はメリットを受ける。世界的な不況でリストラされる人が増えており、消費者家計は高い食料品価格を負担する力がなくなっている。国内の価格が輸入米の価格より下がれば、汚染米の原因となったミニマムアクセス米も輸入しなくてもよいので、食料自給率は向上する。さらに価格競争力が高まれば、アジア市場に米を輸出することが可能となる。EUが穀物価格の引き下げでアメリカから輸入していた飼料穀物を域内穀物で代替したように、価格低下は輸出という新しい需要も取り込むことができる。食料危機が生じた際には、インドや中国が行っているように、輸出していた米を国内に向けて飢えをしのげばよい。平時の自由貿易と食料安全保障は両立するのだ。
戦前農林省の減反政策案に反対したのは、食料自給を唱える陸軍省だった。食料の供給を制限し、高い価格により消費者家計を圧迫する政策が食料安全保障と相容れるはずがない。自給率が40%であることは、60%の食料を国際市場で調達し、食料輸入途上国の飢餓を増幅させていることに他ならない。戦後農政から脱却し、減反を廃止して米価を下げ、輸出によって農業を縮小から拡大に転じることこそ、日本が食料難時代に行える国際貢献であり、かつ我が国の食料安全保障につながる政策ではないだろうか。
つまり、減少を続ける国内米消費を前に、減反を拡大して食料安全保障に不可欠な農地を減少させ、高米価を守るための高関税の代償としてミニマムアクセス米を拡大して食料自給率をさらに低下させ、農業を衰退させるというこれまでの農政を維持するのか、価格を下げて拡大するアジア市場への輸出という新しい需要を開拓し、農地資源を維持しながら食料自給率を向上させるという強い農業を実現するための農政改革を果断に実行するのか、という選択だ。
別の角度から見ると、水田を票田としてとらえるのか、食料安全保障の基礎としてとらえるのか、という政治の選択だ。減反見直しを主張している石破農水大臣はこれを問うているのだろう。これを農業界だけの問題としてはならない。農政を真に食料安全保障に役立つ国民、消費者のものに取り戻せるかどうかという日本国民、消費者自身の選択なのだ。
『地域政策―三重から』2009年春季号 No.31(三重県職員研修センター)に掲載


