石破茂農林水産大臣が、昨年末に「減反見直し」に言及した。自民党農林族議員から猛反発を受けている。大臣の部下であるはずの農水省の役人に、「1年で代わる大臣の言うことを聞くのか、ずっと農林族であり続ける俺たちの言うことを聞くのか」と迫る議員もいる。どちらが日本農業再生につながるのだろうか。
食料安全保障とは、国際価格が高騰したり、海外から食料が来なくなったときに、どれだけ自国の農業資源を活用して国民に必要な食料を供給できるかという問題だ。それに不可欠なものは農地資源の確保である。
戦後、人口わずか7000万人で農地が500万ヘクタール以上あっても飢餓が生じた。現在は人口1億3000万人なのに農地は463万ヘクタールしかない。農地は1961年に609万ヘクタールに達したが、その後公共事業等により110万ヘクタールの農地造成を行った傍らで、現在の水田面積を上回る260万ヘクタールもの農地が耕作放棄や宅地などへの転用によって消滅した。この原因の1つがコメの減反政策だ。
高米価でコメ余りに
61年の農業基本法は、農地改革で固定化した零細な農業規模を拡大することによる農業のコストダウンを目指した。具体的には、農家戸数を減少させ、農地を集積させて農業だけで他産業並みの所得を実現できる規模の大きな農家を育成しようとしたのだ。所得は売上額(価格×生産量)からコストを引いたものだから、消費や売上額の伸びが期待できないコメでも、コストを下げれば農家所得を向上できる(図1)。
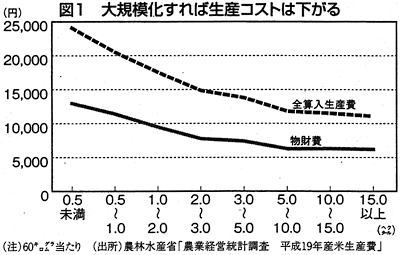
しかし、組合員の圧倒的多数が兼業のコメ農家で、農家戸数を維持して政治力を発揮したい農協は構造改革に反対した。
食糧管理制度の時代、農協はコメ農家の所得向上のため、生産者米価引き上げという一大政治運動を展開した。農協の意図したとおり、コストの高い零細な兼業農家も高いコメを買うよりも自らコメを作る方が得な価格になり、農業を続けてしまった。そのため、規模拡大によるコメ農業の構造改革は失敗した。
高米価は消費を減らす一方で生産を刺激し、コメは過剰になった。このため、70年以降実施しているのが減反(生産調整)政策である。農協は当初、できる限り多くのコメを政府に高い価格で売って手数料収入を多くしたいため、減反に反対した。政府が3兆円もかけた過剰米処理による財政負担を抑えるため、食管の買い入れ数量を制限しようとするのに対し、「全量政府買い上げ」が農協のスローガンになった。
しかし、95年に食管制度が廃止されて、コメの政府買い入れが備蓄用に限定され、かつての生産者米価がなくなってからは、米価は減反によって維持されている(図2)。今では、米価維持に不可欠となった減反を、農協が強力に支持しているのだ。
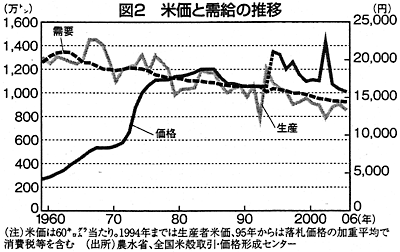
減反面積は今では100万ヘクタールと水田全体の4割超に達している。そして、500万トン相当のコメを減産する一方、700万トン超の麦を輸入するという食料自給率向上とは反対の政策が採り続けられている。
減反は「カルテル」
減反は米価維持の「カルテル」といってよいだろう。カルテルが成立するためには、アウトサイダーが出ないようアメが必要となる。消費者に高い価格を払わせ家計を圧迫しているうえ、現在約2000億円、累計総額7兆円の補助金が、他産業なら独禁法違反となるカルテルに農家を参加させるためのアメとして税金から支払われてきた。
高米価と減反政策は農業依存度の高い主業農家に悪い影響を与えた。低コスト生産のためには、高コストの零細兼業農家にこそ減反面積を多く配分すべきだ。しかし兼業農家は他作物を作る技術も時間もないため、農業収入が農外収入より多い主業農家に過重な減反配分が行われた。
そもそも、高米価で零細兼業農家が滞留し、農地を手放さなかったため、主業農家の農地面積の拡大は困難となった。これに減反が加わり、コストを十分低下できるまでのコメ生産拡大はますます難しくなった。つまり、主業農家の育成・発展は政策により抑制されたのだ。主業農家の生産シェアは、野菜82%、牛乳95%に対し、コメは38%にすぎない(図3)。コメ農家は戸数では全販売農家の6割も占めているが生産額では全農業の2割にすぎない。
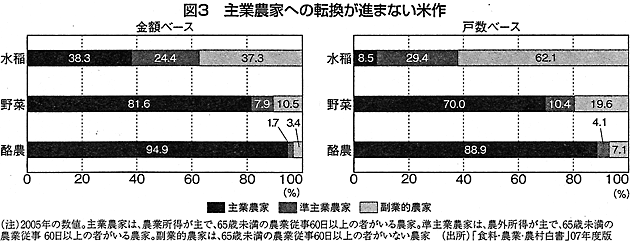
さらに、研究者が品種改良をして単位面積当たりの収量(単収)を上げればコストは下がる。しかし、コメ消費量が増えないなかで単収を増やせば価格が下がる。それを避けるため減反面積を拡大しようとすれば、減反補助金の財政負担が増えるとともに農協も反対する。結局、単収増加のための品種改良はタブーとなった。現在のコメ単収は、ヘリコプターで種まきする粗放的なカリフォルニア農業より3割も低い。
また、食料安全保障に必要な農地は足りないのに、減反で「農地も余っている」との認識が定着し、転用や耕作放棄が進んだ。米価を今後も維持しようとすると国内の人口減少や高齢化にあわせて減反を拡大せざるをえない。これは農地を一層減少させ、食料安全保障を危うくさせる。
アメリカやEUが財政による補助金で農家の所得を保証するという政策に転換しているのに、依然として日本では、高い価格による消費者負担の割合が農業保護の9割を占めている。つまり、税金ではなく国民の食費で農家を支えているのだ。納税者負担による保護は累進的であるのに対し、これは貧しい人も負担するので逆進的である。しかも、減反政策には補助金も必要だ。
減反廃止は三方一両得
減反をやめれば米価は低下する。筆者の推計では、100万ヘクタールの減反面積を5年間かけて毎年20万ヘクタールずつ緩和していけば、米価は現在の60kg当たり1万5000円という価格から中国産米輸入価格約1万円を下回る9500円の水準にまで段階的に低下し、国内需要も拡大する。
それにより、高コストの零細兼業農家は農地を貸し出すようになる。EUが価格を引き下げて直接支払いという補助金を交付したように、減反補助金を減反面積の縮小に合わせて削減する一方、段階的に拡大する価格低下分を主業農家に直接支払いしてその地代負担能力を高めてやれば、農地は主業農家に集積し、コストは低下する。主業農家の収益が向上すれば地主である零細な兼業農家の地代所得も増加する。
誰に直接支払い(補助金)を交付するかということと誰にその利益が帰属するかということは別のもので、農協が主張する零細農家切り捨て論は誤りだ。実際、EUでは耕作者への直接支払いのほとんどが農地の出し手である地主に帰属した。
また、兼業農家が退出したあとは主業農家が引き受けるので、食料供給にはなんら問題はない。例えば酪農において、酪農家は50年前の約40万戸から2万4400戸にまで減った。しかし生乳生産は200万トンから850万トンへと増えている。
そして、直接支払いに必要な額は現在農家に払っている減反補助金総額と同じである。単に、5年間で直接支払いに切り替わるだけだ。財政的な負担は変わらないうえ、価格低下で消費者はメリットを受ける。国内の価格が輸入米の価格より下がれば、汚染米の原因となったミニマムアクセス米も輸入しなくてもよいので、食料自給率は向上する(ミニマムアクセスは輸入義務ではない)。さらに価格競争力が高まれば、アジア市場にコメを輸出することが可能となる。
EUが、穀物価格の引き下げで米国から輸入していた飼料穀物を域内穀物で代替したように、価格低下は輸出という新しい需要も取り込むことができる。食料危機が生じた際には、インドや中国が行っているように、輸出していたコメを国内に向けて飢えをしのげばよい。平時の自由貿易と食料安全保障は両立するのだ。
さらに、コメの先物市場を創設すれば、先物のリスクヘッジ機能によって農家所得は安定するし、政府・財政による価格下落対策は不要になる。農協が先物市場に反対するのは、減反や現物操作による米価維持が困難になることを恐れているためだろう。現在、農協は価格形成のための公的センターを利用しないで、卸業者との相対取引で値決めをしている。農協は、先物価格が高いと農家は減反に協力しなくなるので反対だと主張する。この論理からすれば、減反を廃止すれば先物も導入できて、農家所得は安定するし財政負担も軽減される。
農協の主張の逆に農業再生の道がある。減反見直しが検討の俎上に上ったのは、金融危機で農林中金が大きな評価損を計上し、金融関連事業の利益で農業関連事業の損失を補填するという従来の農協の成功パターンが崩れ、戦前の地主制に代わり農政に大きな影響を及ぼしてきた農協制が揺らぎ始めたことと無関係ではないだろう。
食料安全保障の観点が必要
現在浮上している「減反選択制」は、減反参加農家には米価低下分を補助金で補填したうえで減反に参加させるかどうかは自由にするというもののようだ。これには、減反への参加の程度によって米価低下分が異なり、事前に必要額を予測できない、減反への1割参加農家にも10割参加農家と同じく補填するのか等という制度設計上の困難さがある。
さらに、ある程度の米価低下というメリットはあるものの、減反参加農家のほとんどと思われる現状維持的な兼業農家は、現在の米価水準が保証されるので農業を続けてしまい、主業農家に農地を集積するという構造改革効果は期待できない。筆者の案とは補助金の支払いが逆になるからである。
石破農水相の動きに、2007年の参議院選挙後にマニフェストを変更して減反廃止から維持に転向した民主党はどう出るのか。小沢一郎代表の「関税ゼロでも食糧自給率100%」という主張には減反廃止による米価引き下げがあったはずである。
選択肢は2つだ。1つは、減少を続ける国内米消費を前に、減反を拡大して食料安全保障に不可欠な農地を減少させ、高米価を守るための高関税の代償としてミニマムアクセス米を拡大して食料自給率をさらに低下させ、農業を衰退させるという、これまでの農政を維持する選択。2つ目は、価格を下げて拡大するアジア市場への輸出という新しい需要を開拓し、農地資源を維持しながら食料自給率を向上させるという、強い農業を実現するための農政改革を果断に実行するという選択だ。
言い換えると、水田を票田としてとらえるのか、食料安全保障の基礎としてとらえるのか、という政治の選択だ。石破農水相はこれを問うているのだろう。これを農業界だけの問題としてはならない。農政を真に食料安全保障に役立つ国民、消費者のものに取り戻せるかどうかという日本国民、消費者自身の選択なのだ。今年の総選挙は、「その時」である。
『週刊エコノミスト』2009年3月3日号(毎日新聞社)に掲載


