売上1億円以上の経営体だけが増加
国内市場しか考えてこなかったコメの生産は、1994年1200万トンから800万トンに3分の1も減った。国内市場は、高齢化と人口減少で今後さらに縮小する。これに合わせて生産すると、日本農業は安楽死するしかない。それがいやなら、輸出により海外市場を開拓せざるを得ない。言い換えると、農業が発展しようとするなら、輸出できるような農業となれるかどうかがカギとなる。しかし、日本農業は国際競争力がないというのが定説となっている。農林水産省、農協、大学農学部という農業界の中心となっている人たちも、そう思い込んでいる。
しかし、農業全体が衰退する中で、2010年に農産物販売額が1億円を超えている経営体は5577もある。これ以下の階層の経営体が軒並み減少する中で、この階層だけは5年前より9.5%も増加している(図1)。これらは、ビジネスとして農業を捉えている企業的農家である。また、輸出を開始している農家もいる。日本農業界のリーダーと言われている人たちが、農業のポテンシャルに気づかないでいる間に、農業はその先を動き始めているのだ。
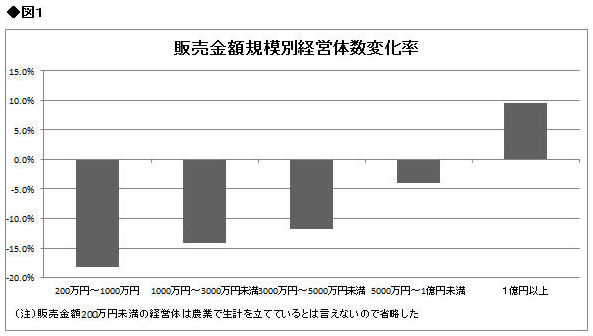
どの産業でも、収益は価格に販売量を乗じた売上高からコストを引いたものだ。したがって、収益を上げようとすれば、価格を上げるか、販売量を上げるか、コストを下げればよい。成功している農家は、このいずれかまたは複数の方法を実践している。農業関係者は農業と工業は違うとよく口にするが、どの産業でも、この経営原理は同じだ。
価格と販売量の関係について見よう。市場全体の供給量に対し個々の農家の生産・販売量は小さい。したがって、個々の農家がいくら販売を増やしたからといって、市場の平均的な価格水準が下がることはない。これは大企業主体の市場構造となっている鉄鋼業、電気機械産業や自動車産業などの製造業とは違う、農業のメリットだ。もちろん、自動車にも高級車と普及車があるように、農業でも付加価値を付ければ、産品の価格を高くすることは可能だ。
市場について見ると、最近の食生活の特徴は、食の外部化(外食、惣菜産業の伸長)が進展していることだ。若年層、高齢者層で単独世帯が増加している。彼らにとって、キュウリ、ニンジン、キャベツなどを丸ごと買って調理するより、外で調理したものを買う方が無駄なく、安上がりになる。スーパーでは売れない曲がったキュウリも、切ってしまえば普通のキュウリと同じだ。外食、惣菜産業を主たるターゲットにする経営方法もある。逆に、単独世帯の内食コストを下げるために、小玉の野菜を販売して成功している農家もいる。どの産業でも、市場の流れを無視しては、生き残れない。
収益を左右するもう1つの要因であるコストをみよう。農産物1トンのコストは、農地面積当たりの生産にかかる肥料、農薬、農機具などのコストを農地面積当たりの収量(単収)で割ったものだ。したがって、コストを下げようとすれば、農業資材価格を抑えたり、規模を拡大したりして、農地面積当たりのコストを下げるか、品種改良等で単収を上げればよい。外国から中古の機械や農業資材を輸入したり、農産物の集荷業に参入することで地域の農地情報を集め、規模拡大に成功している農家がいる。特殊な栽培方法によって、通常の6倍以上の単収を上げている自然薯農家や、栽培期間の短い野菜品種を導入して、1年で何作も行い、年間を通じた単収を上げている農家がいる。
農業界が嫌がる"グローバル化"をうまく利用して成功した例もある。日本では評価の高い大玉をイギリス輸出しても評価されず、苦し紛れに日本では評価の低い小玉を送ったところ、やればできるではないかといわれたというあるリンゴ生産者の話がある。自然相手の農業では大玉も小玉もできてしまうが、大玉は日本で、小玉はイギリスで販売することで、売上高を多くして成功した経営例である。国際分業の点でも、多くの労働が必要な苗までは労賃の安い海外で生産し、それを輸入して日本で花まで仕上げるという経営方法で成功した農家もいる。
企業家的視点で農業を革新
より先進的な例を紹介しよう。
自然相手の農業は、工業と異なる点がある。コメは一年に一作しかできない。20歳で就農して60歳で止めると、40回しかコメ作の経験はできない。しかし、40人の農家を集めると、一年で40回分のコメ作を経験できる。コメ作には、大きく分けて、田植えをする農法と最初からタネを水田にまく農法の違いがあり、その中でも様々な農法がある。40人の農家にいろいろな農法を実施させると、そのメリット、デメリットを一年で判別できる。規模の大きい専業農家を組織化し、このような技術改善を行い、グループ農家全体の生産性向上を図っているのが、株式会社「庄内こめ工房」の斎藤一志代表取締役だ。
金融界から転身した日本アグリマネジメントの松本泰幸代表は、まず、様々な野菜の生産量の変動と価格の変動の状況を分析し、安定型、変動型などに野菜をグルーピング化した。そのうえで、ポートフォリオ・マネジメントの考え方を農業経営に応用し、どのような野菜を組み合わせて生産するかという工夫をしている。同じ経歴を持つサラダボウルの田中進社長は、製造業のものづくりのノウハウを農業に応用して、成功している。
有機農産物は高い価格や高付加価値を追い求めると思われがちだが、らでぃっしゅぼーや株式会社の緒方大助会長は、有機農産物でもコストダウンの重要性を強調する。(山下著『企業の知恵で農業革新に挑む!』ダイヤモンド社)らでぃっしゅぼーやと取引する田中進社長は、価格が並みでもコストが低ければ、高付加価値農業だと言い切る。農林水産省など農業界の多くの人たちは、6次産業化など、いかに付加価値を付けて価格を上げることしか、興味がない。コメでも高い価格ばかりを追い求めるが、今では牛丼チェーンなど低価格のコメを需要する外食・中食の市場が、量的に家庭の内食市場に迫っていることに気がつかない。
ファーム・アラインス・マネジメントの松本武社長は、農作物の生産履歴(トレーサビリティー)の管理を強化するため、農場でも簡単に作業できるタッチパネル方式を開発した。これによって、客が袋に表示された数字をホームページに入力すれば、種まきから収穫時まで使用した農薬や肥料の種類までもすべて分かるシステムを導入し、安全・安心な農産物の供給に努めている。IT技術の農業への適用例だ。これで世界的な認証制度であるグローバルGAP("good agricultural practice"の略語)から表彰を受けている。
自然条件の違いを活用した農業革新
このように、企業的な生産者が独自の創意工夫によって大きな収益を上げている。それだけではない。日本自体、農業のポテンシャルを生む自然条件を備えている。都市の空き地を放っておくと雑草が生えてくる。日本は植栽豊かで、作物の生育に適している。
しかし、日本は土地も狭小で農業には向かない、とくに傾斜地の多い山村などの中山間地域での農業の可能性は小さいと考えられている。一方で高収益を上げられるワサビは標高が高くて冷涼な中山間地域に向いている。日中の寒暖の差を活用し、新潟県魚沼のように食味のよい米の生産も行われているし、花の色も鮮明になる。中山間地域では、気候条件を活かした製品差別化、高付加価値化の道がある。狭小な農地しかない東京都は、農業には条件不利地域だが、巨大市場に近いというメリットを活かし、日本一の小松菜の生産地となっている。
農業には、季節によって農作業の多いときと少ないとき(農繁期と農閑期)の差が大きいため、労働力の通年平準化が困難だという問題がある。コメ作でいえば、田植えと稲刈りの時期に労働は集中する。農繁期に合わせて雇用すれば、他の時期には労働力を遊ばせてしまい、コスト負担が大きくなる。
中山間地域では標高差があるので、田植えと稲刈りにそれぞれ2~3カ月かけられる。これを利用して、中国地方や新潟県の典型的な中山間地域において、夫婦2人の経営で10~30ヘクタールの耕作を実現している例がある。都府県のコメ作農家の平均0.7ヘクタールから比べると、破格の規模である。このコメを冬場に餅などに加工したり、小売へのマーケティングを行ったりすれば、通年で労働を平準化できる。平らで農作業を短期間で終えなければならない10ヘクタール程度の北海道農業より、コスト面で有利になるのである。
野菜作でも、青果卸業から農業に参入した鳥取県の企業は、中海干拓から大山山麓までの800メートルの標高差を利用して、200ヘクタール超の農地で、ダイコンの周年栽培を中核にした経営を実現し、コンビニチェーン店におでん用ダイコンの周年供給を果たしている。
また、日本は南北に長い。この特性を活かし、日本に点在する複数の農場間で、機械と労働力を南から北へ段階的に移動させることで、作業の平準化を実現している企業的経営もある。労働の平準化と機械の稼働率向上によるコストダウンである。
標高差がなくても、早生、中生、晩生を組み合わせれば、作期を長期化することもできる。あるぶどう農家は、異なる品種の栽培、露地と施設による栽培などを組み合わせて、労働をならしている。また、コメ作と野菜、果樹等の複合経営によっても、作業の平準化を実現できる。かなりの畜産農家はコメ作との複合経営で、堆肥を水田に還元し、肥料コストを節約するとともに、稲わらを家畜の飼料に使い、飼料代を節約している。複合経営によるコストダウンである。
つまり、農業と工業は違うと力説する農業界の政治的なリーダーたちをしり目に、労働の平準化を実現し、農業を工業の生産工程に近づけようとしている農業経営が成功しているのだ。工業といっても、セメント業と自動車業とは、農業と工業の差以上に開いているかもしれない。
いまも跋扈する農業特殊論
前号で民俗学者、柳田國男の農業構造改革論を紹介した。農業問題の本質をとらえた先進的な柳田國男の主張は、東大農学部を中心とする当時の農業界のリーダーたちに拒絶された。後日、経済学者シュンペーターの高弟、東畑精一・東大教授は、農業が工業と違うことを力説する農業界と柳田との違いを次のように解説している。
「柳田氏の言論はまさにただ孤独なる荒野の叫びとしてあっただけである。だれも氏の問題意識の深さや広さを感得するものはなく、その影響を受けうるだけの準備を持つものは無くして終わったのである。(中略)農村・農民・農業は、他の社会・商工業者・他産業とは、いかに同一性格を持つかの大本を知ろうとしないで、差異を示し特殊性を荷っているかを血まなこに探し求めるに過ぎなかったのである。どうして柳田國男を理解し得よう。『あれは法学士の農業論にすぎない』のである。」(東畑精一1973『農書に歴史あり』P80、アンダーラインは筆者)
残念ながら、今でも農業界が他産業との差を血眼になって捜している状況に変わりはない。他産業と違うから、農業には保護が必要だと言いたいのだ。私の主張も、農業界の多くの人からすれば、『あれは法学士の農業論にすぎない』のだろう。
DIAMOND online 2013年12月25日に掲載


