主張1:先祖伝来の農地なので、零細な農家が農地を貸したがらないため、規模拡大が進まない
主業農家に、兼業農家が農地を貸し出さないことを、農林水産省などは、「先祖伝来の農地なので、それを貸したがらないからだ」と説明する。しかし、そもそも戦後まもなく実施された農地改革でもらった農地なので、先祖伝来とは言えないし、先祖の霊が、土地を貸す時は枕元に出てくるのに、所有権を手放す売却行為の時には妨害しないというのは、いかにもおかしな話だ。“先祖の霊”は都合のよいときに現れてくれる。
農林水産省はなぜウソをつくのだろうか? 兼業農家が農地を貸し出さないことには、2つの原因がある。
第1に、ヨーロッパと異なり、日本では土地の利用規制(ゾーニング、農地と都市的地域の線引き)が甘いので、簡単に農地を宅地等に転用できる。転用価格(2005年)は、市街化調整区域内で10アール2315万円、農家の平均的な規模である1ヘクタール(1万平方メートル)で2億3000万円の利益である。これは農地を貸して得られる地代収入の2000年分に相当する。大都市周辺地域では、この何倍もの利益となる。土地バブルがはじけた今でも、農家には年間2兆円の転用利益が発生している。
農地を貸していると、売ってくれと言う人が出てきたときに、すぐには返してもらえない。それなら耕作放棄しても農地を手元に持っていた方が得になる。しかも、耕作放棄しても農地扱いなので、固定資産税はほとんどかからない。
第2に、減反政策で米価を高く維持しているため、コストの高い農家も農業を続ける。主業農家が農地を借りようとしても、農地は出てこない。
しかし、農林水産省は、農地のゾーニング徹底と減反廃止という抜本的な対策を、農協や農林族と闘って実行する度胸はない。そのカモフラージュとして持ち出したのが、“先祖の霊”である。幸いにも、多くの非農家の人がこの作り話を信じてくれた。
農家の資産価値の向上は、地域の衰退さえ招いた。市街地の郊外にある農地が大規模に転用され、そこに大型店舗が出店する。賃貸によって、まとまった農地を主業農家に集積することは、極めて困難であるが、売買によって、大型店舗のために広大な農地を転用し、所有権を移転することは、かくも容易である。かつては賑わった市街地の地元商店街は、郊外の大型店舗に客を奪われ、「シャッター通り」化した。“農家栄えて地域滅んだ”。
主張2:農業と工業は違う、だから保護するのは当然だ
農業は工業とは違うという主張がなされる。しかし、戦前の農業と違い、現在の農業への投入物は、化学肥料、農薬、農業機械など工業の生産物が多い。最近では、GPS、センサー、ロボット、コンピューターなど最先端の工業技術が農業の現場でも使われている。
自然を相手にする農業には、季節によって農作業の多いときと少ないとき(農繁期と農閑期)の差が大きいため、労働力の通年平準化が困難だという問題がある。これは、農業が工業と違う大きな特徴である。コメ作でいえば、1週間しかない田植えと稲刈りの時期に労働は集中する。農繁期に合わせて雇用すれば、他の時期には労働力を遊ばせてしまい、コスト負担が大きくなる。
傾斜農地が多い中山間地域では農業の競争力がないと考えられているが、中山間地域では標高差があるので、田植えと稲刈りにそれぞれ2~3カ月かけられる。これを利用して、中国地方や新潟県の典型的な中山間地域において、夫婦2人の経営で10~30ヘクタールの耕作を実現している例がある。北海道を除いたコメ作農家の平均0.7ヘクタールから比べると、破格の規模である。このコメを冬場に餅などに加工したり、小売へのマーケティングを行ったりすれば、通年で労働を平準化できる。
野菜作りでも、青果卸業から農業に参入した鳥取県の企業は、中海干拓地から大山山麓までの800メートルの標高差を利用して、200ヘクタールの農地で、ダイコンの周年栽培を中核にした経営を実現し、コンビニ・チェーン店におでん用ダイコンの周年供給を実現している。
また、日本は南北に長い。この特性を活かし、日本に点在する複数の農場間で、機械と労働力を南から北へ段階的に移動させることで、作業の平準化を実現している企業的経営もある。労働の平準化と機械の稼働率向上によるコストダウンである。
早生、中生、晩生など異なる品種の栽培、露地と施設による栽培、コメ作と野菜、果樹等の複合経営によっても、作業の平準化を実現できる。ある畜産農家はコメ作との複合経営で、堆肥の水田への利用、稲わらの飼料化を行い、コストを節約している。
つまり、農業と工業は違うと力説する農業界のリーダーたちをしり目に、労働の平準化を実現し、農業を工業の生産工程に近づけようとしている農業経営が成功しているのだ。
主張3:食糧危機はいつ起こるかわからない。だから、食料自給率低下は問題だ
我が国の食料自給率は低下し続け、今では39%である。この食料自給率という概念は、農林水産省が作ったプロパガンダの中で、最も成功をおさめたものである。60%以上も食料を海外に依存していると聞くと国民は不安になる。
しかし、食料自給率とは、現在国内で生産されている食料を、輸入品も含め消費している食料で割ったものである。したがって、大量の食べ残しを出し、飽食の限りを尽くしている現在の食生活(食料消費)を前提とすると、分母が大きいので食料自給率は下がる。逆に、餓死者が出た終戦直後の食料自給率は、海外から食料が入ってこないので100%である。分母の消費の違いによって食料自給率は上がったり下がったりするのだ。食料自給率が高かった戦後の方が良かったとは、誰も言わないだろう。
海外から食料を輸入できなくなった食料危機のときに、牛肉も豚肉もチーズもたらふく食べている現在の食生活を維持できないのは当然である。その食生活を前提とした現在の食料自給率はまったく意味を持たない。
食料自給率向上目標はもう15年近く掲げられているが、一向に上がる気配さえ見えない。しかし、農林水産省は目標未達成の責任を取ろうとしないばかりか、これを恥じる様子さえない。農林水産省にとって、食料自給率が上がれば、農業保護の根拠が弱くなって困るのだ。それどころか、減反政策のように、高米価を維持するために、食料安全保障に不可欠な農地資源を減少させるような政策が採り続けられている。
主張4:国際価格高騰や輸出制限で、日本で「食料危機」が起きる?
08年、穀物の国際価格が3倍に上昇し、フィリピンなどの穀物輸入国では、食糧危機が発生し、インドなどは輸出を制限した。
途上国にとって、食料を買う経済力があるかどうかということは、決定的に重要だ。自由な貿易に任せると、穀物は価格が低い国内から価格が高い国際市場に輸出される。そうなれば、国内の供給が減って、国内の価格も国際価格と同じ水準まで上昇してしまう。収入のほとんどを食費に支出している貧しい人は、食料価格が2倍になると、食料を買えなくなり、飢餓が発生する。インドが輸出を制限したのは、これを防ごうとしたのだ。
では、穀物の大輸出国であるアメリカやオーストラリアが不作になったときに、輸出制限をするだろうか。これらの国では生産が国内消費を大きく上回っており、国内での食料供給には困らない。アメリカでは小麦生産の5割、オーストラリアでは8割が輸出される(図1)。生産が相当減少しても、まだかなりの輸出余力はある。価格が上がっても、先進国なので豊かな消費者は食料を買うことができる。価格上昇時は、主要輸出国の生産者にとって稼ぎ時であり、このときに輸出を制限するような愚かなことはしない。
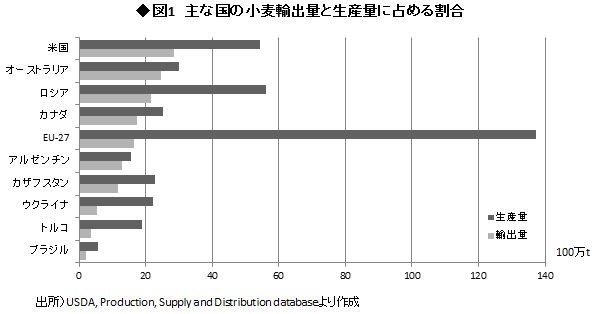
穀物価格上昇の日本への影響はどうだろうか。08年に穀物価格が3倍に高騰しても、食料品の消費者物価指数は2.6%上昇しただけである。これは、国内の飲食料の最終消費額は05年で73.6兆円、このうち輸入農水産物は1.2兆円にすぎないからだ(図2、図3)。輸入農水産物の一部である穀物の価格が上がっても、最終消費には大きな影響を与えない。食料危機をあおる農業界にとって、これは“不都合な真実”である。
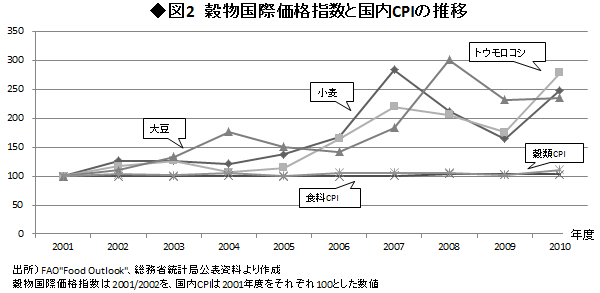
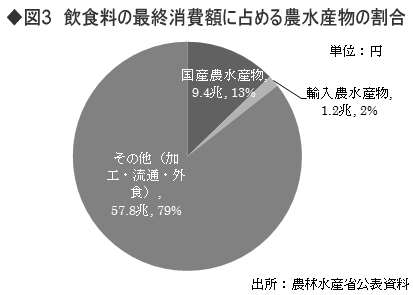
日本で生じる可能性が高い食料危機とは、東日本大震災で起こったように、おカネがあっても、物流が途絶して食料が手に入らないという事態である。最も重大なケースは、日本周辺で軍事的な紛争が生じてシーレーンが破壊され、海外から食料を積んだ船が日本に寄港しようとしても近づけないという事態である。食料を買う資力がある日本では、穀物価格が高騰しても、食料危機は生じない。
DIAMOND online 2013年11月27日に掲載


