国民の多くは、農業や農村に対して、次のようなイメージや考えを持っているのではないだろうか。
「農村のほとんどの人は農家だ」
「規模の大きい農家は、化学肥料や農薬などをたくさん使う近代的な農業を行っているのに対し、貧しくて小さい農家は、肥料や農薬を買えないので、環境にやさしい農業を行っている。だから、小農は保護しなければならない。規模拡大による農業の効率化などとんでもない」
しかし、そのイメージ通りの農業・農村は、いまや日本では絶滅危惧種である。
望郷の歌がヒットしたことが昭和30年代の際立った特徴
国民のほとんどが、農業や農村から遠く離れた都市的地域で、生活している。2005年時点で、日本の人口1億2500万人の半分(6300万人)は、関東、中京、京阪神の三大都市圏に集中している。
このような都市化は、戦後急速に農村から都市へ人口が移動した結果である。昭和30年代とその前後のヒット曲には、田舎から都会に出てきた人たちや田舎に残された人たちに訴えかける、“ふるさと”の歌が圧倒的に多い。主なものだけでも、「リンゴ追分」、「別れの一本杉」、「リンゴ村から」、「哀愁列車」、「柿の木坂の家」、「お月さん今晩は」、「東京だよおっ母さん」「南国土佐を後にして」、「僕は泣いちっち」、「あゝ上野駅」、「ふるさとのはなしをしよう」、「帰ろかな」。遅れて「北国の春」がヒットした。
昭和の流行歌には、青春や恋愛ものは当然として、東京などの都会賛歌、長崎や上海などの異国情緒、股旅、マドロスを歌ったものが多く、望郷の歌は少ない。例外的に、戦前「誰か故郷を想わざる」があるが、これは戦地にいる兵士が歌いだしてから大ヒットしたものである。戦後に「かえり船」、「異国の丘」という望郷の歌があるが、いずれも戦地から故国に帰る復員者の歌である。その逆に童謡「里の秋」や「岸壁の母」は復員者を待ちわびる歌である。いずれも都会に出てきた人たちが故郷を偲んで歌ったものではない。多くの望郷の歌がヒットしたことは、昭和30年代の際立った特徴である。
この現象は、都市への移動が他の時期に比べて大規模だったことを示している。農村の次男、三男等の過剰労働力と都市の人手不足がかみ合い、農村の若者は“金の卵”と称され、就職列車に揺られて、都会に集団就職した。
しかし、これらの曲に共感を持った人たちは既に現役を退き、現在、都市圏に住んで、活動しているかなりの人は、農村とのつながりの薄い、その子や孫たちの世代である。これらの世代の人たちにとって、農業や農村と関わった先祖は、近くても、おじいさんやおばあさんであり、ほとんどの人にとっては、会ったこともない先祖である。
このため、都市的地域に住んでいる多くの国民が農業や農村に対して持っている知識やイメージは、農業や農村との付き合いや実体験を通じたものではなく、学校教育、書籍や「おしん」のようなドラマから得られる、観念的で標準化されたものとなった。つまり、農村では、ほとんどの人が農家で、貧しく、コメ作りに精を出しているというイメージ、既成観念である。
農村集落ですら農家はもはや少数派になった
その農村は、都市への人口移動が終了した後、大きく変化した。昭和30年代に都会に出てきた人たちやその子孫たちの見聞きしている農村と、今の農村は全く異なっている。
農業から他産業への移動の主体は、昭和40年代になると、在宅のままで、他産業へ就職するようになった農家の後継ぎたちとなった。全国各地に新産業都市が建設されるなど、農村の近くに工場等が立地するようになり、農村に住みながら通勤することが可能になったからである。
農村の側からみると、産業化や経済成長の波が押し寄せてきたのである。農村の構成員は、役所、会社や工場などに勤めるサラリーマン、いわゆる「勤労者世帯」が多くなった。また、農業を続けた世帯でも、平日はサラリーマンとして働き、休みの日だけ農作業を営むという「兼業農家」が多くなった。1970年と2010年を比較した図1-A、Bが示すように、農村集落で農家はもはや少数派になってしまっている。
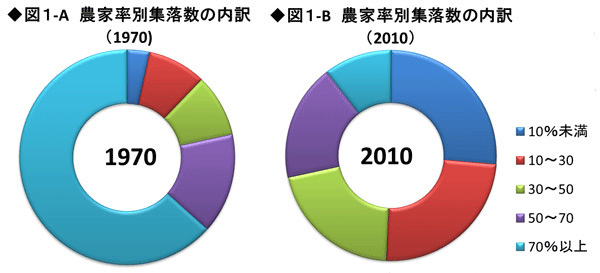
目につく土地の広さからすれば、農業は地域経済の中で大きな地位を占めているように見える。転用が進んだとはいえ、農地は未だに可住地面積の4割を占めている。しかし、農業はとっくの昔に地域経済の中心ではなくなっている。GDP(国内総生産)に占める農業の割合が1%に低下しているだけではなく、北海道、東北、南九州の農業県といわれる地域においても、その経済に占める農業の割合はせいぜい5%程度に過ぎない。
規模の大きい農家ほど環境に優しい農業を行っている
コメについては、機械化が進み、農作業に必要な時間が大幅に縮小したため、平均的な規模の水田では週末の作業だけで十分となった。米と書いて八十八手間がかかると言われた時代は過去のものとなった。1日8時間労働として、1ヘクタール規模の標準的なコメ農家が、1951年には年間251日働いていたのに、2010年ではたった30日しか働いていない(図2)。このため、コメ作農家の兼業化が顕著に進んだ。農村で農業を行っている人も、ほとんどが本業はサラリーマンで週末だけ田んぼに立つ兼業農家となった。
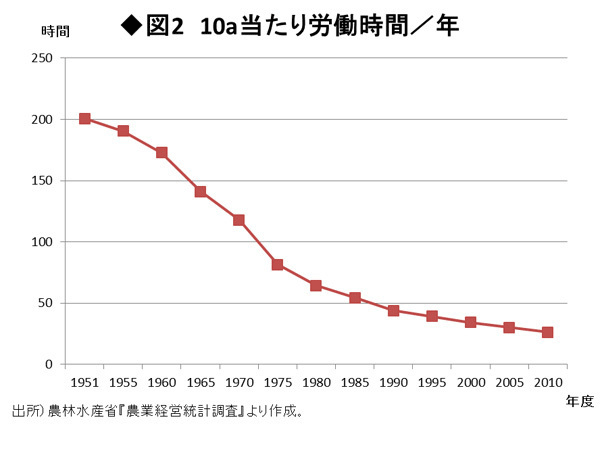
この人たちは、規模が小さい小農だが、サラリーマンなので、決して貧しい人たちではない。人口の大移動が終了した1965年(昭和40年)以降、農家所得は勤労者世帯の所得を上回って推移するようになった。今の農村に小農はいるが、貧農はいない。
小さな兼業農家は、週末しか農業ができないので、農業に多くの時間をかけられない。雑草が生えると農薬をまいて処理してしまうような、農薬・化学肥料多投の手間ひまかけない農業を実施している。規模が大きい農家ほど農業に多くの時間をかけられるので、環境に優しい農業を行っている。コメでは、1ヘクタール未満の農家では環境保全型農業の取り組みは2割もいないのに、10ヘクタール以上だと5割を超える(2000年・図3)。
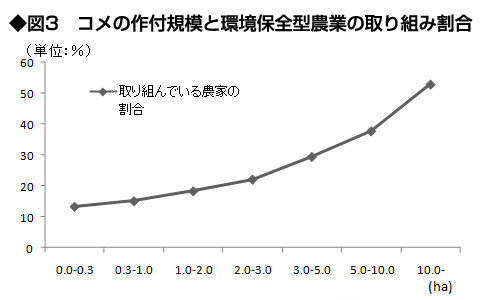
しかしながら、貧農で、肥料・農薬も使えない農業をやっているという、戦前や昭和30年代までの健気な小農のイメージは、農から離れて久しい多くの国民のノスタルジーをかきたて、零細な(兼業)農家への共感を生む。
農業、農村、環境を守っているのは、農業で生計を立てている主業農家と言われる人たちである。しかし、農協や農政が推進してきた高米価・減反政策は、零細な兼業農家をコメ作りに滞留させて、農地が主業農家に貸し出されることを妨げてきた。農協や農政は、主業農家が規模を拡大して生計を豊かにしようとするのを妨害してきたのである。
知識人はこのような事実を知らないで、小農を保護すべきだという主張を行い、自由貿易やTPPに「反対」と叫んでくれる。農協の思う壺である。こうして農業構造改革に対する「小農切捨て反対」という農協のスローガンが、国民にアピールしてしまう。今では農協は“小農”と言って“貧農”とは言わない。兼業農家である小農は、もはや貧農ではないからである。
奇妙な農協の組合員数と農家戸数との関係
このような農村では、奇妙な現象が起きている。
日本農業にはかつて不変の3大基本数字といわれるものがあった。農業就業者数1400万人、農家戸数550万戸、農地面積600万ha、だ。明治初期の1875年から1960年までじつに85年間、この3つの数値に大きな変化はなかった。農家で農業に従事する人(農業就業者)は複数いた。しかし、今では農家戸数が農業就業者の数を上回っている。つまり、主として農業に従事している農業就業者のいない農家がいることになる(図4)。
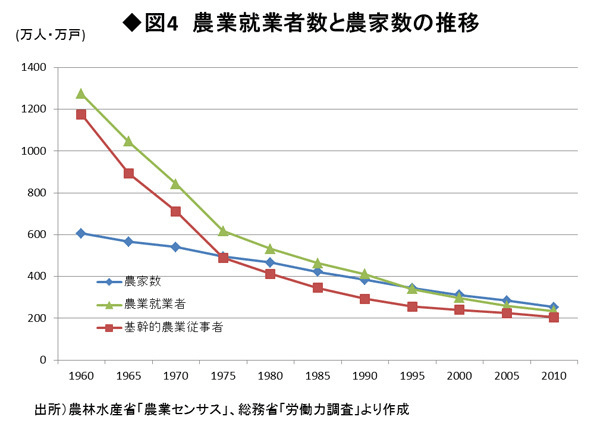
この異常な事態が起きるのは、農林水産省が0.1ヘクタール=10アールまたは年間販売額15万円以上を“農家”と定義しているからだ。零細と言われる、日本の平均的な農家規模でさえ、2.4ヘクタールだということを考えると、あまりに小さい。10アールのコメ農家の生産額は10万円にも満たない。農林水産省の農家定義が、家庭菜園のような、本来農家として扱うべきでない世帯も農家として扱っているため、農業を専業として行っている農業就業者よりも、農家戸数が多くなってしまうのである。しかし、農林水産省にとって農家戸数を多く見せる方が、予算獲得などで何かと便利である。
さらに奇妙なのが、農協の組合員数と農家戸数との関係である。
通常農家は家長1人を農協組合員としている。1960年では、わずかに農家戸数は組合員数を上回っていた。農協に入らない農家もいるので、これは当然である。しかし、それでも、100%近い農家が農協組合員であることは異常である。労働者全てが労働組合員でない(今では組織率は2割を切っている)ことを考えると、この農協の組織力の異常さがわかる。
しかし、今では、農協の異常さの度合が尋常ではなくなっている。正組合員は467万人(2011年)、一戸から複数の組合員を出している農家もいるので、正組合員戸数は401万戸である。これは、農林水産省の農家と言えないような農家定義に該当する農家戸数253万戸を大幅に上回っている。組織率158%である。農業を止めた人も組合員資格を持ち続けているのだ。
しかも、農協には、地域の住民であれば誰でもなれる准組合員という農協独自の制度がある。正組合員と異なり、准組合員は、農協の施設や事業などは利用することができるが、農協の意志決定には参加できない。
混住化の進展と農協の勧誘によって、准組合員の数は年々拡大して、とうとう2009年に准組合員数が正組合員を上回り、2011年では、組合員983万人中准組合員は517万人で、正組合員467万人を50万人も上回っている。図5から准組合員が急速に増加していることがわかる。
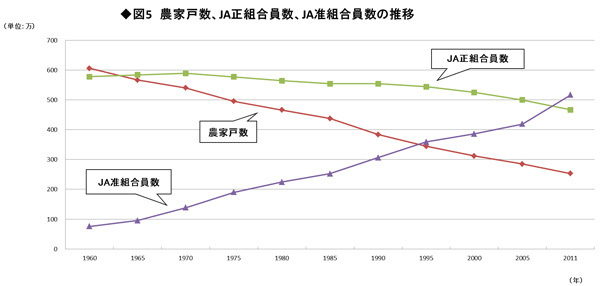
農協にとっては農外所得、年金等の方がはるかに重要
我が国農業が衰退傾向にあることは間違いない。農業総産出額は1984年の11兆7000億円をピークに減少傾向が続き、2011年には8.2兆円とピーク時の約3分の2の水準まで低下した。農業純生産(総産出額から原材料費などの中間投入を除いた農業の付加価値)は1990年の6.1兆円から2007年には3.3兆円へとほぼ半減した。
特に、減少が著しいのがコメである。この結果、農業総産出額に占めるコメの割合は、1960年ころはまだ5割だったのに、2010年には、とうとう20%を切ってしまった。
農業、特にコメ農業が衰退するのに、コメ農業に基礎を置く農協が発展するのはなぜだろうか?
コメの兼業農家の農業所得は少なくても、その農外所得(兼業収入)は他の農家と比較にならないほど大きい。しかも、戸数も圧倒的に多い。コメ以外の農業では兼業農家は少ない。したがって、農家全体では、コメの兼業農家の所得が支配的な数値となってしまう。図6から、農業所得の割合が1955年の67%から2003年では14%へと大きく減少している一方、農外所得、年金等の割合が大きく増加していることがわかる。今では、農業所得110万円に対して、農外所得432万円は4倍、年金等229万円は2倍である。年金等が一貫して増加しているのは、農家の高齢化が進展していることを示している。
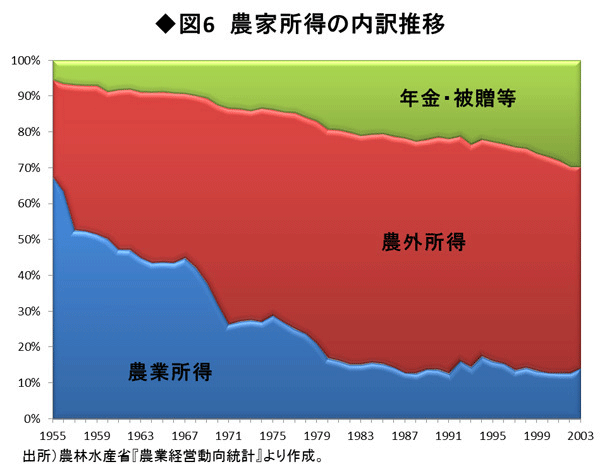
これこそ、農協から見た農家、組合員の姿である。農協は農業所得だけを見ているのではない。農外所得(兼業収入)も入れた農家所得を見ているのだ。農協にとっては、農業所得よりも農外所得、年金等の方がはるかに重要である。コメ農家が農協バンクに預金してくれる兼業や年金収入は、農協発展に大きく貢献しているからである。こうしてみると、農協にとって、コメの兼業農家がいかに重要なのかがわかる。
米価を上げることで、これと比例する農協のコメ販売収入も増加した。また、高米価でコストの高い零細な兼業農家もコメを作り続けた。農地が出てこないので主業農家へ農地は集まらず、その規模拡大・コストダウンは進まなかった。米価が高いので、コメ消費も減少した。こうしてコメ農業は衰退した。しかし、兼業農家の滞留は農協にとって好都合だった。農業所得の4倍に達する兼業所得も年間数兆円に及ぶ農地の転用利益も、銀行業務を兼務できる農協の口座に預金され、農協は日本第2位のメガバンクとなった。
農協の農業に対する融資は今では預金収入等の1~2%
衰退する農業への農協の貸出しは大きく減少し、今では預金収入等の1~2%しか農業に融資していない。その一方、農協はその預金収入等の3割ほどを、准組合員に対する住宅ローン、車ローン、教育ローンや元農家のアパート建設資金に貸し出した。准組合員が増加するのは、末端の農協が融資先を求めて、准組合員を積極的に勧誘したからである。
さらに、農協は、残りの預金収入等をウォール街などで運用し、莫大な利益を上げた。農協は“脱農化”で発展した。農協は自由貿易や経済界の主張を市場原理主義だとか新自由主義とかのレッテルを貼って批判するが、農協こそ資本主義を巧みに利用して発展した存在である。こうして、農業は衰退し、農協は発展する。
DIAMOND online 2013年11月20日に掲載


