「日銀はもはや物価を制御できないところまで追い込まれているのか」――。先日、海外の研究仲間からこんな質問を受けた。新興市場経済では、中央銀行が策を尽くしても高インフレを制御できず、物価が「糸の切れた凧」のようになることがある。デフレ下の日本でもそれと同じようなことが起きているのではないか。これが質問の趣旨である。
日本で起きているのは、消費者物価が毎年1~2%下がる程度の緩やかなデフレであり、かつて多くの人が懸念したデフレスパイラルでもない。新興市場経済の高インフレと同列に論ずるのは不適切だ。しかし一方で、毎年の下落幅は小幅でも、それが1990年代から延々と続いているとなると、累積の下落幅は小さくない。政府・日銀が長期デフレに有効な対策を打てていないのも事実である。
◆◆◆
日本の物価が制御されていないと見ているのは彼だけではないようだ。為替市場では、物価の制御に苦しむ日本を狙い撃ちするかのように円高が進行してきた。これに対して政府・日銀は9月15日、2004年春以来の円売り・ドル買い介入を大規模に実施するとともに、介入によって市場に供給した円資金を吸収せずに市場に放置するという「非不胎化」を行った。
この非不胎化介入はどのような意味をもつのだろうか。
中央銀行が貨幣の供給量を調整し、金利を上げ下げするのが伝統的な金融政策だ。ところが99年以降の日本では、金利がほぼゼロに張りついたままの状態が続いている。
貨幣には商品の売買に伴う決済を円滑にするという機能がある。このような貨幣の流動性サービスを得るために支払う対価が金利である。しかし99年以降、日銀による大量の資金供給の結果、流動性サービスが効用を増加させる度合いがゼロまで低下し、貨幣が飽和状態になった。それを反映して、流動性サービスの価格である金利がゼロまで下がっているのである。
金利ゼロの世界での金融政策は中央銀行にとって未踏の領域であり、試行錯誤で進まざるを得ない。未踏の領域で当惑しているのは研究者も同じであり、金利ゼロの経済でいかにして物価を制御するかについてコンセンサスはいまだ得られていない。
しかしそうした中にあって、日本のデフレを説明する仮説として早い時期から研究者の関心を集めてきたのが「円高原因説」である。たとえば、ロナルド・マッキノン米スタンフォード大学教授と大野健一政策研究大学院大学教授は、人々の根強い円高予想がデフレを発生させたと指摘している。実際、円相場の円高方向へのジャンプが発生し、それに続いて物価下落が進むというパターンを日本経済はこれまで繰り返してきている。
円高とデフレの関係に注目する研究では、デフレを防ぐにはまず円高を防ぐ必要があり、そのためには大規模な為替介入を行うべきだと主張されることが多い。しかし為替介入によりデフレを防ぐという発想は、金融政策のこれまでの常識からすると邪道である。金融政策と為替介入は独立の政策であり、相互関係はないとされてきたからだ。
先進各国では、政策金利(日本では無担保コール翌日物金利)に目標水準を設定し、その目標水準を達成するように貨幣の量を日々調節するというかたちで金融政策が運営される。しかし円売り介入によって市場に出回る円資金が多くなると、政策金利が目標水準から乖離してしまう。これを避けるために、中央銀行は介入資金を吸収する公開市場操作を行う。これが「不胎化」である。
先進各国の中央銀行は通常、ほぼ100%の不胎化を行うことが多くの実証研究で確認されている。100%の不治化が行われる限り、為替介入が円資金の流通量に影響を及ぼすことは決してない。その意味で両者は独立である。これは国際マクロ経済学の教科書にも登場する常識である。ただし、金利が正の世界における常識にすぎない。貨幣が飽和し金利がゼロの世界では異なる仕組みが働く。
◆◆◆
ゼロ金利の世界で介入と金融政策はどのように関連するか。これが明らかになったのは03~04年にかけて政府・日銀が行った大規模な円売り介入を通じてである。この時期の介入は総額35兆円に達する大規模なもので、スタンフォード大学のジョン・テイラー教授は「Great Intervention(大介入)」とよんでいる。
図はこの時期に行われた1兆円の円売り介入が円資金の流通量に与えた影響を推計した結果を示している。介入の2日後に行われる資金決済の時点では、介入によって市場に供給された1兆円のうち6000億円が日銀の不胎化オペで吸収され、残りの4000億円は市場に残る。その後、市場に滞留する資金は4日後には2500億円、6日後には1700億円と徐々に減少し、20日後にほぼゼロになる。つまり、この時期は、平均的にみて、介入資金が20日間市場に滞留した。同じ推計を大介入が始まる前の時期について行うと、介入資金は2日後の資金決済の時点でほぼ100%吸収されていた。
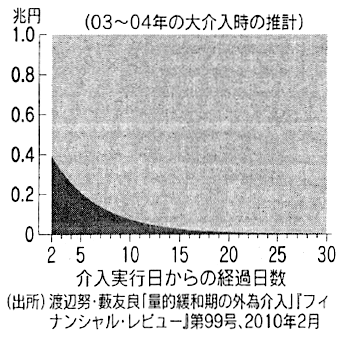
介入資金の滞留が可能になったのは貨幣が飽和していたからだ。大介入に先立つ01年から日銀は量的緩和政策を実施していた。大介入の開始当時、日銀当座預金残高の目標値は15兆~20兆円に設定され、しかも目標の上限値を超えることも可とされていた。
これだけの大量の資金供給の結果、貨幣は既に飽和しており、コール翌日物金利はゼロであった。この状況で、円売り介入によって市場に注入された円資金が放置されたとしても翌日物金利がさらに下がることはない。つまり円売り介入資金を放置したとしても金融政策の目標を達成できなくなるわけではない。これは金利が正の世界との大きな違いであり、「介入は直ちに100%不胎化しなければならない」という「金利が正の世界における常識」がもはや通用しないことを意味する。
ポール・クルーグマン米プリンストン大学教授はゼロ金利の世界を、常識と非常識が交錯する「アリスの『鏡の国』」にたとえたが、介入の非不胎化はまさにその一例である。
では不胎化しないことでどの程度効果があるのか。介入が為替相場に及ぼす影響を大介入の時のデータを用いて、慶応義塾大学の藪友良准教授と計測した結果によれば、介入の効果は直近3カ月間に行われた介入が不胎化されていたか否かに左右される。円売り介入1兆円が為替相場に及ぼす効果(円の下落率)は、全く不胎化しない場合には1.9%、20%不胎化する場合で1.5%、40%不胎化の場合で1.1%である。ちなみに、9月15日の介入では総額約2兆円で1ドル=82円台から85円台へと変化しており、全く不胎化しない場合の推計結果とほぼ同じ効果があったことがわかる。
◆◆◆
不胎化か否かで介入の効果が異なるのはなぜか。すぐに思いつくのは滞留資金の増加が円安を招く可能性だ。しかし貨幣が飽和している以上、これはあり得ない。もうひとつの可能性は「予想」を通じる効果だ。話を単純にするため、介入は一切不胎化されず、介入資金は永遠に市場に残るとする。永遠に残るということは、経済が不況から脱して正常化する遠い将来の時点でも、資金が市場に残っていることを意味する。経済が正常化した時点では金利は正に戻っているはずだから、介入による円資金の追加供給は将来時点の金利を下げる効果をもつ。この金利低下は将来時点で円安を発生させるが、それが人々の予想に織り込まれると、現在の為替が円安になる。
もちろん大介入期といえども、一切不胎化しなかったわけではなかったし、介入資金が永遠に放置されたわけでもない。しかし程度の差こそあれ、このような市場参加者の為替予想の変化を通じるチャンネルが働き、それが介入の効果を高めたと推察される。
介入は他国の事情を無視して行うべきでないことはいうまでもない。介入以外の貨幣の追加供給策との比較が必要である。しかしゼロ金利下では介入を不胎化しないという新たな選択肢が生まれ、金利が正の世界とは異なる効果を期待できる。物価の制御を取り戻すための有効な手段のひとつとみるべきである。
2010年9月27日 日本経済新聞「経済教室」に掲載

