先ごろ政府が物価の持続的な下落、すなわちデフレーションが進行していると宣言し、日銀は先週、量的緩和策を再開した。以下では、現在の物価下落をどう理解すべきか、政府・日銀はいかに対応すべきかを考えたい。
◆◆◆
世間の注目は、日本経済が「デフレスパイラル」に陥っているかどうかに集まっている。デフレスパイラルという言葉は必ずしも厳密に定義されていないが、多くの説明に共通するのは、価格下落→企業収益を圧迫→賃金や雇用の調整→家計所得の低下→個人消費の低迷→さらなる価格下落というサイクルである。価格下落が賃金などを経由してさらなる価格下落を招く点でまさに悪循環であり、価格と賃金がともにフリーフォールするような、底なし沼のイメージがある。
こうしたスパイラルが本当に存在するのかどうか、既存の経済学の知識では十分に理解できていない。だが幸い、日本経済がそうした状況に陥ってしまった、または近い将来そのリスクが高いとの見方は今のところ少数派である。政府は現状をデフレとしつつもそのピッチはあくまでも緩やかだとしている。日銀の白川方明総裁もスパイラルの可能性は小さいと述べている。
では物価の現状はどう理解すべきか。筆者は、現状は価格と賃金のフリーフォールどころか、むしろリーマンショックという未曾有の規模の需要ショックが起きたにもかかわらず、物価の反応は極めて鈍いとみるべきだと考える。
鉱工業生産指数は今年前半、それ以前の水準に比べ40%低下した。その後、回復してきたとはいえ、昨秋のリーマンショックが生産、受注、出荷、雇用などの「数量」に及ぼした影響は甚大だった。一方、物価や賃金など「価格」への影響はせいぜい2~3%で、マイルドと評価できる。
巨大な負の需要ショックに対して「価格」の調整が小さかったがために、大きな「数量」の調整が必要になったともいえる。仮に需要ショックに対して価格や賃金がもっと大幅に下落すれば、量の調整はマイルドですんだはずだ。
価格調整と数量調整のバランスは年ごとの物価上昇率と失業率を図示したフィリップス曲線で確認できる。2000~09年の時期、失業率は3%台から5%半ばへ大幅に上昇したが、消費者物価上昇率の低下は微々たるもので、その結果、フィリップス曲線は2000年以降はほぼフラットになっている(図)。つまり需要変動に対する調整はもっぱら数量で行われ、価格調整の役割は限られていた。この特徴は、1971~89年の急こう配と比べると明らかであり、この時期には需要ショックに対する価格調整の役割は小さくなかった。また90~99年の時期をみると、価格調整の役割が小さいとの性質は2000年以降に急に表れたのではなく、90年代にもその傾向があった(フィリップス曲線がフラットであった)ことがわかる。
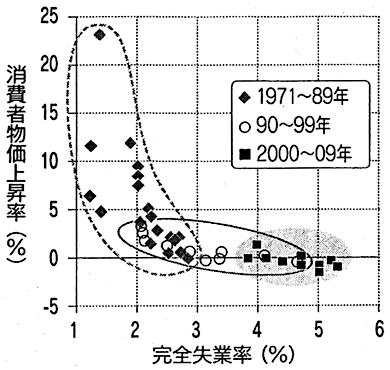
つまり足元のデフレは、価格調整の役割が低下するという90年代はじめ以降続く傾向の中で、リーマンショックを機に大規模な負の需要ショックが発生し、それが動きにくい物価を無理やり押し下げようとしていると理解すべきである。これはデフレスパイラル論で想定された物価のフリーフォールと大きく異なる。
◆◆◆
消費者物価などマクロの指標でみると価格調整の役割は小さい。一方ミクロの企業経営のレベルでは昨今、低価格競争が激化しているといわれている。競争が激しくなれば価格はむしろ伸縮的になるように思えるが、この2つの事実はどうつじつまが合うのか。
メーカーを対象にした一橋大学物価研究センターの価格設定に関するアンケート調査によれば、製造原価が変化する、あるいは製品に対する需要が変化するといった状況の変化に対して「直ちに」価格を変更するかという質問に対し、95%の企業が変更しないと回答した。その理由として最も多くの企業が挙げたのは「同業他社の対応を見極める必要がある」というものだった。つまり各企業はライバルの価格戦略を強く意識し、相互にけん制し合う結果、製造原価や需要が変化してもすぐには価格を調整しないのだ。
自らの価格を決める際、企業は製造原価や需要動向などからなる「ファンダメンタルズ」と、同業他社の価格という2つの要因を考慮する。前者の比重が90%、後者が残り10%なら、需要ショックなどファンダメンタルズの変化に対し価格は迅速に調整される。だが前者が5%で後者が95%だと、企業はお互いの動向を気にするあまり、需要ショックが起きても価格の反応は緩慢になる。価格調整の役割が小さい状況とは、これに他ならない。
この考え方は、価格の「実質硬直性」仮説と呼ばれている。低価格競争が最も頻繁に観察できるのはインターネット市場である。カカクコム社が運営する「価格ドットコム」のデータを用い、水野貴之、楡井誠の両氏と行った研究では、価格ドットコムに出店する各商店はライバル店舗より少しだけ安い価格を提示するという戦略をとっている。
競合店より高い価格では顧客を失ってしまうので、それは避けたい。といって、ライバルの価格を下回れば下回るほど来店客数が単調に増えるわけでもない。よってライバルより少しだけ安い価格を提示するのがベストである。
このようにして各店舗がお互いの価格を模倣するという行動が生まれ、これがゆっくりした価格調整を生み出す。米国での最近の研究では、輸出企業が為替相場の変化をゆっくりとしか転嫁しないという現象も実質硬直性に原因があると理解されている。
◆◆◆
10月末の日銀の展望リポートは、消費者物価の緩やかな下落が少なくとも11年度まで続くと予想している。実質硬直性仮説は需要ショックに対する価格の調整がゆっくりと時間をかけて表れることを示唆しており、これと整合的である。実質硬直性の存在は、金融政策の運営にどんな含意をもつのか。
最も重要なのは、仮に物価の下落幅が小さくても、その背後にある経済厚生の損失(経済のゆがみ)は小さくないということだ。実質硬直性のために物価は動きにくくなっているのだから、その物価がたとえ小幅とはいえ現に下がっているという事実は、それを動かす圧力が非常に大きいことを示唆する。物価の下落幅が小さいからといって、決して軽視はできない。
さらに物価だけを注視するのは危険である。先の図から明らかなように、需要ショックが起きてもインフレは微小にしか変化しない。物価統計の精度にはおのずと限界があり、微小な変化を検知するのは容易ではない。また実質硬直性仮説によれば、企業間の模倣の度合いが価格の調整速度を決めるが、その度合いは企業経営の心理などによって変化し、予測が難しい。これらの限界を踏まえれば、中央銀行は、価格だけをモニターするのではなく、数量も含めた全体として経済の様子をとらえるべきである。価格と数量の両方を合わせた指標として名目国内総生産(GDP)成長率に注目するのも検討に値する。
フィリップス曲線のフラット化は金融政策運営を難しくするが、金融政策の効果を高める面もある。フィリップス曲線がフラットに近ければ、金融政策でマネーの量を増減させるとそれが数量(鉱工業生産など)に与える影響が大きいからだ。金融政策は非中立的であり、数量の安定化を図る上で中央銀行の果たすべき役割は通常よりも大きい。
リーマンショック前との比較では、名目GDPは40兆円、率にして8%下落した。名目GDPをショック前の水準に戻すには、今後、例えば2%の名目GDP成長を4年間続ける必要がある。リーマンショック前の名目GDP水準を回復するまで量的緩和を含む超金融緩和を継続するとアナウンスするなど、企業や家計の物価予想に積極的に働き掛ける施策が必要である。
2009年12月9日 日本経済新聞「経済教室」に掲載

