日米格差が拡大
サービス部門について日米の生産性格差を詳しく検証する。今回は全要素生産性(TFP)よりも詳細なデータがある労働生産性(従業員一人当たりの生産量)という指標を用いる。対象は電力、航空運輸、通信、金融の主要四業種だ。
グラフでは入手可能な1995年までのデータを使い、日米の労働生産性の格差を示した。米国の生産性を1とした場合の日本の水準を指数で表している。
95年時点では全四業種で日本が米国を下回った。電力、航空運輸は米国の半分以下、通信は3分の2の水準だ。この三業種の日米格差は基本的に拡大。金融の格差は90年に縮まったが、95年は拡大した。関連データをみると、その後も四業種の日米格差は大きなままだと考えられる。
競争が限定的なことが日本のサービス部門の効率を低く抑えている。サービスはモノに比べて国際貿易になじみにくく、基本的には国境が市場を分断する。
企業間競争を促す
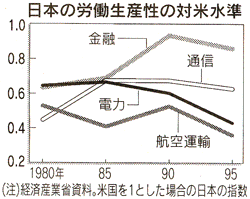 多くの国はサービス部門の新規参入や料金変更を業種ごとに法律で規制してきた。電力、通信など多額の投資が必要で規模の経済性が大きい業種では過度な競争が起こるとかえって非効率になると考えられたからだ。だが一部先進国はその後、新規参入などの条件を緩めて企業間競争を促す規制改革に乗り出した。
多くの国はサービス部門の新規参入や料金変更を業種ごとに法律で規制してきた。電力、通信など多額の投資が必要で規模の経済性が大きい業種では過度な競争が起こるとかえって非効率になると考えられたからだ。だが一部先進国はその後、新規参入などの条件を緩めて企業間競争を促す規制改革に乗り出した。
特に米国は早くから改革を進めた。日米の生産性格差は日本の改革の遅れに起因する可能性が高い。
日米の規制改革を業種ごとに振り返る。電力において米国は70年代後半から発電、送電、小売りの順で参入規制などの緩和を進めた。一方、日本では95年に電力の卸売事業、2000年に大口の小売事業への参入を自由化した。
航空運輸でも米国は78年の法改正で運賃設定などを自由化し、業界再編を促した。日本では98年に定期航空事業への新規参入が35年ぶりに実現、2000年の改正航空法施行で国内線運賃設定などを自由化した。
割高な通信料金
通信では、米国が84年に巨大企業のAT&Tを分割し、長距離分野への新規参入を促した。日本も80年代から日本電信電話公社の民営化、長距離への参入規制緩和などを実施してきたが、料金はまだ割高とされる。
金融に関し、米国は、99年に銀行・証券・保険の業務の垣根を撤廃する金融制度改革法が成立するまで比較的厳しい規制を続けた。一方、銀行、証券それぞれの業界内部だけでなく銀行と証券の間でも日本より激しい競争を続けた。
たとえば70―80年代に多額の資金が銀行から証券に移ったが、背景には証券業界における金融派生商品(デリバティブ)や資産流動化商品といった新商品の投入があった。銀行は預金金利の自由化を受けて開発した新商品で対抗した。
健全な競争は技術革新を促す。ただ、最近の米電力・航空業界などでは一部で競争が行き過ぎ、電力不足や不採算路線廃止などで消費者に不利益をもたらす負の側面も目立ち始めた。
日本経済新聞「経済教室」基礎コース(2002年1月3日~1月31日/全21回)より転載

