1. はじめに
アメリカでは、サービス部門が雇用・付加価値の8割程度を占めている。アメリカに比べれば遅れているが、日本でも、サービス部門のシェアは、雇用・付加価値の7割程度に達している。趨勢的にみても、少なくとも1970年代から、製造業の雇用・付加価値シェアが低下する一方で、サービス部門のシェアは上昇し続けている。こうした傾向は先進国全般で見られる。
しかしながら、国際貿易の分野では、Markusen (1989) など幾つかの例外を除いて、サービス部門の研究は十分になされてこなかった。今回は、サービス部門の国際化、あるいはサービスの国際取引について、近年の研究を紹介し、課題を探る。
2. サービスの特質
そもそもサービスをモノと区別する特徴は何であろうか。サービス貿易に関する包括的な展望論文であるFrancois and Hoekman (2010) は、サービスの財としての特徴を2つ挙げている。
まず第1に挙げられるのが、 サービスは「フロー」(flow)であるということである。そのため、貯めることはできない(not storable)。たとえば、美容室のカットのサービスは、生産者が消費者の髪を切るという行為であり、その瞬間に生産と消費が同時に起こり、サービスを貯めることはできない。
このことと関連して、第2に、サービスは、消費者と生産者の近接性(proximity of supplier and consumption)を必要とする場合がある。たとえば、美容師と客が離れた場所にいては、カットのサービスは行えない。
しかし、近年の情報通信技術などの技術の発展によって、この「近接性の縛り」(the proximity burden; proximity constraints for service transaction)は、緩んできている。たとえば、消費者は日本にいながら、インドの校正会社に英文校正のサービスを依頼できる。
表1は、以上で述べたサービスの財としての特質をモノと比較したものである。
| モノ | サービス | |
|---|---|---|
| 在庫 | 在庫できる | 在庫できない |
| 消費者と生産者の近接性制約 | 制約なし | 制約あり |
| 注:モノの貿易においても、距離が離れているほど輸送費用は生じる。上の表では、消費者と生産者が同じ場所にいる必要があるという意味で「近接性制約」という言葉を用いている。 | ||
3. サービス貿易の4形態
サービスの在庫ができず、消費者と生産者の近接性が必要である場合があるという2つの性質から、サービス貿易には、消費者もしくは生産者の国境を越えた移動が必要となる場合がある。
サービス貿易に関する一般協定(GATS)では、サービス貿易(trade in services)を、形態1「越境取引」、形態2「国外消費」、形態3「商業拠点」、形態4「人の移動」の4つに分類している(表2参照)。このうち、消費者もしくは生産者の国を跨いだ移動を伴うのが、形態2「国外消費」、形態3「商業拠点」、形態4「人の移動」の3つである。
| 形態1:越境取引(cross-border supply) |
|---|
|
供給者と消費者は移動しない形のサービス貿易
例)電話を用いた外国のコンサルタント利用 ネットで外国のソフトウェアを購入 |
| 形態2:国外消費(consumption abroad) |
|
消費者が供給者のいる外国に移動する形で提供されるサービス貿易
例)海外旅行や外国医療機関での治療 |
| 形態3:商業拠点(commercial presence) |
|
供給者が海外に拠点を設立して消費者にサービスを提供するサービス貿易
例)外国直接投資(FDI)により設立した海外子会社を通じた金融サービス レストランの海外支店 |
| 形態4:人の移動(temporary movement of natural persons) |
|
サービス供給者が消費者のいる外国に移動する形でのサービス貿易
例)外国人アーティストによる公演、日本人アーティストの海外公演 コンサルタントが顧客がいる国に出向いてサービス提供 |
| 出所:Francois and Hoekman (2010, p. 649) 、Jensen (2011)、および浦田他(2011、pp.25--26)に基づき作成。 |
形態1の越境取引は、供給者と消費者が移動しない形のサービス貿易である。情報通信技術の発展で、可能性が広がっている。たとえば、インターネットを介し、最も費用の安い国にサービスの海外生産委託を行うことができるようになってきている。
一方で、Head et al. (2009) が指摘しているように、サービスの海外生産委託が先進国の労働市場に与える影響には根強い懸念がある。たとえば、アメリカの企業が労働者の賃金の安いインドの企業に生産委託することがアメリカにおける雇用を減らす恐れもある。ただし、 Amiti and Wei (2005) の著名な研究によれば、そうした恐れはデータからは十分に裏付けられるものではない。
形態2の国外消費は、消費者が供給者のいる外国に移動する形で提供されるサービス貿易である。これには、国際観光が分類される。近年、日本では、訪日外国人の増加が国の政策目標となっている。訪日外国人が増加すれば、宿泊業や小売業を中心に国内サービス産業の受益が期待される。
形態3の商業拠点は、供給者が海外に拠点を設立して消費者にサービスを提供する形態のサービス貿易である。これは、サービス企業の外国直接投資(FDI:Foreign Direct Investment)を通じた海外展開と考えてよい。
マクドナルドやスターバックス、ヒルトンホテル、H&M、イケアなど日本に進出している外国企業も多いが、セブン&アイ・ホールデングス、良品計画、ベネッセ、吉野家、QBハウスのように外国に進出する日本企業も増えつつある。サービス部門では、この他にも多くの日本企業が、国内人口・国内市場の縮小に直面し、海外進出を行いつつある。
形態4の人の移動は、サービス供給者が消費者のいる外国に移動する形でのサービス貿易である。たとえば、アーティストの海外公演がこれに当たる。これまで日本では、海外からアーティストを招聘することが多かったが、近年、逆に日本のアーティストが海外で公演することも増えている。しかし、いまだにサービス収支上の「文化・興行」は赤字が続いている。
「在庫不可能性」と「近接性の縛り」というサービスの2つの特質を踏まえると、消費者が国境を越えて移動する形態2(「国外消費」)や、生産者が国境を越えて移動する形態3および4(「商業拠点」「人の移動」)が、モノの貿易と比較して、重要であろう。
4. 集計レベルでのサービス貿易の実証研究
サービスの貿易が活発になっていることを踏まえ、サービス貿易の実証研究もわずかではあるが、なされるようになってきた(表3参照)。
集計レベルのデータを用いた実証研究としては、まず、国際収支で計上される越境取引、国外消費、人の移動を扱ったKimura and Lee (2006)、Head et al. (2009) がある。また、Ramasamy and Yeung (2010) のように、サービスのFDIを扱っている研究もある。他にも、形態2にあたる国際観光を扱った研究も増えてきている(たとえば、Neiman and Swagel, 2009; Yasar et al., 2012など)。
| 研究 | 研究対象 |
|---|---|
| Kimura and Lee (2006) | 国際収支上のサービス貿易(主に形態1, 2, 4) |
| Head et al. (2009) | 国際収支上のサービス貿易(形態1, 2, 4) |
| Neiman and Swagel (2009) | 国際観光(形態2) |
| Yasar et al. (2012) | 国際観光(形態2) |
| Ramasamy and Yeung (2010) | サービスのFDI(形態3) |
この中で、Kimura and Lee (2006) の研究は、財の貿易よりもサービスの貿易の方がむしろ重力方程式への当てはまりがよいことを明らかにしている。また、財の輸出とサービスの輸入の間に補完性があることを示している。
さらに、Head et al. (2009) は、理論的に重力方程式を導出した上で、欧州統計局(Eurostat)のデータを用いて、サービス貿易(特に金融を除く商業サービス)の実証分析を行っている。そして、モノの貿易同様に、サービスの貿易においても、距離が離れているほど貿易量が減少する傾向が見られるが、その距離の効果は年々低下していることを明らかにしている。Head et al. (2009) は、物理的な輸送費用(physical transport cost)がかからないはずのサービス貿易においても、「距離の効果」が存在することを示唆しており、興味深い。
5. 企業レベルでのサービス貿易の実証研究:形態1「越境取引」
企業レベルでサービスの貿易を分析する研究も近年現れてきた。Breinlich and Criscuolo (2011) は、 イギリス企業のサービス貿易を詳細に分析した論文である。彼らの研究は、形態1の「越境取引」を対象としている。Breinlich and Criscuolo (2011) は、以下のような事実を明らかにした。
(1) サービスの輸出あるいは輸入を行っているのは、イギリスの企業の8.1%に過ぎない。どの産業でも、サービスの貿易をしている企業としていない企業が混在している。
(2) サービスの貿易を行っている企業は行っていない企業よりも、雇用・売り上げ・付加価値が大きい。さらに、サービスの貿易を行っている企業は、行っていない企業よりも、生産性が高く、資本集約的、技能集約的である。加えて、サービスの貿易を行っている企業の方が、外資系や多国籍企業である傾向が強い。
(3) サービスの輸出のみで輸入はしてない企業 (only exporters) は、輸入はしているが輸出はしていない企業 (only importers) よりも規模は小さいが、生産性が高く、技能集約的である。
(4) サービスは輸出しているがモノは輸出していない企業 (services-only exporters) は、モノのみ輸出している企業 (only-goods exporters) よりも規模は小さいが、生産性が高く、技能集約的である。
(5) サービス貿易企業の間でも異質性が大きい。輸出入額、貿易相手国数、貿易品目数、貿易相手国あたり・品目あたりの貿易額も企業によってさまざまである。
(6) サービスの輸出入額は、一部の企業に集中している。そうした企業は、多くの国と多くの品目を輸出入している。
(7) 各企業のサービスの貿易額のうち、上位の貿易相手国、上位の貿易品目が平均的に70%を占めている。
(8) サービスの輸出入額の企業間格差は、主に貿易相手国あたり・品目あたりの貿易額(貿易の内延)の格差によって説明される。これは、貿易の外延が重要であるモノの貿易とは異なる傾向である。
(9) 生産性が高く、規模の大きい企業は、多くの貿易相手国と多くの品目を貿易している。また、そうした企業は、貿易相手国あたり・品目あたりの貿易額(貿易の内延)も大きい。企業の生産性・規模と企業毎の貿易額との相関を生む主要な要因は、貿易相手国あたり・品目あたりの貿易額(貿易の内延)である。
(10) イギリスの貿易相手国ごとのサービスの貿易額の格差は、各相手国に貿易を行う企業の数や品目数 (貿易の外延) が異なることによって主に説明できる。
(11) イギリスからの距離が近く、GDP が大きい国ほど、より多くのイギリスのサービス輸出入企業・サービス品目を引き寄せている。距離やGDP がサービス貿易総額に与える影響は、主にサービス輸出入企業数・サービス品目数 (貿易の外延) を経由している。
これらの発見は、おおむねモノの貿易に関して既存研究が明らかにしてきたことと同様であり、Melitz (2003) などの新々貿易理論と整合的である。つまり、サービス貿易に関しても企業の異質性が重要な要因であることを示唆している。
6. サービスの輸出と外国直接投資:形態3「商業拠点」
近年の研究は、サービス部門の外国直接投資(サービス貿易の第3の形態「商業拠点」)に関しても、企業の異質性が重要であることを示している。Helpman et al. (2004) の新々貿易理論では、最も生産性が高い企業が外国直接投資を通じた海外進出を行い、それに次いで生産性の高い企業が輸出を行うと予測されている。
では、サービス部門の外国直接投資に関しても、Helpman et al. (2004) の予測は当てはまるのであろうか。この問いに答える企業レベルの実証研究が、わずかに出てきた。
たとえば、Buch and Lipponer (2007) は、ドイツの銀行のOECD諸国への輸出 (海外への銀行サービス提供) とFDIの決定要因を分析した研究である。Buch and Lipponer (2007) は、利益率が高い企業ほど輸出よりもFDIを行うという結果を示している。利益率と生産性は性質のかなり異なる企業属性ではあるが、Helpman et al. (2004) の理論予測に「似た」結果といえる。
Ito (2007) も、日本の大企業のデータを用いて、サービス部門では全要素生産性(TFP)がFDI開始決定を説明する要因であるという、Helpman et al. (2004) の理論と整合的な結果を得ている。つまり、低い生産性であれば、企業はFDIを開始しない。しかし、やや奇妙なことに、製造業では、全要素生産性(TFP)がFDI開始決定を説明しないという。
| 研究 | 事例 | 新々貿易理論 |
|---|---|---|
| Bhattacharya et al. (2012) | インドのソフトウェア産業 | 一部修正が必要 |
| Buch and Lipponer (2007) | ドイツの銀行 | 概ね当てはまる |
| Ito (2007) | 日本のサービス部門 | 概ね当てはまる |
もともと製造業を念頭に置いた理論であるHelpman et al. (2004) の理論が、サービス部門にそのまま当てはまるというのは、不思議ではある。
特に、サービスの輸出(「越境取引」の形態での輸出)は、モノの輸出とは、技術的に全く異なる。財の性質上、サービスの輸出は不可能である場合もあるし、逆にインターネットを介してモノよりもはるかに安価にサービスの輸出が可能である場合もある。物理的輸送費用に限れば、モノの輸出では費用がかかるが、多くのサービスの輸出では費用がかからない。
しかし、サービスの輸出に関する費用が仮にゼロであれば、企業がなぜFDIを行うのか説明がつかない。インドのソフトウェア産業を研究したBhattacharya et al. (2012) は、この矛盾にこたえるために、Helpman et al. (2004) の理論を拡張した理論分析を行っている。彼らの理論では、消費者がサービスの質に関するリスクに直面しており、その結果、Helpman et al. (2004) の理論予測とは逆に、生産性の低い企業ほど輸出よりも外国直接投資を選択する。インドのデータは、この修正された理論予測と整合的であるという。
7. 終わりに
今回は、サービス貿易に関する近年の研究動向を紹介した。製造業に比べれば、サービス産業の研究はまだまだ発展途上である。
これまでデータの制約から、サービス貿易の研究は困難であった。近年は、利用可能なデータも徐々に増えてきた。また、Francois et al. (2009) のようにデータの利用可能性を高める努力もなされている。
サービス産業は政策の余地が大きい産業である。また、サービス産業は、規制の多い産業であると言われる(Francois and Hoekman, 2010)。途上国ほどサービス産業の規制は強い(Gootiiz and Mattoo, 2009)。また、サービス貿易に関しても、貿易の自由化は、貿易を促進することを示唆する研究もある(Ceglowski, 2006)。
まずは、利用可能になりつつあるデータをもとにサービス貿易の基礎的な研究を進展させ、サービス貿易に対して、政策的にどのようなことができうるのか、経済学的な考察を深めていくことが課題であろう。
補論:サービス部門概観
サービス部門を統計データで概観しておく。図1と図2は、主要国における、サービス部門の付加価値・雇用シェアをそれぞれ示している。既に述べたように、先進国では、サービス部門の付加価値・雇用シェアが概ね7~8割程度である。それに対して、インドや中国のような途上国においては、サービス部門の付加価値シェアが4~5割程度、雇用シェアが2~3割程度である。
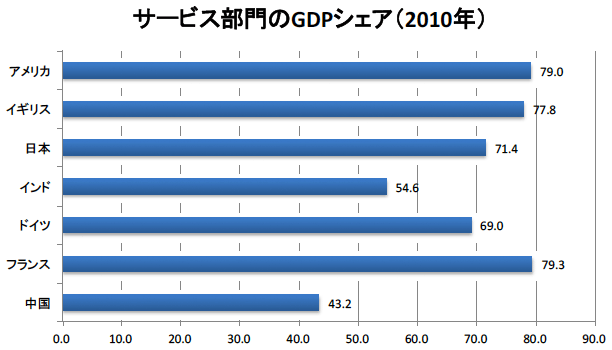
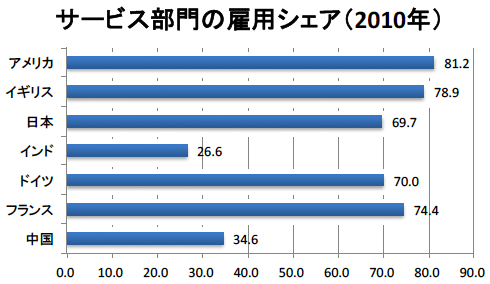
先進国と途上国を比較すれば、先進国の方がサービス部門のシェアが高いといえる。
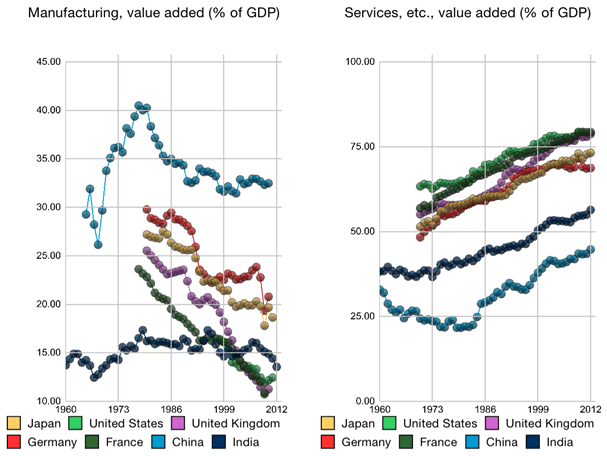
図3は、主要国における製造業およびサービス部門のGDPシェアをデータが利用可能な範囲で図示したものである。日本、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツでは、1970年代以降、製造業のシェアが低下する一方で、サービス部門のシェアが上昇していることが分かる。日本において、サービス部門のシェアは1973年に50%程度であったが、2012年には、75%程度にまで上昇している。代わりに、1970年代に25%を超えていた製造業のシェアは、2012年には20%以下に低下している。
図4は、1人あたりGDPとサービス部門のGDPシェアとの関係を示した散布図である。1人あたりGDPが大きい先進国ほど、サービス部門のGDPシェアが高いことが分かる。これは、先進国の方が、サービス部門に比較優位を有していることを示唆している。
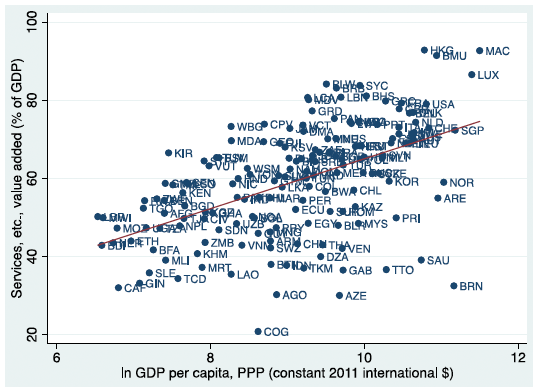
図5は、主要国におけるサービスの輸出額を示している。主要国の中で、アメリカがサービスの輸出額が圧倒的に大きいことが分かる。日本のサービスの輸出額は主要国の中で小さく、中国よりも少ない。
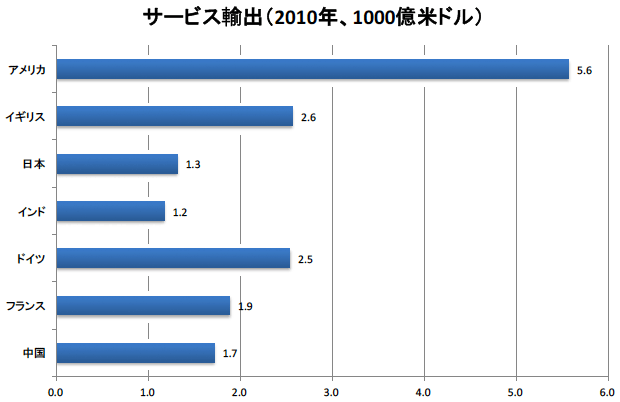
Head et al. (2009) は、1985―2005年の20年間に、モノの輸出以上にサービスの輸出が世界で増加していることを明らかにしている。サービスの輸出は、2005年には1985年の5倍以上に達している。
日本のサービス収支は、長らく赤字である。表5に示すように、輸送、旅行、保険、その他営利業務で大きな赤字額を計上している。一方で、建設や金融、特許権使用料、公的その他サービスに関しては黒字である。貿易収支は、東日本大震災以前は黒字であったが、震災後赤字に転落した。そのため、震災後、日本の貿易・サービス収支は、モノ・サービスともに赤字の状態となっている。
| 受取 | 支払 | 収支尻 | ||
|---|---|---|---|---|
| サービス収支 | 116,167 | 141,067 | -24,900 | |
| 輸送 | 32,048 | 44,167 | -12,119 | |
| 旅行 | 11,631 | 22,248 | -10,617 | |
| その他サービス | 72,488 | 74,652 | -2,164 | |
| 通信 | 772 | 945 | -173 | |
| 建設 | 9,244 | 6,188 | 3,056 | |
| 保険 | -315 | 5,891 | -6,206 | |
| 金融 | 3,706 | 2,573 | 1,133 | |
| 情報 | 1,081 | 3,587 | -2,506 | |
| 特許権使用料 | 25,445 | 15,876 | 9,569 | |
| その他営利業務 | 29,937 | 37,142 | -7,205 | |
| 文化・興行 | 145 | 957 | -812 | |
| 公的その他サービス | 2,474 | 1,494 | 980 | |
| 出所:財務省「国際収支統計」より著者作成 | ||||
アメリカは、Jensen (2011) が指摘しているように、1992―2009年の期間に、モノの貿易収支は継続して赤字であるが、サービスの貿易収支は継続して黒字である。
謝辞
本稿の一部は、椋寛・学習院大学経済学部教授からの御教示に負うところがあります。


