1. はじめに
輸出企業の賃金は平均的に高い。代表的な研究であるBernard and Jensen (1999) によれば、1992年にアメリカにおいて輸出企業の平均賃金は、非輸出企業に比べて9.6%高い。若杉 (2008) によれば、ドイツで2%、フランスで9%、イギリスで15%それぞれ、輸出企業の平均賃金は、非輸出企業に比べて高い。著者の試算によれば、日本では、輸出企業の正規労働者の平均賃金(時給)は約3千578円で、非輸出企業の2千804円に比べて、700円以上 (約25%) 高い (Tanaka, 2012)。このように輸出企業の平均賃金が高い事実は、世界各国で確認されている。
では、どうして、輸出企業の平均賃金は高いのであろうか。今回は、近年急速に進展してきた貿易と賃金に関する新しい研究潮流をもとに、輸出と賃金との関係を考察する。
2. 生産性、輸出、賃金
輸出企業の平均賃金が高いという事実を、伝統的貿易理論や新貿易理論は十分に説明できない。これら新旧貿易理論が同質的な企業を仮定しているため、輸出企業と非輸出企業との間の企業間の差異を説明することができないからである。
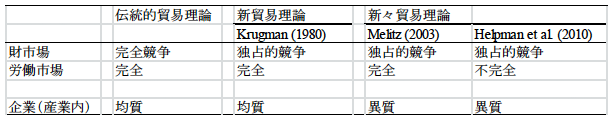
そのため、Helpman et al. (2010) をはじめとする幾つかの理論研究が、企業の異質性を仮定しつつ、輸出企業の平均賃金が高い事実を説明しようと試みている。Helpman et al. (2010) がこれまでの標準的な貿易理論と異なるのは、労働市場の不完全性を貿易理論に導入した点である(表1)。Melitz (2003) の新々貿易理論は、財市場では独占的競争が行われていることを考えていたが、労働市場は完全であり、失業は生じないと考えていた。Helpman et al. (2010) はMelitz (2003) の新々貿易理論に労働市場の不完全性を加え、失業も生じる貿易理論になっている。
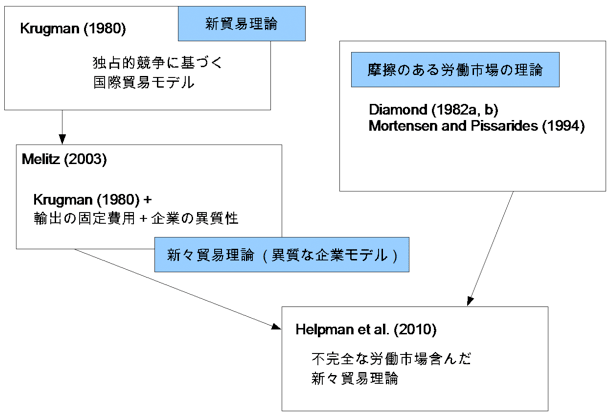
Melitz (2003) が論じたように、生産性の高い企業ほど多くの収入を得られる。また、輸出に伴う大きな固定費用をまかなえるほどに海外で収入を得ることができる輸出企業は、輸出に最低限必要な生産性(輸出閾値)を超える一部の生産性の高い企業のみである。
Melitz (2003) は企業の生産性が異質であると仮定した。それに対して、Helpman et al. (2010) は、企業の生産性のみならず、労働者の能力も異質であり、能力の高い人もいれば、低い人もいると考えている。さらに、企業の生産量は、その企業の生産性だけではなく、雇用している労働者数と労働者の平均的な能力にも依存すると考えている。また、労働者の募集を行い、能力を調べるには、それぞれ探索費用(search cost)と審査費用(screening cost)がかかるという意味で、労働市場には摩擦(search and matching frictions)があると想定されている。
当然ながら、多くの人数の募集を行い、より高い能力の労働者を見つけるために審査するには、高い費用がかかる。そうした費用を負担することができるのは、生産性の高い企業である。生産性の低い企業に比べて、生産性の高い大企業は、より多くの人数の募集をかけ、より高い能力の労働者の審査を行うことができる。結果として、生産性の低い企業に比べて、生産性の高い企業は、雇用者数が大きく、また労働者の平均的能力が高い。労働者の平均的能力が高いので、生産性の高い企業の平均賃金は高くなる。
Helpman et al. (2010) は、企業が国内外の市場から得た収入を労使交渉により労働者に一定割合分配すると考えている。また、非輸出企業に比べて、輸出企業は、海外からの収入も得られ、より大きな収入を得ることができる。労使間分配(firm-worker rent sharing)が本当に行われるのであれば、輸出企業で働いている労働者の賃金は、非輸出企業の同等の労働者よりも高くなる。これまでの考察をまとめると、図2に示すように、第1に、生産性が高い企業ほど、高い賃金を支払う。第2に、輸出企業は、非輸出企業よりも高い賃金を支払う。
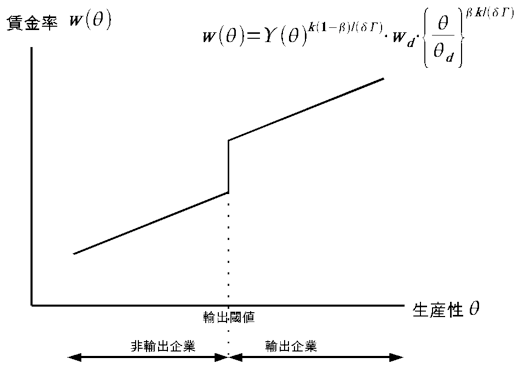
このようにHelpman et al. (2010) をはじめとする新しい理論研究は、労働市場の不完全性を貿易理論に導入することによって、貿易と賃金格差や失業の関係を分析する端緒を開いている。Helpman et al. (2010) 以外にも、この数年、不完全な労働市場を含んだ貿易理論が開発されている。労働市場の理論化は、論文によってやや異なる。下の表2はそれをまとめたものである。
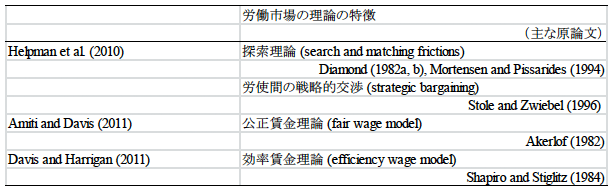
3. 企業・労働者接合データ
Helpman et al. (2010) は、輸出を行うような生産性の高い企業は、高い能力の労働者を雇用しており、そうした企業が輸出収入を労働者に分配するために、輸出企業の平均賃金が高いのだと考えた。つまり、輸出企業の平均賃金の高さは、輸出収入の分配と労働者の能力の高さという2つの視点から説明できる。
では、労働者の能力の違いを制御してもなお、輸出企業の労働者の賃金は、輸出収入の分配によって高いのであろうか。そうした問いに答えるために、近年、「企業・労働者接合データ」(linked employer-employee data) と呼ばれる企業または事業所(雇用主)と労働者(雇用者)双方の情報を含むデータベースを用いた研究が行われるようになってきている。その先駆けとなったSchank et al. (2007) は、ドイツに関して、労働者の質を制御してもやはり、輸出事業所の労働者の賃金が高いことを見出している。Frias et al. (2009) は、メキシコに関して、通貨ペソの減価によって輸出が容易になったときに、輸出事業所の賃金が高まったのは、ほとんど「賃金プレミア」によることを明らかにした。「賃金プレミア」とは労働者の質を制御してもなお残る賃金の高さである。Frias et al. (2009) の結果も、労働市場の不完全性と輸出収入の分配を示唆しているといえる。Helpman et al. (2012) もまた、ブラジルの企業・労働者接合データを用いて、Helpman et al. (2010) の理論予測を裏付けている。
4. 終わりに
貿易によって国全体として利益が生じることは伝統的貿易理論によっても、Krugman (1980) の新貿易理論、Melitz (2003) の新々貿易理論によっても示されている。ただし、貿易が個々の労働者に与える影響は一様ではない。それは、第10回のコラムで紹介した伝統的貿易理論のストルパー=サミュエルソン定理も示している。しかし、ストルパー=サミュエルソン定理は、産業単位の理論であり、企業・労働者単位で貿易が賃金にどのような影響を与えるのかを分析することはできない。
今回紹介したHelpman et al. (2010) は、企業・労働者単位で貿易が賃金にどのような影響を及ぼすのか考察する基礎を築いたといえる。今後、日本においても、貿易が個々の労働者に与える影響を精緻に分析し、政策に活かしていくことが必要であるといえる。


