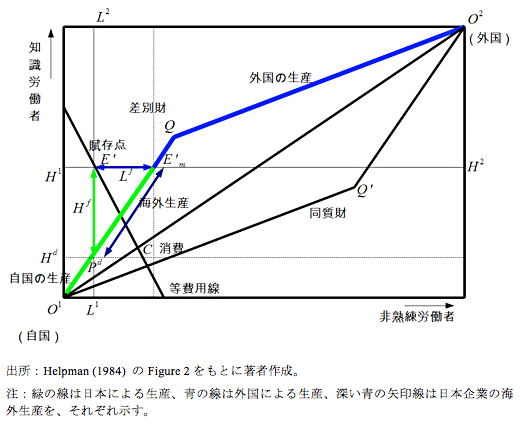1. はじめに
震災後の電力不足によって、以前にまして産業空洞化への懸念が強まっている。電力不足と高い法人税率、円高、労働規制、温暖化対策、貿易自由化の遅れと合わせて、「六重苦」と呼ぶこともある。
企業が生産拠点を海外に設けるとき、国内の資源配分はどうなるのであろうか。こうした問題を考える1つの出発点となるのが、今回紹介するヘルプマンの論文、Helpman (1984) である。
Helpman (1984) は、一般均衡の枠組みを用いて、海外生産の仕組みを理論的に初めて明らかにした。垂直的外国直接投資(垂直的FDI)や多国籍企業の研究の古典的論文である。
前回は、企業の海外進出の理由を俯瞰的に紹介したが、今回は、Helpman (1984) に依拠して、先進国の企業が途上国に進出する垂直的外国直接投資に絞って、海外生産の仕組みを考える。
2. 国境を越える知識
テレビや自動車のように差別化された工業製品の生産には、知識労働者(general purpose input)と非熟練労働者が必要であると考えることができる。知識労働者は、製品の開発や製造工程の設計、企業組織の経営等を行う。非熟練労働者は、製品の製造に従事する。
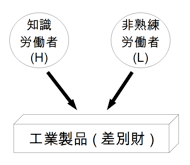
ここで重要なことは、知識労働者が生み出す知識(サービス)は、国境を越えることができることである。たとえば、日本で製品開発されたトヨタのカローラは、タイでも生産できる。日本でデザインされたユニクロのフリースは、中国でも生産できる。知識労働者が生み出す知識は、いわば企業特殊な公共財であり、国境を越える。
3. 垂直的外国直接投資を理解する
では、なぜ、トヨタやユニクロのような日本企業は、日本で開発した製品を中国やタイで生産するのか。
それは、Helpman (1984) に基づけば、日本と中国(タイ)で資源の賦存状況が異なるからである。日本は相対的に知識労働者が多い。一方の中国は相対的に非熟練労働者が多い。日本に比べ、中国にはふんだんに非熟練労働者がいる。逆に、日本は、大卒者の割合が中国に比べて高い。
それぞれの豊富な資源を出し合えば、個々の国で独立に生産を行うよりも、日本と中国全体としてより多くの生産を実現できる。日本の知識労働者の知識と中国の工場労働者の力が合わされば、より多くの財を生産できる。
知識は国境を越えることができる一方で、非熟練労働者は国境を越えることができない。結果として、生産拠点は、日本ではなく中国に位置することになる。海外生産から得られる収入の一部は、日本の知識労働者への対価として日本に還元される。その対価を用いて、日本は別の財を海外から輸入することができる。それによって、日本は豊かになる。
4. 産業は空洞化するのか
Helpman (1984) に基づいて考えれば、日本企業の海外生産は、日本を豊かにする。企業の海外生産を止める必要はない。失業という無駄も生じない。国内雇用の減少も生じない。むしろ、日本企業の海外生産で資源は有効活用される。
では、こうした理論に反して、産業の空洞化の問題に人々が頭を悩ませているのはどうしてなのか。
その理由の1つとして挙げうるのは、理論の想定に反して、労働市場が不完全であることである。労働者は、企業に瞬時に円滑に雇用されるわけではない。その結果、完全雇用が実現せず、失業が生じうる可能性がある。
ただ、国内の失業と企業の海外生産がどのように関連するかは明らかではない。労働市場の不完全性を含めた国際貿易理論は、近年急速に開発されつつあるが、外国直接投資まで含めた理論は、まだ見当たらない。
5. 終わりに
今回は、Helpman (1984) に基づいて、企業の海外生産を資源配分問題として考えた。基本的には、企業の海外生産は、国内外の資源の有効活用を通じて、日本を豊かにする。一方で、労働市場の不完全性を考慮すれば、企業の海外生産と労働市場との関係については、未解明の点も残る。
今回の垂直的外国直接投資の議論を踏まえて、次回以降、契約理論を用いて本社と海外子会社との関係を分析する新しい研究潮流を紹介することにしたい。