1. はじめに
前回、「新々貿易理論」の基本であるMelitz (2003) の理論を紹介した。Melitz (2003) は、外国に製品を販売する手段として「輸出」のみを考慮していた。しかし、現実には、「外国直接投資」(foreign direct investment, FDI)によって外国に工場を建設し、現地生産した自動車を外国の消費者に販売する場合もある。
Melitz (2003) は、輸出を行わない企業よりも輸出を行う企業の生産性が高いと主張した。では、輸出と外国直接投資のいずれを行う企業の生産性が高いのであろうか。Melitz (2003) を拡張し、その点について分析を行ったHelpman et al. (2004) を今回は紹介する。
2. 近接集中仮説
外国に製品を供給・販売する手段として、輸出と外国直接投資の2つがある(図1参照)。第1に、輸出の場合、国内で製造した製品を外国に輸送し、外国消費者に供給する。この場合、国内の工場に生産を集約して、工場レベルの規模の経済をいかすことができる一方で、外国への輸送費用(関税含む)がかかる。
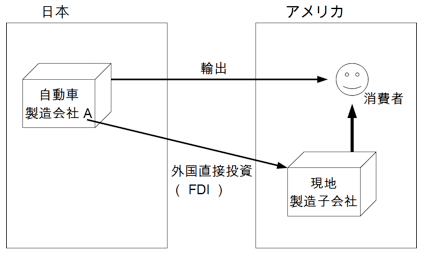
第2に、外国直接投資の場合、日本の企業が外国に現地製造子会社を設立し、その子会社で製造した製品を外国消費者に供給する。この場合、現地製造子会社を設立・維持する費用がかかる一方で、輸送費用は輸出に比べてかからない。
輸出と外国直接投資の利点と欠点をまとめると、以下の表のようになる。
| 利点 | 欠点 | |
|---|---|---|
| 輸出 | 工場レベルの規模の経済を生かせる | 輸送費用(関税含む)が大きい |
| 外国直接投資 | 輸送費用が小さい | 外国子会社の設立・維持費用が大きい |
Brainard (1997) が、これらの輸出と外国直接投資の特徴を定式化した。輸出で生産を集中するか、外国直接投資で外国消費者に近接するか、いずれかを企業は選択するという意味で、「近接集中仮説」(proximity-concentration trade-off)と呼ばれている。Helpman et al. (2004) は、この近接集中仮説を踏襲している。つまり、輸出に比べて、外国直接投資は、相対的に可変費用が小さく、固定費用が大きいものとして、彼らは分析を行った。
3. 生産性と輸出・外国直接投資
輸出と外国直接投資の利点と欠点を踏まえて、Helpman et al. (2004) は、生産性の高い企業は、輸出よりも外国直接投資を選択すると考えた。外国直接投資は固定費用の負担が大きいものの、輸送費用を節約できるため、売上の大きい高生産性企業にとって有利な手段である。また、Melitz (2003) と同様に、輸出を行える企業は、輸出に伴う費用をまかなうことができるので、国内にのみ供給する非国際化企業よりも生産的である。
結果として、最も生産性が高い企業が外国直接投資を行う「多国籍企業」になり、それに次ぐ企業は外国に輸出を行う「輸出企業」、最も生産性の低い企業は国内にのみ製品を供給する「非国際化企業」になる。それを図示したのが図2である。
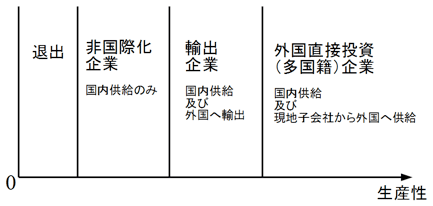
4. 終わりに
Helpman et al. (2004) が示した輸出と外国直接投資の理論は、現実を単純化したものであるが、世界各国の研究によって実証的に支持されている。経済産業研究所でも若杉他 (2008) が日本企業について包括的な検討を行っている。
しかしながら、外国直接投資の目的や種類は多様化している。本稿で説明した外国直接投資は、輸送費を節約するための「水平的外国直接投資」と呼ばれるものである。その他の外国直接投資についても、また稿を改めて議論していきたい。


