1. はじめに
企業単位のデータが利用可能となり、1990年代頃から輸出企業の実証分析が盛んに行われるようになった。ペンシルバニア州立大学のMark J. Roberts教授とJames R. Tybout教授らは、簡便な部分均衡の動学理論に基づいて、「なぜ企業は輸出するのか」という問いに答えようとした。それら初期の研究の枠組みは、その後の数多くの実証研究に引き継がれるとともに、Melitz (2003) の一般均衡の新々貿易理論(firm heterogeneity model)の基礎を成している。そこで、今回は、「なぜ企業は輸出するのか」という問いに挑んだ実証研究の枠組みを紹介する。なお、ペンシルバニア州立大学は今では、Jonathan Eaton教授、Stephen Ross Yeaple准教授らを擁する、国際貿易に関しては世界有数の研究拠点となっている。
2. 企業の輸出決定の動学理論:Roberts and Tybout (1997)
Roberts教授とTybout教授は、2つの点に着目して「なぜ企業は輸出するのか」という問いに答えた。第1に、彼らは、輸出により外国から追加的な利潤が得られるはずであると考えた。これまで国内市場からの利潤しか得られなかった企業が外国市場からも利潤を得るようになれば、当然その企業の企業価値は上昇する。輸出を開始した時点において外国市場からの利潤が得られるのみならず、輸出による利潤増加によって企業価値が増加するのだから、企業は輸出するのである。
第2に、彼らは、では「なぜすべての企業が輸出を行わないのか」を考えた。彼らによれば、輸出により利潤が増加するのに輸出を行わない企業がいるのは、輸出開始に際して巨額の固定費用を負わないといけないためである。外国に製品を輸出し販売するためには、販路を開拓し、流通網を整備するために巨額の費用がかかる。流通網の整備等にいったん投資すれば、後で売却し費用を回収することは多くの場合困難であろう。そのため、輸出の決定は不可逆な性質をもってしまう。巨額の投資を行う以上、容易には輸出をやめることはできない。そのため、輸出に伴う固定費用を負担するほどに外国での利潤を期待できない企業は、そもそも輸出を行わない。
以上の2点を踏まえれば、輸出に伴う固定費用(sunk cost)をまかなえるほどに、輸出によって追加利潤の獲得(それによる企業価値の上昇)が見込まれるのであれば、企業は輸出を行うことを決定するはずである。
下の図1は、上で述べた企業の輸出意思決定の動学理論を図にしたものである。
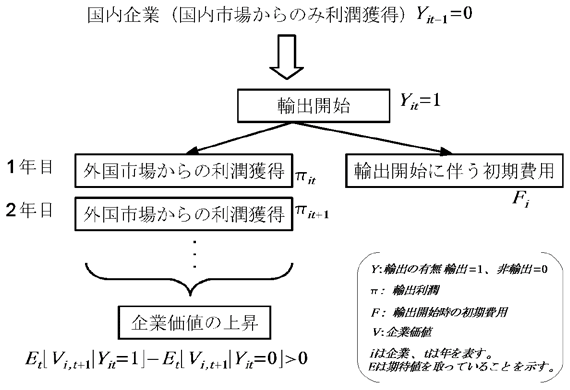
3. 企業の輸出決定の推定方法:Bernard and Jensen (2004)
Roberts教授とTybout教授の考えた輸出決定の枠組みは単純なものであるが、実際にそれをデータで検証することは難しい。彼らの理論に基づけば、輸出を今年開始する企業は外国市場での流通網の整備への投資など巨額の固定費用がかかるので大変である。一方、輸出を前年行った企業は既に輸出の固定費用を支払っているので、今年も輸出を継続することはそれほど大変なことではないはずである。
この考えがどれほど本質的であるかを確かめるには、過去の輸出経験がある企業ほど今期に輸出する傾向がどの程度強いのかを検証すればよい。しかし、過去の輸出経験が今年の輸出決定に与える影響を推定するのは難しい。輸出決定には当該企業の製品属性や経営能力のように研究者の観測できない企業特性(unobserved firm heterogeneity)が大きな影響を持つと考えられる。こうした観測できない要因を制御できない以上、通常の最小二乗法による推定では過去の輸出経験が今期の輸出決定に与える影響を過大に評価してしまうのである。
そのため、これらの観測できない企業特性をいかに処理するかについて慎重に検討しなければならない。主に以下の3つの方法があるが、それぞれに問題が残る。
- 「通常の最小二乗法」
⇒既述のように、過去の輸出経験を過大に評価してしまう。 - 「変量効果法」:観測できない企業特性は確率的なものとみなす。
⇒観測できない企業固有の要因が説明変数と相関しないと仮定することが必要。現実的な仮定ではない。 - 「固定効果法」:観測できない企業特性は当該企業に固有のものとみなす。
⇒過去の内生変数(過去の輸出経験)を説明変数に用いるときには、その推定係数の不偏性・一致性が保証されない。固定効果が説明変数の効果を吸収し、過去の輸出経験の推定係数は実際よりも過小に評価される。
そこで、ダートマス大学のAndrew B. Bernard教授とジョージタウン大学のJ. Bradford Jensen准教授は、従属変数・説明変数の階差を一度とり、時間によらない企業特性を消去したうえで、一般化積率法(GMM)で推定するという手法を採用している。Roberts教授とTybout教授の枠組みによれば、過去の輸出経験があるほど今期に輸出する傾向は強い。アメリカのデータを用いたBernard教授とJensen准教授によれば、その効果は、一般化積率法を用いると、39.1%であることが推定された (Bernard and Jensen , 2004)。前年輸出していれば、39.1%だけ輸出を行う確率は高まるのである。この結果は、1.の手法での65.5%よりも小さく、3.の手法での20.3% よりも大きい値である。用いる手法によって、大きく結果が異なってしまうので、慎重に手法を検討する必要がある。
なお、技術的には、輸出するか否かという2項選択を分析するための推定手法として、たとえば、以下の3つのものがある。
- プロビット法
- 条件付きロジット法
- 線形確率法
Bernard教授とJensen准教授は線形確率法を採用している。これらのいずれを使うかも大きな問題ではあるが、詳細はBernard and Jensen (2004) に委ねて、本稿では触れない。
4. 政策含意
輸出意思決定の動学理論からは、第1に、輸出開始段階において生じる初期費用を削減する政策が、輸出促進にとって重要であることが分かる。残念ながら、Bernard教授とJensen准教授はアメリカの州政府の輸出促進補助金に統計的に有意な効果を見出していない。効果的な輸出促進策のために考えねばならないのは、「輸出の初期費用とは何か」ということであろう。外国市場に関する情報収集費用、外国市場における流通網の整備費用、外国事務所の設立、外国消費者に合わせた商品開発費用などが考えうる。企業にとって輸出の障壁となっている初期費用を明らかにし、その費用を削減するために自由貿易の枠組みの中でどのような政策手段を取りうるのか考える必要がある。たとえば、日本貿易振興機構(JETRO, http://www.jetro.go.jp/)の活動は外国市場に関する情報収集費用を低減する上で、重要であると考えうる。民間の商社も輸出に関する様々な費用を低減することに大きな役割を果たしてきたと考えられる。
第2に、輸出開始に当たっては、金融や保険の役割も重要である。輸出の利潤が年を追って発生するのに対して、輸出初期費用は輸出開始段階で発生する。将来の企業価値を適切に評価し、輸出開始段階において輸出初期費用を融資する金融機関が存在しなければ、輸出に踏み切れない企業もいるだろう。スタンフォード大学のKalina Manova助教授は、輸出における金融の重要性を指摘する実証研究を行っている (Manova, 2008)。
また、将来の輸出利潤の発生は不確実である。為替レートが2010年は大幅な円高となり、円換算の輸出利潤が減少した。途上国において製品代金の受け取りができないこともありうる。国内活動以上に輸出には不確実性が大きい。これらの高い不確実性のために、企業が輸出を開始できないということもありうる。日本貿易保険(NEXI, http://nexi.go.jp/)が行っているような貿易保険の取り組みは、輸出の不確実性を軽減するうえで、意味のあるものと考えられる。
5. 終わりに
企業の輸出意思決定を扱う研究は、Roberts教授とTybout教授の研究から10年以上を経たいま、膨大な量になっている。経済産業研究所(RIETI)でも戸堂康之・東京大学教授/RIETIファカルティ・フェローらによって研究されている。戸堂教授は、研究者には観測できないが輸出に影響する企業特性とは何かを明らかにしようと、独自の調査を用いて研究を続けられている (戸堂、2010)。国際的には、Sanghamitra, Roberts, and Tybout (2007) がこの分野を新しく切り拓いている。


