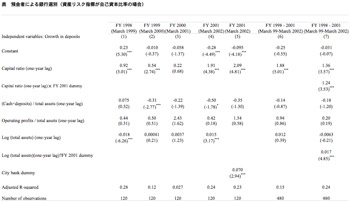1. イントロダクション
2002年という年は、今後の金融システムの方向性に大きな影響を与えうる政策が実行、または、決定された年として記憶されるかもしれない。96年度から6年間続いてきた預金等の全額保護は2002年4月から定期預金などは定額保護(元本1000万+利息等)となり、残された普通預金や当座預金なども2003年4月から定額保護に移行される予定であった。
しかし、7月末の小泉総理の指示をきっかけに、決済機能の安定化の御旗の下、ペイオフの完全実施は延期され(3年間)、それ以後「決済性預金」の新たな(選択)導入とその全額保護が決定された。また、10月末には、主要行の不良債権問題解決を目指した「金融再生プログラム」が策定され、資産査定の厳格化については新たな手法が検討されることになったものの、肝心の銀行経営のガバナンス強化については中途半端なものに終わってしまった。また、12月には地銀や信金・信組などはその合併促進のために行政が過度なまでのインセンティブを与える法案が国会で成立した。どんな形であれ預金の全額保護を残し、また、やみくもに合併を促進させる政策は、銀行経営者の責任、けじめをあいまいにさせるという意味で、むしろ不良債権問題解決に逆行するような政策といわざるを得ない。
こうした金融行政の迷走を正す視点として、もう一度、銀行のガバナンスのあり方を検討することが必要である。本稿では、銀行に規律を与える方法として、市場からの規律、特に、債権者である預金者からの規律とその前提となる銀行選別の重要性を指摘したい。銀行のような規制産業の場合、後でみるように規制・監督当局からの規律が重要ではあるが必ずしも完全ではない。特に、現在の日本のように、金融行政がさまざまなジレンマの中でがんじがらめになっている状況においては、なんらかの市場メカニズムを伴った規律付けが補完的な役割を果たすと考えられる。
以下では、まず、銀行のガバナンスのあり方について通常の非金融企業との対比を行いながら、簡単に整理し、中でも、預金者(債権者)からの規律付けの重要性を指摘する。次に、預金者による規律付けと預金保険との関係を議論し、諸外国などの経験や日本における預金者による銀行選別の実際について議論する。最後に、決済性預金の導入とペイオフ完全実施延期、並びに、金融機関の合併促進策について評価を行うことにしたい。
2. 銀行のガバナンスと預金者の規律付けの重要性
最初に、銀行のガバナンスはどうあるべきかという一般論から考えることにする。通常、コーポレート・ガバナンスの議論を行う場合、その対象は暗黙的に事業会社(非金融機関)が想定され、銀行などの金融機関はむしろ、規律付けを行う側の重要なプレーヤーとして位置付けられてきた。しかし、銀行危機、不良債権問題の本質をよりよく理解するためには、銀行へのガバナンスを通常のコーポレート・ガバナンスと同じフレーム・ワークで再考することは、これまでの経済学ではやや見過ごされてきた感はあるものの、有益と考えられる。具体的な分析視点としては、株主からの規律、債権者からの規律、競争相手(同業者)からの規律などが挙げられる。
銀行の特色:「不透明性」と政府による規制
それぞれの規律に関して銀行独自の特色を考える際に重要なポイントは、銀行の「不透明性」と政府による規制である(Caprio and Levine (2002))。銀行が規制産業であることは異論ないであろうが、銀行が「不透明」というのは若干の説明が必要であろう。まず、金融機関の場合、その扱う商品・サービスは基本的に「将来の支払い約束」で取引されるため、すぐその質を知ることは難しいという特徴がある。特に、銀行の扱う貸出の場合、流動性のある効率的なセカンダリー・マーケットが成立していないため、この問題は他の金融商品を扱う企業よりも深刻である。また、通常の事業会社に比べ、資産のリスク配分を変化させたり、不良企業に追貸しをしてリスクを隠すことも比較的容易にできる。実際、Morgan(1998)は、債券アナリストの評価を利用して、事業会社よりも銀行の債券発行の方が評価の異なる度合いが大きいこと、また、銀行は、資産における貸出の割合が高く、債券の割合が低いほど、または、自己資本率が低いほど、評価が分かれやすいことを示した。企業の現状パフォーマンス(リスク)を適切に評価することが難しいという意味で銀行は「不透明性」を持つといえる(Caprio and Levine (2002))。
こうした観点から、銀行の「不透明性」は、とりもなおさず、情報の非対称性問題を深刻にし、株主や債権者(預金者等)による経営のモニタリングやテイクオーバーを難しくするのと同時に、経営者の私的利益追求をより容易にしているであろう。また、銀行は規制産業の1つとして、政府からさまざまな制約や保護を受けていることが、通常のガバナンス・メカニズムを阻害している面がある。たとえば、参入制限などは競争相手からの規律を弱めているし、預金保険は保護された預金者のモニタリング意欲を奪うという問題がある。また、大口の株主になって有効な規律付けを行うことも規制上の問題で必ずしも容易ではない。つまり、通常の、株主、債権者、競争相手からの規律付けは、銀行の場合、弱くならざるを得ないのである。
規制当局の失敗:評判への配慮と先送り
したがって、銀行の場合、規律付けを与える主体として重要なのは、いずれの国も規制・監督当局である。しかし、銀行の「不透明性」の問題は、他の規制産業よりも規制・監督当局のコントロールを難しくしている面がある。また、当局者自身を国民から銀行の規制・監督を依頼されたエージェントとして考えると、当局自身も銀行に有効な規律付けを行うという以外に私的な利益を追求するインセンティブが生まれる。たとえば、金融当局が、銀行業を監督していくに当たり、事前に行う監視と事後に行う検査を同時に行っているとすると、事後的に不正を見つけたとしてもそれは事前の監督が不十分であったことを明らかにすることになるので、自己の評判に配慮する当局者は、それを見逃したり、そもそも事後的に不正を見つけるインセンティブは弱くなってしまうであろう(Boot and Thakor (1993))。規制当局者が自らの責任を回避するために問題の先送りを選択するという行動は80年代にアメリカのS&L問題が深刻化した大きな要因とされており、また、日本の不良債権問題の解決の遅れに影響を与えているといえる。/p>
預金者による規律の重要性
したがって、政府当局も銀行に対して完全な規律付けを行うことができないことを前提とすると、やはり、なんらかの形でマーケットからの規律で補完するという発想が重要となろう。また、銀行のガバナンスを考える上で重要な特色として挙げた、「不透明性」と政府規制の影響を考えると、コントロールや干渉の対象として注意しなければならないのは銀行のリスク・テイク行動である。競争の激化やバブル崩壊で自己資本の毀損した銀行は、政府のサポートをあてにして(預金保険、資本注入)、却ってリスクの高い資産に投資し、「起死回生」を狙うという戦略を採る傾向があるためである。このようなリスク・テイク行動を抑制するには、株主からの規律はあまり効果がない。株主もアップサイド・リスクを選好するため、経営者と利害が一致するためである。一方、債権者(預金者等)は、銀行のリスク・テイク行動が成功したとしても、そのハイ・リターンは享受できないだけでなく、それが行き過ぎて銀行が破綻した場合、そのロスは応分に負担しなければならない。このため、債権者の側からすればこうした銀行のリスク・テイク行動を抑制したいというインセンティブは大いにあるのである。
企業の業績が良い場合は株主がガバナンスを担い、業績が悪化すれば債権者がガバナンスを受け持つという状態依存型のガバナンスは、銀行のみならず通常の非金融企業にも有効な手法である。銀行の債権者は小口の預金者が中心であり、実効あるモニタリングができないため(フリー・ライダー問題)、規制・監督当局が預金者の利益を代弁し、代表してモニタリング、コントロールを行うというのが、Dewatripont and Tirole (1994)の理論フレーム・ワークである。しかし、小口の預金者はモニタリングが行えないとしても、預金先の銀行の破綻リスクが高いと思えば、預け先を変える(銀行選別)というオプションを持っている。これは、A. O. Hirschman(1970)が指摘した、意見("voice")ではなく、退出("exit")による規律付けとして機能しうると理解できる。
以上まとめると、銀行のガバナンスについては、通常の事業会社とは違っていくつかの難しい問題を持つ。それは、銀行がその他の企業に比べて「不透明な」存在であり、また、政府の規制を受けていることに関係する。たとえば、「不透明性」が銀行の外部投資家との間のエージェンシー問題を大きくしており、また、規制の存在が同業者との競争による規律を弱めている部分がある。また、ガバナンスの主体を担っているとされる監督当局も私的利益を追求する場合があり、必ずしも完全な存在ではない。こうした状況の下、預金保険の存在でその有効性は弱められているものの、銀行のリスク・テイク行動を抑制するインセンティブを持つ債権者(預金者)からの規律、つまり、マーケットからの規律を効果的に活用することが重要である。
3. 預金者による規律付けと預金保険の関係
銀行のガバナンス、特に、規制・監督当局によるガバナンスが必ずしも有効に働かない場合、預金者による規律付けが重要な補完的役割を果たしうることを強調したが、預金者の規律付けが有効に働く条件として、以下の二つの制度的要因が重要である。
預金保険、破綻処理の効率性が預金者による規律付けに与える影響
第一は、預金保険の仕組みである。預金が全額、完全に保護されれば、預金者が銀行を選別したり、モニタリングするインセンティブはかなり低下してしまう。したがって、預金者からの規律を働かせるためには、他の条件を一定として預金保護の程度が低い方が望ましいといえる。事実、Demirguc-Kunt and Detragiache (2002)は、67カ国、1980-97年までデータを使い、明示的な預金保険制度を持つ国、または、保険の適用上限が高い国ほど銀行危機が発生しやすいことを示した。したがって、銀行のモラル・ハザードを抑制するには、預金保険でカバーされる額は、銀行を選別したり、モニタリングしたりするコストを負担できない、または、インセンティブのない(フリー・ライダー)小口預金者に対しての最低限のセイフティ・ネットを提供するという目的に限定すべきである。
一方、預金保険の重要性は、預金者を安心させ、パニック的な銀行取付けを未然に防ぐという役割もしばしば強調される。なぜなら、Diamond-Dybvig (1983)のモデルにも示されているように、理論的には、預金者の期待いかんによっては健全な銀行にも取り付けが起こり、伝染病のように次々に波及していく可能性があるからである(伝染的銀行取付け、"contagious bank run")。つまり、このような無差別的銀行取付けの可能性が、預金保険の存在意義に大きくかかわってくると考えられる。しかし、システミック・リスクに繋がるような伝染的な取り付けは実際、どの程度の頻繁さで起こりうるのかということは必ずしも自明でない。債務超過でつぶれるべき銀行に取り付けが行われるのと、健全な銀行にまで取り付けが及ぶ場合を明確に区別することが必要である。
たとえば、アメリカの大恐慌時代の包括的な銀行データを利用した、Calomiris and Mason (2000)は、1929から32年の間については、銀行の破綻はそれぞれの地域や銀行に固有の要因によって起こっており、伝染("contagion")や流動性危機ではなかったことを示している(一方、1933年初の銀行危機はファンダメンタルズでは説明できないとしている)。したがって、伝染的な取り付けの可能性を過度に強調することは必ずしも適当でない。
第二は、預金の保護の程度は所与として、銀行の破綻時にいかに迅速にかつ確実に預金が支払われるかという制度的要因である。いくら預金が完全に保護されても、破綻時における払い戻しに時間がかかる場合、預金者の利便は著しく損なわれる。この場合、預金者はなるべく安全な銀行を預金先として選別するという、預金者の規律が働くことに注意する必要がある。したがって、他の条件を所与とすれば、預金の払い戻しに伴うさまざまなコストが高ければ、預金者の規律は働きやすいと考えられる。
アメリカの大恐慌時代と日本の90年代の比較
このように、預金者の規律、預金保険、預金払い戻し制度には、それぞれトレード・オフがあり、どのような組み合わせが最適なのかは必ずしも定かでない。ここでは、Calomiris and Mason (2001)に基づいて、大恐慌時のアメリカと90年代の日本についての比較をしてみよう。
アジア危機に見舞われた国や日本(見込み)の場合、債務超過銀行を救済するのに必要な直接的コストはGDPの20%から30%ほどであったが、アメリカ大恐慌時(1929-33年)はGDPの約3%の低い割合であった事実を指摘した上で、Calomiris and Mason (2001)は、当時、まだ、預金保険制度がなく(1934年設立)、また、破綻銀行の資産流動化は迅速ではなく預金の払い戻しに時間がかかるという深刻な流動性の問題(これは、消費を抑制しマクロ経済に大きなマイナスの影響を与えた)があった分、むしろ、預金市場からの規律が強く働いたことを強調した。事実、大恐慌の期間中、自己資本の毀損によって破綻リスクが大きく上昇した銀行は、預金流出も大きかった。当時、銀行は、自己資本増強のための株式発行は逆選択の問題があって不可能であったため、破綻リスクを低下させるためには、資産内容をよりリスクの低い資産へと急速に代替させるとともに(リスクの高い貸出の削減)、配当の大幅なカット断行を余儀なくさせられたのである(Calomiris and Wilson (1998))。また、RFCの優先株買取りといった救済策をみても、債務超過の銀行には援助せず、また、援助を受ける銀行には厳しい条件を課すといったように、市場からの規律付けを補完するような政策が行われた(Calomiris and Mason (2001))。
一方、日本の場合、預金保険機構は、1971年に設立され、破綻した銀行の預金者にペイオフを行う機能を持っていたが、一度もペイオフが発動されることはなかった。預金保険機構自体、1992年に伊予銀行を資本増強するまで機能していなかったといえる。政策的には銀行をつぶさないという「不倒神話」の下、破綻しそうな銀行を余力ある銀行が救済合併するという手法で問題処理を行ってきた。このような包括的なセーフティ・ネットがしかれてきたため、日本の場合、預金者によるモニタリング、銀行選抜のインセンティブはほとんどなかったといえる。さらに、Calomiris and Mason (2001)は、日本の会計制度は、1930年代のアメリカと比べても不透明であり、預金者の規律が働かないことが債務超過の銀行(ゾンビ・バンク)がいつまでも生き延びつづけていることを強調している。アメリカの経験をみると、銀行危機を収束させるための最終的なコストを最小化するためには、むしろ、預金市場からの規律をできるだけ活用することが大切であるといえよう。
日本における預金者の銀行選別
このように、預金者の規律が働きにくい状況が日本の不良債権問題の深刻化に影響を与えたことは予想できるが、1990年代半ば以降、「銀行の不倒神話」が崩れるとともに、預金者も初めて預金の保護や銀行の選別に目覚める土壌が生まれてきたと考えられる。ここでは、日本の預金者による銀行選別の実際について、筆者の行った実証分析を紹介してみたい(詳しくは、RIETI Discussion Paperとして近日公表予定の「銀行のガバナンス:預金者による規律付けと預金保険のあり方」参照。都銀と地銀を含む121行に関する財務データを使い、1998年度(1999年3月期)から2001年度(2002年3月期)までの5年間のパネル・データを利用)。それぞれの銀行の預金の伸び率を、自己資本比率(資産リスク要因)、現金・預金比率(流動性リスク要因)、ROA(収益要因)、資産規模(または、都市銀行ダミー)(「大きすぎてつぶせない」要因)で説明する推計式を計測した。
表はその結果であるが、特徴的なのは、定期預金等がペイオフ解禁される直前の2001年度において、自己資本比率の高い銀行が預金伸び率も高いという効果が更に強まっており(当該年度の追加的な効果も統計的に有意)、また、預金者が政府の「大きすぎてつぶせない」政策を予想して、規模の大きい銀行(または、都市銀行)の預金が伸びるという効果も、やはり、2001年度のみ明確に表れている点である。つまり、ペイオフ部分解禁を控えて、預金者が銀行の資産リスクを判断して銀行を選別する傾向が明確に強まるとともに、資産リスクや収益性などの銀行のパフォーマンスとは別に資産規模の大きい銀行や都銀が預金者に選別される傾向があったことが指摘できる。ここで、注意しなければならないのは、資産リスクで銀行を選別するのは、それが銀行側に破綻リスクを低く抑える行動を促すという意味で規律付けになり、「良い銀行選別」といえるが、規模の大きい銀行を選択するというのは、銀行の規律付けには必ずしも結びつかないため、「悪い銀行選別」であることだ。この問題は以下で更に検討することにする。
4. ペイオフ完全実施延期と合併促進策の評価
ペイオフ完全実施延期の評価
2001年から2002年にかけて、預金者による銀行選別が明確化し、資産リスクが高い銀行ほど預金増加率が低くなるという市場からの規律が働き出したにもかかわらず、当初、予定されていた2003年からのペイオフ完全実施(当座、普通預金等)は延期されることになった。具体的には、決済機能の安定確保を図るため、全額保護の対象とする「決済性預金」を2005年4月から導入することが決定された。
96年度から適用された預金等の全額保護の特例措置は、当初5年間の適用で、2001年4月からペイオフが実施される予定であった。しかし、中小金融機関の経営問題などを背景に、1年延期されることになった。その際、当座預金、普通預金等は更に2003年4月まで全額保護が適用されることになっていた。
このように当初の予定に反しペイオフが何回も延期された状況をどう評価すべきであろうか。まず、金融危機の状況に、一時的な緊急避難的措置として、政府が預金の全額保護をコミットすることは、預金者の動揺を抑え、特に、銀行取り付けを阻止する上で一定の評価ができる。たとえば、90年代に世界各地で起こった銀行危機をみてみると、このような預金の全額保護("a blanket guarantee")を導入した国として、フィンランド(1992年)、スウェーデン(1992年)、日本(1996年)、メキシコ(1995年)、インドネシア(1998年)、韓国(1996年)、マレーシア(1998年)、タイ(1997年)、ジャマイカ((1998年)、クウェート、トルコなどが挙げられる(Garcia(2000))。
しかし、こういった臨時措置は一定の猶予期間の間に不良債権処理などの銀行のリストラクチュアリングを断行し、金融危機の不安が去った段階で直ちに部分保護に戻すべきである。たとえば、スウェーデン、フィンランド、韓国はそれぞれ1996年、1998年、2001年に全額保護を解除している(韓国では、無利子の決済性預金については、2003年末まで全額保障を続けることになっている)。いずれも、早期に銀行危機、不良債権問題の解決を図った国である。一方、日本のように不良債権問題の解決に手間取れば、金融危機への不安を断ち切ることができず、政府はペイオフ延期を余儀なくさせられてしまう。問題なのは、ペイオフ導入の信頼性が失われれば、銀行側は預金が全額保護されている間に不良債権処理、銀行のリストラクチュアリングを終了させるという意欲を失い、モラル・ハザードの問題が発生することである。これでは、潜在的に銀行パニックの可能性を更に大きくし、ますます、ペイオフが完全実施できなくなるという悪循環にはまる。したがって、金融システムが不安定な時期に預金全額保護を導入するということは、政府が当初コミットした解除時期を必ず守るというクレディビリティがなければ、金融システムの潜在的な不安定さを更に増すことにつながる。
「決済性預金」の全額保護:日本の特殊性?
このように、ペイオフの度重なる延期には「諸刃の剣」の側面があるが、今回の決定においては、新たに創設される「決済性預金」については全額保護を制度化することが大きなポイントとなっている。「決済性預金」の基本的な仕組みは、(1)要求払い、(2)決済サービスの提供、(3)無利子を想定しているが、こうした預金を全額保護しなければならない理由としては、日本の場合、名寄せのデータ処理や破綻処理の法制度整備などに時間を要するという事情もあって、決済が円滑に結了できない可能性が指摘されている(金融審議会答申「決済機能の安定確保の方策について」平成14年9月5日)。確かに、部分保護の場合、上記のような理由で、付保金額が確定するのに時間がかかるのは事実である。一方、アメリカの場合は、保護のあるなしにかかわらず、預金は銀行が法的に破綻してから、一日または二日後(営業日ベース)以内に、支払われるべき全額が連邦預金保険公社(FDIC)から支払われるという非常に迅速な手続きが確立されている(Kaufman and Seelig (2000))。
しかし、制度的な事情を考慮してもそれが果たして全額保護という例外的な措置を残す強い理由になるとは考えにくい。なぜなら、第一に、アメリカのような全額かつ迅速な払い戻しはむしろ例外で、ヨーロッパなど諸外国では、保護された預金で数カ月、保護されていない預金であれば数年かかることは珍しくなく、名寄せの問題も日本固有の事情ではないからである。にもかかわらず、OECD加盟国では、預金の全額保護を継続している国は日本とトルコのみである。第二は、このような仕組みの導入で恩恵を受けるとみられる預金者は、決済目的のために口座残高が元本一千万以上必要な、企業などの大口預金者である。彼らは大口でかつ決済という生命線にかかわる機能を銀行に依存しなければならないため、預金者の中でも銀行をモニタリングしたり、選別するというインセンティブは最も高いはずである。このような預金者を完全に保護することは、預金市場からの規律で最も効果的であるはずの部分をみすみす無効にしてしまう措置といえる。むしろ、保護された預金、保護されない預金ともに迅速に払い戻しするシステムを構築することが先決であるはずだ。
「決済性預金」導入に関わる問題点
また、「決済性預金」という制度を新たに作り出す意味合いも慎重に考える必要がある。たとえば、欧米諸国では、個人のメインの口座は無利子の当座預金が普通であり、決済手段として小切手が使われる。一方、日本の場合、個人にも当座預金の制度があるが、有利子の普通預金がメインの口座として使われ、1973年の全銀システムの稼動以来、口座引落し、口座振込が資金決済手段として広く利用されてきた。しかし、普通預金は、決済手段としての口座にもかかわらず、金利付与、口座維持無料というサービスが提供されてきたため、その見合いで口座振込手数料などが比較的高く維持されてきた。超低金利が続く中で、国際標準である当座預金という制度を前向きに見直すことも重要であろう。
銀行側からすれば、新しいタイプの預金を導入することは大幅なコスト増となる。顧客に対する周知徹底やシステム導入に相当な費用がかかるだけでなく、このような全額保護の預金を導入する場合、銀行は部分保護の預金よりも高い保険料率を負担しなければならないためである。こうした事情から、導入のためのコストを負担できない金融機関にも配慮して、先の金融審議会での答申では、「決済性預金」導入の一律義務付けは適当でないとされた。
しかし、新型預金導入の選択性は、政策的にみれば自殺行為といえる。なぜなら、このようなコスト増があっても新型預金を導入しようとする銀行は、多くのコストを払っても預金者の安心を買いたいという意味で自行の破綻リスクの高さをクレディブルにシグナルしていることになるからである。一方、優良な銀行は新型預金を導入しないということで預金者に自行の健全性を明快にアピールすることができる。こうなると新型預金を導入したいと思っている銀行も尻込みせざるを得ない。一方、銀行の負担するコスト(導入コストや保険料コスト)は、預金者に無利子、口座維持手数料として転嫁されることが予想される。しかし、銀行の破綻リスクに係る保険は一義的には銀行自身がその責任において負担すべきであり、アメリカを始めとする21カ国で実施されている可変保険料率の適用(銀行のリスクに応じて保険料率が変化)もそうした考え方に基づいている。したがって、銀行側がコストを預金者に転嫁させて行くという行動自体、銀行のモラル・ハザードを助長するものである。また、預金者もコストを支払って、新型預金を選択するよりも、絶対安全な銀行の普通預金、当座預金を選択してしまうというインセンティブが生じてしまう。
金融機関合併促進策の評価
ペイオフ完全実施延期に加えて、預金者を安心させる政策としては、特に、経営基盤の脆弱な地銀、協同組織金融機関などの合併を促進するための法律が12月に国会で成立した。これは、自己資本不足の金融機関と合併し自己資本比率が下がったとしても、それを回復させるために預金保険機構が資本増強を行うとともに、合併を行った銀行は1年間に限り、預金保険の保険基準額が通常1000万のところ、1000万×合併した金融機関の数が認められるというものである。つまり、経済的な合理性のないような合併も政策的な「大盤振る舞い」で無理やり促進していこうという内容である。これは、銀行行政でしばしば指摘される「大きすぎてつぶせない」("too big to fail")という原理を逆手にとって、「つぶせなくなるほど大きくする」ことで、預金者に安心感を与えるという政策と考えられる。先でみたように、2001年度に銀行選別が強まったのだが、選別方法としては資産リスクの低い銀行を選別するという「良い銀行選別」と規模の大きい銀行を選別する「悪い銀行選別」があったことが重要である。そもそもペイオフ延期と決済性預金の全額保護は預金者の銀行選別へのインセンティブを弱めるものであるが、この合併促進策は、政府が「規模の大きい銀行は安心」ということを積極的にアピールすることで、むしろ、「悪い銀行選別」を預金者に奨励しかねない。
以上のように、ペイオフ完全実施延期と金融機関の合併促進策は当面の金融危機を「くさいものにふたをする」ように、無理やり封じ込めようとするには役に立つかもしれない。しかし、それは銀行の更なるモラル・ハザードを招き、潜在的に金融システムを不安定化させることにつながる。より重要な視点は、こうした近視眼的な政策ではなく、金融機関の破綻処理の際、保護の有無にかかわらず預金者に迅速に預金が支払われることが可能になるような制度設計が重要である。アメリカの場合をみると、早期是正措置などにより、問題銀行の情報を徐々に蓄積させていることは参考とすべき点であろう(Kaufman and Seelig (2000))。これが預金保険の部分保護へのスムースな移行を可能にするのみならず、規模の大きい銀行も破綻させることができるようになるためである。また、それは資産リスクなどのファンダメンタルズで銀行が選ばれるという「良い銀行選別」を促進していくことにもつながるのである。