中国では、景気の減速を受けて、インフレが沈静化に向かっている。これを背景に、2011年12月以来、預金準備率が2回にわたって引き下げられるなど、金融政策のスタンスが引き締めから緩和に転換されつつある。今後、インフレ率が一層低下し、更なる緩和策の実施が予想されることから、景気は2012年前半に底を打ち、秋に5年ぶりに開催される中国共産党全国代表大会(党大会)に向けて回復に向かうだろう。
インフレの低下で広がる金融緩和の余地
2012年第1四半期の中国の経済成長率は8.1%に低下しており、2009年第1四半期以来の低水準となった。成長鈍化の理由として、リーマン・ショック以降に導入された4兆人民元に上る景気対策の効果が薄れてきたことや、ヨーロッパ債務危機の影響が長引いていること、インフレを抑制するために金融引き締め策が採られてきたことなどが挙げられる。もっとも、リーマン・ショックを受けた2009年当時と比べて、現在の輸出は、対EUが伸び悩んでいるものの、全体では比較的高い伸びを維持している(図1)。これを反映して、景気の減速は緩やかにとどまっている。
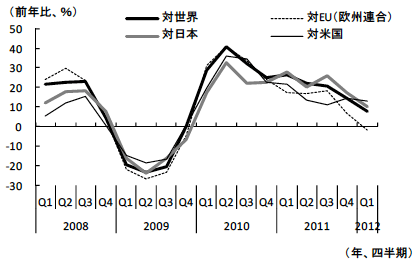
一方、消費者物価指数(CPI)の前年比上昇率で見たインフレ率は2011年7月の6.5%をピークに低下傾向に転じており、2012年3月には3.6%となった。次の理由から、インフレ率は今後一層低下する可能性が大きいと見られる。まず、インフレ率は成長率の遅行指標に当たるため、これまでの景気減速を反映して、今後さらに低下すると予想される。また、金融引き締めが功を奏する形で、マネーサプライM2の伸びは、2009年11月の前年比29.7%から2012年3月には13.4%に低下している。さらに、インフレ率を大きく押し上げていた食料価格も2011年7月(前年比14.8%)をピークに低下傾向に転じており、2012年3月には7.5%となった(図2)。
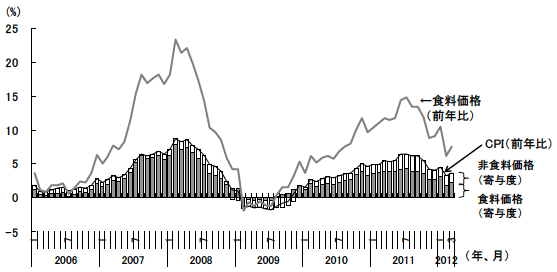
インフレの低下を受けて、2011年12月以降、預金準備率が二回にわたって計1.0%ポイント引き下げられ、当局の金融政策のスタンスが引き締めから緩和に転換されつつある。今後、金融緩和の余地は一層広がっていくだろう。
景気は後退期を経て回復期へ
インフレ率が経済成長率の遅行指標であることを考慮すれば、景気は、成長率とインフレ率がそれぞれの基準値と比べて高いか低いかによって、①「低成長・低インフレ」の「後退期」、②「高成長・低インフレ」の「回復期」、③「高成長・高インフレ」の「過熱期」、④「低成長・高インフレ」のスタグフレーション期という四つの局面に分けることができる(図3)。
-GDP成長率とインフレ率の推移-
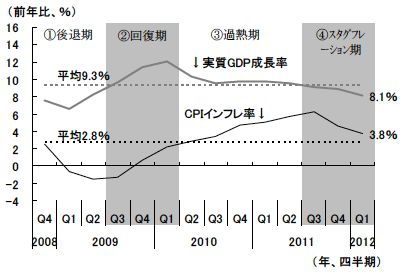
リーマン・ショック以降(2008年第4四半期~2012年1四半期)における成長率の平均値(9.3%)とインフレ率の平均値(2.8%)をそれぞれの基準値とすると、中国経済は、①「後退期」(2008年第4四半期~2009年第2四半期)、②「回復期」(2009年第3四半期~2010年第1四半期)、③「過熱期」(2010年第2四半期~2011年第2四半期)を経て、2011年第3四半期以降④「スタグフレーション期」に入っている。
このような景気循環は、横軸を成長率、縦軸をインフレ率とする座標平面において、成長率が先行し、インフレ率がついてくることを反映して、反時計回りの円を描いている(図4)。これまでのパターンから判断して、中国の成長率とインフレ率の推移を描いた円は今後も反時計回りに回転し続けるだろう。すなわち、インフレ率がさらに下がっていくという形で、2012年の第2四半期に景気は「スタグフレーション期」から「後退期」に移る。この段階で、緩和策が本格的に実施され、これがきっかけとなって、秋に5年ぶりに開催される党大会に向けて、成長率は上昇に転じ、景気も「回復期」に進むだろう。
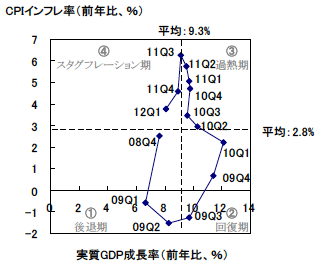
2012年5月2日掲載


