中国では、政府は、景気過熱の解消を目指して、2010年年初から引き締め政策を採ってきた。海外における景気の低迷も加わり、景気が減速しており、これまで上昇し続けてきたインフレ率も2011年の7月をピークに低下し始めている。これを受けて、預金準備率が引き下げられるなど、金融政策のスタンスは引き締めから緩和に転換されつつある。景気は当面減速を続けるが、利下げや拡張的財政政策を含むさらなる緩和策の実施により、2012年前半に底を打ち、秋に開催される中国共産党全国代表大会(党大会)に向けて回復するだろう。
一段と鮮明になった景気減速
中国経済は、2008年9月のリーマン・ショックを受けて、一時景気後退を余儀なくされ、2009年第1四半期の成長率が6.6%まで落ち込んだが、4兆元に上る景気対策と金融緩和を受けてV字型回復を見せ、2010年第1四半期の成長率は11.9%に達した。しかし、その後、ヨーロッパの財政危機をきっかけに世界経済が再び混迷に陥ったことに加え、国内では景気対策の効果が薄れ、またインフレを抑えるために金融政策が緩和から引き締めに転換されたことを背景に、成長率は低下傾向に転じ、2011年第3四半期には9.1%と2009年第2四半期以来の低水準となった。
景気は第4四半期に入ってから一段と悪化している。工業生産(付加価値ベース、一定の規模以上の企業のみが対象)の伸び(前年比)は第3四半期の13.8%から10月には13.2%、11月には12.4%にさらに減速している。小売売上と都市部の固定資産投資の伸びから判断して内需は比較的好調だが、ヨーロッパをはじめとする世界経済の低迷により、輸出(ドルベース)の伸びが直近のピークであった2011年8月の24.5%から11月には13.8%へと鈍化している(図1)。外需の落ち込みは工業生産の伸びを押し下げている。
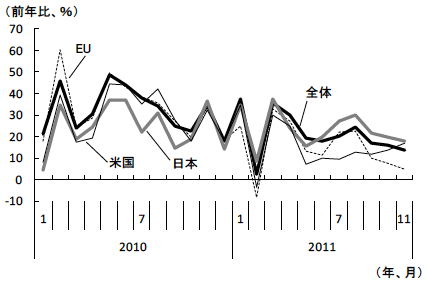
企業の景況感を示す購買担当者指数(PMI)の動きも、景気の悪化を裏付けている。工業生産の伸びの鈍化と同調して、2011年11月のPMIは10月の50.4%からさらに低下し、49.0%と2009年3月以来初めて、景気判断の分かれ目となる50%を下回った(図2)。
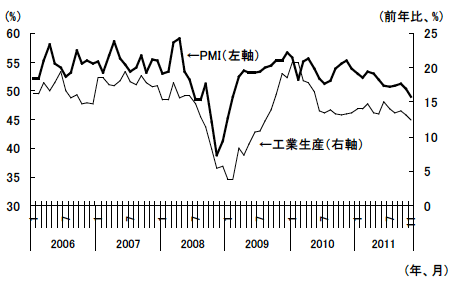
2011年10月と11月の経済統計をベースに判断すると、第4四半期には成長率がさらに低下し、8.5%程度にとどまるだろう。
沈静化に向かうインフレ
金融引き締めと景気減速を背景に、消費者物価指数(CPI)の前年比上昇率は2011年7月の6.5%をピークに低下傾向に転じており、11月には4.2%となった(図3)。生産者物価指数(PPI)の前年比上昇率も、ピークであった7月の7.5%から11月には2.7%に低下している。前月比で見てもCPIとPPIの上昇が鈍ってきている。次の理由から、今後のインフレ率は一層低下する可能性が大きいと見られる。
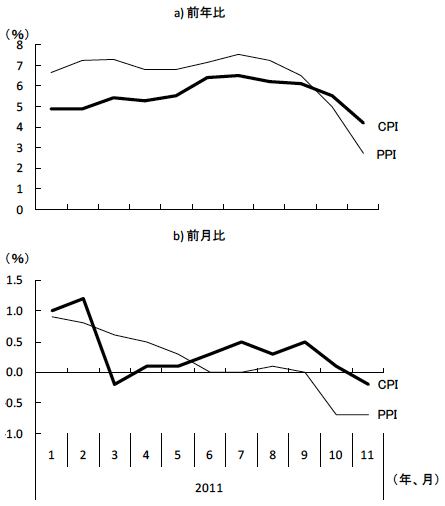
まず、経済成長の減速が続いており、市場の需給関係の改善により、物価上昇圧力が緩和されている。インフレ率は成長率の遅行指標に当たるため、これまでの成長率の低下を反映して、インフレ率は今後さらに低下すると予想される。
第二に、金融引き締めが功を奏する形で、マネーサプライM2の伸びは、2009年11月の前年比29.7%から2011年11月には12.7%に低下している。インフレが常に貨幣的現象であるという経済学の常識に沿って言えば、2010年以降のインフレの高騰は、リーマン・ショック後の金融緩和の結果であり、逆に、最近のマネーサプライの伸びの鈍化は、インフレの沈静化につながるだろう(図4)。
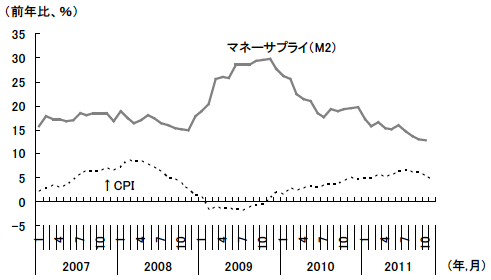
第三に、インフレ率を大きく押し上げていた食料価格の上昇に歯止めがかかった。食料品はCPIを構成する財・サービスの約3割のウェイトを占めており、これまでのCPI上昇率のうち約7割は食料価格の上昇によるものである。しかし、CPI全体と同じように、食料価格の上昇率も7月(前年比14.8%)をピークに低下傾向に転じており、11月には8.8%となった。景気が悪化する中で、食料品に対する需要が減る一方で、都市部で職を失った出稼ぎ労働者が農村に戻り、農業に従事することにより食料品の供給は逆に増えるという需給関係の変化を反映して、食料価格の上昇率さらには鈍化すると予想される。
最後に、世界経済が減速している中で、国際商品市況は低下傾向に転じている。このことは、中国における輸入インフレ圧力の低下につながっている。
スタグフレーション期から後退期へ
現在の成長率は、リーマン・ショック以降の平均値の9.5%を下回っているが、これに対してインフレ率は、ピークアウトしたとはいえ、まだ同平均値の2.5%を上回っている。景気循環に沿って言えば、中国経済は、「高成長・高インフレ」という「過熱期」(2010年第2四半期から2011年第2四半期)から「低成長・高インフレ」という「スタグフレーション期」に入っている(図5、6)。これまでの金融引き締め政策の影響が今後一層顕著になり、2012年の初めに、景気は「低成長、低インフレ」という「後退期」に入るだろう。
― GDP成長率とインフレ率の推移 ―
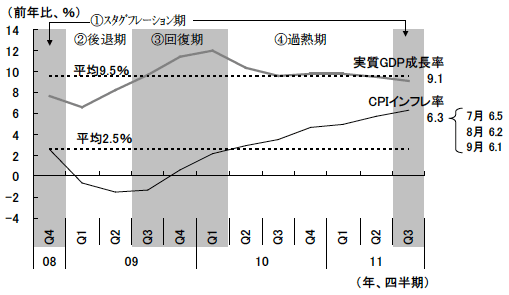
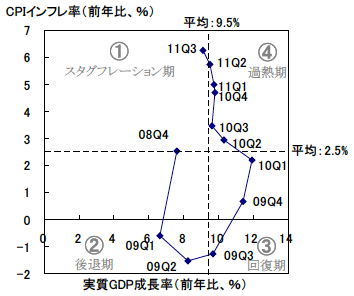
引き締めから緩和へ転換する金融政策
金融政策は景気に強い影響を与える一方で、景気の変化によって調整される。中国は、リーマン・ショックの後、素早く金利と預金準備率を下げるという形で金融緩和を実施した。2008年12月までの間に、貸出基準金利(1年もの)が5回にわたり計2.16%ポイント、預金準備率は3回で計2%ポイント引き下げられた。その後、景気回復とともにインフレが加速したことを受けて、当局は、金融政策を引き締める方向に舵を切った。具体的には、2010年1月から2011年6月にかけて預金準備率を12回にわたって計6%ポイント、また2010年10月から2011年7月にかけて貸出基準金利を5回にわたって計1.25%ポイント引き上げた(図7)。
- 金利と預金準備率の推移 -
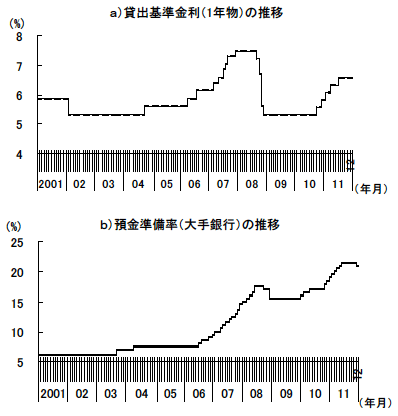
しかし、景気が悪化し、インフレも低下傾向に転じたことを受けて、当局がついに2011年11月30日に、預金準備率を0.5%ポイント引き下げると発表した(12月5日に実施)。これは、金融政策のスタンスが引き締めから緩和へ転換されつつあることを意味する。今後、インフレ率の低下と歩調を合わせて、預金準備率がさらに引き下げられると予想され、利下げの実施も視野に入りつつある。さらなる緩和策の実施により、2012年秋に開催される党大会に向けて景気は回復するだろう。
2012年秋の党大会に向けて回復へ
5年毎に開催される党大会は、中国共産党にとって経済面の実績をアピールし、また、次世代のリーダーたちにとって地方での実績をテコに中央入りを目指す絶好の機会である。これを反映して、党大会が開催される年には拡張的財政金融政策が採られがちで、成長率も高くなるという傾向が見られる。1981年から2010年にかけて、中国の年平均成長率は10.1%だが、党大会が開催される6年分(1982年、1987年、1992年、1997年、2002年、2007年)に限ると、それを1.2%上回る11.3%となっており、前回の2007年に至っては14.2%に達した(図8)。2012年も、拡張的財政・金融政策が採られると見られ、秋に開催される党大会に向けて、景気は再び「高成長、低インフレ」という回復期に入ると予想される。
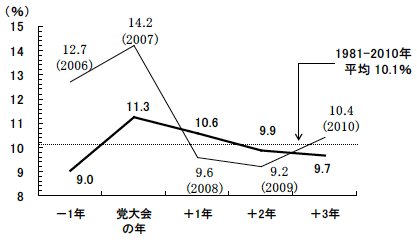
中国だけでなく、米国においても、4年毎に行われる大統領選挙に合わせて、好景気を迎える傾向が見られている。実際、1976年から2010年までのアメリカの平均GDP成長率は2.9%であるのに対して、選挙の年の平均は3.5%と最も高くなっている(図9)。米国と中国におけるこのような「政治的景気循環」は、2012年に20年ぶりに同時にピークに達することになる。米中という世界第一位と第二位の経済大国が同時に好景気を迎えることになれば、低迷が長引いている世界経済にとってまさに朗報である。
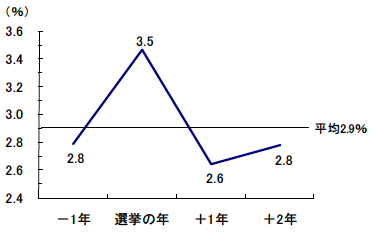
2011年12月27日掲載


