中国経済は2003年以来5年連続の二桁成長を経て、緩やかな調整局面に入っている。それでも、深刻な金融危機に見舞われている米国やその影響を強く受けている日本とヨーロッパ諸国に比べ、むしろ好調さが目立っており、景気のデカップリング(非連動性)という現象が鮮明になっている。
薄い中国と米国との経済成長率の連動性
サブプライム問題を契機に、米国経済が急速に冷え込んできているが、その中国経済への影響は限定的であると見られる。IMFの推計によると、米国の成長率に対する中国の成長率の弾性値はアジア各国・地域の中で最も低い0.1%にとどまり、日本の0.3%よりも小さくなっている(図1)。これは、米国の成長率が1%下がれば、日本の成長率が0.3%押し下げられることになるが、中国の成長率は0.1%しか下がらないことを意味する。
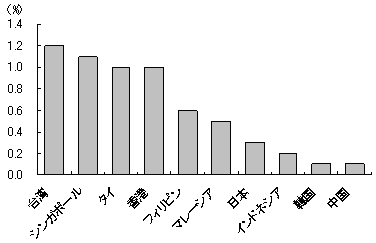
中国は、対米輸出の対GDP比で見た対米輸出依存度が日本のそれを大幅に上回っているが、それにもかかわらず、次の理由から、GDP成長率(実質)で見た米国経済との連動性が日本より低くなっている(図2)。
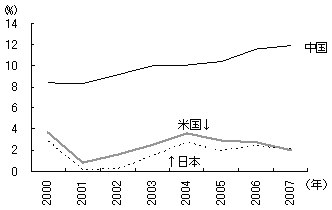
まず、中国の対米輸出依存度は、見かけほど高くない。中国では、貿易財(輸出入)は国際価格で取引されているが、非貿易財(サービス)の価格が日本など先進国よりはるかに低くなっている。購買力平価(PPP)を考慮したGDPをベースに計算すれば、中国と日本の対米輸出依存度の差は大幅に縮まる(図3)。その上、中国の対外貿易の半分は加工貿易であり、輸出される製品の中には、国内でつけた付加価値よりも、海外から輸入される部品や中間財が多く含まれているのに対して、日本の場合、輸出に含まれている「輸入コンテンツ」の比率が比較的低い。これを考慮すると、中国の対米依存度は、日本を大幅に下回るはずである。
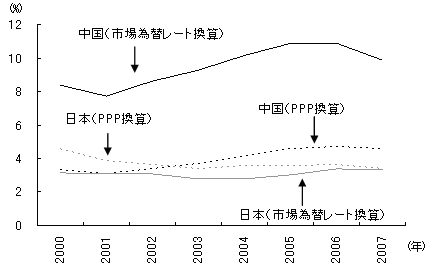
また、中国は資本取引に対して厳しい規制が敷かれており、貿易と比べて、資本移動の規模が小さくなっている。特に、中国の証券市場は対外開放度が低く、株価は海外要因よりも主に国内要因に左右され、海外との連動性は必ずしも高くない。IMFによると、日本と米国の株価の相関係数は0.52に達するのに対して、中国と米国の株価の相関係数は0.08にとどまっていると推計される(対象期間はいずれも2000年-2007年)。実際、上海総合指数は2007年10月に史上高値を記録してから今年の9月中旬のリーマン・ショックまで海外を上回る70%急落を記録したが、その後は逆に、海外市場における株価が暴落している中で、上海市場は比較的落ち着いている(図4)。また、中国の金融機関は保有している外貨資産が少なく、今回のサブプライムローンの不良債権化による直接的影響も小さい。
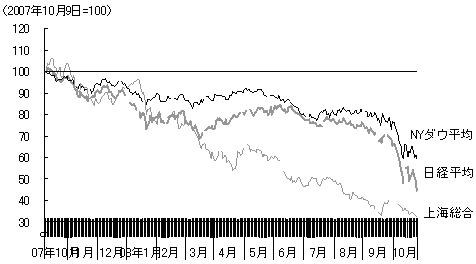
なお高い政策対応の自由度
確かに内外環境の悪化を受けて、中国経済も減速を余儀なくされているが、当局は、金融政策や財政政策など、景気刺激策を発動する自由度を十分確保している。
まず、景気が減速するにつれて、インフレも沈静化に向かいつつある。これまで、インフレ率(CPI、前年比)が、約3四半期遅れて経済成長率(前年比)の動きに追随するという傾向が見られる(図5)。今年の第3四半期には、成長率は9.0%と、ピークであった昨年第2四半期(12.6%)と比べて3.6%低下しており、インフレ率も5.3%(9月は4.6%)と、第1四半期の8.0%(2月は8.7%)を大幅に下回っている。景気の減速に加え、最近の原油価格の反落も、インフレ圧力の低下につながっている。これを背景に、当局は9月以降、利下げと預金準備比率の引き下げをそれぞれ二回にわたって実施している(図6)。今後、金融緩和の余地がさらに広がるものと見られる。
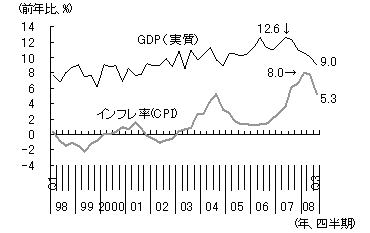
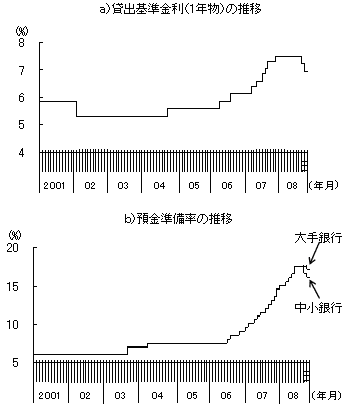
第二に、人民元の切り上げ圧力が収まりつつある。人民元の切り上げは昨年来加速していたが、7月中旬以降は一段落している。海外で取引されている人民元の先物(NDF、一年物)に至っては急落しており、現物に対するプレミアムも今年春に記録した10%を超えた水準から、ゼロ前後まで縮小している(図7)。これは、ホットマネーの流入、ひいてはインフレの上昇を招いた人民元の切り上げ期待が収まっていることを示している。その結果、金融政策だけでなく、人民元切り下げを含む為替政策の自由度も高まっている。
- 現物Vs.先物(NDF) -
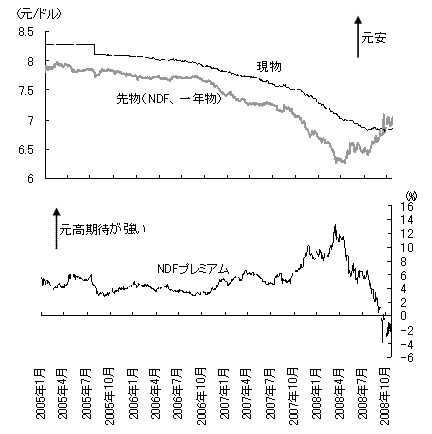
第三に、中国は財政面においても、減税や支出拡大を通じて景気を刺激する余裕を持っている。2007年の中国における中央政府の財政黒字の対GDP比が1.1%に達する一方で、国債残高の対GDP比は21.1%にとどまっている。これに対して、日本における中央政府の財政赤字と国債残高の対GDP比はそれぞれ2.5%と164.1%に上っている(いずれもIMF調べ)。1997年-1998年のアジア金融危機の時に、中国は積極的財政政策を中心に景気対策に取り組んだが、今回も必要に応じて財政政策が発動されると予想される。すでに当局は、2008年11月1日から3486品目の製品について、輸出増値税(付加価値税)の還付率を引き上げると発表している。また、来年から増値税の生産型から消費型への移行も決まっていると伝えられ、これによる減税の規模は1,500億元を超えると推計される(注)。
第四に、中国は、1.9兆ドルに上る外貨準備を保有しているため、拡張的金融・財政政策を採って内需の拡大を図った結果、経常収支が大幅に悪化しても、直ちに外貨不足に陥ることはない。また、1997年-1998年のアジア金融危機当時のタイや、韓国、インドネシアのように、通貨の投機に遭い、大幅な切り下げを余儀なくされる心配もない。
最後に、危機に直面した時、コンセンサスの形成に時間がかかる民主主義体制下の先進諸国より集権体制を採っている中国の方が素早く対応できる。9月29日に、米国において、最大7000億ドルの公的資金を投入して金融機関から不良資産を買い取る「金融安定化法案」が下院で否決されたことを受けて、世界の金融市場が大混乱に陥ったが、このような事態は、中国では起こりえない。
一人勝ちの様相を呈する中国
米国発の金融危機の影響を受けて、世界経済は、今年に続いて来年も更なる景気の減速が避けられないと見られる。10月に発表されたIMFのWorld Economic Outlookによると、2009年の主要先進工業国の成長率は、米国が0.1%、ユーロ地域が0.2%、日本が0.5%と低迷し、これを反映して、世界経済の成長率は、2007年の5.0%、2008年の3.9%から2009年の3.0%に鈍化すると予想される。その結果、日米欧の世界経済成長への寄与度は、合わせても0.1%程度にとどまることになる。これに対して、中国は減速基調が続くものの、2009年も9.3%という比較的高成長を維持できると予想される。中国のGDP規模(購買力平価ベース)が世界の12.0%に当たることを合わせて考えれば、中国による世界経済成長への寄与度は、全体(3.0%)の4割近くに相当する1.12%(9.3%×12.0%)に上ることになる(図8)。このように、今回の米国発金融危機は、中国がグローバル大国として台頭することを象徴する出来事になりそうである。
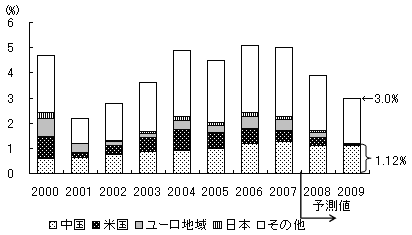
2008年10月29日掲載


