日米欧といった先進工業国が中国に対して人民元切り上げを求める大合唱が起こっている中で、ASEAN諸国は静観する姿勢をとっている。本来、中国と補完関係にある先進工業諸国よりも、競合関係にあるASEAN諸国にとって、人民元の切り上げによる景気浮上効果は大きいはずである。我々の推計によると、米国市場におけるASEAN諸国の中国との競合の度合いは、インドネシアの83.5%をはじめ、タイの76.1%など軒並み高くなっている(表)。それにもかかわらず、ASEAN諸国は中国に対して人民元の切り上げを求めていないのは、切り上げ圧力が自国に波及してくることを恐れているからであろう。
ASEAN諸国と中国との経済関係が競合的であるという前提に立てば、「元高」から受ける影響は次のように分析できる。
まず需要面では、人民元が高くなれば中国製品が国際市場において高くなり、中国と競合するASEAN各国の製品のコスト競争力がその分だけ高まるはずである(需要曲線が大幅に右へシフト)。一方で、中国市場への依存度はまだ低いため、仮に「元高」を受けて中国経済が減速し対中輸出が鈍化しても(需要曲線が左へ小幅にシフト)、他の市場への輸出拡大によって十分補うことができるはずである。その一方で、供給面では、中国からの部品などの輸入価格が高くなり、生産コストを押し上げる効果もあろうが、対中輸入はまだ規模が小さいことから、その生産へのマイナスの影響は軽微であろう(供給曲線が小幅に左へシフト)。需要と供給の両面の要因を合わせて考えると、元高が貿易を通じてASEAN諸国の生産へ与える影響はプラスになるだろう。この結果は、中国と補完関係にあるため、元高によるマイナスの影響がそのプラスの影響を上回る日本の場合と対照的である。
その上、元高になれば、多国籍企業から見て、中国と比べたASEANの生産基地としての魅力は相対的に高まるであろう。近年、ASEANと中国の間で直接投資における受け入れ競争が益々激しさを増しており、日本をはじめ、先進国のアジアへの投資をASEANから中国へとシフトさせる動きが活発化している。人民元の切り上げはそういう動きに歯止めをかける力として働くであろう。
以上の分析は、あくまでもASEAN通貨がドルに対して、引き続き安定的に推移することを前提にしている。しかし、ASEAN諸国は、もし中国が外圧に屈する形で人民元の切り上げに踏み切ることになれば、明日はわが身に及ぶことを危惧している。実際、日本の人民元切り上げ要求が皮肉にも円高を招いてしまった。また、1985年のプラザ合意後の円高を受けて、米国が矛先を韓国や台湾をはじめとするNIEs諸国に向けたという経緯からも、これは決して杞憂とはいえない。当時と比べて、国際投機資金の規模が大きくなり、資本管理も難しくなっていることから、ASEAN諸国は、単に米国など貿易相手国の政府からの切り上げ要請だけでなく、民間資金の投機的な動きにも神経を尖らせている。
振り返ってみると、1997-98年にアジア通貨危機が勃発した当時、中国は人民元の安定維持に努め、危機の一層の拡大と深化を防ぐことに貢献した。これは、円安の進行を容認した日本と対照的であり、ASEAN諸国から高く評価された。今回、中国が通貨の切り上げ圧力に晒されているときに、ASEAN諸国があえて日米欧諸国に同調しなかったことは、その恩返しの意図が込められているのかもしれない。
| 1990 | 1995 | 2000 | 2002 | |
| 日本 | 3.0% | 8.3% | 16.3% | 20.5% |
| 韓国 | 24.0% | 27.1% | 37.5% | 41.1% |
| 台湾 | 26.7% | 38.7% | 48.5% | 57.1% |
| 香港 | 42.5% | 50.5% | 55.9% | 64.4% |
| シンガポール | 14.8% | 19.2% | 35.8% | 44.2% |
| インドネシア | 85.3% | 85.5% | 82.8% | 83.5% |
| マレーシア | 37.1% | 38.9% | 48.7% | 54.5% |
| フィリピン | 46.3% | 47.8% | 46.1% | 57.0% |
| タイ | 42.2% | 56.3% | 65.4% | 76.1% |
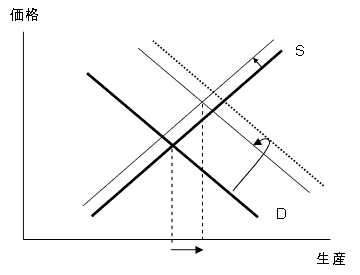
2003年10月3日掲載


