中国の台頭の日本経済への影響を議論するときに、「中国発デフレ」に象徴されるように、絶対価格の変動が焦点となっているが、中国からの所得移転を意味する対中交易条件の改善という相対価格の変化にもっと注目すべきである(注)。
まず、中国の台頭が中国自身の交易条件にどういう影響を与えているかについて見てみよう。改革開放によって、この20年あまりの間中国は比較優位に沿って世界経済に組み込まれつつある。改革・開放前は、中国は自力更生を旗印に何でも自前で造ることにこだわったが、1978年の改革開放からこのフルセット主義を放棄し、市場原理に委ねるようになった。自らの比較優位に沿って、中国は付加価値の低い労働集約型製品の輸出と、付加価値の高い技術・資本集約型製品の輸入を同時に増してきた。この需給関係の変化を反映し、輸出価格が輸入価格に比して低下してきた。このように、中国の輸出主導型成長は、中長期的にわたる交易条件の悪化を招いているのである。中国は輸出入の価格について統計を発表していないため、交易条件がどのくらい低下したかは確認できないが、人民元の中長期にわたる大幅な下落傾向は、交易条件の悪化を示唆している。
中国とは逆に、日本は技術・資本集約型製品を輸出し、労働集約型製品を輸入するので、両国は補完関係にある。すなわち、中国の交易条件は労働集約財の価格/技術集約財価格に対応しているのに対して、日本の貿易条件はちょうど分子と分母がそれと逆さまになっている。これを反映して、中国の交易条件の悪化は、日本にとって交易条件の改善を意味する。日本の消費者にとって、中国(そして中国と競合する国)からの輸入が安くなった分だけ実質所得が向上し、企業にとっても、投入価格の低下と産出価格の上昇を通じて利潤が増大するのである。
実際、日本側の統計によると、1990年と比べ、日本の対中輸出価格は3.0%上昇したが、対中の輸入価格が18.4%低下している(図)。その結果、日本の対中交易条件は26.2%ほど上昇している。2002年の対中輸出が5.0兆円、対中輸入が7.7兆円であることをベースに試算すると、2002年の中国からの輸出入価格は1990年当時のままであれば、輸出金額は実際より0.2兆円少なく、また中国からの輸入金額は実際より1.7兆円多いという計算になる(表)。このように、日本にとって対中交易条件の改善によってもたらされている外貨の節約は年間1.9(0.2+1.7)兆円にも上る。これは日本のGDPの0.4%、また日本企業による対中直接投資(財務省統計による)の約10倍に相当する巨大な金額である。
より広い視野から日本経済全体への影響を捉えるときに、中国の台頭に伴うこの直接効果の他に、日本の対他の貿易相手国に対する輸出と輸入の価格への間接的影響も合わせて考えなければならない。まず、日本の対中輸出は、対他の地域と同様、機械類が中心になっており、中国での需要拡大は日本の輸出価格全体を押し上げるようになっているはずである。一方、輸入の面では、中国と競合する労働集約型製品については、供給の拡大により、日本の輸入価格全体が押し下げられるはずである。もっとも、石油のように一部の一次産品では中国も日本と同じ純輸入国になっており、中国の輸入拡大によってそれらの価格が押し上げられることも考えられるが、その世界全体に占める割合がいまだ非常に小さいことを反映して、その影響は限定的である。従って、間接効果は、直接効果を強化するものであり、日本が得た全体の利益は先の試算結果をさらに上回ることになる。
このように、中国の台頭は、中国自らの交易条件の悪化と日本の交易条件の改善を通じて、日本経済に大きい恩恵を及ぼしている。これは、中国にとって、輸出が増えれば増えるほどその単価が下がるという一種の「豊作貧乏」の状況に当たる(ただし、農業部門ではなく、工業部門で起こっている)。これに対して、日本はその「豊作」の一部を享受しており、中国から日本へのこのような所得移転は不況下の日本の国民生活を支えているのである。
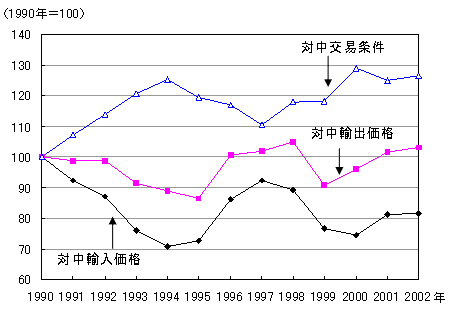
手法とデータ源は原田泰著『奇妙な経済学を語る人びと』(日本経済新聞社、2003年)を参考にした。
| 金額 (2002年価格) (a) | 価格指数 (1990年=1) (b) | 金額 (1990年固定価格) (c)=a/b | 金額の変化 (a)-(c) | |
| 対中輸出 | 5.0兆円 | 1.030 | 4.8兆円 | 0.2兆円 (1) |
| 対中輸入 | 7.7兆円 | 0.816 | 9.4兆円 | -1.7兆円 (2) |
| 外貨節約 (1)-(2) | - | - | - | 1.9兆円 |
2003年8月29日掲載


