2002年は日中国交正常化30周年という節目の年である。振り返ってみると、日本における中国に対する見方は、この30年間、大きく変化してきた。ここで、世論が中国の未来を楽観的に捉えるか、それとも悲観的に捉えるか、また、中国を脅威と見て対立姿勢をとるか、それともパートナーと見て協力姿勢をとるか、という二つの基準軸を基に、日本の中国に対する見方の推移を辿ってみる(図)。
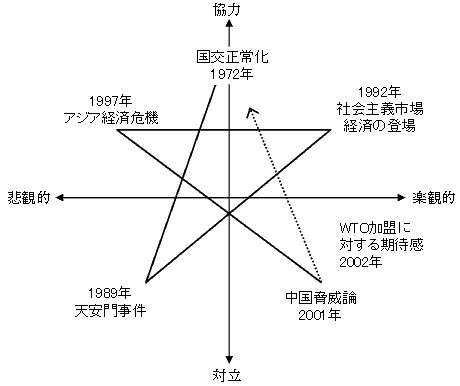
日中国交正常化は、1972年に当時の田中角栄首相と周恩来首相らによる共同声明の調印により実現した。また、これに伴い中国からパンダが贈られ、その後も両国の首脳が互いに訪問し合うなど、友好関係が深まった。そして、共同声明に基づき、6年後の1978年には「日中平和友好条約」が締結されたのである。しかし、この友好ムードは1989年の天安門事件を契機に一転した。日本では、中国での人権問題や民主化の遅れなどの政治的・社会的不安定要素や、それによる混乱から経済発展が行き詰まるということを懸念し、悲観的な見方が大半を占めた。また、米国が人権問題の改善やさらなる民主化を要求し、中国に対して経済制裁を実施したことに同調する形で対立姿勢をとったのである。しかし、92年に鄧小平の「南巡講話」により改革・開放路線の加速化がうたわれると、社会主義市場経済の登場で高成長が達成されるという楽観論が大半を占めるようになり、中国をビジネスチャンスとして捉えた日本企業の対中投資の促進に見られるように、積極的な協力姿勢がとられるようになったのである。
その後、97年のアジア通貨危機を契機に中国に対する見方は一変する。人民元の切り下げリスクに対する懸念や、98年の広東国際信託投資公司(GITIC)の破綻などから金融不安が拡大するという悲観論が大半を占めるようになり、その日本への悪影響を防ごうと金融面での支援を通じた協力姿勢がとられていた。しかし、そのような経済不安が沈静化し、中国が引き続き高成長を達成するようになると、日本の国内経済の長引く景気低迷やそれによる国民の自信喪失が拍車をかけたこともあり、2001年頃には中国脅威論が台頭してきた。つまり、中国の経済状況を楽観的に捉えながらも、中国に雇用が奪われ、国内産業が空洞化してしまうのではないかという不安から、昨年のセーフガード発動問題のように対立姿勢をとるようになったのである。
それ以降も中国では高成長が続いており、中国の経済状況は依然として楽観的に捉えられているが、WTO加盟によって中国の市場環境が改善し、中国が「世界の工場」から「世界的な市場」になるという期待感から、最近では中国の活力を活かそうという動きが企業レベルにおいてようやく活発化してきている。政府レベルにおいても、中国を含む東アジア全域を対象とするFTA(自由貿易協定)への模索が始まっている。
このように、日本の中国に対する見方は揺らぎ続けており、一貫した中国観というものがあるとは必ずしも言えない。日中国交正常化からすでに30年という歳月が過ぎたが、そろそろ中国の現状を冷静に判断し、その上で協力姿勢を強め、日中両国の真の友好関係を深めていくことが果たしてできるのであろうか。
2002年12月6日掲載


