長期にわたる景気低迷と金融システム不安が続く中、昨年末以来、円ドルレートは130円台を突破し、下落傾向にある。日本が意図的に円安を仕掛けたという批判が中国の新聞の紙面を賑わせている。中国当局の見解を代弁する「人民日報」も昨年12月29日に「円の切り下げを熟慮すべし」というコラムを掲載し、円安がアジア諸国間のみならず、日米欧という三極間の切り下げ競争を誘発しかねない危険性について警告した。確かに、筆者が繰り返して強調しているように、「円安」は「近隣窮乏化政策かつ自己窮乏化政策である」(「金融財政事情」、2001年9月3日号、その一部は中国「金融時報」、2001年12月11日付にて紹介される)。しかし、中国への直接的影響に限っていうと、日中関係が競合的よりも補完的であることを反映して、円安は必ずしも悪い影響ばかりではないはずである。
まず、円安によって、中国の輸出が打撃を受けるのではないかと懸念されるが、その範囲は小さいと見られる。中国の輸出は労働集約型製品に集中しているため、国際市場において、日本の技術集約型製品とはあまり競合していない。我々の米国輸入統計に基づく綿密な計算によると、日本との競合度は中国の場合、2000年には約25%となっている(図)。アジアNIEsとASEAN諸国の平均50%前後と比べて、中国のレベルが非常に低いことがわかる。このため、円安によって、国際市場における日本の輸出製品の価格競争力が向上したとしても、これが中国の輸出需要を浸食するという範囲は極めて限られると考えられる。
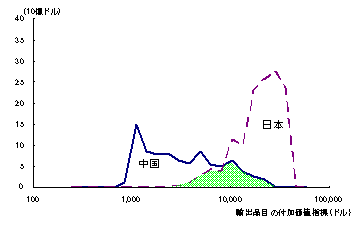
これに加え、円安は日本企業の対中投資を抑制する要因として働くが、日本の対中投資の金額が非常に小さく(年間30億ドル、中国のGDPの0.3%)、その動向が中国経済全体に与える影響は小さいと見られる。その上、近年、日本の対中投資の中心は、輸出型から現地販売型にシフトしているため、為替変動の影響を受けにくくなっている。
マスコミでは、中国にとっての輸出と直接投資の減少といった円安のデメリットばかりが強調されているが、一方では、輸入価格と債務返済負担の低下といったメリットも見逃してはならない。まず、円安は機械類や中間財など日本からの輸入を割安にし、生産コストの低下に寄与する。2000年の日本から中国への輸出品目を見ると、半導体等電子部品が全体の7.9%、鉄鋼7.0%、有機化合物5.6%、プラスチックが4.7%を占めており、部品や素材部門の輸出の比重が高いことが分かる。これに加え、円安になると、中国が抱えている円建ての債務(主に政府間の円借款)はドル換算で減ることになる。その結果、元本を含めて返済負担がその分だけ軽くなる。
これらのメリットとデメリットを合わせて考えると、円安の中国経済全体への影響は、世の中の常識とは逆に、マイナスよりも、むしろプラス面の方が大きくなると考えられる。同じ理由から、円安は中国の対外収支を悪化させる要因にはならず、人民元の切り下げ圧力になっているという批判も当たらない。
2002年1月11日掲載


