中国では、エネルギー消費の拡大とともに、大気汚染をはじめとする環境問題が深刻化しており、すでに危機の域に達している。これまで中国は、環境を犠牲にしても経済成長を優先させてきた。しかし、所得水準が上昇するにつれて、国民の環境保護への意識が高まっており、政府も本格的に省エネルギーと環境対策に取り組むようになった。このことは、環境産業を中心に、国内外の企業に多くのビジネスチャンスをもたらしている。
エネルギーの消費拡大とともに深刻化する環境問題
急速な工業化とモータリゼーションの進展を背景に、中国におけるエネルギー需要が急速に伸びている。英石油大手BPの統計によると、中国は、2010年に米国を抜いて世界最大のエネルギー消費国になった。2013年の中国における一次エネルギーの消費量(石油換算)は、28.5億トン、世界全体の消費量に占めるシェアも22.4%に達している。一次エネルギーの構造を見ると、日米欧といった先進国の場合、石油が中心になっているのに対して、中国の場合、2013年に石炭が依然として全体の67.5%を占めており、石油のシェアは17.8%にとどまっている(表1)。それでも、中国の石油消費量は、5.07億トン(世界全体の消費量の12.1%)と日本の2.09億トン(同5.0%)を大きく上回っている。
中国では、エネルギー消費の拡大とともに、環境問題が深刻化している。先進国に比べて、CO₂排出量の多い石炭をはじめとする化石燃料への依存度が高いことが、この傾向に拍車をかけている。中国のCO₂排出量は2006年に初めて米国を抜いて世界一の規模となり、その後も増え続け、低下傾向に転じた米国との差を広げている(図1)。
現に、環境の悪化が急速に進んでおり、国民の健康に多大な被害をもたらしている。特に、2013年1月12日、北京市内の多くの観測地点でPM2.5(粒径2.5μm以下の微小粒子で、その主な排出源は自動車の排気ガスや、工場の煤煙など)の観測値が中国の環境基準値の約10倍、日本の環境基準値の約20倍に当たる700μg/m³を超え、町全体が濃霧に覆われた。大気汚染は北京、天津、河北、河南、山東、江蘇、安徽、湖北、湖南など、143万km²の広範囲を覆い、8億人に影響し、工場の生産停止や、建設工事の中止、交通事故の多発、高速道路・空港の閉鎖など様々な影響が出た。呼吸器患者も急増した(岡崎雄太「北京市の大気汚染について―微小粒子状物質"PM2.5"とは―」、在中国日本大使館主催「大気汚染に関する講演会」資料、2013年2月6日)。
こうした中で、元CCTV(中国中央テレビ)女性キャスターの柴静が自主制作した中国の大気汚染についてのドキュメンタリー『穹頂之下』が、2015年2月末にネットで公開された。同ドキュメンタリーは、環境悪化の背景にある企業の違法行為、これに対する当局の無策、そして国有企業と政府の癒着などを具体的に描いており、改革の必要性を訴えた。これはアクセス数が2億回を超えるほど大きな話題を呼び、国民の環境保護への関心を高めた。
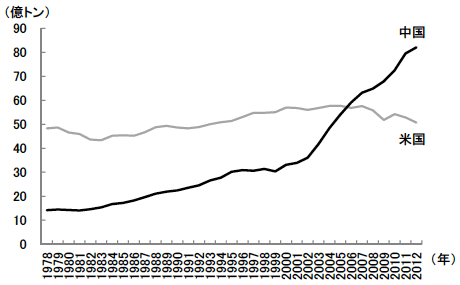
環境保護部の陳吉寧部長は、中国における環境問題の深刻さについて、次のように認めている(陳吉寧、第12期全国人民代表大会第3回会議のプレスセンターで行った記者会見での発言、2015年3月7日)。
「汚染物質の排出量は依然として非常に高い水準にあり、環境容量の上限に近づくか、超過している。一部の地域、一部の期間・時間帯においては、超過量が依然として大きい。このため、中国の環境問題は依然として非常に深刻である。これらの問題は、以下の三つの面に現れる。第一に、煙霧の問題、水系の富栄養化の問題、地下水の汚染問題、都市の悪臭を放つ汚れた水の問題など、環境の質が悪い。第二に、生態系の損失、特に水系の生態系損失が深刻である。第三に、産業の配置が合理的でないために、大量の重化学工業が川沿い、湖沿いに分布している状況は、高い環境リスクをもたらしている。環境問題は今や、小康社会の全面的実現のボトルネックとなっている。」
中国において環境の悪化に歯止めがなかなかかからない背景には、経済の急速な発展に加え、次のような制度上の問題もある。まず、現行の党と政府機関の人事評価体制では、経済発展を強調する(GDP至上主義)傾向が強い。次に、司法改革は進んでいるものの、地方レベルにおいて党と政府が、司法機関の独立した裁判権の行使を妨げる問題は依然として残る。そして、成長転換期を迎えつつある中国が進めている省エネ・環境保護分野における規制強化に対し、生産事業者の腰は重く、多くの企業が環境コストを犠牲に、非効率で環境負荷の大きい古い生産設備を頼りに、経済利益のみを追求してきた現実がある。最後に、環境保護法は基本法としての性格を持っているため、関連法の整備がないと実行力はない(汪勁、「2014年中国改正『環境保護法』の制定及び法執行への影響」、科学技術振興機構中国総合研究交流センター主催第82回研究会での報告、2015年3月12日)。
本格化する政府の環境対策
環境が経済発展の初期に悪化し、ある程度の発展段階に達すると、改善に転じるという現象は、日本をはじめとする多くの国の経験を通じて観測されている。このことを、環境汚染度と一人当たりGDPの関係で示すと、逆U字型の曲線(いわゆる「環境クズネッツ曲線」)で表すことができる(図2)。環境が悪化から改善に転換するきっかけとして、産業構造の変化(経済のサービス化など)や技術発展、国民の意識向上に応じた環境政策などが挙げられる。これまで、日本などの「成功例」に勇気付けられたこともあって、中国は、環境を犠牲にしても経済発展を優先させる戦略を取ってきた。しかし、中国が直面している環境問題の深刻さと、世界全体へ及ぼす影響を考えれば、この戦略はもはや限界に来ている。「環境クズネッツ曲線」を「山」にたとえれば、中国はその両側をつなぐトンネルを掘らなければならない。
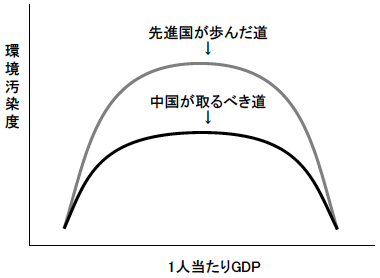
指導部も、真剣に対策に取り組む必要性を十分認識している。2007年10月に開催された中国共産党第17回全国代表大会(党大会)で、「エコ文明の建設」が初めて共産党の戦略目標の一つとなった。続いて、2012年11月に開催された第18回党大会では、「美しい中国」という目標を目指すべく、「エコ文明の建設」は、「経済建設」「政治建設」「文化建設」「社会建設」に加わって、「五位一体」とされる社会主義事業の柱の一つに位置付けられた。
エコ文明の建設に向けた大きな一歩として、中国政府は、2013年6月14日の国務院常務会議において、10項目にわたる大気汚染対策を決定した。
- ① 汚染物質の排出を減少する。小型石炭ボイラーを全面的に整理し、重点業種の脱硫脱硝除塵改造を加速する。都市の粉塵対策を実施する。燃料の質を高める。排ガス基準を満たしていない車を淘汰する。
- ② 高エネルギー消費・高汚染物質排出業種の新規生産能力の拡大を厳しく抑制する。鋼鉄、セメント、電解アルミ、板ガラスなどの重点業種の遅れた生産能力を淘汰するという第12次五ヵ年計画(2011-2015年)の目標を1年繰り上げて達成する。
- ③ クリーン生産を強力に推進し、重点業種における主要大気汚染物質の排出密度を2017年までに30%以上引き下げる。公共交通を大いに発展させる。
- ④ エネルギー構造の調整を速め、天然ガス、石炭由来メタノールなどクリーン・エネルギーの供給を拡大する。
- ⑤ 省エネ・環境保護の指標による制約を強化し、エネルギー評価、環境評価に合格していないプロジェクトは着工を認めず、土地供給や融資支援、電気・水供給を行ってはならない。
- ⑥ インセンティブと制約の両方を同時に実行する省エネ・排出削減の新しい仕組みを推進し、汚染物質排出に対する料金徴収を強化する。大気汚染対策に対する融資支援を拡大する。国際協力を強化し、環境保護や新エネルギー産業を育成する。
- ⑦ 法律や基準によって産業のタイプ転換と高度化を迫る。重点業種の汚染物質排出基準を制定・改正し、大気汚染防止法などの法律の改正を提案する。汚染物質排出の多い業種の企業については環境情報を強制的に開示する、重点都市の大気の質ランキングを発表する。違法行為に対する処罰に力を入れる。
- ⑧ 北京・天津・河北を含む環渤海、長江デルタ、珠江デルタなどの地域の合同対策の仕組みを構築し、人口密集地区と重点大都市のPM2.5(微小粒子状物質)の対策を強化し、省レベルの政府の大気環境対策目標の責任考課体系を構築する。
- ⑨ 重大な大気汚染を招く天候を地方政府の突発的事件応急管理の対象とし、汚染のレベルに基づいて重大汚染企業に対して生産制限、排出制限、自動車通行規制などの措置をとる。
- ⑩ 社会全体が「同じに呼吸し、共に奮闘する」行動準則を確立し、地方政府が地元の大気に対し全責任を負い、企業の汚染対策の責任を実施し、国務院の関係省庁が連携し、節約やエコ消費様式、生活習慣を提唱し、環境保護・監督に全人民を動員する。
これらの方針を盛り込んだ「大気汚染防止行動計画」は同年9月に国務院から発表された。その中で、①2017年までに全国の一定規模以上の都市(地級市)のPM10の濃度を2012年比で10%以上低下させること、②京津冀(北京市、天津市、河北省)、長江デルタ、珠江デルタなどの地域のPM2.5の濃度をそれぞれおよそ25%、20%、15%程度低下させること、③北京市のPM2.5の年間平均濃度をおよそ60μg/m³にすることが掲げられている。
これらの目標を達成するためには、省エネルギーとクリーン・エネルギーへのシフトが不可欠である。それに向けて、2014年11月19日に、「エネルギー発展戦略行動計画(2014-2020年)」が発表されている。その中で、中国のエネルギー発展に向けた5項目の任務を挙げている。
- ① エネルギーの自主保障能力を向上させる。
- ② エネルギー消費革命を推進する。
- ③ エネルギー構造を改善する。
- ④ エネルギーの国際協力を拡大する。
- ⑤ エネルギー科学技術のイノベーションを推進する。
同計画では、次の目標と対策が打ち出されている。まず、省エネルギーに関して、エネルギー効率の向上に力を入れ、2020年までに一次エネルギー消費総量を約48億標準炭換算トン(tce)に、中でも石炭消費総量を約42億トンに抑制する。また、クリーン・エネルギーへのシフトに関しては、エネルギー消費に占める天然ガス、原子力、再生可能エネルギーなどの割合を高める一方で、石炭の割合を下げることを通じて、エネルギー構造の最適化に取り組むことが挙げられている。具体的に、2020年には一次エネルギーに占める非化石エネルギーの比率を15%以上、天然ガスの比率を10%以上とする一方で、石炭消費の比率は62%以下に抑える。特に、石炭消費の抑制については、北京・天津・河北、長江デルタ、珠江デルタなどの地域の石炭消費総量を削減しなければならないとしている。2020年には北京・天津・河北・山東の四つの省・直轄市の石炭消費を2012年比で1億トン純減させ、長江デルタと珠江デルタについては石炭消費総量のマイナス成長を実現するとしている。
そして、1989年に制定された「環境保護法」は25年ぶりに改正され、2015年1月1日に施行された。新しい「環境保護法」は改正前と比べて、特に次の点において厳しくなった。
- ① 環境保護の監督管理をめぐる政府の職責がより明確に定められた。
- ② 「生態レッドライン」体制、汚染物質の総量規制、環境モニタリングと環境アセスメント、行政区を跨ぐ地域共同予防システムなど、環境保護基本制度が整備された。
- ③ 環境汚染および改善に対する企業責任が強化された。
- ④ 環境に関する違法行為に対する法的制裁が厳格化された。
成長が見込まれる省エネ・環境保護産業
省エネと環境保護に関する国民の意識の向上と政府の支援が後押しとなり、省エネ・環境保護産業は、中国にとって有望な成長産業の一つとなってきた。
国務院は2013年8月に発表した「省エネ・環境保護産業の発展加速に関する意見」で、省エネ・環境保護産業の生産額の年間平均成長率を15%以上に引き上げ、2015年までに年間生産額を4兆5,000億元にし、中国の支柱産業にすることを掲げている。
その上、省エネ・環境保護産業の発展の加速を推進するため、①重点分野を中心に発展のレベルの全面的向上を促進する、②政府が牽引力を発揮することで、資金が省エネ・環境保護関連事業に投入されるよう誘導する、③省エネ・環境保護関連製品の普及に力を入れ、市場の消費需要を拡大する、④技術のイノベーションを強化し、省エネ・環境保護産業市場における競争力を高めるという四つの重要課題が示されている
中でも環境産業への期待が大きく、その根拠として、環境部の呉暁青副部長は、次の四つの環境変化を挙げている(「環境産業は大きいチャンスを迎えている」、「中国環境上場企業サミット」での演説、新浪網、2014年12月28日)。
まず、大規模な集中的汚染対策は「新常態」となってきており、環境産業の規模はさらに拡大すると見込まれる。すでに発表された「大気汚染防止行動計画」に加え、「水汚染防止行動計画」はほぼ完成し、「土壌汚染防止行動計画」の作成も加速しているところである( 注 )。この三つの行動計画に関連する環境投資は6兆元を超えると予想される。
第二に、法に基づいた汚染防止と厳格な法の執行は「新常態」となってきた。法律を守るよりも、守らないほうが得をし、監督管理が緩く、法律が確実に執行されないという従来の状況が改善されている。
第三に、政府による環境保護サービスの外部調達は「新常態」となってきた。ゴミの無害化処理、環境観測と水源地の安全確保などのサービスが、その対象となる。
最後に、環境産業の投融資主体の多様化は「新常態」となってきた。環境産業が発展していくなか、金融の役割は非常に重要である。一部の地域では政府と民間との資本協力で生態環境保全プロジェクトを進めている。
省エネ・環境産業は日本が得意とする分野であり、これまで多くの技術と経験を蓄積してきた。予想される中国における同産業の目覚ましい発展は、日本企業にも多くのビジネスチャンスをもたらすに違いない。
2015年5月13日掲載


