「普遍的価値」Vs.「中国的特色」
近年、中国経済の躍進を背景に、その「成功の秘訣」が、内外の学者によって「中国モデル」としてまとめられている。特に2008年9月のリーマンショック以降の世界的な金融危機で米国の威信が低下したのに対し、中国はいち早く景気回復して世界への影響力を強めたことから、「中国モデル」が大きく注目されるようになった。「中国モデル」は、新自由主義の政策綱領とされる「ワシントン・コンセンサス」と対峙する「北京コンセンサス」としてとらえられることもあるが、その内容については、百家争鳴の状態になっており、まだコンセンサスに至っていない。
「中国モデル」を巡る各種の主張は、中国が自由・民主・法治・人権といった「普遍的価値」を受け入れるべきだと主張する「右派」と、あくまでも「中国的特色」を堅持すべきだと主張する「左派」に大別される。右派はさらに海外の学者たちが提唱する「権威主義体制論」、歴史学者たちが主張する「体制移行論」、新自由主義者たちが主張する「中国モデル否定論」に分かれるが、左派は中国政府が掲げる「中国的特色のある社会主義論」を支持している(表1)。
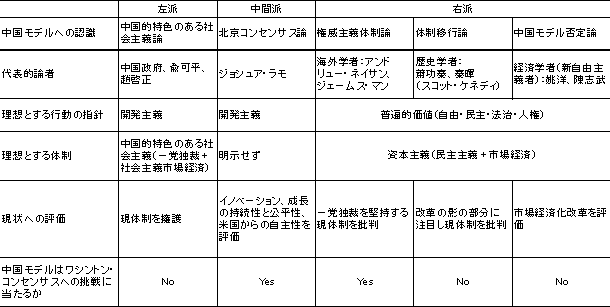
「左派」は社会主義の優越性を強調しているのに対して、「右派」は民主主義と市場経済を組み合わせた資本主義こそ人類にとって最良の体制であると見なしている。右派の中では、中国が資本主義を「目標」として目指すべきだという認識が共有されているが、その実現に向けての改革の「過程」に対する評価が分かれている。まず、「権威主義体制論」者たちは、改革、中でも政治改革のペースがあまりにも遅いことに強い不満を持っており、改革の見通しについても悲観的である。また、「体制移行論」者たちは、改革に伴うマイナスの側面を強調し、その是正を求めている。これに対して、「中国モデル否定論」者たちは、体制移行が比較的に順調に進んでいると判断している。
コンセンサスに至らない「北京コンセンサス論」
中国モデルを巡る大論争の口火を切ったのは、米国の中国専門家ジョシュア・クーパー・ラモ氏が2004年に発表した「北京コンセンサス」と題する論文である(Joshua Cooper Ramo, "The Beijing Consensus: Notes on the New Physics of Chinese Power," The Foreign Policy Centre)。ラモ氏は、中国の発展モデルを「北京コンセンサス」として、①科学技術の飛躍と絶えざるイノベーション、②公正な富の再分配と持続可能な成長パターン、③自主性(「ワシントン・コンセンサス」に対抗すること、自らの判断でグローバル化に参加すること、軍事力ではなく、ソフトパワーで中国の影響力を樹立すること、自分の限られた「非対称的力」を最大限に活かして米国を牽制すること)という三点に総括している。
ラモ氏による「北京コンセンサス」論については、支持する意見がある一方で、批判する意見も多い。中でも、インディアナ大学のスコット・ケネディ助教授による次の反論には説得力がある(Scott Kennedy, "The Myth of the Beijing Consensus," Paper presented at International Conference: Washington Consensus versus Beijing Consensus, Sustainability of China's Development Model, University of Denver, May 30-31, 2008)。
まず、中国はイノベーションをリードしているわけではない。多くの中国企業が生産している製品と提供しているサービスは海外で設計され、発明されたものである。中国政府は、自主イノベーション能力の向上を進めているが、大きな成果を挙げるに至っていない。
次に、中国が公正な富の再分配と持続可能な成長方式に励んでいる証拠は乏しい。大目に見ても、それはあくまでも将来の目標に過ぎず、中国の改革の主流となっていない。中国は環境保護面について規制を強めようとしているが、環境と経済成長が両立できない場合、往々にして、経済成長が優先されてしまう。その上、中国における不平等は拡大している。
最後に、中国は、資本主義の先進国やアジア各国の経験を参考にしており、全くの独自の発展戦略を持っているわけではない。その上、資本主義を中心とする世界体制にうまく適応してきた中国は、それを大きく変えようとしないだろう。
「東アジア型開発的独裁」との類似性を強調する「権威主義体制論」
ラモ氏の「北京コンセンサス」と違って、西側の主流派の中国専門家たちは、「中国モデル」の最大の特徴が、政治面における一党独裁と経済面における市場経済の活用だと認識している。これは、1980~90年代まで、韓国、台湾、インドネシアなどのアジア諸国が採っていた「開発的独裁」と呼ばれる権威主義体制と共通している。
中国式の権威主義体制の下では、政府は国民の政治参加に対し厳格な規制を敷くことで、政治的安定を実現し、国内外企業の投資に有利な環境を作り出した。同時に、投資の拡大と無限に近い廉価な労働力とがうまくかみ合って、輸出をテコに高成長を遂げた。その一方で、政府の権力と企業の資本の暴走を防ぐ仕組みが欠如しているため、所得格差の拡大と、それに伴う労資の対立と官僚と大衆の対立が招かれ、労働者のストと集団暴動が頻発している。これらの問題に対処するために、1980~90年代以降のアジア諸国は相次いで民主主義体制に移行したが、現在の中国では、このような動きはまだ見られていない。
コロンビア大学のアンドリュー・ネイサン教授は、中国における権威主義体制が「強靭」であるという認識を示した上、その強靱さの理由を次のようにまとめている(Andrew J. Nathan, "Is Communist Party Rule Sustainable in China?" Reframing China Policy: The Carnegie Debates, Carnegie Foundation, Library of Congress, Washington, DC, October 5, 2006)。
① 国民は、経済成長に伴って生活が改善されており、彼らはこのような恩恵を受けている間は、共産党政権を支持し続けるだろう。
② 共産党政権は、2008年の北京オリンピックや、いくつかの問題における日米との対立、台湾独立の阻止などを通じて、国民に自信を持たせている。
③ 共産党政権は、不十分でありながらも、「信訪制度」(国家機関や公務員による違法行為、職務怠慢に対して上申、告訴または告発する制度)など、国民の政府に対する不満を受け付けるチャネルを用意している。
④ 共産党政権はアメとムチを使い分けながら反対派の形成をうまく阻止している。
⑤ 共産党政権はマスメディアをしっかりとコントロールしており、一部の言論の自由を認めながらも、政治的に敏感な問題に関する議論を厳しく制限している。
⑥ 共産党はエリートを取り込んでおり、志を持つ人にとって党に入ることは理想を実現するための「最善の選択」である。
⑦ 中央政府に限らず、地方政府も優秀なテクノクラートに支えられて、政策決定と実施能力が高い。
⑧ 指導者層が団結している。最高指導者の定年制、集団指導体制、定年した指導者による関与の排除が定着しており、このことは、党の分裂を防ぐのに、大きい役割を果たしている。
国民に支持されている共産党政権は、簡単に崩壊することがないという。
「権威主義体制」に伴う弊害の克服を訴える「体制移行論」
歴史学者を中心とする一部の学者は、「中国モデル」を全体主義から民主体制への移行期の体制ととらえた上で、腐敗や格差の拡大など、その影の部分を克服するために、政治の分野を含む改革の深化が必要であると訴えている。
上海師範大学の蕭功秦教授は、現在の中国の体制を、毛沢東の時代の全体主義体制から生まれた権威主義体制と位置づけ、その特徴として、「強い政府、弱い社会」を挙げている(「中国モデル:優位性の背後に隠れた五つの難題」、『人民論壇』、2010年11月(上)、第307号)。蕭教授によると、中国の強みは、革命党の強い権力基盤を受け継いだ共産党政権が、市場経済においても社会をコントロールできたことにある。このような体制は、発展の初期段階において資源を動員する威力を発揮できたが、社会の発展に伴い、次のデメリットも顕著化しているという。
① 強い国家、弱い社会という体制の下で、国民の政府に対する監督能力は低く、腐敗防止と撲滅は至難である。
② 政府機関と官僚は既得権益集団と結託して、社会から資源をしぼりとる。その結果、国は富む一方で、国民は困窮する。
③ 国有企業こそ国家の安全と体制の安全を確保する根源であるという考え方が根強く残っている。実際、独占的な国有企業はイノベーションによってではなく、権力でたやすく巨大な富を手に入れることができるのに対し、民間企業の発展がますます難しくなる。
④ 権力に守られている官僚と企業は独占的な利益集団になる一方で、中産階級と一般大衆はなかなか豊かになれない。
⑤ 政府は教育や文化事業をコントロールしており、これによって、国民の独創性、ひいてはイノベーション能力の向上が妨げられている。
社会の矛盾がたまれば、集団の抗議行動などが多発する。政府はこれを弾圧しようとするが、その結果、社会の矛盾がますます激しくなってしまう。公民社会の育成こそ社会矛盾を解消し、強権社会から民主政治に向かわせるカギとなると蕭教授は訴えている(注1)。
また、清華大学の秦暉教授は、いわゆる「中国モデル」は「低人権」を前提としていると批判している(「中国の台頭と中国モデルの台頭」(その1~4)、財経網、2010年9月25、26日)。中国は、低賃金、低福祉に加え、人為的に労働力、土地、資本、そして資源の価格を抑えながら、価格交渉をはじめとする取引にかかわる国民の多くの権利を制限している。これを通じて生産コストと取引コストを抑え、「低人権の優位性」を作り出している(注2)。中でも、農民の移動の自由を戸籍制度で制限し、農民に農地の所有権を与えず、従業員の権利を主張する労働組合を実質上認めないといった中国の政策は、1994年までアパルトヘイトが実施されていた南アフリカと共通している。対外開放が進む中で、これらの政策は、外資誘致と製品の輸出において、中国に驚くべき競争力をもたらし、これを通じて、資本の原始的蓄積を加速させたのである。しかし、このように実現された「中国の奇跡」は、国民の大きな犠牲の上に成り立ったことを忘れてはならない。中国は、「低人権」を優位性として持続させるのではなく、問題として改めなければならないという。
「ワシントン・コンセンサス」との共通点を強調する「中国モデル否定論」
新自由主義者を中心に、一部の経済学者は、中国に高成長をもたらした要因が、決して特殊なものではないとして、「中国モデル」の存在を否定している。
まず、北京大学の姚洋教授は、改革開放以来の中国の経済発展の経験は、「ワシントン・コンセンサス」を否定するものよりも、それを支持するものであると主張している(「中国における経済の高成長の由来」(その一)、『南方周末』、2008年9月11 日)。「ワシントン・コンセンサス」はジョン・ウィリアムソン氏によって次の十カ条にまとめられている (Williamson, John, "What Washington Means by Policy Reform," in Williamson, John (ed.), Latin American Readjustment: How Much has Happened? Washington D. C.: Institute for International Economics 1990)。
① 規律的な財政
② 純粋な収入再分配の抑制
③ 公共サービス支出(教育と健康)の増加
④ タックスベースの拡大と適度な限界税率の低減
⑤ 金利の自由化
⑥ 競争力のある為替レートの維持
⑦ 貿易の自由化と外資投資の自由化
⑧ 国有企業の民営化
⑨ 企業の参入と退出に対する規制緩和
⑩ 財産権に対する保護
姚洋教授によると、金利の自由化を除けば、中国の政策は、おおむねこれらの方針に沿っている。このような政策が実施できた背景には、①重視された社会の平等、②確立されたエリート体制、③制度の純潔性よりも優先される制度の有効性、④特定の利益集団に偏らない「中立的な政府」の存在、といった現体制の特徴が挙げられるという(注3)。
また、イエール大学の陳志武教授は、中国の改革開放の成果は「自由こそ発展を促す」という理論を証明したものであり、中国の発展の経験は例外的なものではなく、「中国モデル」は存在しないと主張している(『没有中国模式這回事』(中国モデルは存在しない)、八旗文化出版社、2010年)。中国は持続的な発展を実現するために、さらなる制度改革を推進していかなければならない。また、米国が主導する国際秩序は、自由や民主といった「普遍的価値」を基礎としており、この秩序を守ることは、中国の発展にとって有利であるという。
中国の公式見解としての「中国的特色のある社会主義論」
一方、共産党政権と体制内の学者は、政治面の一党独裁と経済面の社会主義市場経済を組み合わせた「中国的特色のある社会主義」が中国にとって最良の体制であると主張している。
まず、中国政府は、「中国モデル」という表現を避けながらも、「改革開放以来、われわれがすべての成果を挙げ、進歩を収めた根本的原因は総じて言えば、中国的特色のある社会主義の道を切り開き、中国的特色のある社会主義の理論体系を形成したからである。」と強調している(胡錦涛、「中国的特色のある社会主義の偉大な旗印を高く掲げ小康社会の全面的建設の新たな勝利をかち取るために奮闘しよう」、中国共産党第十七回全国代表大会における報告、2007年10月15日)。ここで言う「中国的特色のある社会主義の道」とは、「中国共産党の指導のもと、基本的国情に立脚し、経済建設を中心として、四つの基本原則(社会主義の道、人民民主独裁、共産党の指導、マルクス・レーニン主義と毛沢東思想)を堅持し、改革開放を堅持した上で、社会生産力を解放し、発展させ、社会主義制度を強固なものにし、充実させ、社会主義市場経済、社会主義の民主政治、社会主義の先進的文化、社会主義の調和社会を築き上げ、富強の、民主化、文明化した、調和した社会主義国の近代国家を築き上げること」である。
また、政府の公式見解に沿って、中央編訳局副局長の兪可平氏は、「中国モデル」が伝統的社会主義モデルや西側の社会発展モデルと異なり、中国の国情に合わせた特殊性を持つものであると解説している(「兪可平が『中国モデルと普遍的価値』について語る」、『上海党史与党建』、2008年11月号)。具体的に、所有制においては、中国は私有化を全面的には実施せず、公有制経済を主導とする混合所有制を実行している。公有制経済は依然として、国の基幹産業を握っている上、土地や森林、鉱山などの資源の私有化も行われていない。また、資源配分においても、市場の果たす役割は大きくなっているとはいえ、政府の介入はまだ強い。さらに、政治において、中国は多党制と議会政治を行わず、立法、行政、司法の三権分立も行っていない。そして、イデオロギーにおいて、多様な思想が許されるようになったとはいえ、いまだマルクス主義の主導的地位が維持されている。
共産党政権と体制内の学者たちは、さらなる改革の必要性を認めながらも、その目的があくまでも「社会主義体制」の完備であり、民主主義を前提とする「資本主義体制」への移行ではないと強調している。それゆえに、政治改革には消極的である。
「中国モデル」は「ワシントン・コンセンサス」への挑戦になるか
ラモ氏の「北京コンセンサス論」は初めて「中国モデル」を、「ワシントン・コンセンサス」、ひいては、米国を中心とする世界の秩序の挑戦者としてとらえた(前掲論文)。ラモ氏によると、中国は軍事力など伝統的手段に依存せず、その模範性と経済力を活かして超大国になろうとしている。自国の国益を守ろうとする単独主義を遂行する米国に対し、中国は国際関係における多くの分野において、米国の覇権的行動を制約する環境を作り上げている。何よりも、中国は、米国による一極支配の世界において、自らの生活様式や政治的選択を守りながら、経済を発展させ、グローバル化の波に乗るという道を示したという。
このように高まる「中国モデル」の影響力に対して、「権威主義体制論」者である元『ロサンゼルス・タイムズ』のベテラン記者であるジェームズ・マン氏は、懸念を表明している(Mann, James (2007) The China Fantasy, Viking Adult, 2007. 邦訳:渡辺昭夫訳『危険な幻想』PHP研究所、2007年)。マン氏は、中国の未来について、「いまから25年先、30年先、より豊かで、国力の大きくなった中国が、相変わらず一党支配下に置かれ、組織的反対勢力は今と同じように弾圧される。その一方で、中国は対外的には開放され、貿易や投資その他の経済的な絆で世界各国と深く結びついている。」と予測した上、中国が権威主義的体制を存続させたまま経済が発展し、大国として台頭していくと、世界中の民主主義的価値観を推進しようとする努力に水をさすことになると警告している(注4)。
しかし、現状では、「中国モデル」は深刻な問題を抱えており、「ワシントン・コンセンサス」に取って代わるどころではない。
外交の面では、ハーバード大学のジョセフ・ナイ教授が指摘しているように、「中国モデル」は、権威主義もしくは半権威主義の発展途上国にとって魅力的かもしれないが、その一方で、西側における中国のソフトパワーの影響力の低下につながっている(Joseph S. Nye, "The Rise of China's Soft Power," The Wall Street Journal Asia, December 29, 2005.)。まず、中国は国際社会から孤立している北朝鮮や、スーダン、ジンバブエ政府と緊密な関係を維持することで、一部のメリットを得ることができるかもしれない。しかし、これにより、中国が道徳を無視してまで経済の利益を追求する異質な国であると見なされ、このことは中国のイメージダウンにつながっている。また、2010年度のノーベル平和賞が国家政権転覆扇動罪で服役中の中国の民主運動家である劉暁波氏に授与された。その際、ノーベル賞委員会は、世界第2位の経済大国となった中国の新たな立場には、さらなる責任が伴わなければならないとした上、中国は自らが調印した国際的な協定や自国の憲法に反し、市民の言論や報道、集会、デモなどの自由を制限していると厳しく批判した。これに対して、中国は反発し、劉暁波氏の授賞式への出席を認めず、各国に対して授賞式へ出席しないよう要請した。これに応じた17カ国(中国を含む)の代表が欠席したが、その中には、先進国はひとつも含まれていない(注5)。
一方、内政の面では、「中国モデル」の限界が顕著になってきており、その持続可能性について疑問が生じている。「体制移行論」者である秦暉教授が指摘しているように、「低人権の優位性」の上に成り立った「中国モデル」は、決して他の途上国の手本にならない(前掲論文)。
結局、中国は、自らが目指している「平和的発展」を実現するために、「中国的特色」にこだわるのではなく、自由・民主・法治・人権といった「普遍的価値」を受け入れながら、「世界の文明の主流」に溶け込むしかない。これは、国際社会が中国に望んでいることでもある。
2010年12月28日掲載


