1.はじめに
中国は、70年代末改革・開放政策に転じて以来、高度成長期に入っており、アジア経済におけるプレゼンスを高めている。特に、近年のIT革命の波に乗って、従来の労働集約型製品に加え、一部のIT製品においても、国際競争力を持つようになった。IT技術の活用によって中国が従来の工業化の長いプロセスを飛び越えて(Leapfrog)、短期間で先進国への仲間入りを果たす可能性が指摘されている。これを背景に、日本では中国はすでに日本と競合関係にあるという見方が主流になり、「中国脅威論」が浮上する。これと同時に、アジア各国の発展段階に即した域内の分業体制のダイナミックな変化を捉える、いわゆる「雁行的経済発展」が崩れたのではないかとしばしば指摘されるようになった。
中国脅威論にせよ、雁行形態崩壊論にせよ、中国がIT製品を中心に産業構造がすでに相当高いレベルに達していることを前提にしている。しかしながら、これらの前提は個別の事例に基づくものがほとんどで、中国を中心とする国際比較は、まだ体系的になされていない。その原因の一つに、個別の製品や業種の国際競争力を計る指標は確立されている一方で、輸出構造の高度化の進展を計る指標がまだ開発されていないことがある。それを補うために、ここでは、輸出を構成する各製品の付加価値度を指数化して、各国の輸出構造を計量的に評価する手法を提案している。これをベースに、アジア各国の最大の輸出先である米国の輸入統計を各国の対世界輸出の代理変数として使い、IT関連製品を中心に中国と日本をはじめとするアジア各国の品目別構成を詳細に調べる。直近のデータに基づく国際比較(クロス・セクション分析)に加え、90年まで遡って、各国の地位の相対的変化にも焦点を当てる。
2.雁行的経済発展を巡る議論
東アジア地域における経済発展は、異なった発展段階にある国々による追い上げの過程としてとらえることができる。この雁行的な経済発展において、各国は工業化の発展段階に応じ、それぞれ比較優位を持つ工業製品を輸出するといった分業関係を維持しながら工業化の水準を高めている。追い上げる国も、追い上げられる国も、それぞれがより高い工業化の発展段階を目指して積極的に産業構造調整を進めていくことが、地域全体のダイナミックな発展の原動力となっている。
経済発展の雁行形態という考え方の起源は、戦前、赤松要教授(東京商科大学、現一橋大学)の産業の盛衰に関する研究にまで遡る。最初の焦点は特定の国における特定の産業に絞られていた。その後、その応用範囲が、特定の国における産業構造の変化(産業の主役交替)、さらには国境を超えた産業の移転に拡張された。雁行形態の「国内版」では、資本蓄積(直接投資を含む)と産業間の連関関係の変化は、国全体の比較優位を変えることを通じて、産業構造の高度化をもたらす。次から次へと形成される新しい産業の資本集約度もしくは技術集約度が古い産業より高くなるのが一般的である。日本をはじめとしたアジア各国の場合、産業の中心が繊維から、化学、鉄鋼、自動車、電子・電機へとシフトしていくという順番がよく見られる(図1)。一方、雁行形態の「国際版」は先発国から後発国への産業移転を説明しようとするものである。一つの典型例としては、アジア地域における繊維産業の中心が、発展段階の順番に従って、日本から、NIEsへ、ASEAN、そして中国へシフトしていくことが挙げられる。
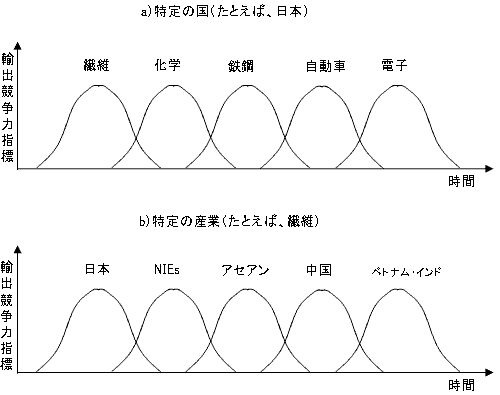
これに対して、経済産業省の平成13年版通商白書では、中国の台頭を受け、これまで日本→NIEs→ASEAN諸国→中国、の順番でキャッチアップ過程にあると見られてきた、東アジア諸国の雁行形態が、崩れつつある、と指摘している。近年の中国では、従来の雁行形態論で裏付けられる労働集約型産業のみならず、情報関連産業など技術集約的な産業まで、幅広く海外から直接投資を受け入れており、生産拠点として拡大を続けている。この結果、発展段階による産業の棲み分けが崩れ、先端産業を含めた競争が激化している。中長期的には、競争は生産性の向上を通じて域内経済全体を利する可能性もあると見られる。しかし、短期的には、中国とASEAN諸国との競争激化がアジア通貨・金融危機の一因であるともされるなど、域内国への影響は、よい面ばかりとはいえないとも言及している。
黒田篤郎氏(2001)も中国の登場で、「雁行モデル」は崩れ始めた、と主張しており、その理由として次の2点を挙げている。一つは、中国は、「雁行モデル」が示唆するような、労働集約型産業から資本集約型産業へという通常の発展段階を飛び越し、ある程度ハイテク産業にも独自の強みを持っているということである。もう一つは、これまで日本を先頭に、NIEs→ASEAN諸国→中国、の順で進むと考えられてきた経済発展の順序を崩して、中国がASEAN諸国にとっては脅威になっているのではないか、という点である。
3.アジア各国の輸出構造における高度化の進展
本節では前節で述べられたような議論がどの程度中国と世界の現実を反映しているかを考察しよう。まず、輸出構造を「高度化」という観点から評価するために、輸出を構成する各製品の付加価値度を指数化した上、中国をはじめとするアジア各国の輸出構造高度化の指標を算出する。
まず、第一段階では「高付加価値の製品ほど、高所得国から輸出される」という前提に基づいて、個別製品の付加価値を輸出国の一人当たりGDPの加重平均で表す。ただし、ウェイトは対象製品における各輸出国の米国輸入に占めるそれぞれのシェアとする。例えば、米国が半導体のすべての輸入を日本、韓国、そして中国の3カ国に頼っており、それぞれのシェアが70%、20%、10%である場合について考えてみよう。日本の一人当たりGDPが40000ドル、韓国は10000ドル、そして中国が1000ドルの時、半導体の付加価値が40000×70%+10000×20%+1000×10%=30100ドルになる(この場合、ほかの国のウェイトはすべて0)。言い換えれば、半導体はいろいろな国で作られているが、平均で見て、一人当たりGDPが30000ドル前後の国から輸出されていることになる。これに対して、テレビの場合、各国のシェアは逆に中国が70%、韓国が20%、日本が10%とすると、その付加価値は40000×10%+10000×20%+1000×70%=6700ドルに止まることになる。このように、半導体はテレビより付加価値の高い製品であると見なすことができる。同じように、すべて製品の付加価値を計算することができる(図2)(注1)。
次に、第二段階では、各国の輸出構造高度化指標を計算する。ここでは、「輸出品目の構成の中で高付加価値の製品のシェアが大きいほど、輸出構造の高度化が進んでいる」と見なす。実際の計算では10000品目にわたる製品が対象となるが、説明のために、ハイテク製品、ミドルテク製品、ローテク製品の代表として、半導体(付加価値指標=30100)、テレビ(同6700)、靴下(同2000)の三品目からなる輸出構造を考えよう。例えば、Aの国の輸出額のシェアが半導体50%、テレビ30%、靴下20%となっている場合を考える。その輸出構造高度化指標として、この三製品の付加価値指標の加重平均(30100×50%+6700×30%+2000×20%=17460)が有効となってくる。同じように、Bの国の輸出が半導体10%、テレビ20%、靴下70%からなるとすれば、B国の輸出構造高度化指標が、30100×10%+6700×20%+2000×70%=5750となる。このように、Aの国の輸出構造高度化指標がB国のそれより大きいことから、Aの国がBの国より輸出構造の高度化が進んでいると見なすことができる。
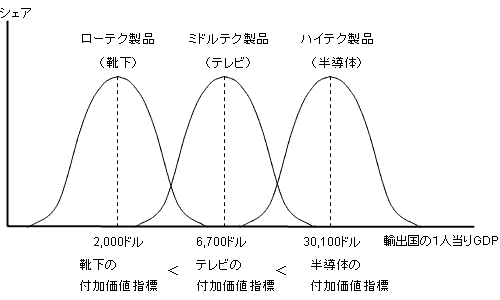
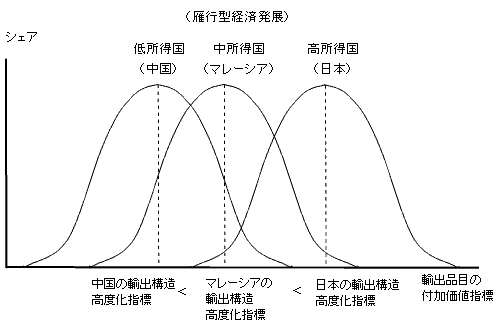
この第二段階の計算は、図3を使って説明することができる。すなわち、輸出品目をローテク製品からハイテク製品まで第一段階で得られた付加価値指標に沿って横軸に並べ、また縦軸に各品目の輸出全体に占めるシェアを対応させると、対象国の輸出構造を、一つの分布として表すことができる(注2)。国の輸出構造高度化指標は、この分布の期待値にほかならない。
輸出構造の高度化指標の計算は大学入試の成績の計算に類似している。各製品が各科目に対応し、個別製品の付加価値指標は各科目の配点に当たる。そして、それぞれの製品の輸出額の分類ごとのシェアは個別科目の成績、輸出構造の高度化指標は総合得点に当たる。入試成績に関して全体の分布と比較して、偏差値を算出することができるのと同じように、国の輸出構造の偏差値も計算することができる。そのとき、アメリカを除く世界全体の輸出構造の偏差値は50に標準化され、輸出構造の高度化が進んでいる国ほどその偏差値は50を大幅に上回り、逆に、遅れているほど、50を大幅に下回ることになる。
以上の分析の枠組みを持って、中国を中心とするアジア各国の産業高度化の進展を見てみよう。世界のすべての国を網羅した詳しい品目別の輸出統計を入手するのは困難であるため、ここでは、米国の輸入統計を使い、米国の各国からの輸入を各国の輸出の代理変数としている。商品分類に関しては、最も詳しいHS10桁分類(国際統一商品分類)を使い、全ての工業製品(約10000品目)を対象とする。また、個別品目の付加価値指標を算出するに当っては、工業製品をアメリカに輸出しているすべての国(多い場合約200カ国)を対象とする。時系列での比較ができるように、1990年、1995年、2000年の三年分について指標を算出している。
米国の輸入統計に示されるアジア各国の輸出構造をここで提示している枠組みに当てはめると、高度化の進展が未だおおむね発展段階に比例していることが確認できた(図4)。すなわち、日本は「失われた10年」を経ても、アジア諸国の中で最も進んでいる輸出構造を持ち、逆に中国は未だ雁の行列の後ろを飛んでいる。真中に挟まれているNIEsとASEAN諸国にとって居場所が狭くなったことは事実だが、雁行形態が崩れるにはまだ至っていないようである。また。これらの分布に基づいて、各国の輸出構造の偏差値を計算していると、中国の輸出構造の偏差値は1990年の31.1から1995年には33.5に、さらに2000年には36.2に上昇しているが、それでも世界平均である50に遠く及ばない(表1)。他のアジアの国々と比べても、未だ最下位にランクされており、雁行形態の議論に基づく発展順序が崩れているとは考えにくい。
(米国への輸出品目の付加価値分布)
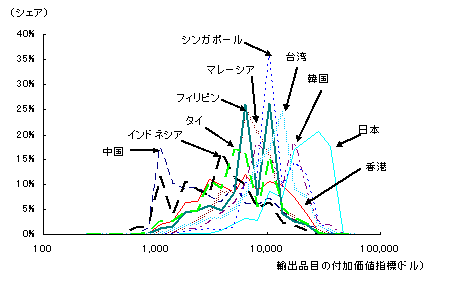
(世界の対米輸出構造=50)
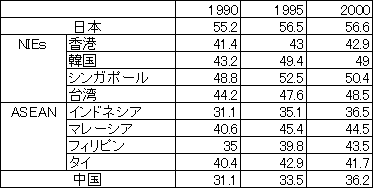
4.補完し合う日中関係
以上の枠組みをベースにすると、最近の日中関係をめぐる議論は、次の図によって整理することができる(図5)。すなわち、先のように得られた製品の付加価値指数に沿って、産業をローテク産業からハイテク産業の順で並べば、日中の輸出構造は、それぞれ一つの山のような形をとる分布として表すことができる。図4と同じように、その位置が右に偏っているほど輸出構造の高度化が進んでいることを表す。ただし、縦の軸はシェアではなく、金額となっているので、山の大きさは輸出規模に比例する。この二つの山の重なる部分が日本の輸出全体に対して大きいほど、日本にとって、中国との競合性が強く、逆に小さいほど補完関係が強いことになる(注3)。
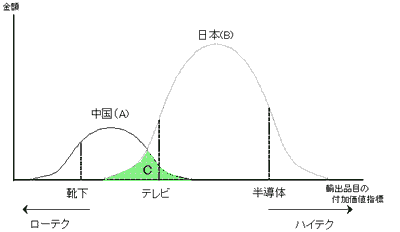
今のところ、日本の輸出規模が中国より大きく、その構造も中国より進んでいる点に関して異論はないであろう。しかし、中国の工業化の進展を反映して、中国の山は規模を拡大しながら、急ピッチで右にシフトしつつある。これに対して、日本の山は動きが止まったままで、更なる高度化の展望も開けていない。このような状況を背景にして、中国がすでに日本の手強い競争相手となっており、そう遠くない将来、日本の山はいずれ中国の山の裏に隠れてしまうであろうと、多くの日本人が懸念している。中国脅威論はこの恐怖感の現れに他ならない。
しかし、現状は、中国の輸出額全体が伸びているとはいえ、その輸出構造は未だ労働集約型製品が中心で、日本との競合性は必ずしも高くない。これを確認するために、米国の輸入統計を使って、米国市場における日中両国の輸出品目の重なる度合いを調べてみた。これによると、米国市場においては日本と中国が競合している品目が拡大しているが、金額ベースでは、まだ日本の対米輸出額の16.3%に過ぎない(1990年には3.0%、1995年には8.3%)。
ここで得られた結果はあくまで日中間の輸出品目の重なる度合いを表すもので、より正確に両国間の競合の度合いを測るためには、次の二点も考慮しなければならない。まず、同じ商品に分類されても、多くの場合日本は高級品、中国は汎用品にそれぞれ特化している。例えば、テレビの場合、中国製の標準型と日本製のハイビジョンの単価は一桁も違う。また、日本と比べると、中国は中間財や部品の輸入依存度が非常に高い。中国の輸出に含まれる輸入コンテンツは50%前後と報告されているが、この比率はハイテク製品ほど高いと見られる。このように、日中間における実際の競合の度合いは先の推計で得られた数字をさらに下回ると見るべきであろう。しかも、両国の間で競合している業種は、もっぱら日本がもはや比較優位を持たない付加価値の低い衰退産業に限っているといっても過言ではないだろう。
5.中国のIT製品輸出の実力
次に、IT製品に焦点を当ててみよう。ここでいうIT製品とは、日本貿易振興会(JETRO、2000年)の定義に従って、①コンピュータ・同周辺機器、②事務用機器、③通信機器、④半導体などの電子部品、⑤その他の電子部品、⑥映像機器、⑦音響機器、⑧測定器・検査機器の8分野を対象としている。
2000年の米国におけるIT製品の輸入規模は2529億ドルと、1990年の762億ドルと比べ約3.3倍となり、3分の2は日本、NIEs、ASEAN、中国からなる東アジア諸国からの輸入が占めている。その中で、日本・NIEsといった先発組から、ASEAN・中国といった後発組への生産移転を反映して、日本とNIEsの代わりに、ASEANと中国のシェアが高まっている(表2)。
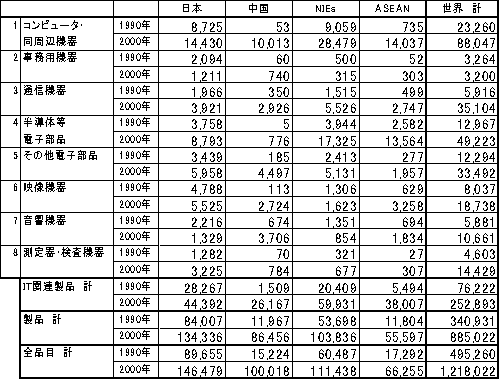
中でも、近年、中国のIT製品は国際競争力を高めている。IT製品の対米輸出は90年の15億ドルから2000年には262億ドルに急増した。これは中国の対米輸出を上回るペースであり、これを反映して、中国の対米輸出に占めるIT製品のシェアが9.9%から26.2%に上昇している。これと同時に、米国のIT製品の輸入に占める中国のシェアも2.0%から10.3%に上昇している。
これに対して、日本の対米IT製品輸出は90年の283億ドルから2000年には444億ドルに増加しているが、米国輸入に占めるシェアは逆に37.1%から17.6%に低下している。これは、多くの日本企業が、直接投資やOEMなどを通じて中国やASEANに進出し、その製品を従来通りに米国に輸出するというMade in JapanからMade by Japanという戦略変更の現れに他ならない。
中国が躍進している中、ASEANのIT製品が中国との競争で敗退するのではないかという悲観論が多いが、米国市場の動向を見る限り、ASEANが意外に健闘していることが分かる。インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイの主要ASEAN5カ国の対米IT製品輸出は1990年のわずか55億ドルから、2000年には380億ドルに急増している。ASEANの対米輸出全体に占めるIT製品のシェアも31.8%から57.4%へと上昇し、米国のIT製品輸入に占めるASEANのシェアも7.2%から15.0%へと倍増している。
中国のIT産業の躍進は顕示比較優位指数(RCA)の推移からも読み取れる(表3)。ここでいうRCA指数とは、「対象国の対象商品(対米)輸出」の「対象国の(対米)輸出全体」に占める割合を「世界の同商品の(対米)輸出が世界の(対米)輸出全体に占めるシェア」で割ったものである。対象製品の自国輸出全体に占めるシェアが、同製品の世界輸出に占めるシェアより大きい時に、RCA指数が1を上回ることになり、対象国が同製品において国際競争力を持つことを示す。中国のIT製品全体のRCA指数は1990年の0.64から2000年には1.26に上昇している。分野別では、特に、コンピュータ・同周辺機器(0.07から1.38)、事務用機器(0.60から2.82)、映像機器(0.46から1.77)の伸びが目覚しい。その一方、IT製品の中で特に付加価値の高い半導体等電子部品(0.01から0.19)と測定器・検査機器(0.49から0.66)に関しては、RCA指数がそれなりに上昇しているものの、水準としてはまだ低い。
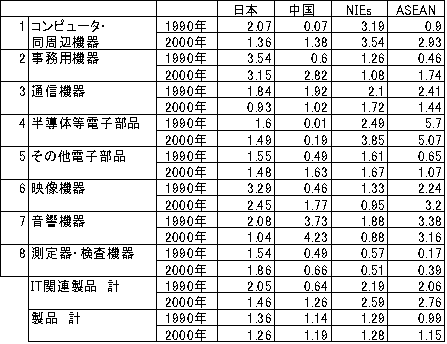
時系列の変化で見てみると、中国のIT製品の競争力が急速に上昇しているものの、日本やNIEs、ASEANなどのアジア諸国と比べて、中国の競争力が未だ特に強いわけではない。2000年現在、アジア各国のIT製品のRCA指数は、ASEANが2.76、NIEsが2.59、日本が1.46と、いずれも中国の1.26を上回っている。各分野におけるRCA指数から判断すると、ASEANと比べて、中国は事務用機器、その他の電子部品、音響機器、測定器・検査機器において比較優位にあるが、コンピュータ・同周辺機器、通信機器、半導体等電子部品、映像機器においては比較劣位にあることがわかる。
RCAに基づく分析は、各IT製品(または分野)における中国の比較優位を示すのには有効だが、これをもってIT製品全体を評価することはできない。なぜなら、一言IT製品といっても、付加価値の高いものから低いものまで多種多様だからである。中国のIT製品における本当の実力を評価するためには、第3節と同じ方法で、中国を中心とするアジア各国のIT製品全体と主要8分野の偏差値を計算してみた(表4)。これによると、中国のIT製品の偏差値は90年の33.9から40.7に上昇しているものの、世界平均である50にはまだ遠く及ばないだけでなく、アジアにおいても、未だインドネシアのすぐ上の、下から第二位に留まっている。これは、中国のIT製品の輸出が急速に伸びているとはいえ、その大半が付加価値の低い製品に集中していることを反映している。IT全体はもとより、8分野にわたって、例外なく日本の偏差値が中国を大きくリードしていることがわかる。
| 分類 | 日本 | 韓国 | 台湾 | 香港 | シンガポール | インドネシア | マレーシア | フィリピン | タイ | 中国 | ||
| 1 | コンピュータ・同周辺機器 | 1990年 | 54.8 | 41.1 | 43.4 | 45.5 | 48.6 | 43.1 | 41.3 | 47.5 | 46.2 | 44.8 |
| 2000年 | 55.9 | 47.7 | 52.9 | 46.2 | 52.4 | 41.9 | 46.1 | 47.2 | 44.3 | 44.3 | ||
| 2 | 事務用機器 | 1990年 | 53.2 | 37.6 | 35.2 | 47.3 | 41.8 | 53.0 | 24.2 | 54.4 | 24.2 | 28.0 |
| 2000年 | 56.2 | 51.9 | 41.7 | 48.3 | 49.5 | 36.9 | 38.4 | 52.3 | 48.1 | 42.4 | ||
| 3 | 通信機器 | 1990年 | 54.7 | 47.5 | 45.2 | 48.8 | 50.1 | 45.5 | 37.5 | 34.9 | 41.6 | 34.8 |
| 2000年 | 53.8 | 47.3 | 47.5 | 42.2 | 47.8 | 41.2 | 40.0 | 38.4 | 40.5 | 36.0 | ||
| 4 | 半導体等電子部品 | 1990年 | 55.1 | 49.0 | 47.6 | 46.2 | 49.7 | 47.3 | 43.1 | 42.4 | 45.3 | 38.7 |
| 2000年 | 54.6 | 51.2 | 49.9 | 46.6 | 52.9 | 47.0 | 43.7 | 43.9 | 44.2 | 47.3 | ||
| 5 | その他電子部品 | 1990年 | 52.9 | 49.4 | 49.8 | 50.6 | 44.6 | 50.8 | 44.2 | 47.8 | 44.4 | 48.5 |
| 2000年 | 56.4 | 52.3 | 51.7 | 47.8 | 53.4 | 44.1 | 47.6 | 39.0 | 42.0 | 41.7 | ||
| 6 | 映像機器 | 1990年 | 55.6 | 47.8 | 42.2 | 49.6 | 41.0 | 52.4 | 41.6 | 44.5 | 48.0 | 35.9 |
| 2000年 | 58.9 | 51.2 | 57.9 | 43.9 | 49.3 | 37.4 | 46.1 | 49.0 | 42.8 | 43.9 | ||
| 7 | 音響機器 | 1990年 | 56.2 | 48.2 | 47.0 | 43.9 | 48.0 | 42.8 | 43.6 | 40.1 | 41.0 | 41.1 |
| 2000年 | 56.6 | 53.7 | 52.7 | 48.0 | 52.1 | 48.2 | 48.5 | 40.8 | 52.1 | 42.8 | ||
| 8 | 測定器・検査機器 | 1990年 | 52.3 | 44.2 | 43.9 | 45.5 | 46.8 | 38.9 | 33.2 | 50.6 | 43.7 | 36.9 |
| 2000年 | 54.2 | 46.3 | 43.0 | 40.9 | 52.0 | 33.7 | 44.8 | 36.8 | 41.8 | 39.2 | ||
| IT関連製品全体 | 1990年 | 54.5 | 46.2 | 47.4 | 48.6 | 49.8 | 44.0 | 38.8 | 39.5 | 46.0 | 33.9 | |
| 2000年 | 55.5 | 49.7 | 51.3 | 47.0 | 51.8 | 38.7 | 44.7 | 45.9 | 44.0 | 40.7 | ||
次に、IT製品における日中間の競合度を算出してみた。全製品と同様、IT製品に限ってみた場合、AとBという二つの国における競合の度合いは、各IT製品における両国の重なる部分の合計がそれぞれの国のIT製品輸出全体に占める割合によって表すことができる。これによると、IT製品において、日本から見た中国との競合度は1990年の3.5%から2000年に31.8%に上昇している。各ITの主要分野においても、日本から見た中国との競合度はいずれも高まっている。しかし、その中身を詳しく調べてみると、日本と中国がそれぞれ高付加価値製品と低付加価値製品に特化している棲み分けは明らかであり、特に付加価値の高い製品において重なる部分がほとんど見られない(図6)。日中間が競合している最先端分野は皆無であるといっても過言ではないであろう。
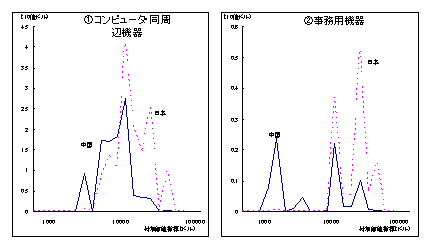
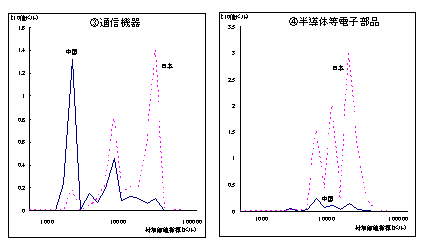
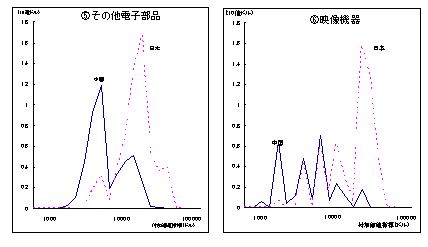
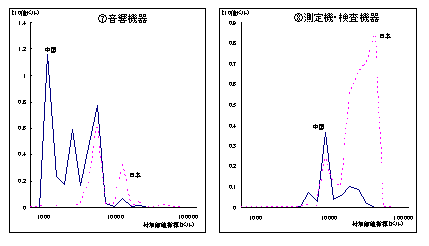
6.残された課題
以上の分析は各国の輸出構造を評価するための新しい枠組みを提供しているが、次の改善すべき点が指摘されている。
まず、各製品の付加価値指標として、輸出国の一人当たりGDPの加重平均が採用されているが、輸出国の数の少ない一部の製品に関しては、バイアスがかかる可能性がある。極端な場合、輸出国が一つしかない製品に関しては、同国の一人当たりGDPがそのまま対象製品の付加価値指標となる。これを反映して、製品別の付加価値指標をベースに算出される各国の輸出構造高度化指標もバイアスがかかっている可能性がある。特に、中国のように、所得が低いが、品目によって高いシェアを持っている場合、このように計算される国の輸出構造高度化指標が過小評価される可能性がある。
また、同じ品目に分類される以上、どこの国からの輸出も同質的であると見なされ、同じ付加価値指標が付けられているが、この前提が必ずしも成立しない。実際、同じ品目に分類されても、先進国が高級品、途上国が汎用品にそれぞれ特化していることは一般的である。多くの製品に関して、輸出国ごとの輸出単価が発表されているので、これをベースにある程度の修正が可能である。この要因を考慮すると、中国をはじめとする途上国の輸出高度化指標(ひいては偏差値)が下方修正されなければならない。
さらに、ここでは(米国の輸入)通関統計を使っているため、輸出金額の全額が輸出国でつけた付加価値と見なされている。加工貿易を中心とする中国のような国では、輸出には多くの輸入コンテンツが含まれているため、このように得られた輸出構造高度化指標が、実勢を過大評価していることになる。
2002年5月2日掲載


