RIETI政策対談では、政策担当者とRIETIフェローが、日本が取り組むべき重要政策についての現状の検証や今後の課題に対し、深く掘り下げた議論を展開していきます。
90年代以降における一連の商法・会社法の改正によって、日本においてもM&Aが大きく進展してきた。そして、本年5月に、三角合併制度が解禁された。
グローバル化された市場環境の中で、M&A市場は、今後、どのように進展していくのか。また、日本企業を取り巻く環境は、どのように変化し、その対応をどのように考えていくべきなのか。
RIETI政策対談第3回では、第2回の後編として引き続き、経済界・実務界と議論を重ね、実際に規制改革の推進に当たる経済産業省 経済産業政策局大臣官房審議官(産業資金担当)立岡恒良氏とRIETIにおいて1990年代後半以降の日本企業における統治構造の改革の実態と、その企業パフォーマンスに対する影響の解明についての研究を行っている宮島英昭ファカルティフェロー/早稲田大学商学学術院教授のお2人に、M&Aの進展や三角合併の解禁に向けられた誤解、敵対的買収防衛策、独占禁止法との関係について、論じていただいた。


(このインタビューは2007年3月16日に行ったものです)
対談のポイント
- M&Aの効果
- M&Aは、経済全体の資源配分効率性の上昇に寄与している。1999年の商法改正で新設された「株式交換」や「株式移転」制度には、大きな意味があると考えられる。
M&Aにおいて、最も重要なのは、「質」の面。M&Aを行うことにより、どのようなシナジー効果が生まれるのか、ということに着目していかなければならない。
また、外資企業の日本企業に対して持っているアドバンテージ(特に、ノウハウや知的資産などの無形資産)がM&Aによって、日本企業に導入されることによって、日本企業の企業価値を上げることも想定されことから、クロスボーダー型のM&Aが増加していくような環境整備も重要。
- M&Aは、経済全体の資源配分効率性の上昇に寄与している。1999年の商法改正で新設された「株式交換」や「株式移転」制度には、大きな意味があると考えられる。
- 三角合併制度の解禁に向けられた誤解
- 三角合併の場合、基本的には、投資家同士が契約を交わして、株主総会の決議を経るというプロセスがある。つまり、三角合併は、敵対的買収を狙ったTOB(株式公開買付)を経た後の話である。すなわち、三角合併制度の解禁について、それ自体が外資による敵対的買収を招くものであるかのように誤解を受けていることについては、認識を直す必要がある。また、時価総額の問題についても、TOBの問題であり、三角合併固有の問題ではない。海外からさまざまな外資企業が入ってくることに対する財界や産業界の懸念という心理的な面で誤解が生まれている。ただし、外資が「欲しいもの」だけ買っていくという危険性は、当然にあるので、その点については検討が必要。
- 敵対的買収防衛策について今後の対策をどう考えるか?
- 米国では、敵対的買収に関連して、いろいろな事例が積み重なってきている。そのため、司法判断を含めて制度が定着し、さらに発展した結果、防衛策の活用や司法判断を見越した安定性が確立してきたという過程がある。日本の場合には、その積み重ねが少ないので、ガイドラインが置かれ、そのガイドラインに従って実態が進んできた。しかし、本当に敵対的買収に関する予見可能性が形成されたかというと、まだ未成熟。今後、事例の蓄積をしていく中で、それぞれの事例からの教訓を継承しながら、絶えず防衛策をブラッシュアップしていかなければいけない。
- M&Aと独占禁止法
- 企業結合に関する独占禁止法上のチェックは、予防規制。技術の進歩が著しく、グローバル化された市場の中では、事前に予防するよりは、事後的に弊害があった場合に修正をしていく手法も併用していくべき。
欧州なり米国の考え方は、審査の慣行として、合併固有の理由で、効率性の向上や雇用増加のような効果が実現可能であり、それがユーザーに還元される部分が相当ある場合には、企業結合が競争を制限するかもしれない蓋然性を相殺するようなファクターとして取り入れるということが定着してきている。今回のガイドラインでは、公正取引委員会は、このような考え方に近い立場を取っていると理解している。
- 企業結合に関する独占禁止法上のチェックは、予防規制。技術の進歩が著しく、グローバル化された市場の中では、事前に予防するよりは、事後的に弊害があった場合に修正をしていく手法も併用していくべき。
なぜM&Aは増加したのか?
宮島:
M&Aの進展をどのように見るのかという問題があると思います。なぜM&Aは、急に増加したのか。また、日本で起きているM&Aは、日本経済全体の効率性を引き上げるポジティブな性格を持つものであると見ることができるのか。もしくは、ややマネーゲーム的なきらいがあって、法律事務所と投資銀行、証券会社は、利益を得ているけれども、日本経済の実態に対して、効果はないと見るべきなのか。
立岡:
M&Aの件数は、2000年ぐらいを境に増えています。これは、日本経済全体が、当時、直面していた課題と関係していると思います。経済全体の中で、さまざまな過剰が発生していて、その中でM&Aは「選択と集中」、つまり、資産効率を上げるための手段であ ったわけです。実際に、制度の面から見ても、むしろ、M&Aを行いやすくする方向で整備を進めたという意味では、基本的にはポジティブな見方をとってよいと思います。もっともM&Aは手段なので、何かを達成するためにM&Aが必要な手段であったということです。ただ、M&Aの内容を個別に見ていくと、やや批判を受けるようなものもあったかもしれなません。しかし、全体で見ればポジティブな評価をしていいと思います。
現に、M&Aの件数が増えているのはIn-In(国内企業間のM&A)の案件が圧倒的に多いわけです。クロスボーダー的な案件は、徐々には増えています。しかし、M&A全体の件数を見ると圧倒的にIn-Inが多い。この意味は、国内経済が持っていたさまざまな「過剰」の問題を片付けていくという過程の中で、M&Aの増加という現象が法改正とあいまって起こってきたということだと思います。
参考資料
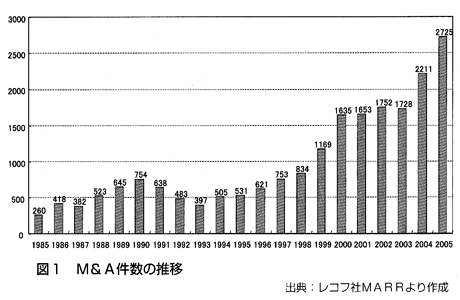
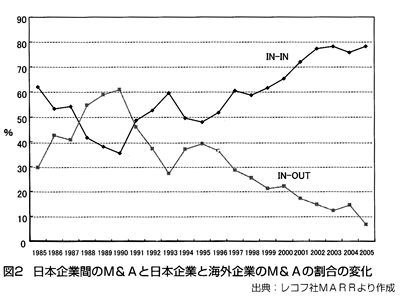
※図1と図2は、宮島・蟻川著「M&Aはなぜ増加したのか」より抜粋。
なお、詳細な分析結果については、
宮島(2006)「急増するM&Aをいかに理解するか:その歴史的展開と経済的役割」
宮島・蟻川(2006)「M&Aの経済分析:M&Aはなぜ増加したのか」
深尾他(2006)「M&Aと被買収企業のパフォーマンス:対日M&Aと国内企業間M&Aの比較」
をご参照ください。
M&Aに効果を与えた法改正
宮島:
経済学の言葉でいうと、M&Aは、経済全体の資源配分効率の上昇に寄与しているというわけですね。そのように考えますと、経済産業省として、これまで行ってきた一連のM&A促進政策のうち、どの政策処置がM&Aにとって効果があったとお考えですか?
立岡:
歴史的に分析したことはないですが、持株会社の解禁から始まり、さまざまな部分の改正を行ってきました。これは、商法本体だけではなく、商法の特例法の改正まで行いました。また、大きい改正としては、税制の整備があります。企業統合法制を整備しても、税制が付いてこないと実質的にそろばん勘定が合わないということになります。全体的には、相当な勢いで法制度は変わってきています。さらに、会社法の現代化で、三角合併の解禁を含めて、相当のところまで来たと思います。
宮島:
商法絡みでは、「株式交換」や「株式移転」に関する改正には大きな意味があったと思います。特に、企業のDNAがそれぞれ違いますから、企業が独立性を維持しながら統合できるというスキームの開発が非常に重要だった。合併は組織を一緒にしなければいけないので、なかなか決断ができない。しかし、全体的に影響力を行使しながらも、合併前のそれぞれの企業の独自性は維持できるというスキームは、合併の充実感が高まると思います。その意味では、1999年の改正は非常に意味があったと思います。
M&Aの現状をどのように見るか?
宮島:
また、これも議論のあるところですが、今、M&Aは増えたけれど、この水準をどう見るかということがあります。まだ少ないという見方と、大体これでピークかなという見方の両方がある。
先進国でのM&Aのブームを見る場合、一般にM&Aのターゲットの企業価値の合計値をGDP等で測ります。このように見ると、米国でのブームは10%ぐらいのウェイトでした。日本は、2001年に都市銀行が合併した際に多く上昇し、昨年は、その時よりやや上回って、大体17兆円ぐらいでした。これを、GDP比で見ると、最大で約3%ということになります。
他の先進国のブームでは10%ぐらいに達しますから、それに比べるとまだ少ない。日本も米国も欧州も同じように経済や社会が成熟していて、その意味で、経済全体の資源配分を改善しなければいけないという要請があるとすれば、日本では、M&Aはまだ少ないといえる。これが1つ見方です。
しかし、もう1つの見方としては、一般企業の競争力のコアは「ものづくり」にある。「ものづくり」のコアというのは、M&Aではなかなか買ってくることができない。だから、競争力を上げることを目的とする場合、M&Aでできることは、実はあまり多くない。その意味では、現在の日本のM&Aの状況を少なすぎると認識しなくても良いのではないか、というものです。
立岡:
最も大事なのはGDPに対する規模ではなく「質」だと思います。M&Aを行ったことによって、シナジー効果が本当に生まれるのか、など、「質」の部分に着目して問われなければならないと思います。確かに、「ものづくり」に関しては、企業が合併するだけでは、シナジー効果は生まれないでしょう。「擦り合わせ」型の産業の本当の強みは、日々のいろいろなコミュニケーションであったりする部分が大きいと思います。ですから、むしろ、そのような企業内の関係性の密度や頻度が大事であり、必ずしも資本形態ではないと思います。他方で、「ものづくり」においても、国際的な競争を考えていくと、リスクを取れる体力が当然必要になるわけです。特に、開発力などを考えたときに、一社だけではとてもできないというような問題があると思います。
そのように考えると、日本の企業としては、M&Aに取り組んでいくということは、絶えず求められることだと思います。
クロスボーダー型のM&Aは少ないのか?
宮島:
先ほどの整理でいきますと、審議官は、M&A案件は少なすぎるということはないという見方に立たれていると思います。クロスボーダー案件については、いかがでしょうか。日本において、クロスボーダーの案件は少ない。しかし、少ないといっても、クロスボーダー案件が大きな効果をもつ部分というのは限られているかもしれない。たとえば、消費財の分野に、外資が参入しましたが、成功をしている事例というのはあまり多くない。つまり、外資がアドバンテージを持っている分野というのは金融とか製薬とか一部の分野に限られていると考えられるわけです。このことを考えれば、クロスボーダー案件が成功する分野が限られているのですから、案件の数そのものは、少なすぎるということはないと見ることができます。
立岡:
私も同じ認識です。M&Aに限りませんが、国の方針として、対日直接投資を促進させようとしています。ですから、当然、資本のIn-Out、Out-Inという流れが、さらに活発化していく必要があります。ただ、宮島先生がおっしゃるとおり、クロスボーダー案件が質の高いものになるために、外資がアドバンテージを持つ分野は、どのような分野なのかということを考えると、金融などいくつかのサービス分野です。
クロスボーダー案件が少ない理由として、もう1つ考えられるのは、製造業分野における三角合併の問題にも絡むかもしれませんが、今後、海外からさまざまな企業が入ってくることに対する財界や産業界の懸念があるということも考えられます。
私たちは、外資が入ってくることによって、日本の外と中で資本が交流することにより、経済全体に良い効果が出るということを期待しているわけです。しかし、外資が単に欲しいものを持って行ってしまうという危険性もあり、これは、日本の技術流出の問題として、別のコンテクストで考える必要が出てきます。この問題については、M&Aだけの話ではなくて、外国為替及び外国貿易法(外為法)や不正競争防止法など、さまざまな問題が関わり、そのあたりのことも含めて、考えなければいけないと思います。ただし、総論としては、In-Out、Out-Inの交流がさらに進んでいく環境を整備していくことが必要でしょう。
三角合併制度の解禁に向けられた誤解
宮島:
三角合併制度について、そもそも解禁する必要がどのあたりにあるのかということを、RIETIサイトの読者の皆さんに簡単にご説明いただけますか。
立岡:
基本的には、組織の再編を行っていくにあたって、経営の自由度や再編のスピードを上げていくときの流れの1コマだと思っています。株式交換などの制度を組み合わせて行っていくよりは、簡単にできるということだと思います。その過程の中で、クロスボーダー的な合併を考えれば、この三角合併という手法があったほうが良いということも視野にありました。
誤解されることとして、三角合併制度が解禁されると、日本の企業が外資に買われやすくなる、敵対的買収をされてしまうという指摘があります。しかし、三角合併の場合、基本的には、投資家同士が契約を交わして、株主総会の決議を経るというプロセスがあるわけです。三角合併が事実上意に反して行われるとすれば、それは敵対的買収を狙ったTOBを経た後の話なので、こうした誤解には問題があると思います。三角合併制度の解禁について、それ自体が外資による敵対的買収を招くものであるかのように誤解を受けていることについては、認識を直す必要があると思います。
したがって、外資による日本企業の過度の買収の危険性に関する議論を行うのであれば、むしろTOB回りのルールの世界をどう考えるのかということが重要だと思います。
クロスボーダー型のM&Aが与えるプレッシャー
宮島:
クロスボーダー案件の促進の狙いは、海外の企業の持つノウハウなりマネジメントなり技術なりという部分で、日本企業に対してアドバンテージを持っており、そのような企業が日本に入ってくることが、日本企業の企業価値を上げるというところにある。その意味では、日本側に、経済効果的には、三角合併制度の解禁を阻止する理由は、あまり見い出すことができない。
その一方で、国内企業に対しても、合併対価の柔軟化が進んでいるわけです。そこで、海外企業との間で、合併対価の平衡性を維持するための対応をしっかりとやりましょう、ということがあるわけです。ここまでは、大方の部分で、意見の一致があると思います。
そこで、お聞きしたいのは、経済産業省としては、クロスボーダー案件の中で、日本企業に対してポジティブな効果を生むシナリオを、どのように描いているのか、ということです。
1つは、業界再編を促すような圧力を与えるのではないか、というイメージです。これは、カルロス・ゴーンさんが日産で行ったような経営改革のケースです。つまり、国内の企業に任せていても、企業内部からは、いろいろなしがらみのため改革の圧力が加わらない。そこで、クロスボーダー案件によって、圧力がもう一段強まるのであれば、変革が起こるかもしれないということです。
もう1つは、規模の経済性が働くことによる効果です。日本企業だけでは、規模が小さいので、外資企業と一緒になっても良いから、規模を大きくして、開発力を付けていくことが、日本の経済全体にとって、ポジティブな効果が出る面があるのではないか、ということです。
立岡:
その産業が、製造業やサービス業でも置かれている状況が違っているのだと思います。「ものづくり」で、そこそこ強い産業は、業界再編成を促すような圧力を期待する面があるかもしれません。また、どうしても規模が足りないのでサイズが足りないというのは事実です。電機産業などでは、これだけ資本や人、財、サービスの移動が自由化されている中で、戦略的な事業を行うためのリスクが取れる体力を付けていくということは、むしろ圧力の下で生まれてくるものです。その点で言えば、外資の参入によって、経営に対する圧力が効いてくることを期待しているところがあります。もちろん、外資が日本企業を買うことによって、シナジー効果がうまく出るということや補完関係でポジティブな効果が出てくることは良いのですが、それが大きく期待できるものなのかと言えば、私は、その点は、あまり重要視していません。
むしろ、サービスの領域で、日本にはないビジネスモデルであったり、日本にない知的資産であったりと、日本には無い無形資産を導入するための方法として、クロスボーダー型のM&Aは、ポジティブな効果を期待できると思います。
三角合併の議論における時価総額に向けられた誤解
宮島:
現在、危惧されている問題として、日本企業と海外の企業では、時価総額に大きな格差があり、三角合併制度が解禁されると株式による対価の支払いが可能になるために、大きなインパクトがあるのではないかという意見もあります。
立岡:
三角合併とは、基本的には経営陣同士が契約を結ぶわけです。それが買収される側の企業にとって、企業価値を高めるために良いことだという判断をするのであれば、特段の問題はないと思います。
問題としては、その時に、買収する側が力任せにくることがどうかという議論だと思います。しかし、この場合は、三角合併というよりもTOBの世界の話です。TOBで、株式の対価が不均等な形になるのではないか、ということだと思います。しかし、実際にそのようなことは日本企業と外資企業との関係でこれまでに全く起こっていません。ただ合併対価としては、株を使わず、当然キャッシュで行ってもいいわけですから、その点で、時価総額の問題の本質的な部分は、三角合併の問題ではないと思います。
時価総額の問題は、これまでもあったわけで、三角合併制度が解禁されたから、新たに起こる問題であるというわけではないのです。
宮島:
審議官がおっしゃっているシナリオは、たとえば、IBMが株価が高いときに、増資をして、キャッシュを作って、日本企業を買収するということは、今でもできるということですね。
敵対的買収防衛策には積み重ねが必要
宮島:
関連した問題として敵対的買収防衛策の問題があると思います。敵対的買収防衛策については、かなり議論されてきて、そのガイドラインも明確になりました。それを踏まえて、経済産業省として、あるいは審議官が、この点について、今後、考えていかなければならない問題として、どのような課題をお考えですか。
立岡:
米国でそうであったように、敵対的買収に関連して、いろいろな事例が積み重なってきて、司法判断を含めて制度が定着し、さらに発展し、その結果、防衛策の使い方とか、司法判断を見越した安定性ができてきたという過程があると思います。日本の場合には、その積み重ねが少ないので、ガイドラインが置かれ、そのガイドラインに従って、実態が進んできました。
しかし、本当に敵対的買収に関する予見可能性が形成されたかというと、買収防衛策を使い込んでいく中で徐々に出来ていくということがあると思います。特に有事に関しては、事例の蓄積をしていく中で、それぞれの事例からの教訓を継承しながら、絶えず防衛策をブラッシュアップしていかなければいけないと思います。この意味では、もっと多くの事例が出てくる中で、私たちとしても出来ることをしなければいけないと思います。現在は、まだ成熟していないかなという気がします。
宮島:
最近、RIETIの研究プロジェクトの一環として進めた分析によりますと、1999年~2003年頃までのM&Aは過剰設備処理タイプ、産業再生型でしたが、2003年以降は、企業が成長戦略の一環としてM&Aを使う事例が増加しています。ただ、M&Aの手法を使う場合も、友好的なものでなければ難しいというのが現状です。さすがに相手が「うん」と言わないときに、力づくではなかなか難しく、どうしても限界が出てきます。「うん」と言わないところはできない。ですから、その先を、一歩踏み出す必要があるのではないかという感じがします。
立岡:
欧米の例を見ていても、TOBをかけても、結局、出口を見出しているところがあります。企業買収後の経営は、買収が敵対的な状態であれば、絶対にうまくいかないわけです。宮島先生がおっしゃる通り、敵対的買収であっても、企業価値を高めるような提案が出会っていく中で、自ずと「こうだ」というところに熟して、企業内の体制が変わっていくケースというものが早く定着してくることを期待しています。
M&Aと独占禁止法
宮島:
M&Aを政策的に促進していく場合は、独占禁止法との関係で、折り合いをつけなければいけないと思います。つまり、規模の経済性を実現することと、独占力の乱用を阻止することは裏表の関係にある。このバランスについては、どのようにお考えですか。
立岡:
いくつかの論点があると思います。まず、そもそも論で考えると、企業結合などに対する独占禁止法上のチェックは予防規制なのです。つまり、カルテルと同様に、結合行為自体が直ちに市場を歪めるということではなく、その恐れが出てくることを事前に抑えるということです。
おそらく、経済のダイナミズムがさほど大きくない時代には、企業結合によって市場が歪められるかどうかということを、規制当局あるいは第三者の官が予見することは、そんなに難しいことではなかったと思います。しかし、今の世の中は、技術の進歩は著しく、市場はグローバル化している。市場によっては、ごく短期間に市場構造が変わることもあるわけです。その中で、予防的規制という理由で、当局が過剰に介入して良いかどうかということに、私は疑問を持っています。事前に押さえ込むよりは、まず結合をした上で、事後的に弊害があれば修正していくという手法を併用していくことを考えなければいけないと思います。
もう1つは、企業結合ガイドラインの問題です。去年の秋口から、公正取引委員会と議論してきている問題です。このガイドラインは、独占禁止法に従って、一定の取引の競争を制限してはいけないという運用基準です。このガイドラインを改定する作業の中で、M&Aや企業合併などに伴う効率性の向上を、どの程度ファクターとして捉えるのかという議論が多くありました。合併によって効率が上がるからといって、競争を制限することまで認めても良いのか。それは、だめだと思います。しかし、これは予防規制なので、その部分をどのように捉えるのかという問題があると思います。
欧州なり米国の考え方は、審査の慣行として、合併固有の理由で効率性の向上や雇用増加のような効果が実現可能であり、それがユーザーに還元される部分が相当ある場合には、企業結合が競争を制限されるかもしれない蓋然性と相殺するようなファクターとして取り入れるということが定着してきています。私は、今回のガイドラインでは、公正取引委員会はこのような考え方に近い立場を取っていると理解しています。
その意味では、グローバル化が活発化している領域においては、このような考え方を配慮していかなければならないと思いますし、このようなファクターを配慮する枠組みが、徐々に出来つつあるという気がしています。
(後編了)
矢尾板俊平(RIETIリサーチアシスタント/中央大学経済研究所準研究員)

