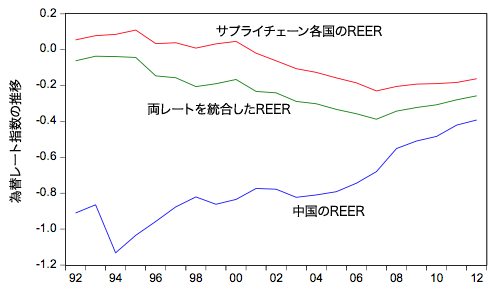| 執筆者 | THORBECKE, Willem (上席研究員) |
|---|---|
| 研究プロジェクト | East Asian Production Networks and Global Imbalances |
| ダウンロード/関連リンク |
このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。
国際マクロプログラム (第三期:2011~2015年度)
「East Asian Production Networks and Global Imbalances」プロジェクト
中国は2005年以降、加工貿易優遇税制と称される関税措置の下、巨額な黒字を計上している。加工輸出品とは、加工目的で非課税にて輸入された部品を用いて製造したコンピュータなどの最終財のことである。中国の加工貿易黒字は、2012年には4000億ドルを上回った。
中国の加工貿易黒字は主として欧米との関係におけるものであり、加工に使われる部品の大半の輸入元である韓国・台湾などの東アジア諸国との間では、貿易赤字を抱えている。スマートフォンやタブレットPCなどの輸出加工品の付加価値の大半が、東アジア諸国から輸入された投入物であり、中国のみならず地域全体が欧米に対して黒字となっている。このことにより、サプライチェーン諸国の通貨を押し上げる圧力が生じている。
本稿では、2012年までのデータに基づき、東アジア全体の通貨高によって加工品輸出は減少に転じ、加工目的の輸入は増え続けるため、加工貿易は均衡化に向かうことを示す。人民元高と台湾・韓国などの黒字国の通貨安が同時に起こる場合、中国の加工貿易黒字は減少せず、(労働集約型の)一般貿易の赤字が増加する。
図は、人民元高がサプライチェーン各国の通貨安によって相殺されている状況を示す。また、中国の加工品輸出における実質実効為替レート(REER)を示している。本稿で用いた24カ国との間の二国間為替レートを、中国から各国に輸出している加工品の割合に応じたウェイトに基づいて加重平均したものがREERである。この計算法によると、中国のREERは2002年から2012年にかけて39%上昇した。しかし、同時期、サプライチェーン各国のREERは10%下落している。この結果、加工品輸出に影響力を持つ、双方のレートを統合したREERは、2012年次点で基本的に2002年と同水準だったことになる。中国のREER上昇により、中国の労働集約型製品の(一般)輸出は、減速した。しかし、サプライチェーン各国の通貨安により、中国の加工品輸出は人民元高の影響を受けなかった。
以上の結果から、各国の政策立案者や、国際通貨基金(IMF)、ASEAN+3マクロ経済リサーチ・オフィス(AMRO)などの国際機関は、国だけでなく域内サプライチェーンのレベルでも、サーベイランス活動を行うべきである。中国が巨額の経常収支黒字となれば、人民元高を推奨する可能性もある。しかし、図が示すように、人民元高がサプライチェーン各国の通貨安で相殺される場合、中国の黒字を生み出している加工貿易は影響を受けないが、採算が低い労働集約型製品の貿易赤字はさらに拡大するだろう。中国の貿易黒字や為替レートに関する提言を行う場合、東アジア全体の為替レートを考慮に入れる必要がある。