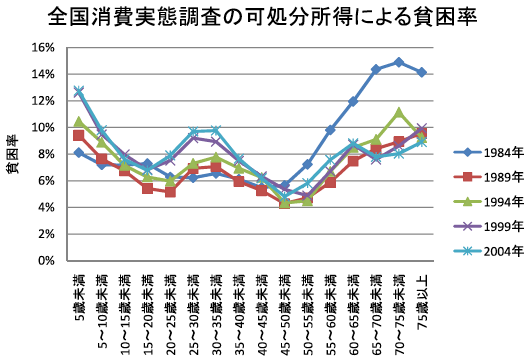| 執筆者 | 大竹 文雄 (大阪大学社会経済研究所) |
|---|---|
| 研究プロジェクト | 労働市場制度改革 |
| ダウンロード/関連リンク |
このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。
人的資本プログラム (第三期:2011~2015年度)
「労働市場制度改革」プロジェクト
2009年に厚生労働省が日本の相対的貧困率が15.7%という高い水準にあることを発表した。実は、日本の相対的貧困率が先進国の中では高い方であることは、OECDの研究でも明らかにされている。貧困解消手段には、景気回復による所得上昇、所得再分配政策による低所得者の所得上昇、低所得者に対する職業訓練による生産性上昇と並んで、最低賃金の引き上げ政策がしばしば挙げられる。2009年の衆議院選挙では民主党が最低賃金を1000円に引き上げていくことを公約に戦って、政権を取ったのはその典型である。最低賃金の引き上げは、少なくとも短期的には財政支出を増やさない政策であり、財源を確保する必要がないので、政治的にも好まれる政策である。
最低賃金引き上げは、本当に貧困解消策として有効なのだろうか。結論から述べると、最低賃金引き上げは貧困対策としてあまり有効な手段ではない。川口・森(2009)の実証分析によれば、日本において最低賃金引き上げで雇用が失われるという意味で被害を受けてきたのは、新規学卒者、子育てを終えて労働市場に再参入しようとしている既婚女性、低学歴層といった現時点で生産性が低い人たちだ。貧困対策として最低賃金を引き上げても、運良く職を維持できた人たちは所得があがるかもしれないが、仕事を失ってしまう人たちは、貧困になってしまう。こうした人たちの就業機会が失われると、仕事をしながら技術や勤労習慣を身に着けることもできなくなる。最低賃金引き上げで雇用が失われるという実証的な結果は、労働市場が競争的な状況における最低賃金引き上げに関する理論的な予測と対応している。ただし、最低賃金引き上げによって仕事を失うのが、留保賃金が高い労働者から低い労働者という順番であったとすれば、雇用が失われることによる社会的余剰の減少よりも、雇用を維持できた人たちの賃金が上昇する効果による余剰の増加の方が大きくなる可能性がある (Lee and Saez(2012))。
最低賃金の引き上げよりも貧困対策として、経済学者の多くが有効だと考えている政策は、給付付き税額控除や勤労所得税額控除である。給付付き税額控除は、低所得層に対する定額の給付が、勤労所得の上昇とともに勤労所得の増加額の一部が減額されていくというものである。現行の日本の生活保護制度は、勤労所得が増えるとほぼその額が給付額から減額される。その場合には、勤労意欲を保つことが難しいとされている。給付付き税額控除制度は、カナダで消費税逆進性対策として導入された他、米国、英国、カナダ、オランダで児童税額控除として導入されている(森信(2008))。一方、勤労所得税額控除は、勤労所得が低い場合には、勤労所得に比例して給付額が得られ、勤労所得額が一定額以上になれば、その額が一定になり、さらに勤労所得額が増えれば、給付が徐々に減額されて消失していくという制度である。この制度は、給付付き税額控除よりも、労働意欲の刺激効果が強いとされている。勤労所得税学控除制度は、米国と英国で導入されている。Lee and Saez(2012)は、勤労所得税額控除と低めの最低賃金の組み合わせが望ましいことを最適所得税の枠組みで示している。
日本において貧困対策は高齢者層に集中してきた。高齢層の貧困率の水準は高いものの、貧困率は公的年金の充実のおかげで大きく低下してきている。一方で、図に示したように、かつて貧困率が低かった20歳代、30歳代の年齢層における貧困率が高まってきている。その結果、その子供の年齢層である10歳未満層の貧困率が上昇しており、中でも5歳未満の年齢層の貧困率が高まっている。このような子供の貧困率の高まりは、20歳代、30歳代の雇用状況の悪化や離婚率の高まりが影響している。保育や教育といった現物サービスを通じて、子供に対する貧困対策をすると同時に、若年層の雇用を促進する政策が必要とされている。その際に、勤労所得税額控除や給付付き税額控除をとりいれていくことが効果的だと考えられる。